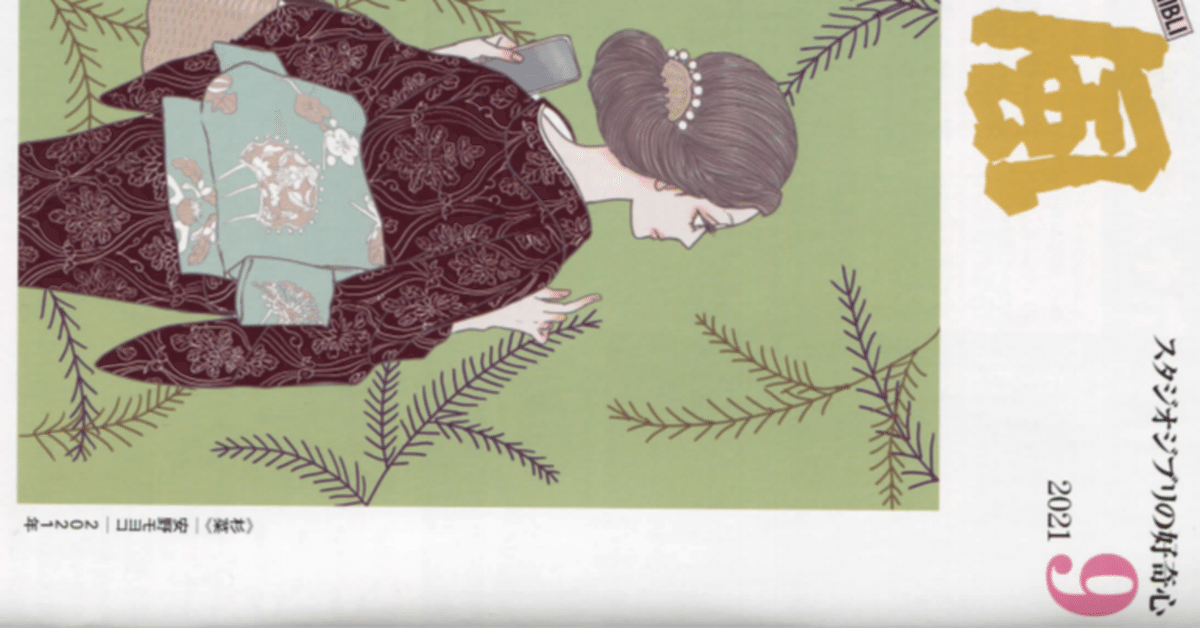
「アニメの『てにをは』事始め」~『熱風』2021年9月号より
わたしはジブリのフリーペーパー『熱風』にて、2021年4月号から2022年3月号まで12回にわたって、アニメ論考『アニメの「てにをは」事始め~アニメを新しく視るために』を連載いたしました。
一部の方から読んでみたいと要望がありましたので、今回その一回分9月号(連載第6回目)をこのノート上で再録いたします。
全編を読みたい方は申し訳ありませんが、古買サイトにて『熱風』バックナンバーを入手してみてください。
★1:第二章の補足~「全セル」について
セルアニメは平べったい素材で出来ているので、上下左右に視界がひらける光景を提示するのは比較的得意です。上下左右に伸びたセル素材を想起すると分かりやすいでしょう。
それに対し奥へと向かう光景を提示するのはなかなかに困難です。セルアニメの一番下の層に位置する背景美術はカメラがどうのぞき込んでも平べったく、奥行きに変化をもたらすことは難しいからです。せいぜいカメラがズームするぐらいが精一杯で、瞬間的な提示ならば奥へ向かう錯覚を抱かせることができますが、一定時間その効果を維持すればそれはただのズーム(拡大)だと分かってしまいます。
宮崎アニメが天才的ひらめきを見せるのは、この困難とされている奥方向への空間設計を構築することにあり、奥方向の奥行きに関しては「手前・中間・奥」の三層構造を提示し、「斜め奥」の奥行きに関しては左右方向から圧迫されて斜め方向に伸びる道を設定することで、これらセルアニメの苦手とされる奥行きを解決する技法を編み出したのはいままで見てきたとおりです。
しかし宮崎アニメにとっても奥方向への視界の展開は、三層構造・斜め奥の技法で万全ではなく、視界全体を奥方向に人もモノも風景も全て動かしたいとするときは「全セル」の技法を使います。「全セル」とは、ふつう動作するひとやモノだけがセル画として処理されて、背景は背景美術によってセルの下に敷かれてあるのですが、この背景美術にあたるものもセル画にしてしまう技法が「全セル」です。その瞬間、木々や家や道がセル画として動き出し、動作の主体である人やモノと一体化して奥方向へと視界を展開させるのです。
特に有名な全セルのシーンは『トトロ』の、妹メイを探しに姉のサツキが乗る猫バスが田んぼを疾走する場面でしょう。

辺りの田んぼがセルとなって動き出し、通り過ぎる畦道におばあちゃんの姿が奥から手前へと接近し、猫バスが疾駆して通り過ぎるとおばあちゃんが手前から奥へと遠ざかっていくダイナミックな奥行きと動きが提示されます。
他にも例を挙げておくと、『紅の豚』で追手から逃げたポルコロッソの乗る飛行艇が草原上を飛ぶ場面です。飛行艇が低く飛ぶその下を草原が左右にひろがりながら、奥へ奥へと光景が展開されます。草原上にある横切る道やたたずむ小屋、羊などがどんどん背後へ消えていきます。それらすべてがセルとしての背景として処理されています。そしてその草原がいきなり眼下の視界から消えると一面の海面がひろがるという、視界のカタルシスが起こるのです。
全セルは奥方向の動きにだけ活用されるのでもありません。斜め奥方向にも活かされています。『魔女の宅急便』(八九)で主人公少女キキが汽車の上で新天地を見つける場面などがあります。

画面としては三層構造の奥行きを作っています。手前が汽車の車体、中間が木々と草むら、奥が海と島です。このシーンも全セルと言えるのは、動くモノとしての汽車だけでなく、中間層の木々と草むらの風景もセルとして処理され動いている点です。斜め奥方向への動きの躍動感が生まれているシーンです。
ただし全セルは万能な技術ではありません。セル画と背景美術の組み合わせによって発展してきたセルアニメですが、局所的に全セルが採用されても、前後のシーンの背景美術とのタッチの違いから、全セルのセルとして動く背景の異和感が浮き出てしまいます。長らく分業制として固定化されていた背景美術部の存在意義にも関わるという問題も抱えています。
スタジオジブリの場合、その美術部の存在意義が問われたのが高畑勲監督『ホーホケキョ となりの山田くん』(九九)でしょう。簡略化した水彩画タッチの背景画が求められ、従来的な背景美術の技術をご破算にさせられたこの作品は、また一方で、セル画もまた塗り残しのあるぼやけた輪郭のキャラクターを求められました。セルと背景とが従来の技術をご破算にして合い寄って出来たこの作品は一種「全セル」的なアニメーションとして呼んでもかまわないでしょう。

『山田くん』の試みが可能になったのはデジタル化のおかげですが、宮崎アニメでもデジタル化を受けてたとえば難点としてあった全セル的な技法を解消するものとしてデジタルとくにコンピューターグラフィックスを用いられて背景美術が処理されたりします。『もののけ姫』の序盤、主人公青年アシタカが祟り神を討ち取ろうとする丘の斜面の立体的な動きがそれにあたります。
また『千と千尋の神隠し』(〇一)の花が咲き乱れる高い生垣の間を千尋がかいくぐる場面もそれにあたります。しかしどちらのシーンも、新技法であるCGの試み的な処理に終わった感があり、前後のシーンの背景美術との齟齬感はぬぐえませんでした。
あれらのシーンは新技術導入ゆえの過渡的な試みとして思えてしまうのは、『風立ちぬ』(十三)の震災を目前とする汽車のシーンがあるからです。①走る汽車と②通り過ぎる土手、③遠くの風景と三層構造を提示していて、先に挙げた『魔女の宅急便』のシーンを思わせます。



この『風立ちぬ』を確認すると、三層構造を組み立てながら特に中間層に当たる通り過ぎる地面が、ところどころで背景美術、全セル、デジタルと三種の方法が使い分けられていることが分かります。
このシーンを確認すると、宮崎駿というアニメーション作家は従来的な技法と新しい技術とを適宜使い分けるだけの判断力を、時間をかけてものにしていったことが確かめられるのです。CG技術が草創期に比べ手軽に行われるようになった昨今は、この『風立ちぬ』の汽車のシーンは、後学に資するためのお手本のような周到深い検討が確認でき、アニメ文化のために残した貴重な遺産のような印象すら受けます。
★2:インターバル。表層批評ついて
専門家たちもただアニメに対し「ストーリー・テーマ・心理」ばかり「観て」いたわけではありません。様々な知見でアプローチしようとしています。そのひとつを確認してみましょう。
実写映画の批評・鑑賞の仕方のひとつに、「表層批評」というものがあります。表層批評はこう提言しています。ストーリーやテーマは画面には「視えていない」はずなのに、なぜそれを「観た」と思うのか。「視ている」のは「画面の表面そのもの」である。だから映画を見るとは、「画面そのものの表層を視ること」である。
画面・スクリーンという「表層」を「視て」、「奥深くに・隠された」テーマやらストーリーやら心理やらを「観ない」。あくまで「表層的に見る」。それが表層批評の基本的態度です。この表層批評は、蓮實重彦という映画批評家が創始したものであり、多くの追随者を輩出しました。
「画面そのものを視る」、その態度は私がいま展開している「視せ方、視え方」ととてもよく似ています。しかし実際のところ、この表層批評的方法でアニメの画面を「視た」とき、それは多くの場合失敗しています。
蓮實は表層批評の方向性のひとつとして、「運動性を視る」ことを重視しました。落下、宙吊り、縦方向、横の広がりなど。
蓮實自身はアニメに対して表層批評を施しませんでした。自身の方法をアニメに適用する方途が見つからなかったからでしょう。その意味で、蓮實は実写映画の「視方」をアニメに「応用」することに慎重でした。
しかし追随者のいくばくかは、アニメへの応用を試みました。そしてそれは結局、ひとつの見解しか披露できませんでした。「アニメの画面に、落下運動を発見する」、これだけです。アニメにおいて、特に宮﨑駿作品は落下運動の表現が優れている、そう指摘できただけです。たとえば映画雑誌『リュミエール』六号所収の岡村民夫による「『天空の城ラピュタ』の活劇=空間」(八六)を嚆矢として、上島春彦の『宮﨑駿のアニメ世界が動いた』(〇四・清流出版)などは落下運動その一点だけで一冊の本にしています。しかし言っていることとは単に、宮﨑作品には落下がよく起こる、というだけの指摘です。
この指摘は、大したことなのでしょうか。実際のところ、「落下」はアニメにおいて、ほぼどんな作品でも頻繁に起こっています。人が歩くとき足を「踏み下ろす」という落下運動です。アニメにおいて基本中の基本となるアニメーション読み書き能力を必要とする運動です。そしてその「落下運動」が「アニメとして成功しているかどうか」は、「作用―反作用」に基づく動きの質感の創造に関わっていることは、この文章をいままで読んできたひとには、よくお分かりでしょう。
実写専用の「表層批評」をアニメに拙速に応用するひとたちは、アニメの画面に頻発している落下運動=「歩き」を「可視化」できないまま、ただ特別に人目を引く「派手な」落下運動にだけ反応しているに過ぎないのです。そうやって反応はしていても、それをアニメ固有の空間と運動から出来上がった画面として「視る術」は知らないでいるのです。
ではその「派手な落下運動」について私たちは何か言えるでしょうか。「視えている」と言えるでしょうか。
アニメにおける「派手な落下運動」は、大きく分けて三つに分類できます。
ひとつは上空からの視点。派手な落下運動は、画面奥にある地面へと向かって進行します。ふたつ目は逆に地上からの視点。上空から落下物が落ちてきます。そして大抵、衝撃力をともなって着地します。みっつ目は横からの視点です。視線の前方を、画面の上から下へ落下物がすべり落ち、通り過ぎてゆきます。以上の三つであり、そしてこの三つの落下運動はそれぞれに、アニメの運動として「全く異なる運動をしている」のです。だからそれは「同じ落下運動」ではないのです。それが「同じもの」に「視えてしまう」ひとに、アニメを固有性において論じる適性があるとは思えません。
さて、それではこの三つはどう違うのでしょう。
まず、これまで展開してきた論点を踏まえて説明しやすいという点で、二つ目の、地上から見て上空から落下し着地する「アニメとしての運動」についてみてみましょう。(ひと言、言い添えれば、もうそれは「落下」としての特別性はないと思いながら書き進めています。)
この二つ目の運動は、画面を視ている者からすると、画面の奥から手前へ、あるいは「斜め手前」への方向の軌跡を描きながら、徐々に物体として大きく視えてくる、つまり「膨張する運動体」となって顕われている、そう説明できます。そういう風に画面は作られています。そしてもちろん、それらすべて、運動の軌跡・運動の膨張は、「ひらべったい紙・セル」の上で展開されているものです。
しかし、このひらべったいものの上で展開されているはずの絵が、立体的な落下に「視えて」きます。そう「視える」ためには、軌跡の方向(画面の縦横フレームに対しやや傾いた方向)、膨張という運動、そして着地した際の大仰な「作用―反作用運動」の効果、それら三つの「視せ方」が最低限必要で、その条件を満たしたとき、ひらべったいはずの絵が、立体的に生き生きとした運動として、「視えて」くるのです。くりかえし言えば、それは「落下」では「ありません」。「ひらべったいもの」がいくつもの条件下で「平面上で運動」することによって、空間的・運動的に立体性を帯びて出現したように「視える」、そういう錯覚効果なのです。そしてその錯覚の手法が手際よく創造性豊かに作られていればいるほど、私たちは「視る」ことの楽しさに包まれるのです。(視せる/魅せる差を、「未来少年コナン」とアニメ版「ドラゴンボールZ」それぞれの、落下「運動」ならびに「着地の仕方」の差で注目してみるのもいいでしょう。)
アニメにおける「派手な落下」運動の、残りの二つについても簡単に見ておきましょう。
上空から見た、画面奥方向の地面へ向っての落下。これは先の落下「運動」の逆です。画面手前から斜め奥へ、そして膨張ではなく収縮運動。さらに言い添えておけば、三つの「派手な落下」の際にはしばしば、「運動そのものに注意させるために」・「運動そのものを魅せるために」、「動きの質の変化」を導入したりもします。
三つ目の、横から見た、画面の上から下への落下通過。これは、しばしば落ちる重力とそれに逆らう動作(つまり「作用―反作用の演技」)をつけて注意をうながしたり、落下物の速度そのものによって魅せたりもします。『天空の城ラピュタ』でのラピュタ島の底が抜ける場面や、『千と千尋の神隠し』で龍が湯屋の壁面際を飛び抜ける場面などを視なおしてもらえればよいと思います。さらに総合的に、これら三つのタイプの落下「運動」を一カットごとに組み合わせる工夫をして魅せる有名な例として、『ラピュタ』の序盤部、浮遊しつつ徐々に落下する女主人公シータを、坑道から突き出た板棒の上で男主人公パズーが抱き取るシーンがあります。
表層批評に限らない従来のアニメ批評一般において、特に宮﨑駿作品における「落下」について、あまりに同じことが言われ続けてきて、しかもそれがアニメ固有の「視え方」としては間違っているので、その誤りを具体的な「運動」の相において記述しながら書きました。
意地が悪いようで気がひけますが、実写映画の表層批評をアニメに応用した専門家たちは、表層を気にかけながら、アニメの肝心の表層性=「ひらべったさ」からの出発についてあまりに無頓着すぎ、その結果大きな「視誤り」を犯してしまっています。
表層批評に由来して誤用してきた、アニメのこの「落下」運動への着目が、アニメの「ひらべったさ」を無視している点で滑稽な着目であるのは、以下のことを指摘すれば明らかでしょう。
本当にアニメで「落下」が起きてしまったら、それは、「落下物」が動画やセル画やレイヤーを突き破って、動画机や撮影台・モニターの下に落っこちてしまうはずです。「落下に見える」ものは、ただ平らな紙・セル・仮想レイヤーの上に描かれた「線の水平線」でしかありません。
これほどに表層批評的錯誤を強調するのは、悪意があるからではなく、表層批評自身がしばしば「唯物的」と自ら定義しているからです。唯物的とは、物質的な規定に沿って厳密に考える、という程度の意味です。しかし、彼らは紙・セル・レイヤーという、「ひらべったいもの」の「物質性」に全く無頓着で、落下に「見える」ものが実はひらべったさの上で「すべって」いることの重要性に何ら関心を向けません。
実写映画の(そしてアニメの)専門家たちですらそうなのです。劇場へ足を運びお金を払ってスクリーン上のアニメの画面を観ている多くの人たちも、そのひらべったさに注意を払わないでいるのが実情なのも仕方ありません。むしろひらべったさを全く意識させず、あたかも実写映画のように立体的な空間で立体的な運動をただ「写している」かのように無造作に創造性を発揮しているアニメ群の、その「錯覚の手腕」はすごいものであることを、この多くの無関心が、逆に証明していると言ってもいいのでしょう。
あらためて言えば、アニメはただひらべったいがゆえに、立体性を欲望する。空間的に運動的に。そこにこそ「アニメを視る喜び」は向けられるべきでしょう。表層批評はその役割を担いませんでした。
★3:アニメ・メモ(アニメを視る芽)その2
アニメ論にまだ組み込めない・考える素材をそのままお見せするシリーズ「視る芽メモ」その2です。
前回、短編「On Your Mark」を採りあげました。「On Your Mark」は短いながら宮崎駿の表現のエッセンスが沢山詰め込まれています。たとえば、助けられた天使がオープンカーの車上からこわごわと飛翔をこころみて、二、三度ためらう。もうお分かりですね。「飛べるかな・飛べないかな?の作用―反作用」ですね。
しかし論者わたしにはまだ本論に組み込めない表現があります。 たとえば再び、この「On Your Mark」の表現を見てみましょう。壁からサイレンが出てくるという、ほんとうに一瞬のカットがあります。天使を盗んで逃げ出そうとするチャゲとアスカの二人組(全身スーツ姿)。ふたりが逃走する通路の壁からサイレンが飛び出ます。この、壁から飛び出るサイレン、ここにもアニメの不思議があります。
その壁が映ったとき、すでにサイレンの台座が壁の表面に浮き出ています。そのまま台座は傾きつづけながら、垂直に位置して落ち着き、その台座の上に載っていたサイレンが回転して鳴り始めます。このとき注意を怠ってならないのが、サイレンの台座が出た後に壁に穿たれて見える、サイレンが出て来た穴部です。
仕組みは単純です。最初に・すでに穴部の空いた状態の壁が描かれた背景美術が用意されます。その上に、可動する・つまりセルとして動く、サイレンとその台座が背景美術の上に重ねられます。つまり壁に穿たれた穴部は最初は、サイレンの台座のセル画で隠されているのです。そして台座が動くにつれ、セルの下に隠されていた穴部が現れるのです。



このカットは、宮崎監督のどのような判断で、この効果が選ばれたのか気になります。というのも、宮崎駿というアニメの演出家は次のような表現にもこだわりがちな人物でもあるからです。「サイレンの台座の出現と、背景の演技」は次のようでもあり得たでしょう。(めんどうくさい記述がつづくので、この次の段落は飛ばして読んでもかまいません。)
つまり穴の空いていない壁一面の背景画が描かれます。そして壁の表面上にサイレンの土台の輪郭線が途切れ途切れに浮き上がってきます。壁の上から台座の登場を予告する輪郭線をセル画で描き出そうとするのです。そして台座の輪郭が一本線で描かれた瞬間、台座の輪郭の内もセルの塗りとなります。つまり途切れがちだった表面の断線が輪郭線を結んだ瞬間、その輪郭内も壁の色に似せたセル画になるのです。そしてそのまま台座の底は壁から突き出るように現れてきます。台座とその上に乗ったサイレンが登場してくると、サイレンが格納されていたはずの穴部も見えてきます。しかしこの穴部ですが、最初に確認したように、背景画に穴部は描かれていませんでした。では穴部はどうやって出現したのでしょうか。それは輪郭線が一本につながり、穴部の底部がセル画で描かれた瞬間に起こります。このとき壁(1層目)と輪郭~底部のセル(2層目)の2つの重なりで出来ておたはずです。そして底部が台座となって傾きながら出現したとき、壁に穴部が見えるのです。つまりこの瞬間、壁の背景画の上に、穴の絵が描かれた透明なセルが乗せられ、そしてさらにその上に、動く台座のセルが乗ることになります。つまり壁(1層目)+穴部を描いたセル(2層目)+動く台座のセル(3層目)という重なりになります。
アニメの仕組みにくわしくないひとなら、「そんなに複雑な仕組みがあったんだ」と驚くことでしょう。ではその仕組みを知っているひとは驚かないでしょうか? そうとは思えません。アニメの仕組みに詳しいひと・あるいはプロのひとも驚くはずです。
「うわー、こんな細かいところまで、よくも丁寧にやっているなあ!」と。
そして場合によったらわたしがしたように、この台座の2種類ある表現を考えて、「どうして、こっちの方にしたんだろう? スケジュールがなかったとか、何か事情があったのかな?」などと正解のない推理をめぐらしたりもするでしょう。
それにしても不思議です。多くの観客が気づかない表現にまで手を抜かない宮崎駿というアニメの作り手に、賞賛の気持ちとともに、「なぜそこまでやるんですか?」という疑問が浮かびます。
宮崎駿というひとは、効率とか無駄を度外視して、こういう細部まで・アニメの可能な表現をつぎつぎと思い浮かべてしまうひとであるのは確かでしょう。見方によって無駄とも言えるし贅沢とも言えて、手間がかかっているとも言えるし、効率の悪い表現とも言えて。
宮崎駿はこんな細かすぎる表現まで意識した作り手だからこそ、こうまで多くの支持を得たのでしょうか? これはとても難しい問いです。しかし宮崎アニメファンが、これら細かいアニメ表現をまったく無視して作品を楽しんでいるとも思いません。技術的な細かいことは知らずとも、何かを感じているはずです。しかしときには、そこまでする必要があるのか?と問いたくなるほどのアニメならではな表現の過剰さがあるのも確かです。
宮崎駿はこれらアニメ表現の可能性を、実際のところ誰に向けて発信しているのか? 今回、わたしがこの論考で明らかにしなければ、あるいはなかったもののようにされてしまった宮崎の表現の数々。それは、いったい何のために発想されたというのか。観客の数々が確かに視ていながら、言葉に出来ていなかったこと。だから、穴をふさぐセル画表現に気づいてしまったわたしはいったい、何を知ったと言えるのでしょうか。
わたしはこれまで、作用―反作用の動きの質感を言い、斜め奥や三層構造を言ってアニメの空間表現を言ってみました。それらは多少、アニメを「視る・効用」になっているかも知れません。
しかし穴を隠すセル画の表現を知ったところでどんな効用があるのでしょうか。まだこの気づきは、わたしのアニメ論のなかで最適な位置を見出せていません。仮にメモとして書いているのは、そういう理由があるからです。
それでもサイレンの台座を、わたしは見つけてしまいました。この表現を見つけてしまったその瞬間、わたしは「面白い!」と思いました。だが、なぜ面白いのか。そこには論者のまだ知らない、アニメのさらなる魅力があるのだと思うのです。
さて次回は、3つあると予告した「アニメのてにをは」の最後、3つ目の登場です。でもすでに幾たびか予告しておいた話題、「運動の複数性」です。
なぜヒトやモノがうじゃうじゃと(複数)動くだけでアニメは面白くなるのか。またまた宮崎アニメを具体的に参照しながら視ていきたいと思います。(おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
