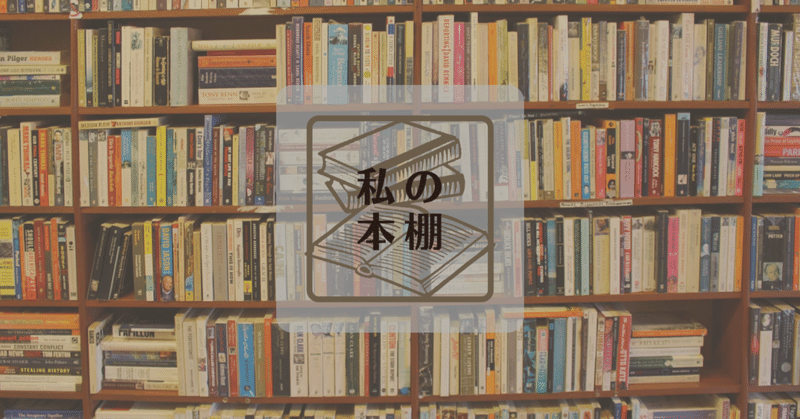
読書感想文:中谷内 一也『リスク心理学 ─危機対応から心の本質を理解する』(ちくまプリマー新書、2021)
私ごと、この春から放送大学の大学院でリスク学の勉強をしている。原発事故のあと、自分がしてきた放射線測定に関連する活動は、一般的には、「リスク・コミュニケーション」というジャンルに該当する。自己流で四苦八苦しながらしてきた活動が、大枠ではリスク学にカテゴライズされることがわかったので、自分のしてきたことの意味を学術的に整理しておきたい、というのが大きな動機だ。
ただ、それとは別に直接の動機がもうひとつある。
2021年に朝日新聞社の論座に、以下の記事を書かせてもらった。これは、福島第一原発の処理水問題に関連して、処理水の性状を伝えるために復興庁がつくったパンフレットに、除去しきれない放射性物質「トリチウム」をキャラクター化してあったことが炎上を巻き起こした顛末について書いたものだ。
この時は、「トリチウムくん」をキャラクター化したことが、キャッチーな引き金となり炎上となったけれど、そもそも復興庁が行ってきた「リスク・コミュニケーション」じたいが、検討外れでおかしいものだ。
わざわざ「」付きの「リスク・コミュニケーション」と書くのは、原発事故に関連して使われる「リスク・コミュニケーション」は、リスク学の展開にともなって現在学術的に定義されているリスク・コミュニケーションからは離れた、ガラパゴス的な用いられ方をしているからだ。
さらに大元を辿れば、現在、日本政府が採用している復興庁の「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」自体が、リスク学のこれまでの知見を完全に無視した、控えめにいって見当違いな思いつきの羅列でしかない。戦略の大方針が誤っているところに、なにをやってもうまくいくはずがない。
リスク学という分野は、日本のアカデミアのなかではあまり大きな勢力となっていないように見受けられる。そもそもが学際的な分野なので、「リスク学」というまとまりでの見解を強く主張することが難しいということもあるのかもしれない。そのせいか、原発事故後は、アカデミアで大きな力を持つ医療や物理といったジャンルの研究者の、これまでの知見の積み重ねを無視した、我流の「リスコミ」が大きく幅を効かせることになり、それが直接復興庁の政策に反映されてしまっている。
この見当違いの大方針に基づいて、環境省、エネ庁、復興庁、県庁がそれぞれの予算を投じてキャンペーンを発注し、広告代理店がそれを受注し、マーケティング的宣伝手法で彩ったコンテンツを大量に生産する、というかなり悲惨な状況になっているのが現状だ。「風評払拭」の大義はあるし、やっている感は出せるために、それを止める人もいない。太平洋戦争の負け戦も真っ青の非論理的な非合理的な非戦略性と(これまで推進してきた人たちの顔を潰せないという)忖度のオンパレードである。
上述のようなことを論座の記事には書きたかったし、書いたつもりではあるのだけれど、正直、あまりうまく書けた気がしなかった。ひと言で言えば、このことを論理的に書き切るだけの力が自分にはないな、と力不足を痛感した。ほんとうは、復興庁がグウの根も出ないくらい、徹頭徹尾論理的にどこがどうダメなのかを書きたかったのだが、それができていないな、と思ったのだった。
実を言うと、大学院で勉強しようと思った直接のきっかけは、このことだった。とにかく、原発事故後の日本政府のリスコミ戦略は徹頭徹尾、壊滅的にダメで、予算の無駄遣い以外のなにものでもないのだけれど、それを根拠を明示しながら論理的に示せるようになりたい、のである。(ただ、修論のテーマはこれではなく、原発事故後の「信頼」についてのナラティブを分析する計画になっている。)
前置きが長くなった。
で、こちらはわたしが書けなかったことの論拠となるリスク心理学の概要について、一般の人にもわかりやすく、展開の流れから、どういうことが言われているかまでが書かれている。
リスク学は、すぐれて社会実用的な分野で、科学技術の社会実用がこれだけ進んでいる現代社会では、この分野の知見なしでは社会が成立しないと言ってもいいと思う。急速に発展する科学技術の社会実装の局面では、当該技術と人間社会の調整役として、リスク学の知見は必須のものとなるからだ。あるひとつの技術が、社会実装に耐えるかどうか、つまり社会に受け入れられるかどうかの局面においては、科学技術そのものよりも、リスク学などの知見がハンドルを握ることになる。欧州でこの分野に力を入れているのは、技術の社会実装においてこの部分のハンドリングが科学技術の発展そのものと並ぶだけの影響力を持つ、と理解されているからだろう。だが、そのことの認知がまず日本では進んでいない、と感じている。
たとえば、原発事故のあとに、除染基準となった「0.23μSv/h」は、長く安全基準とみなされてしまい、多くの人を悩ませることとなったのだけれど、これは本書のなかでも書かれている「アンカリング効果」が強烈に働いたものと理解できる。不安的な状況のなかで最初に根拠として示された数値は、それが確かな根拠に基づくものであろうともなかろうとも、われわれは優先的に基準として採用してしまう認知構造を持っている。これを「科学リテラシー」の問題と片づけるのは容易いけれど、そういう人だって、他の場面では同じことをしているのだから、人間とはそういうものだ、と理解して対応をそれに合わせた方が社会的には低コストで済む。
ちなみに、「科学リテラシー」が不安に影響するかどうかという調査も本書の筆者らによってなされている。
こうした知見の積み重ねがリスク学の分野ではなされている。日本では、近接分野である「科学技術社会論(STS)」の方が存在感が強いようにも感じるが、重なる部分は多いものの、STSのほうがより言論、社会学よりである、というのがわたしの印象だ。
本書最後には、人間の必ずしも好ましくない認知のクセを踏まえつつ、効果的なリスク対応を行なっていくには、個人の取り組みではなく、社会の制度によって取り組む必要性が指摘されているけれど、これはまったくそのとおりで、知見を積み上げた持続的な対応ができなければ、意味のあるリスク対応(リスク・コミュニケーション)はできないと言ってもいいだろう。上述の「アンカリング効果」も、事前にそのことを知っていれば、いざその局面になったときに、アンカリング効果を起こさないような情報周知の仕方、ないしは、基準の設定の仕方を行えばいいのであり、咄嗟にそれができるようになるには、その知見を共有している組織部署が必要となる。
そうでなければ、復興庁の見当違いの「大方針」のようなものが、毎回、場当たり的にできるばかりだ。行政府がその知見を絶えず参照できるような、第三者機関的な組織にリスク学やリスク・コミュニケーションの知見を積み上げていく社会的な対応は、今後必須である、と、私は思っている。
ほとんど本書の感想になっていないけれど、新書で手に取りやすいし、読みやすく書かれているので、まずは手にとって読んでみてください。
気に入られましたら、サポートをお願いします。
