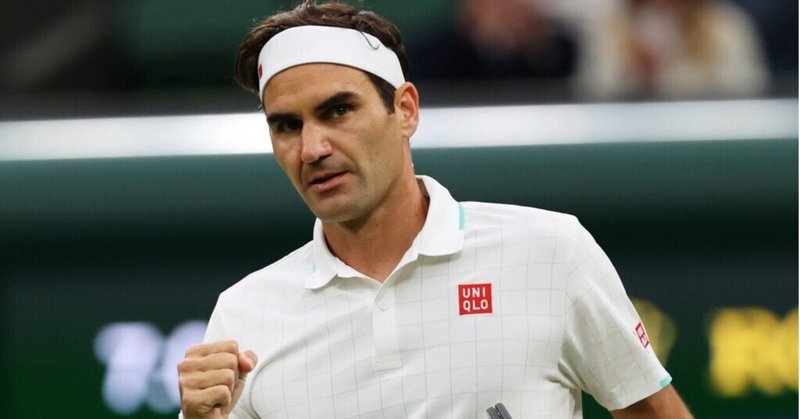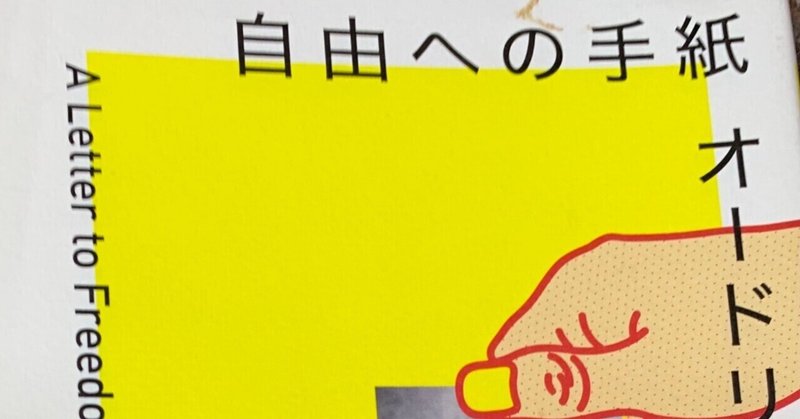今日ときめいた言葉。日常生活で出会った素敵な言葉、心動かされた言葉あるいは事柄について書いています。そんな言葉に出会った時、凡庸な日常が一瞬輝きます。ああ、私は言葉に生かされてい…
- 運営しているクリエイター
#学問への愛を語ろう

今日ときめいた言葉11ー「絶望を救うのは、日常そのものだけなのです。朝のコーヒーの一杯でもよい。何か人間らしいことによって、人は救われるのです」
(2023年1月1日付 朝日新聞 「誰もが孤独の時代 人間性失わないで」 スベトラーナ・アレクシエービッチさんの言葉から) 彼女は、「戦争は女の顔をしていない」で独ソ戦を戦った女性兵士の声を集めて戦場での生々しい現実を描いた作家で、ノーベル文学賞受賞者でもある。他にもアフガンに侵攻したソ連兵やその遺族、チェルノブイリの事故の遺族や被災者を取材して社会や時代の犠牲になった人々の声を作品にしてきた人でもある。 そんな絶望の淵にいる人々を見てきた彼女が、 「絶望を救うのは日常

私たちはなぜ学ぶのか(9)ー「自転車が乗れた時のように、何かが身についた前と後では風景が変わる」その新しい世界を観る喜びのため
(2022年12月11日付 朝日新聞「知は力なり」慶応大学教授(物理学) 松浦壮氏の言葉から) 「学ぶ」ということは、 「ひとたび自転車に乗れてしまったら、自転車に乗れない自分を想像できないように、何かが本当の意味で身についた前と後では風景が変わってしまうということである」 松浦氏は、幼い頃父親から教えられた数字の不思議に触発され、数の世界への【眼】が開いたと言う。 ー父親の話というのは、2+4=6、6÷2=3、2と4の間の数字は3。「足して半分にするといつも真ん中の