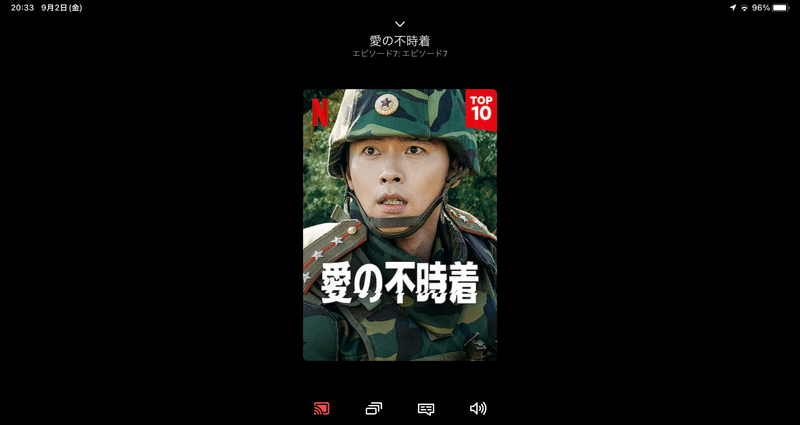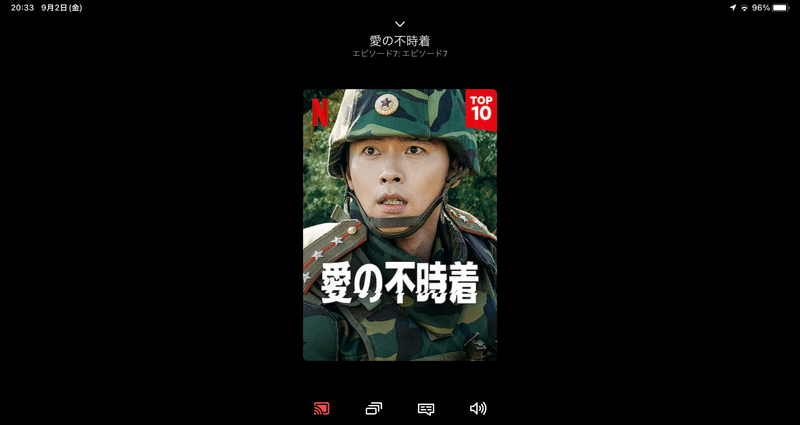「私たちはなぜ学ぶのか?」(1)ー自分に見えないことがあると知ること
ー学ぶことの意義はたくさんありますが何より「自分に見えないことがあると知ること」だと思います。ネットはアルゴリズムに左右されているので、自分が思っていることしか出てきません。アンテナを張って学ばないと、「自分がこう思いたい」情報しか手に入らず、世界観が狭くなってしまう。違う意見を持っている人が見えなくなると、許容度がどんどんなくなっていきます。普段は行かないところに行ったり、外の世界に出て他者の意見に触れたりすると、人生が広がります。(2022年7月6日 朝日新聞 「私たちは