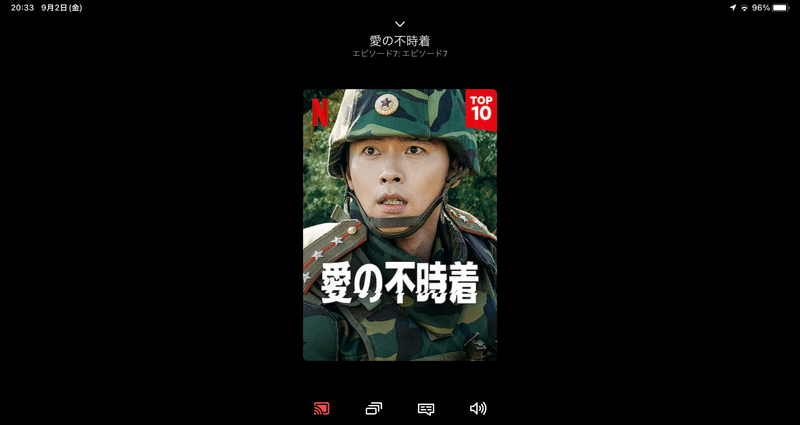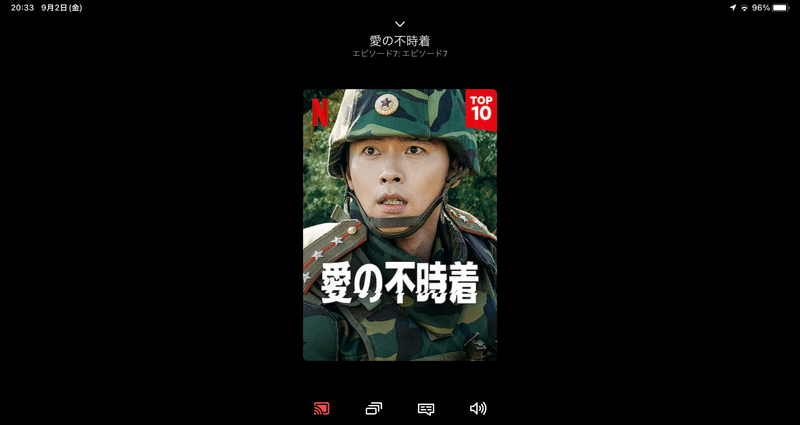今日ときめいた映画159ー黒澤監督作品「生きる」を見る
(タイトル写真はU-NEXTからの転載)
昭和27年制作の映画である。もちろん白黒映画で、薄暗い市役所の一室で働く一人の男の話である。この作品を見ようと思ったきっかけは、この映画のリメイク版が英国で作られ(タイトル“Living”)、脚本を書いたのがイシグロカズオであることに興味を持ったからである。作品についてのインタビューで、彼は自分の脚本をオリジナルから少し変更したと語っていたのでまずはオリジナルを見てみようと思ったのだ。
日本生まれで英国育ちのイシグロカズオは日本の