
これから楽しみ
どう指導してらっしゃる??
寄り添うことの難しさ
最近、ある小学校のタグラグビーの指導に携わっている。
なかなか全国大会が手に届かず、悔しい思いをしている。
そんな中でコーチとして招集してくれたのは、とてもありがたい。
ただ、私はタグラグビーはほとんど経験がない。未経験に近い。
コンタクトがない中、さらに人数も少ない中どうしていくのか。
正直、指導当初はかなり悩んだ部分もあった。
寄り添うことが難しい……というか、寄り添えないのではないかとも思ったが、選手としてはいざというときに監督やコーチに頼れないのは辛い。
(今までの自分自身の経験から……)
であれば、やはり寄り添えるように自分自身が変わらなければならない。
ラグビーとタグラグビーは似て非なる部分が多々ある。
コンタクトはないし、コートも小さい。ルールも多少違う。
身体を張って背番号を取ってきた自分にとっては、しっかりとした指導ができるのか……不安があった。
試合を観て、基礎を学んで
分からないなら分からないなりに、試合を何度も観た。
コーチングを始めてすぐに、遠征があったのが救いだった。
子どもたちの試合を後ろから、横から、前から観て、立体的にどのように動いているのかを考える。
子どもたちが何を考えて攻めて、守っているのかをコミュニケーションを大事にしながら、ハーフタイム時に聞いた。
さらに基礎となるルールも勉強した。
どこまでがセーフでグレーなのか。アウトの境目も見込んで学んだ。
ルールと言っても座学だけでは分からない。学んだら観るし、プレーする。

ラグビー以上にコミュニケーションが必要かもしれない……
学んでいくうちにタグラグビー≠ラグビーではなかった。
通じる部分もあるし、やはり大本はラグビーだから戦術として似ている部分もあることに気が付き始めた。
とにかく基礎、基礎、基礎‼
そこが足りないのだと、私自身も感じ始めた。
基礎から応用へ
基礎徹底の難しさ
とにかくタグラグビーは、タグが取られるまでの4回の攻撃しか認められていない。ラグビーみたいにスローテンポにできない難しさがある。
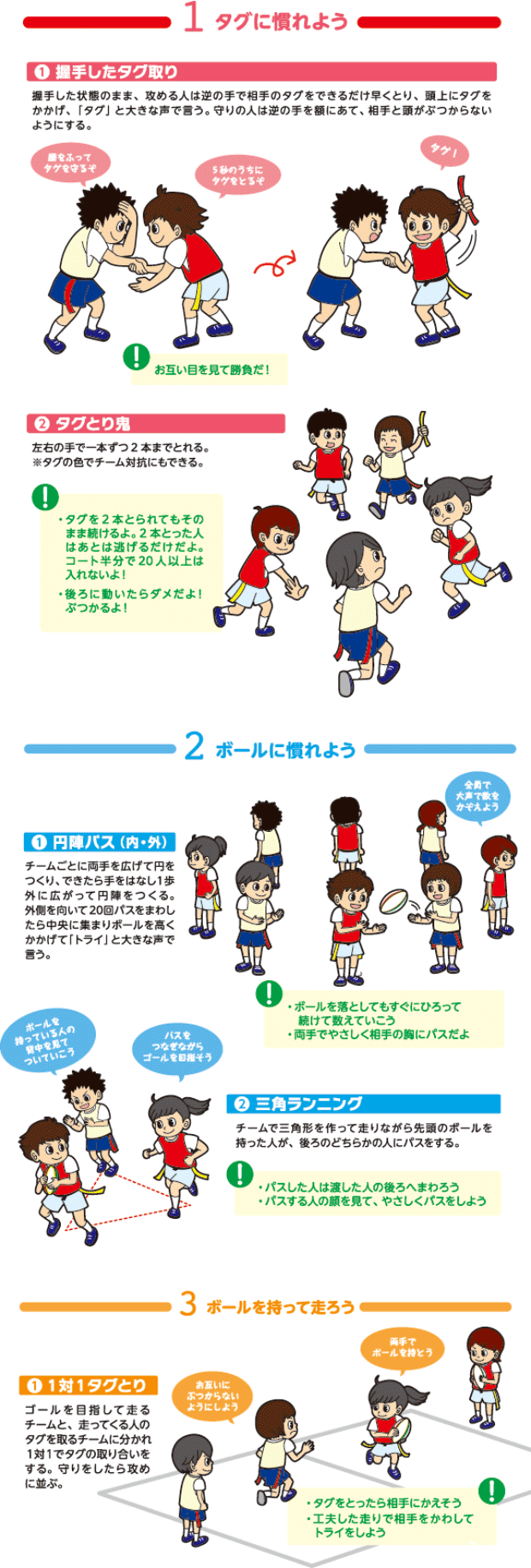
とにかく基礎を叩き込んでいくところから……
しかし、スローテンポにできずともできることはある。
タグをしっかり見て取る、相手がボールを落としたら拾ってすぐにパスでつなぐなど、とにかく基礎を徹底して今もやっている。
少しずつではあるが、ボールがつながる場面が増えてきた。
私自身も基礎の徹底は難しい。
それでもこれからの子どもたちのために、身につけさせていきたい。
全国大会へ向けて
まだまだシーズンはこれから。
今年こそは、何とか全国大会まで行かせてやりたい。
だが、その気持ちが空回りしてもダメだ。しっかり子どもたちの意向にも耳を傾けながら、一緒になってチームを構築していく必要がある。
今の私の立場は、とても楽しい。
子どもたちに教える立場であることは、教員時代と何ら変わりはないが、対話をしながら、意向を聞きながら私自身も考えるこの過程が楽しい。
一緒になって築き上げていくことの大切さを身に染みて感じている。
これから合宿や遠征も予定されているとのこと。
勝ち負けは大事ではあるが、それ以上に大事なのは子どもたちがこの競技から何を得たのかということ。これからの糧になること。
時には考えさせ、悩ませることもあるだろう。
しかし、私自身は最適解を提示できるよう、しっかり学んでいきたい。
それが選手とコーチの間柄では必要になることだと思うから――。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
