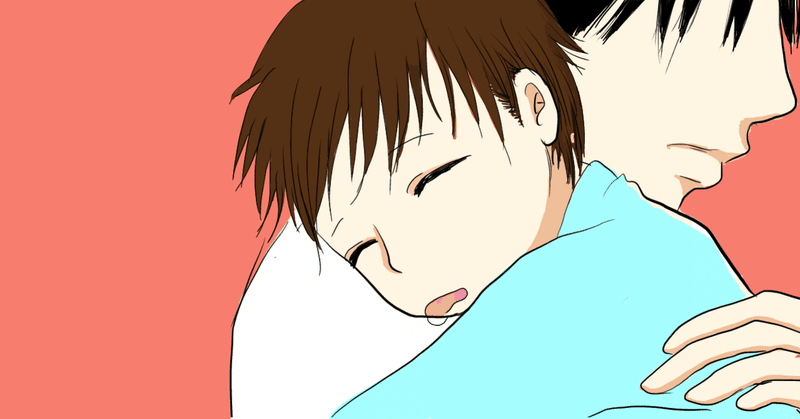
口の中に苦虫
妹から渡された“お迎えカード”。
なにかあったときのための、念の為。
俺が駆り出されることはないはずだった。
その日は、小さなことが積み重なった日。
いつも迎えに行く妹が37.5度の微熱を出し、行けなくなった。
義弟は日帰り出張で、今から戻っても間に合わない。
近くに住む父や母は、珍しく夫婦旅行に出かけている。
電話口の二三の声には、苦渋があった。
「お兄ちゃん、保険としてお願いしていた“お迎えカード”を行使するときが来てしまいました。……頼れる人はお兄ちゃんしかいません。舞流人(まいるど)のお迎えに行ってもらえないでしょうか」
生まれてこの方、二三に敬語をつかわれた覚えのない俺は、妹が敬語をつかえることに安堵した。
「お前、敬語つかえたんだな」
「はあ? 当たり前でしょ! 私のこと、なんだと思ってんの?」
頼み事をする態度ではないが、それは置いておくとする。
「迎えには行けるが、なんでそんなに嫌そうなんだ? なんかあるのか」
「お兄ちゃんに頼むのが嫌なだけ」
「なんだよ、まだ根に持ってんのか。あれはたまたまそういう気分だっただけだろ。本気じゃない」
「当たり前でしょ! 舞流人の家族は私たちでお兄ちゃんじゃないんだから!」
言い終わるか終わらないかのタイミングで回線は切れた。
“あれ”とは一ヵ月前、妹の家でのこと。虫が苦手な妹夫婦に代わり甥っ子の虫取りに付き合い、時給代わりの晩飯をもらうと、いつも通り帰ろうとした。
「おいさん、どこいくの? まいーどとおふろはいろ?」
「おいさん帰る時間なんだ。また今度な」
「……まってるひといる?」
「あ? いや一人だよ。お前も来たことあるだろ」
こそばゆいほど柔い髪をひと撫でし、「またな」と帰ろうとした。
「やっ!」
振り向くと抱き抱えていたカエルのぬいぐるみを放り投げ、靴を履こうとしている。
舞流人の叫び声を聞きつけて、義弟と、遅れて二三がダイニングから顔を出した。
「なにしてんの?」
俺の裾を右手で握り、左手だけで靴を履こうとしているから一向に進まない。
「まいーどもいっしょにかえる」
「は?」
「まいーど、おいさんちのこになる」
「なに言ってんだ!」
びびったのは舞流人だけじゃない。俺も、二三も、義弟の聞いたことのない怒号に肩を震わせた。
いつも穏やかで、口数の少ない2歳上の義弟。その彼が、はっきりとした敵意を目に湛え、俺を睨んでいる。
「……パパ?」
震える声で呼ぶ息子を目にし、我に返った義弟はすぐに謝ってきた。仕事が忙しくて心に余裕がなかったのだと、何度も頭を下げた。それが理由じゃないことは、舞流人以外みんなわかっていた。だから笑顔で別れた後、近づかないようにしたのだ。
ケータイの地図アプリで検索しつつ、初めてのお迎えに向かった。
「あれえ? おいさん?」
気のせいだろうか、ちょっと見ない内に大きくなった気がする。
「おう」
怪訝そうな先生に“お迎えカード”を見せると、警戒心が目に見えてとけた。こんなペラペラの紙が不審者か否かを分けるのだ。今の俺にとっては、ハローワーク並みに近づきたくない場所だ。
「ちょっとまってえ」
ここから早く離れたい俺は、じりじりと距離をあけていたらしい。舞流人は、置いていかれないよう呼びかけながら、一生懸命靴を履いている。
「帰るぞー」
先を歩き出した俺に小走りで追いつくと、薬指と小指を握り込んでくる。
「おいさん」
「んー」
「こうえんいく?」
「今からかー? お前のママ心配してるしなぁ」
最前の二三の言葉が脳裏に浮かぶ。
“舞流人の家族は私たちでお兄ちゃんじゃないんだから!”
口の中が、なんだか苦い。
「……たまにはいっか」
「いく? こうえんいく?」
期待でほっぺをぴかぴかさせている甥に苦笑しつつ、俺は頷いた。
電話がひっきりなしにかかってきている。
面接の合否連絡ではない、めっきり音信不通の恋人からでもない、もちろん二三からだ。
舞流人が目をつけていたらしい、幼稚園の帰り道にあるブランコと滑り台だけの小さな公園。
俺はベンチに座り、誰もいない公園を眺めている。舞流人はアリの行列についていき、ツツジの裏で這いつくばっている。
「なあー」
「なーに」
ひょっこりとツツジの間から顔を出し、膝にのしかかってくる。
「おいさんちの子になるか?」
脇に手を入れ抱き上げると、膝に乗せる。
「いいよぉ。おいさんをほかのこがもってかえったらたいへんだもんね! まいーどがおうちでまっててあげる!」
「ん?」
意味のわからない同意に俺は首をかしげた。
「ほら、おいさん! だんごむし!」
甥の一番好きな虫を鼻の先に出され、過去のやりとりが脳裏に浮かんだ。
捕まえた虫を持って帰ると、舞流人が大泣きしたときのことだ。
『幼稚園のお友達も連れて帰ってるのか?』
『みいくんもけんちゃんもおうちがあるもん。ママとパパがまってるんだよ』
『こいつらにも帰る場所はあるんだぞ。なんで誰も待ってないって思うんだ?』
「おいさんのこと、みいくんもほたるちゃんもいいなっていってるからね。とられないようにだいじにだいじにしなきゃ」
「……けんちゃんどこ行った?」
「けんちゃんはもういいの! ぜっこうしたんだから!」
途端にぷりぷりしている。喧嘩したことでも思い出したのだろう。
「ふうん。……ところで俺は叔父さんであって、ゲームのモンスターじゃないぞ」
「しってるよー! おいさん、かわいくないもん!」
「あっそ。……そろそろ帰るか、腹へったろ?」
「うん! おいさん、だっこ!」
膝の上の舞流人は両手を広げて待っていたが、買っておいたミネラルウォーターで土だらけの手を洗ってから抱き上げる。はしゃぎ疲れたのか、舞流人はすぐに寝つき、寝息を立てはじめた。
だいだい色の空の中、温もりを抱え、初めての家路を歩く。
早晩妹夫婦の嫉妬は消えるだろう。
義弟はしばらく気まずそうな顔をするかもしれない。
二三はけろっとして、虫に関するあれこれを変わらず押しつけてくるに違いない。
ほっとしたような、それでいて口の奥が苦いような。
「まあ、そうだよなぁ」
俺のかごは空っぽのまま、いつも通り帰るとしよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
