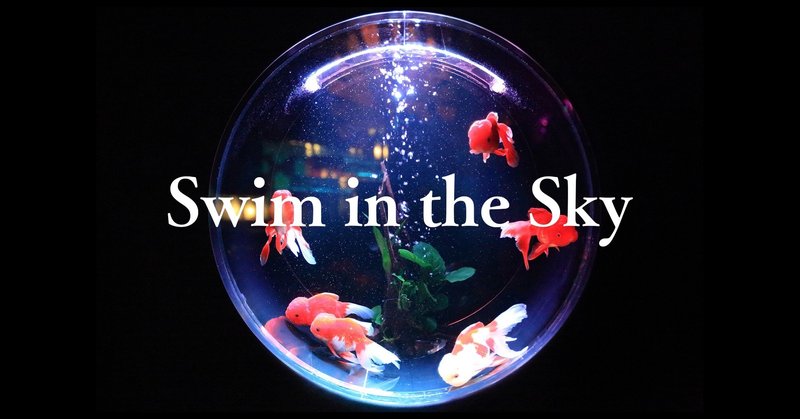
新連載小説 | Swim in the Sky - ep2
「俺の仕入れた情報によると、工藤亜里香は今、六本木にいる」
カメラのレンズを調整しながら、助手席に座る安東が言った。運転手より先に乗り込みすでに寛いでいる彼は、四十を超えているにも関わらず今でも若い女の子と楽しく遊び、そこから得た情報を余すことなく活用しているような男だ。やっと成人したような女の子達にとっては、この若々しくて、かつどことなく謎めいたワルい雰囲気が魅力なのだろうか。一日中重量のあるカメラを握っているだけあって、上腕二頭筋はしなやかに膨らんでいる。
環状線に車を乗り入れ、皇居の横をすり抜けていく。平日の夜、もうすぐ日を跨ぐというのに、カラフルなスポーツウェアを着た男女が談笑しつつ、軽やかに駆けていった。
工藤亜里香は、最近事務所のゴリ押しで売れ始めたモデル上がりの若手女優だ。演技が上手いとはとても言えないにも関わらず、次々に主役やヒロインの座を射止め、今期で三期連続主役を張っている。
そこが、安東のアンテナに引っかかった。この人は本当にそういう勘が働く。
「これは大物が釣れるぞぉ」と嫌な笑みを浮かべたとき、すっかりバディ扱いを受けている俺は頭を抱えた。これは掴むまで絶対に帰れない。
週刊誌の編集部に来て半年。安東と俺が組むのは三件目になる。
新卒で入った出版社を辞め、路頭に迷いそうになっていたところを、知り合いの伝手でこの会社に拾われた。前職では、思いっきりお堅い文芸雑誌の部署にいたが、疲れ果てた俺は、ここなら紹介できるけどどうするか、と声をかけてくれたその人に、力なく「似たような仕事ならなんでもいい」と二つ返事で答えた。その時の俺は、なんというか、文芸雑誌以上に辛い現場などないとさえ思っていて、芸能人や政治家の裏の顔を追いかける今の仕事の実情などろくに想像ができていなかった。脳みそが疲労でしっかりと起動できていなかったのかもしれない。
そうやって入社してしばらくは他の人の仕事の世話をしたり、記事をまとめたりするのが主な仕事で、オフィスで穏やかに過ごすことができていたが、現場に駆り出されるまでにそう時間は掛からなかった。常に人手不足。当たり前だが過酷な仕事だった。アンカーマン採用だったはずが、今や昼も夜もなくターゲットを追い続け、その隙間で情報収拾をし、写真が撮れたらすぐに記事を書く日々だ。いかに早く信ぴょう性の高い情報を世に出すかが大事で、ウェブ版もできた今じゃ戦況は一秒ごとに変わっていく。ライバル誌に先を越されればそれまでの苦労はすべて水の泡になるシビアな世界だ。
そんな中でこの安東とタッグを組んで掴んだのが、とある人気俳優の不倫だった。
それはもう大スクープだ。清潔で知的なイメージのある、これ以上ないほど好感度の高い彼が、実は結婚し、子供もいる三歳年上の女優とデキていた。
二人は、あっという間にドラマはもちろん、CMも、司会を務めていたバラエティ番組やラジオ番組まで降板。天から地へ堕ちていった。
何日も何日もつらい張り込みをして、やっとの思いで上げた成果だったから、彼らの不幸には御愁傷様と手を合わせて、俺たちは珍しく祝杯を上げた。
だが、問題はそのあとだった。旨い酒をたらふく呑んで、前後不覚になりながらたどり着いた我が家のダイニングには、見慣れない紙がポツンと置いてあった。
ぐらぐらと揺れる頭を抑えて必死に焦点を合わせ手に取ると、それは紛れもなく離婚届だった。右の欄はもちろん、ご丁寧に証人の欄までしっかり埋まっている。名前は、俺に妻、いや元妻を紹介した大学の同期とその妻の名前だった。
ソファに体を埋めて、なんだっけ、と呟く。
カーテンの隙間から差し込む朝日がちょうど自分の顔に差し掛かって煩わしかったが、その時はそのまま眠りこけてしまった。夢の可能性にも縋ってみたかった。
何時間経っただろう。目が覚めると、すっかり陽は傾き、窓から差す光はオレンジ色を帯びていた。
自身はというと、頭蓋骨の内側が独自のリズムで脈打ち、不快感はマックスまで跳ね上がっている。体はドロドロ、顔も脂でドロドロだ。何日も家に帰らずに走り回っていたのだから当然だ。身体中が鉛のように重かった。
胃酸が逆流してきそうな雰囲気を察知して、急いで洗面所に駆け込むと、体の奥から酸っぱいものが吹き出て、突然我に返った。
そうだ、離婚届……。
酔った勢いで見た幻想かもしれないと思いつつ、リビングに戻ると、それはソファの下に虚しく倒れ込んでいた。拾い上げるとやはり彼女と友人達の名前が並んでいる。
妻と出会ったのは、五年ほど前。まだ文芸部で働いていた頃だ。
日々忙しなく働き、職場には出会いもない。それならと友人が紹介してくれたのが、彼女、水瀬由紀だった。肌は白く黒髪のロング、顔は華やかで美しく、趣味は読書というから期待した。
初めて会ったのは、友人が用意してくれた席で、銀座のお洒落なカフェバーだった。もちろん初めて行った場所だったし、慣れない雰囲気に戸惑ったが、気さくで笑顔を絶やさない彼女に俺はすぐに惹かれた。
二人で会うようになって、趣味の読書が実はラノベや漫画の類だったことがわかり、それはお互いに全く好みが合わないという誤算になったが、それを抜いても一緒にいれば楽しく、つまらない仕事の話さえ笑顔で聞いてくれるので、会話はいつも弾んでいた。
彼女はいつも積極的で、次々にデートの約束を取り付け、あれよあれよと言う間に結婚というゴールまで駆け上がった。俺は、結婚対して特別な願望はなかったが、仕事も忙しかったし、彼女が望むならそれがいいだろうと、半ば思考停止のいいなりで判を押した。
だが、後悔はなかった。それほど多くの時間一緒にいられないでいても、彼女は文句ひとつ言わず、一人の時間も楽しんでいるようだったから安心しきっていた。仕事を辞める際にはひどく反対されたが、転職しても収入は変わらないからと言いくるめ、納得させたつもりでいた。
なぜだろう……。
ゴンゴンと銅の鐘が鳴り響く頭では考えがまとまらず、またソファに沈み込む。ローテーブルの上にあったリモコンでテレビを点けると、先ほどまで祝杯を上げていたネタについて、コメンテーターが意見を交わしていた。
「素敵な俳優さんだと思っていたのに、残念です」、「お子さんもまだ小さいのに」、「不倫はダメだ。最近こればっかりなんだから、もうわかってただろう」。大して知らないくせに、好き勝手な物言いで論を飛ばす彼らに、ため息が漏れる。
「インターネットでは擁護する声もあるようで――」そうアナウンサーが言うと、アイコンにモザイクがかけられたツイッターのスクリーンショットが何件か映し出された。ファンのツイートだろうか、早く帰ってきて、と彼らを求める悲痛な叫びが羅列した。
そういえば、彼女もこの俳優をかっこいいと言っていたな。
ブブッ
マナーモードにしたままのスマートフォンがローテーブルで振動し、ガラスを鳴らした。手を伸ばして、通知を開くと、それは彼女からのラインだった。
「離婚届見た?」
絵文字も何もない、素っ気ない一言だった。
「そういうことだから」
「私、人の不幸を食い物にしているあなたのこと、もう好きでいられない」
「もう、限界なの」
返信をする間も無くポンポンと送られてくるメッセージに、あぁこれは話し合いすらできない決定事項なのだと察する。始まりに決定権がなかったように、終わりにもないのだ。
「あんなに素敵な人をダシにするなんて、信じられない」
「人にも言えない仕事を旦那さんがしてるなんて無理」
「元の出版社に戻るなら、許せるけど……」
その後もメッセージは次々に送られて来た。既読がつくから、読んでいることは伝わっているのだろう。謝罪も反省もしない俺に業を煮やしているのかもしれない。
最後の言葉なんて顕著だ。彼女は週刊誌で働いている俺は嫌で、元の大手出版社の文芸部で働いている俺が好きなのだ。
そう思ったら、合点がいった。俺は彼女にとって愛する夫ではなく、人に自慢できる良好物件だったに過ぎない。
思考がそこに至ると、途端に冷めた。幸い俺たちには子供もいないし、俺は戸籍にバツがつこうが構わない。元来独りでいることを寂しいと思うタイプでもないし、彼女もまだ三十を超えたところだ、おそらく次を見つけるのは容易いだろう。
俺は、彼女からの通知の音を聞きながら、手早く欄を埋め、その日のうちに区役所に離婚届を提出した。
サポートしようかと心の隅の方でふと思ってくれたあなた!ありがとうございます!毎日夜のカフェでポリポリ執筆してるので、応援してくれたらうれしいな!なんて思ったりしてるよ!
