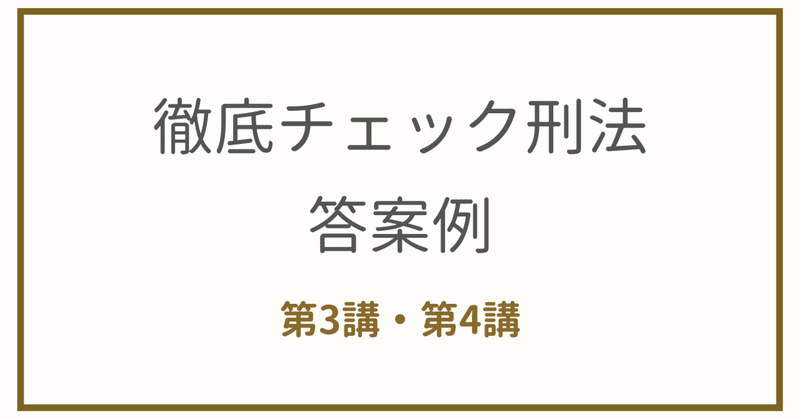
【徹底チェック刑法答案例】第3講・第4講
この記事では、「徹底チェック刑法(有斐閣)」の答案例を掲載しています。答案例は、同書、第0講「刑法の事例問題への取り組み方」において述べられている答案作成の基本、及び各講の解説内容に準拠して、一貫したフォーマットで作成しています。
内容には細心の注意を払っておりますが、正確性を担保するものではない点についてご了承ください。
刑法論文の書き方については、以下の記事もご参照ください。
第3講 故意
事例1 (1)
1. Xが、溺れているAを助けにいかなかった行為について、殺人罪(刑法199条)の成否を検討する。
2. Xの行為は不作為であるところ、このような不作為に実行行為性が認められるか。
(1) 不真正不作為犯における行為は、作為による構成要件実現と同視できる場合にのみ、実行行為性が認められると解する。具体的には、作為義務の存在及び作為の可能性・容易性が必要である。
(2) Aの親であるXには、泳いでAを救助するという作為義務が認められる。また、Xは泳ぎが達者であったことから、作為の可能性・容易性も認められる。
(3) よって、Xの不作為には、殺人罪の実行行為性が認められる。
3. Aは死亡しており、殺人罪の結果も発生している。また、Xが助けにいっていれば、Aが助かることは確実であったことから、Xの不作為と、Aの死亡という結果との因果関係も認められる。
4. では、Xに殺人罪の故意(38条1項本文)が認められるか。
(1) 故意とは、客観的構成要件を基礎づける事実についての認識又は認容をいう。
(2) Xは、今から泳いで助けにいっても到底間に合わないと考えていたことから、客観的構成要件のうち実行行為性を基礎づける作為の可能性についての認識がない。
(3) よって、Xに殺人罪の故意は認められない。
5. 以上から、Xの行為には殺人罪は成立しない。
事例1 (2)
1. Xが、溺れているAを助けにいかなかった行為について、殺人罪(刑法199条)の成否を検討する。
2. Xの行為は不作為であるところ、このような不作為に実行行為性が認められるか。
(1) 不真正不作為犯における行為は、作為による構成要件実現と同視できる場合にのみ、実行行為性が認められると解する。具体的には、作為義務の存在及び作為の可能性・容易性が必要である。
(2) Aの親であるXには、泳いでAを救助するという作為義務が認められる。また、Xは泳ぎが達者であったことから、作為の可能性・容易性も認められる。
(3) よって、Xの不作為には、殺人罪の実行行為性が認められる。
3. Aは死亡しており、殺人罪の結果も発生している。また、Xが助けにいっていれば、Aが助かることは確実であったことから、Xの不作為と、Aの死亡という結果との因果関係も認められる。
4. では、Xに殺人罪の故意(38条1項本文)が認められるか。
(1) 故意とは、客観的構成要件を基礎づける事実についての認識又は認容をいう。
(2) Xは、親でも子どもを助ける義務はないと考えていたものの、自身の子どもが溺れているという、作為義務を基礎づける事実自体は認識していた。また、その他の客観的構成要件を基礎づける事実について認識を欠くこともない。
(3) よって、Xに殺人罪の故意が認められる。
5. したがって、Xの行為は殺人罪の構成要件に該当する。
6. もっとも、Xには義務の存否について錯誤があることから、責任故意が阻却されないか。
(1) 原則として違法性の意識の有無は故意に影響を与えないものの、責任主義の見地から、違法性の意識を欠くことにつき相当の理由が認められる場合には、責任故意が阻却されると解する。
(2) Xの錯誤は、親でも子どもを助ける義務はないというものであるところ、親が子どもの監護義務を負うことは民法上も規定されている(民法820条)。したがって、Xが違法性の意識を欠くことについて相当の理由は認められない。
(3) よって、責任故意は阻却されない。
7. 以上から、Xの行為には殺人罪が成立し、Xはその罪責を負う。
事例2 (1)
1. Xが、肉用ナイフでAの腹部を2度刺した行為について、殺人未遂罪(刑法203条、199条)の成否を検討する。
2. Xは、刃渡り12cmほどの鋭利な肉用ナイフでAの腹部を2度刺しており、この行為には人を死亡させる危険性があることから、殺人罪の実行行為が認められる。もっとも、Aは病院に搬送され、一命をとりとめていることから、死亡という結果は発生していない。
3. では、Xに殺人罪の故意(38条1項本文)が認められるか。
(1) 故意とは、客観的構成要件を基礎づける事実についての認識又は認容をいう。
(2) Xが使用した凶器は刺突すれば人に致命傷を負わせるのに十分なものであり、Xはその凶器を実際に刺突の態様で用いてAの腹部を2度も刺している。腹部という人体の枢要部への刺創は死亡結果を発生させる可能性が高く、2度刺していることからすれば、Xが刺創によってAが死亡する高度の可能性を認識していたことを推測させる。また、XはAから罵倒を毎日受け続け、犯行直前に嘲笑されていたことから、Xが憤怒して突発的にAに対して殺意を抱いたとしても不自然はない。なお、Xは犯行後に救急車を呼んでいることから、その時点ではAが死亡することを望んでいなかったとはいえるものの、犯行時にAを殺害するつもりがなかったことを直ちに意味するものではない。
(3) よって、Xには殺人罪の故意が認められる。
4. したがって、Xの行為は殺人未遂罪の構成要件に該当する。
5. もっとも、Xは刺突後に救急車を呼んでおり、その結果としてAは一命をとりとめていることから、中止犯(43条ただし書)が成立しないか。
(1) 「犯罪を中止した」というためには、結果惹起の危険性を消滅させる行為が必要である。Xには、Aの死亡という結果を回避するために自分の携帯電話で救急車を呼ぶという積極的作為が認められる。よって、同要件を充足する。
(2) 「自己の意思により」とは、中止が外部的障害により強制されていないことをいう。Xは、自分のやったことが怖くなり、外部的事情によらず自らの意思で救急車を呼ぶという中止行為に及んでいる。よって、同要件を充足する。
(3) したがって、Xには中止犯が成立する。
6. 以上から、Xの行為には殺人未遂罪が成立するが、中止犯として刑が必要的に減軽される。
事例2 (2)
1. Xが、鉄パイプをAに向けて振り回した行為について、殺人罪(刑法199条)の成否を検討する。
2. Xは、鉄パイプをAに向けて振り回しており、この行為には人を死亡させる危険性があることから、殺人罪の実行行為が認められる。また、Aは鉄パイプが頭部に当たり死亡しているため、殺人の結果発生及び実行行為と結果の因果関係も認められる。
3. では、Xに殺人罪の故意(38条1項本文)が認められるか。
(1) 故意とは、客観的構成要件を基礎づける事実についての認識又は認容をいう。
(2) 鉄パイプのような形状の鈍器は頭部に当たらない限り死亡結果をもたらず可能性は高いとはいえず、また、Xの行為はAからの攻撃に対して咄嗟に一度行われたもので、Aの頭部を狙ったものではない。さらに、犯行に至る経緯も、Aから因縁をつけられ工事現場に連れていかれて殴りかかられたという、受動的で偶発的なものである。したがって、Xに、殺人罪を基礎づける事実の認識があったとはいえない。
(3) よって、Xに殺人罪の故意は認められない。
4. 以上から、Xの行為には殺人罪は成立しない。
5. 続いて、同行為について、傷害致死罪(205条)の成否を検討する。
6. Xは、鉄パイプをAに向かって振り回すという有形力の行使を行っており、その結果としてAに傷害が発生し、最終的に死亡しているため、同罪の客観的構成要件該当性が認められる。
7. また、Xには、鉄パイプをAに向かって振り回すという暴行の認識があるため、故意が認められる。
8. したがって、Xの行為は傷害致死罪の構成要件に該当する。
9. もっとも、Xは、Aが殴りかかってきたことから反撃として同行為に及んでいるため、正当防衛(36条1項)として違法性が阻却されないか。
(1) 「やむを得ずにした」とは、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有することをいう。Xは、素手で殴りかかってきたAに対し、咄嗟とはいえ鉄パイプで反撃行為に及んでいることから、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当とはいえない(※)。
(2) よって、Xに正当防衛は成立しない。
10. 以上から、Xの行為には傷害致死罪が成立し、Xはその罪責を負う。
※ 問題文中には記されていませんが、年齢差や体格差といった事情によっては、同じ状況の下でも相当性が認められることがあります。
第4講 錯誤
事例1 (1)
1. Xが、Bを銃撃した行為について、殺人罪(刑法199条)の成否を検討する。
2. Xは、Bを銃撃しており、この行為には人を死亡させる危険性があることから、殺人罪の実行行為が認められる。また、Aは銃撃により死亡しているため、殺人の結果発生及び実行行為と結果の因果関係も認められる。
3. Xは、殺意をもってCを銃撃していることから、殺人という罪を犯す意思がある。もっとも、Xは、CをBと間違えて銃撃しているが、この錯誤により故意(38条1項本文)が阻却されないか。
(1) 故意とは、客観的構成要件を基礎づける事実についての認識又は認容をいう。そして、行為者が認識した事実と発生した事実が異なっていても、それらが法定の構成要件の範囲内で一致していれば、構成要件の実現を思いとどまることは可能であることから、故意は認められると解する。
(2) Xは、Bを銃撃するつもりでCを銃撃しているが、Xが認識した事実と発生した事実のいずれも殺人罪の構成要件の範囲内で一致していることから、Xには故意が認められる。
4. したがって、Xの行為は殺人罪の構成要件に該当する。
5. 以上から、Xの行為には殺人罪が成立し、Xはその罪責を負う。
事例1 (2)
1. Xが、A、B、及びDを銃撃した行為について、殺人未遂罪(刑法203条、199条)の成否を検討する。
2. Xは、A、B、及びDを銃撃しており、この行為には人を死亡させる危険性があることから、殺人罪の実行行為が認められる。もっとも、発射された弾はBには命中せず、Aの腹部をかすめ、その後命中したDも瀕死の重傷を負ったにとどまるため、死亡という結果は発生していない。
3. Xは、殺意をもってBを狙って銃撃していることから、殺人という罪を犯す意思があるといえ、Bに対する故意(38条1項本文)が認められる。もっとも、Xは、Bのみを狙うつもりで、AとDに対しても銃撃しているが、AとDに対する故意も認められるか。
(1) 故意とは、客観的構成要件を基礎づける事実についての認識又は認容をいう。そして、行為者が認識した事実と発生した事実が異なっていても、それらが法定の構成要件の範囲内で一致していれば、構成要件の実現を思いとどまることは可能であることから、故意は認められると解する。また、構成要件のレベルで故意を抽象化して考える以上、一つの故意犯を選び出すことは理論上無理があるため、認識していない事実が複数発生した場合には、発生した事実それぞれについて故意犯が認められる。
(2) Xは、Bを銃撃するつもりでA、B、及びDを銃撃しているが、Xが認識した事実と発生した事実のいずれも殺人罪の構成要件の範囲内で一致していることから、3名それぞれに対して故意が認められる。
4. したがって、Xの行為は殺人未遂罪の構成要件に該当する。
5. 以上から、Xの行為にはA、B、及びDに対する殺人未遂罪が成立し、それらは観念的競合(54条1項前段)となる。
事例2
1. Xが、Aを銃撃した行為について、殺人未遂罪(刑法203条、199条)の成否を検討する。
2. Xは、Aを銃撃しており、この行為には人を死亡させる危険性があることから、殺人罪の実行行為が認められる。もっとも、発射された弾はAには命中せず、死亡という結果は発生していない。
3. Xは、殺意をもってAを銃撃していることから、殺人という罪を犯す意思があるといえ、故意(38条1項本文)が認められる。
4. したがって、Xの行為は殺人未遂罪の構成要件に該当する。
5. 以上から、Xの行為には殺人未遂罪が成立する。
6. 次に、同行為について、器物損壊罪(261条)の成否を検討する。
7. Xは、Aの飼い犬Bを銃撃しており、この行為にはBを傷つける危険性があることから、器物損壊罪の実行行為が認められる。また、Bは銃撃により死亡しているため、器物損壊の結果発生及び実行行為と結果の因果関係も認められる。
8. では、Xに器物損壊罪の故意が認められるか。
(1) 故意とは、客観的構成要件を基礎づける事実についての認識又は認容をいう。そして、罪刑法定主義及び責任主義の観点から、認識した事実と発生した事実が異なる構成要件に該当する場合は、原則として故意が阻却される。もっとも、それらの構成要件が重なり合う場合は、その限度で構成要件の実現を思いとどまることは可能であることから、例外的に故意が認められると解する。
(2) Xが認識した事実である殺人罪の保護法益は人の生命である一方、発生した事実である器物損壊罪の保護法益は財産であり共通性はない。したがって、両者の構成要件に重なり合いは認められない。
(3) よって、Xに器物損壊罪の故意は認められない。
9. 以上から、Xは殺人未遂罪の罪責を負う。
事例3 (1)
1. Xが、Aからコカインを購入した行為について、コカイン譲受け罪(麻薬及び向精神薬取締法66条1項)の成否を検討する。
2. Xは、Aからコカインを購入していることから、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、…譲り受け…た者」に該当する。
3. では、Xにコカイン譲受け罪の故意(刑法38条1項本文)が認められるか。
(1) 故意とは、客観的構成要件を基礎づける事実についての認識又は認容をいう。そして、罪刑法定主義及び責任主義の観点から、認識した事実と発生した事実が異なる構成要件に該当する場合は、原則として故意が阻却される。もっとも、それらの構成要件が重なり合う場合は、その限度で構成要件の実現を思いとどまることは可能であることから、例外的に故意が認められると解する。
(2) Xが認識していた事実は覚醒剤の購入であり、発生した事実はコカインの購入である。そして、それらは違法薬物の譲受けという点で行為態様が共通し、それぞれを取り締まる規定の保護法益も、違法薬物の濫用を防止し、薬物の蔓延を防ぐという点で共通する。したがって、両者には、軽いコカイン譲受け罪の限度で構成要件の重なり合いが認められる。
(3) よって、Xには、コカイン譲受け罪の故意が認められる。
4. したがって、Xの行為はコカイン譲受け罪の構成要件に該当する。
5. 以上から、Xの行為にはコカイン譲受け罪が成立し、Xはその罪責を負う。
事例3 (2)
1. Xが、Aからヘロインを購入した行為について、ヘロイン譲受け罪(麻薬及び向精神薬取締法64条の2第1項)の成否を検討する。
2. Xは、Aからヘロインを購入していることから、「ジアセチルモルヒネを、…譲り受け…た者」に該当する。
3. では、Xにヘロイン譲受け罪の故意(刑法38条1項本文)が認められるか。
(1) 故意とは、客観的構成要件を基礎づける事実についての認識又は認容をいう。そして、罪刑法定主義及び責任主義の観点から、認識した事実と発生した事実が異なる構成要件に該当する場合は、原則として故意が阻却される。もっとも、それらの構成要件が重なり合う場合は、その限度で構成要件の実現を思いとどまることは可能であることから、例外的に故意が認められると解する。
(2) Xが認識していた事実は覚醒剤の購入であり、発生した事実はヘロインの購入である。そして、それらは違法薬物の譲受けという点で行為態様が共通し、それぞれを取り締まる規定の保護法益も、違法薬物の濫用を防止し、薬物の蔓延を防ぐという点で共通する。したがって、両者には構成要件の重なり合いが認められる。
(3) よって、Xには、ヘロイン譲受け罪の故意が認められる。
4. したがって、Xの行為はヘロイン譲受け罪の構成要件に該当する。
5. 以上から、Xの行為にはヘロイン譲受け罪が成立し、Xはその罪責を負う。
事例3 (3)
1. Xが、Aから覚醒剤を購入した行為について、覚醒剤譲受け罪(覚醒剤取締法41条の2第1項)の成否を検討する。
2. Xは、Aから覚醒剤を購入していることから、「覚醒剤を、…譲り受けた者」に該当する。
3. もっとも、Xは、コカインを購入する意図しか有していなかったため、軽い罪の認識で重い罪が実現している。したがって、刑法38条2項より、重い罪に当たる覚醒剤譲受け罪は成立しない。
4. では、Xに、軽い罪に当たるコカイン譲受け罪(麻薬及び向精神薬取締法66条1項)が成立するか。
(1) 認識した事実と発生した事実の構成要件が重なり合う場合は、その限度で軽い罪の客観的構成要件該当性を認めても良いと解する。
(2) Xが認識していた事実はコカインの購入であり、発生した事実は覚醒剤の購入である。そして、それらは違法薬物の譲受けという点で行為態様が共通し、それぞれを取り締まる規定の保護法益も、違法薬物の濫用を防止し、薬物の蔓延を防ぐという点で共通する。したがって、両者には、軽いコカイン譲受け罪の限度で構成要件の重なり合いが認められる。
(3) よって、Xの行為はコカイン譲受け罪の構成要件に該当する。
5. 以上から、Xの行為にはコカイン譲受け罪が成立し、Xはその罪責を負う。
事例4
1. Xが、Aの首をネクタイで絞めた行為について、殺人罪(刑法199条)の成否を検討する。
2. Xは、Aの首をネクタイで絞めており、この行為には人を死亡させる危険性があることから、殺人罪の実行行為が認められる。また、最終的にAは死亡していることから、殺人罪の結果も発生している。
3. では、実行行為と結果との間に因果関係が認められるか。
(1) 因果関係は、条件関係を前提として、行為の危険性が結果へと現実化したといえる場合に認められると解する。
(2) まず、XがAの首をネクタイで絞めて失神させなければ、XがAを海から転落させることによりAが溺死することはなかったため、実行行為と結果との間に条件関係が認められる。もっとも、Xが首を絞めた行為からAの死亡までの間に、X自身がAを海に転落させるという介在事情が存在しており、Aはそれにより死亡していることから、実行行為の危険性が結果へと現実化したとはいえないとも思える。しかし、殺人行為後の死体遺棄は、行為者の心理状態からすれば、著しく不自然・不相当ではないことから、XがAの首を絞めた行為がAを海に転落させる行為を誘発し、前者の危険性が後者を介して現実化したといえる。
(3) よって、実行行為と結果との因果関係が認められる。
4. Xは、殺意をもってAの首を絞めていることから、殺人という罪を犯す意思があるものの、実際には海に転落させる行為でAが死亡していることから、因果関係の錯誤がある。
(1) 発生した事実について因果関係が認められ、かつ行為者が、因果関係が認められる因果経過を認識していれば、両者は法定の構成要件の範囲内で一致しているといえ、構成要件の実現を思いとどまることは可能であることから、故意(38条1項本文)は認められると解する。
(2) Xは、Aの首をネクタイで絞めて殺害するという、因果関係の認められる因果経過を認識している。
(3) よって、Xには殺人罪の故意が認められる。
5. したがって、Xの行為は殺人罪の構成要件に該当する。
6. 以上から、Xの行為には殺人罪が成立する。
7. 次に、Xが、Aを車のトランクに入れて海に転落させた行為について、殺人罪(199条)の成否を検討する。
8. Xは、Aを車のトランクに入れて身動きのできない状態で海に転落させており、この行為には人を死亡させる危険性があることから、殺人罪の実行行為が認められる。また、最終的にAは死亡していることから、殺人罪の結果も発生している。
9. もっとも、Xは、死体遺棄罪(190条)の認識しか有していなかったため、軽い罪の認識で重い罪が実現している。したがって、刑法38条2項より、重い罪に当たる殺人罪は成立しない。
10. では、Xに、軽い罪に当たる死体遺棄罪が成立するか。
(1) 認識した事実と発生した事実の構成要件が重なり合う場合は、その限度で軽い罪の客観的構成要件該当性を認めても良いと解する。
(2) Xが認識していた事実は死体の遺棄であり、発生した事実は殺人である。そして、前者の保護法益は死者に対する敬虔感情であるのに対し、後者の保護法益は人の生命であることから、構成要件に重なり合いは認められない。
(3) よって、死体遺棄罪の客観的構成要件該当性は認められない。
11. 同行為について、過失致死罪(210条)の成否を検討する。
12. Xは、Aの生存を看過するという「過失」により、Aを生きたまま海に転落させ、その結果「死亡」させている。
13. したがって、Xの行為は過失致死罪の構成要件に該当する。
14. もっとも、同罪を成立させると死亡結果の二重評価となるため、同罪は殺人罪に吸収されると解する。
15. 以上から、Xは殺人罪の罪責を負う。
参考文献
書き方講座記事のご案内
本noteでは、論文の書き方についてゼロから丁寧に解説した記事を公開しています。これから論文を書き始める方、論文の勉強方法に悩んでいる方はぜひご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
