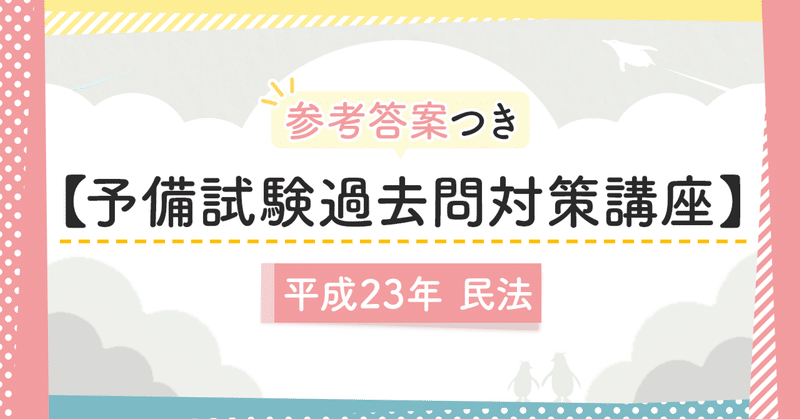
【予備試験過去問対策講座】平成23年民法
はじめに
この記事は「予備試験過去問対策講座」講義記事です。
今回は、平成23年民法を題材に、実際に過去問を解く流れを思考過程から段階的に解説していきます。
予備試験民法の思考方法
はじめに民法の問題一般に共通する思考方法の例を紹介します。ベースは「独学者のための論文勉強法①」で述べた「質問に答える(条文・当てはめ・結論)」、「法律文書としての体裁を整える」の2ステップです。
請求の内容と法律構成の検討
民法の問題は多くの場合、原告の請求がベースにあるため、まずは請求を特定することが重要です。
その前提として、はじめに「請求の主体」、「相手方」を確認します。しっかり読めば間違えることはないですが、後続作業への影響が大きいので確実に押さえます。
続いて、日本語レベルでの「原告(請求の主体)の要望」を確認します。例えば、「お金を返してほしい」や「土地を明け渡してほしい」といった内容がこれに当たります。
慣れてくればいきなり法律構成から始められるのかもしれませんが、検討の中で、原告の要望に応えるという大筋を見失わないようにするためにも、あらかじめ言語化しておくことは重要です。
次に、原告の要望に応えるための「法律構成」を検討します。
当事者間に契約関係があれば、債権的請求から考えます。履行が完了していれば、解除に基づく原状回復請求権や契約不適合に基づく各種請求権等が根拠として考えられます。また、履行が完了していない場合、履行が可能であれば契約に基づいて履行を請求したり、併せて履行遅滞責任を問うケースが多いかと思います。履行が不可能であれば、解除や債務不履行を原因とする請求が候補に挙げられます。
契約関係がなければ物権的請求を検討することになります。試験的には、原告が相手方に対し、自分が真の所有者だと主張し、所有権に基づいて動産の引渡しや、不動産の明渡し等を請求するケースが多いです。
以上の例外として、事故や暴行のように明らかに過失や故意を窺がわせる事情がある場合は、不法行為責任も併せて検討します。また、いずれにも当てはまらないものの、原告の損失や相手方の利益が常識的に納得しがたいものであるときは、不当利得の可能性を疑います(後二者も請求の性質としては債権的請求に当たります)。
いずれの場合も、選択した条文の法的効果が発生した場合に、原告の要望が適えられているのか、という視点を忘れないことが大事です。大外しを避けることができます。
反論の内容と法律構成の検討
相手方の反論(抗弁)を検討します。
原告の請求と同様に、相手方の要望や言い分を確認した上で、根拠条文を探します。
もっとも、原告の請求が確定しているので、法律的に意味のある反論はかなり限られます。例えば、原告が所有権に基づいて物の引渡しを請求している場合、相手方としては、原告が物を売ったり、時効取得されたりして所有権を失ったことを主張するか、または、自身に賃借権のような占有権限があることを主張することが試験問題上は多いかと思います。ほかには、条文のただし書も反論の根拠になり得ます。
こういったことを想定しながら反論の事実を拾い、その法律構成を考えると、検討漏れが少なくなると思います。要件事実をすでに勉強している方は、抗弁として何があり得るか、という観点がとても役に立ちます。
原告の再反論が考えられる場合も、上記と同様に検討します。
要件該当性の判断
請求・反論それぞれについて条文の要件に対応する事実があるか検討します(当てはめ)。その際、条文の文言が曖昧であったり、設問の事情に直接当てはめられないような場合には、条文の解釈を行います。例えば、文言が不明確なケースでは、具体的な判断基準としての規範を定立し、それに対して事実を当てはめます。
その後、請求・反論それぞれの要件該当性から、結論として請求が認められるか判断します。
構成・文章化
以上の検討事項を一定のフォーマットに沿って並べます。絶対にこれ、というものはありませんが、まだ書き方を確立していない場合は、「独学者のための論文勉強法①」で紹介した三段論法・ミニ三段論法の形が迷わず書けておすすめです。
請求→反論→結論の流れの場合は、以下のイメージです。
請求
請求の根拠条文(大前提)
条文の要件該当性(小前提)
要件の解釈・判断基準の提示(ミニ大前提=規範定立)
判断基準の該当性(ミニ小前提=当てはめ)
要件該当性(ミニ結論)
結論(結論)
反論
反論の根拠条文(大前提)
条文の要件該当性(小前提)
要件の解釈・判断基準の提示(ミニ大前提=規範定立)
判断基準の該当性(ミニ小前提=当てはめ)
要件該当性(ミニ結論)
結論(結論)
全体の結論
最後に、これを文章化すれば答案の完成です。
平成23年民法
では、実際の問題を解いていきます。
請求の内容と法律構成の検討
DのCに対する請求は、甲土地の明渡請求です。これは、所有権(206条)に基づく物権的返還請求権が根拠となります。
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
物権的返還請求権の要件は以下の2つです。
自己に目的物の所有権があること
請求の相手方が目的物を占有していること
まず、争いのなさそうな2から確認していきます。
本問では、もともとBが甲土地上に乙建物を建築してこれを所有していましたが、BC間で乙建物の売買(555条)がなされた結果、Cが乙建物を所有するに至っています。甲土地上に乙建物を所有することにより、Cは事実上甲土地を占有しているといえるため、2の要件を充足します。
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
続いて、1の充足性を検討します。
基本的な法律関係を時系列に沿って追っていくと、もともと甲土地を所有していたAから(外形的には)Bが甲土地を買い受け、DはBから甲土地を買い受けているため、Dは甲土地の所有権を有しているとも思えます。
しかし、AB間の売買は、税金の滞納による差押さえを免れるために、AB間で「通じてした虚偽の意思表示」であるため無効です(94条1項)。したがって、BD間の契約は他人物売買となり、無権利のBから甲土地を譲り受けたDは原則として甲土地の所有権を取得することができません。
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
そこで、Dが94条2項の「第三者」に当たり保護されないかが問題となります。
第九十四条
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
「第三者」とは、虚偽の意思表示の当事者以外の者で、当該意思表示による物権変動について利害関係を有する者をいいます。Dは、虚偽の意思表示の目的物である甲土地について、Bと売買契約を締結していることから、AB間における甲土地の所有権の移転について利害関係を有するに至っているため、これに該当します。
また、Dは売買契約の当時、甲土地についてAB間の売買が仮装によるものであることを知らなかったため、「善意」の要件も充足します。
よって、同項により、Bは虚偽表示の無効をDに対抗できない結果、Dは甲土地の所有権を有効に取得します。
以上から、Dの請求は要件を充足しています。
反論の内容と法律構成の検討
まず、本問では、甲土地についてBを起点とするCとDに対する二重譲渡類似の関係にあることから、Cとしては、自己が177条の「第三者」に当たり、Dは甲土地の所有権をCに対抗することができないと主張することが考えられます。しかし、Dは甲土地について所有権移転登記を備えているため、この主張は認められません。
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
次にCは、自己が甲土地を占有する賃借権を有していることを主張することが考えられます。これは、Aの死亡による相続の発生前後で法律関係が変わるため、順に検討します。
Aの死亡前においては、前述の通りBは甲土地の所有権を有しないため、BC間の甲土地についての賃貸借契約(601条)は、他人物賃貸借となります。
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
他人物賃貸借も債権的には有効であるため、賃貸人は賃借人に目的物を使用させる義務を負います。もっとも、これはあくまで当事者間でのみ有効であるため、原則としてCはDに対して賃借権を主張して明渡請求を拒むことはできません。Cは、AB間の甲土地についての売買が仮装によるものであることを知っていたため、94条2項により保護されることもありません。
なお、この時点では、Cに占有権限が認められないことから、Cが対抗要件を具備しているかどうかは問題とならない(いずれにしてもDに対抗できない)点に注意しましょう。
では、Aの死亡後はどうでしょうか。
Aの唯一の相続人であるBは、Aの一切の権利義務を相続(896条本文)しています。
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
他人物賃貸借は、契約外の第三者にはその効力を主張することができませんが、賃貸人が目的物の所有権を取得した場合には、通常の賃貸借契約と同様、対外的にも有効になります。
したがって、仮にDへの譲渡という事情がなければ、Cは少なくともBには賃借権を主張して甲土地の引渡しを拒絶できたはずです。そこで、CD間においても甲土地の所有権がBに帰属していたという効果が認められるかどうかが問題となり、これによって両者の優劣が決せられることになります。
この部分は決まった正解があるわけではなく、考慮すべき事情を漏れなく検討した上で、説得力のある結論を導けているかどうかが重要です。
考慮すべき事情としては、以下のものが考えられます。
BC間の他人物賃貸借の対外的有効性の要件は充足
Dは1以前に甲土地の所有権取得 + 対抗要件具備
Cは2以前に対抗要件具備状態(ただし占有権限なし)
なお、3について、Cは甲土地上に乙建物を所有し、自己名義の登記を経ていることから、借地借家法10条1項により、甲土地の賃借権の対抗要件具備が認められます。
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
以下、考え方の一例を紹介します。前述の通り、これが唯一の正解ではない点にご留意ください。
まず、2を踏まえれば、Dの所有権はCを含むすべての第三者に対抗できるようにも思えます。もっとも、Cには他人物賃貸借という認識があったとはいえ、Bが所有権を取得した際に賃貸借が有効になるというCの期待は正当なものであるといえるでしょう。そして、自己があずかり知らないDへの譲渡という事情によってその期待が裏切られるのは酷であるとも思えます。
一方で、Dは、そもそも甲土地がAからBへ有効に譲渡されていることを前提に、Bから甲土地を購入しています。そうすると、Bが所有権を有することを前提にした法律関係、すなわち、Cが甲土地の賃借権を有効に有することを認めたとしても取引の安全が害されるとはいえません。したがって、CD間においても甲土地の所有権がBに帰属していたという効果は認められ、Cの賃借権はDに対する関係でも有効であると解すべきです。
そう考えた場合、3より、Cの賃借権はDに対抗することができるため、CはDの請求を拒絶することができます。
以上から、DのCに対する明渡請求は認められません。
解説は以上です。
出題の趣旨
本問題について公表されている出題の趣旨は以下の通りです。
不動産の仮装売買(民法第94条第1項)を前提に,仮装名義人が不動産を一方に賃貸し,他方に売買した事案における,賃借人と買主との法律関係についての理解を問うものである。民法第94条第2項の善意の第三者に関する基本的理解を前提に,他人物売買及び他人物賃貸借をめぐる法律関係を検討し,さらに,他人物の売主及び賃貸人が所有者を相続した場合の法律関係を問うことで,正確な法的知識とそれに基づく事案分析能力,論理的思考能力及び応用力を試すものである。
参考答案
以上の内容を反映した参考答案を添付します。
参考書籍
書き方講座記事のご案内
本noteでは、論文の書き方についてゼロから丁寧に解説した記事を公開しています。これから論文を書き始める方、論文の勉強方法に悩んでいる方はぜひご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
