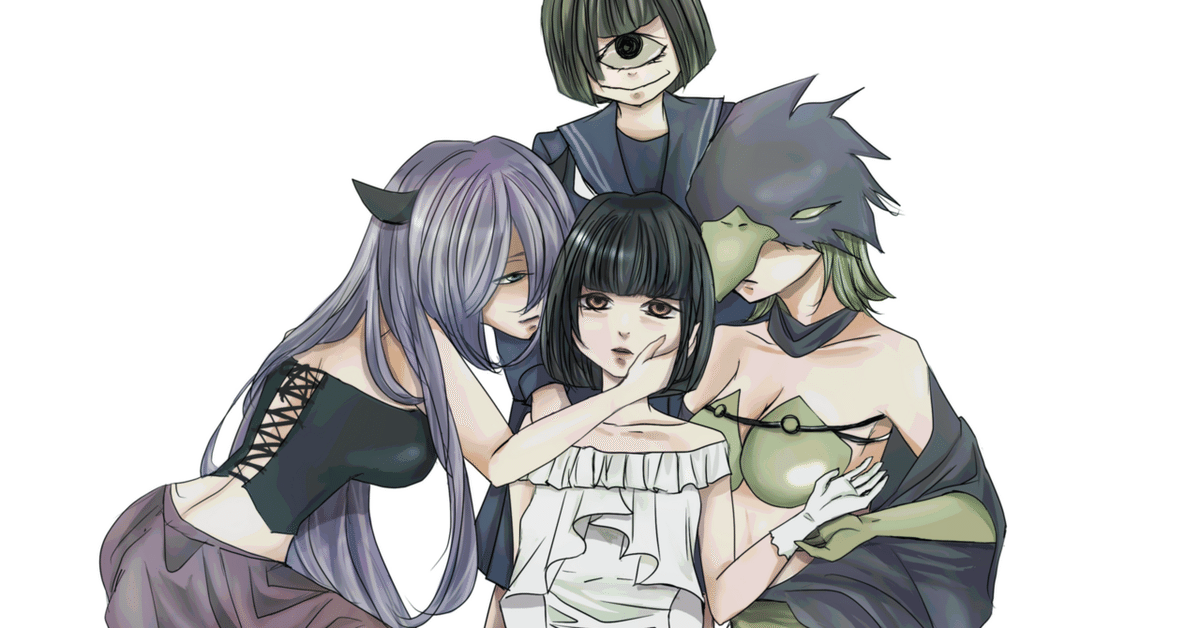
架空謎解きRPGサウンドトラック《飽きのこない人生全集》ストーリー草案
※注意書き
こちらの文章は、「性的被害のトラウマを持つ方」「小児性愛の要素を(例え内容がこうていてきではなくても)嫌悪する方」「その他重たいストーリーを苦手とする方」は閲覧しないようお願いいたします。
作品概要
架空の謎解きRPGのストーリーを作り上げ、そのサウンドトラック集を自作しました。
試聴は下の動画からお願いします。
また、過去記事にて楽曲タイトル、英題、楽曲説明欄一覧を展開しております。
https://note.com/amamiya_sarasa2/n/n4c33f0470147
ストーリー草案
第1章
《わたし》が目覚めたとき、視界一面が真っ白だった。
よく見るとそこは四角い空間のようで、《わたし》自身の身体にはたくさんの管と手足を拘束するベルトが繋がれている。
鉄格子の向こうでは、知らない誰かたちの談笑が聞こえる。
現状の把握は難しかった。自分がどのような流れでこのような状況におかれたのか、直前まで何をしていたのか、いつからこうだったのか、考えたくても心にもやがかかり邪魔をする。
《わたし》の意識や記憶は、とある男性《あの人》へと1点集中していた。
彼女と結婚を誓いあった仲で、とても紳士で気さくな歳上の相手だった。
現状把握が上手くいかない不安から、《あの人》への衝動的な欲が高まる。
《わたし》を生涯守ると誓った《あの人》がなぜこの場にいないのか、彼女には理解できなかった。
《あの人》と会えば、この胸のつかえは治まるはずだ。
約束してくれたのだ。《わたし》をお姫様にすると《あの人》は約束した。
目覚めた直後は気づかなかったが、拘束具は半分外れているようなものだった。
それを外し、管を抜き、鉄格子の元へ近づくと、硬い柵はいとも簡単に錆びて崩れる。
そのまま外へ出る。四角く白い空間がどこまでも続いている。
《わたし》は、この空間を《白の街》と名付けることとした。
風ひとつない乾いた場所で、まるで浮いているみたいに足取り軽く、《わたし》は進んだ。
《あの人》以外の声はききたくない。街の外で《わたし》の道を阻む者は忌むべきものだ。
自身を愛してくれる人の元へいきたくて、《わたし》の冒険は始まった。
楽曲《今までなかったはずの街》~《取るに足らぬ安息と取ってつけた安穏》
第2章
旅を続けるうちに《わたし》は《あの人》を失った理由を思い出す。
《あの人》を誑かした悪女がいた。その悪女《貴方》は色目を使い、誰かの最愛を奪うことを趣味とする人間だった。
《貴方》がターゲットを愛することは一切なく、彼女が食い荒らしていたのは奪われるものの自尊心や自己愛である。
《貴方》のことを許せないな、と思った。そして、《貴方》にまんまと誑かされた《あの人》のことも。
湧き出た感情は嫉妬よりもっと深い何かだった。
するとその瞬間、《貴方》と同じ顔をした悪魔が目の前に現れた。
《あの人》を奪われた《わたし》のことを嘲笑う目で見下す《貴方》。
さらに増す嫉妬心で無数の傀儡を作り、《貴方》の臓器を食い荒らすよう命じる。《貴方》が《わたし》の自尊を食い荒らしたのと同じように、《貴方》の骨さえ残さずに食う。
愛がわからずに他の人のを貪っていた《貴方》は自分の愚かさに気づき消滅するのだが、消えゆく《貴方》の表情はどこか悲しげだった。
《貴方》の口元が動く。「たすけてあげたいよ」。
聞こえなかった言葉は《わたし》の心にまたもやを残した。
忌むべきものを倒す度に約束が遠ざかっている気がする。
《あの人》は、どこにいるのだろうか。
楽曲《Erase a promise》~《嫉妬よりも深いエゴ》まで
第3章
《わたし》が《貴方》を倒したあと、急に耐え難い目眩がした。
次に目を覚ますと、そこは雑居ビルの裏路地だった。
この路地に見覚えがある。《わたし》が中学生の頃学校帰りに通っていた道だ。
友人関係に乏しかった《わたし》は下校時、同じ校区内同じクラスの生徒と鉢合わせしないよう、通学路から少し遠回りしていた。
そういえば、《あの人》と出会ったのもこの辺りだったかもしれない。
「かもしれない」というのは、《わたし》が《あの人》と出会った当時のことをはっきりと思い出せなかったからだ。
甘い記憶だけ反芻する。でも、なぜ《あの人》が《わたし》をお姫様にすると誓ってくれたのか、わからない。ただ《あの人》への情念だけがここにある。
ふと、《貴方》がわたしへ投げかけようとしたさいごの言葉を思い出した。
「たすけてあげたいよ」。一体何のことだったのだろうか。
すると、突如《わたし》の腕が何者かに引かれた。
吃驚し顔をあげると同時に口元を塞がれる。「これはまずい」と本能的に感じた《わたし》が抵抗の意を示そうと相手の顔を見ると、待ち望んでいた《あの人》がいた。
呼吸荒く、《わたし》の服の中へ手を差し入れてくる《あの人》に、《わたし》は違和感を覚える。
《あの人》はこんな人だっただろうか。自分の記憶とまるで別人のような人格で、《あの人》は彼女を襲う。
記憶がどんどん流れ込んでくると、《わたし》の思考は恐怖で満たされていった。
燃えるような《貴方》への嫉妬。その嫉妬は《あの人》という最愛を《貴方》が奪ったからだと思っていた。
だけど、記憶を辿り繰り返し行き着いた事実が嘘を暴いた。
楽曲《今までなかったはずの街》~《シニカルゲート》
第4章
嫉妬なんてはじめから、どこにもなかった。
中学生の頃この路地で行われたのは、《あの人》から《わたし》への性加害だった。
あの頃の《わたし》に性的な知識がなかったわけじゃなく、なんなら薄く嫌悪さえ抱いていたと思う。
それでも、重大な被害とは思っていなかった。なぜなら、歪に続く関係で会う度に《あの人》はこう言っていたからだ。
「ぼくは《わたし》を大切に愛したいんだよ。《わたし》はお姫様だからね」。
周りと上手く打ち解けられず、そのせいで家族とのコミュニケーションもギクシャクしていた《わたし》にとって、その言葉に根拠はなくても信用たるものだった。
《わたし》が今まで嫉妬だと思っていたものは、《あの人》との歪な関係を当たり前にそこにあるものだと信じたかったからだ。
関係が壊れてしまったら《わたし》には何もなくなってしまうから、恐れた。そしていつしか、《あの人》への恋愛感情が本物であると錯覚してしまったのだ。
《わたし》の信じた希望は嘘。そう思うと、なんだか《わたし》自身のことをかわいそうで仕方なく感じてきた。
自己を搾取され続けたその責任はどこにあるだろうか。少なくとも、わたしは健全だったはずだ。
どうしよう、イライラがおさまらない。わたしの爪は自身の肌を抉る。やまない自傷。
ただただ《わたし》は、助かりたかった。
事実を思い出してしまったのがつらい、《あの人》が自分を愛してくれていなかったのがつらい。そして何より、わたしの自我がずっとなくなっていたのが受け止めきれないほど悲しかった。
耐えられず手首に立てた爪をさらに食い込ませると、少量の血液が地面に落ちた。
そこで悟った。恋は盲目って言うけれど、ちがった、恋は損得で成り立っているのだと。
わたしがした恋は自分の心を守ったけど、同時に自己を失った。それだけの話。
取り戻さなくちゃ、《わたし》を。
自己正当化のために揺らいだ静かな怒りを「たすかりたい」という強いきもちで消し去り、物語は最終フェーズへと進む。
楽曲《砂のお城》~《恋って損得》
第5章
《わたし》はあの頃から夢を見ていた。
例えば《あの人》からのその愛が支配欲求から成る偽物だと気づかなければ、起こった悲劇を忘れたまま永遠のお姫様として人生を全うしただろう。
今、《わたし》の視界は自己嫌悪で淀んだ風景を捉えている。
けれど、ここで真実を知ることもなんとなく、心の核では勘づいていたのかもしれない。
鏡写しで見た自分の泣き顔と重ね、《わたし》自身から噴出した悪感情すべてを忌むべき者として倒してきた。そこから既に、気づいていたのだと思う。
最初に目覚めた場所である四角く白い部屋は《わたし》の核へ1番近い場所にあった。それなのに、事実を忘れたままでいたくて逃げ出してしまったのだった。
《わたし》を生かし続けていたのも、忌むべきものと戦う力を持てたのも、《わたし》が例えそれが嘘なのだとしても愛のようなものを手におさめることができたのも、《あの人》への嫉妬心ゆえだった。
《あの人》への嫉妬心がどこにもなかったのだと知った彼女には、もう何も無い。怖いものさえも、何もかもが虚無に還ってしまった。
じゃあ、果たして《わたし》の人生はあのままでよかったのだろうか。嘘偽りだけを希望として生きていたほうが、《わたし》は幸せだったのだろうか。
「そんなことない」と、声がする。
見上げると、かつて存在を消しさったはずの《貴方》がそこにいた。
「たすけてあげたいよ」《貴方》が泣きそうな声で話しかけてくる。
そうだ、《貴方》は《わたし》から《あの人》を奪おうとなどしていなかった。
《貴方》は確かにわたしから自尊心を奪っていった。優秀で、でも何かに怯えたようにいつでも自信のなさを見せていた《貴方》は、《わたし》の生育環境を不安定にさせる要因でもあった。
だけど、《わたし》が《あの人》とはじめて出会い不合意でのセックスをしたあの日、《貴方》は《わたし》になんて声をかけただろう。
怒られたはずだ。
「お母さんが上手く育ててあげられなくて、不安にさせたのはごめん。それでもお母さんは、《わたし》が《あの人》を好きだと言うのは反対だよ」
《あの人》について嬉々として語る《わたし》へ、《貴方》は確かにこう言ったのだ。
「たすけてあげたいよ」
貴方の声が反響して聞こえる。
楽曲《最初に知ってた今日の部屋》~《もう無い》
第6章
セーラー服姿の《わたし》の目が溶けてひとつになった。
かつての《わたし》はこう言う。
「だって《貴方》はわたしの初恋を否定したじゃないか。
学校のみんなはわたしとはおしゃべりしてくれないし、ブスだって笑った。
先生はわたしがそうやって言われるのが悪いって言った。《貴方》だってそうだ。
《わたし》のこと全部受け入れてかわいいって撫でてくれたのは《あの人》だけだったのに。
好きな人と引き離されるなんてつらいよ。
なんでこの感情を嘘って言うの?
お前だって、そう思っているだろ」
捲し立てる過去の《わたし》の言葉を噛み砕いて飲み込んでいく。
そうだ、そう感じていたから《わたし》は《あの人》へ依存し、すべての他者を憎むようになっていった。
《あの人》にほんとは妻子があったことを知ってしまって、《わたし》の心は閉ざされた。代わりに言いようのない色の憎悪を他者に向けてしまった。
けれど、年齢を重ね考え方が多少大人になっていた《わたし》は「他者へ反発すること」を「他者への加害」だと認識した。人のせいにするなんて最低だ、と感じた。
正気の重さを抱えきれなかった《わたし》の意識はそこで途絶えて、次に目覚めたときは最初に見た景色…閉鎖病棟の保護室の中だった。
長い夢を見ていたようだった。ほんとに夢だった。《わたし》の手足は、最初と変わらないまま拘束され続けていたのだ。
《わたし》が助かるためにはどうしたらいいのだろうか。
欠けた自尊を「もう大丈夫だよ」とやさしく撫でてあげることはできるだろうか。
救わなくちゃいけない、《わたし》は《わたし》を。
楽曲《魔王は貴方だ》
最終章
あの日は雨だった。
ぐちゃぐちゃに濡れた《わたし》は、まるで水を得た魚みたいに爛々とした目で《貴方》へ事の一部始終を話した。
《貴方》は怒ったような表情で《わたし》を抱きしめたあと、わたしが話した一部始終についてよくないことだと諭した。
当時のわたしに愛情を受け取ったり察したりする器はどこにもなかった。《貴方》も、適切な愛情の渡し方を知らなかった。
もう少し気づくのが早ければ、無償の愛のトリガーが《あの人》からの性的加害じゃなければ、結末は違ったかもしれない。
欠けて戻らなくなった自尊心を埋めようとした、傲慢な《わたし》の末路だった。
セーラー服の《わたし》を抱きしめてやると、1粒の涙を零して身体の中へ吸収されていく。
《わたし》は、20歳そこらの娘だ。
自分の人生が実は本質から逃げていただけの悲劇のヒロイン物語だったなんて、まだ受け止めきれないほどに《わたし》は幼い。
歳相応に成長できなかった自尊と知能で救えるのは、あの日の嘘を自身の死をもってして事実に替えることだけだった。
自分を守るために論理をねじ曲げ作った静かな怒りも、愛されたいのに愛を取りこぼしてしまった自己嫌悪も、他者からの何かを食べ散らかしていたのは実は自分のほうだったという事実も、《わたし》が生み出したものなら《わたし》が全部連れていこう。
これはひとつの説だが、7つの大罪で最も罪が重いのは嫉妬とされている。
7つ目の嫉妬が嘘だったから、その分だけ少し身体が軽くなった。宙に浮くと四肢は自由で、どこまでも飛んでいけそうだった。
どこにもない嫉妬心で、それに伴う復讐心で、或いは事実を受け止められなかった自己嫌悪で、大切な誰かを破壊する前に終われてほんとによかったと思う。
わたしの人生はわたしのものだ。だから、主人公も敵も全部ぜんぶわたしなんだ。
飽きのこない人生だったけど来世では猫になりたいな、とぼんやり思いながら、《わたし》の思想はまだ見ぬ誰かへと託される。
楽曲《わたしはそうして手に入れたのね》~《我が人生こそ脆く正しくRPG》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

