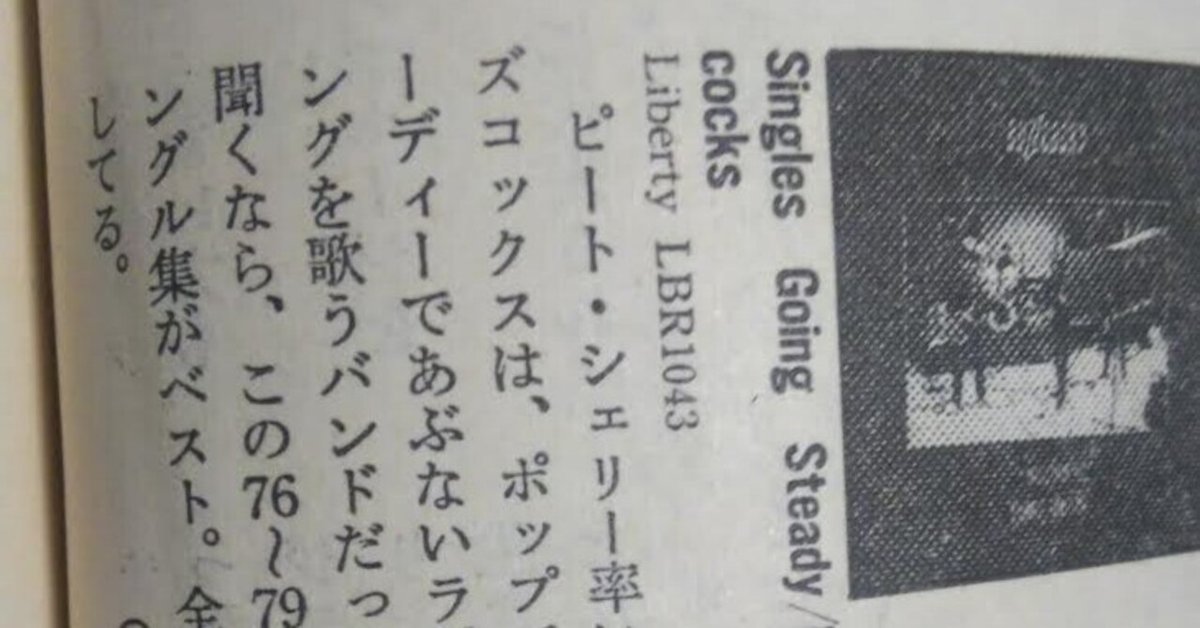
パルスビートの衝撃―バズコックス
バズコックスに関しては、今年前半にピート・シェリーのバイオ本にCDライナーの(私自身の下手糞な)和訳を掲載し、それらの後記にバズコックスに関する所感なり歌詞についての若干の考察を書きつけた。もうそれで十分だろうと思った。既にメディアには優れた文章があるし、バズコックスへの愛情たっぷりな文章もたくさんある。これらに接していると、もう私がこれ以上しゃしゃり出ていくのはひんしゅくであろうと思ってしまっていた。私はファン、といってもいい加減なファンである。音源も全部聴いてはいない。ライヴだって行ったこともない。メンバーのソロ作品もほぼ全く聴いたことがない。バズコックス自体ロクに聴いていなかった期間も長い。そんな私がここでバズコックスの事を語るのもおこがましい・・と思いつつ、性懲りもなく、また吐きだしたくなった。まだバズコックスとの出会いから今日までを書いていなかったことに気付いたのである。バズコックスも、私のミュージック・ライフ(と言えるほど聴いていないが)を語るうえで欠かせないバンドであるからである。いやそれどころか、彼らは私の音楽の、判断規範形成期―堅苦しい!―の最後期を飾るという一点においても重要な存在であり、やはり今一度、語っておきたくなったのである。ピート・シェリーの評伝を、バズコックスのCDライナーを、無謀にも訳し掲載してしまったのも、彼らが特別なバンドであるからという証左なのである。この機会を逃したら、たぶん二度と彼らを語る機会はないであろう。せっかく語れる機会を与えられたのである。存分(とは言えないが)に語らせてもらうことにしたい。もちろん、ひんしゅくは覚悟のうえである。まあ読みたくない方は無視すれば済むだけの事ではある。
ちょっとわき道に逸れるが今、私は音楽の判断規範形成期、と記した。私の、聴いている音楽の傾向というか、守備範囲というか、その好みの基準が固まったのは、13歳くらいから19歳くらいではなかったかと思う。もちろんそれ以降(あるいはそれ以前)も音楽との出会いはあったけれど、それらも煎じ詰めれば、13歳から19歳までに聴いた音楽の、コラロリー~バリエーションと言い切ってしまってよい。それ以前に聴いていた音楽は、今思い出してみると、たいして重要ではないというか、単にラジオで流れていてああ、いいな、とか、クラスで流行っていたとか、その程度であった。つまり自分の生活の一部と言えるほどのものではなかったわけである。19歳以降に出会い、気に入った音楽やミュージシャンで言えば、例えば私は一時期ブラインド・レモン・ジェファーソンが大好きであったのだけれど、その1曲「マッチボックス・ブルース」は、ずっと後にビートルズがカバーしたからであった(厳密にはジェファーソンを聴いたカール・パーキンスが改作し、それをビートルズが取り上げたのである)。もうひとつ例を挙げれば、私はポイズン・アイデアもかなり入れ込んで聴いていたが、彼らのルーツはダムドであり、ニュー・ヨーク・ドールズであり、ザ・フーであったからである。ビートルズ、ダムド、ドールズ、ザ・フー。皆、私が13歳から19歳までに、のめり込んだバンドである。
そしてバズコックス。彼らとの出会いは18歳。最初のレコード(単独の)を買ったのは19歳の春。私の音楽判断規範形成期の最後期である。しかも、この最後期を飾るバズコックスは、ある意味、私のそれまで聴いてきたミュージシャンの要素をことごとく内包していた。ピート・シェリーは幼年時代からビートルズにマーク・ボランのファナティックであったし、スティーヴ・ディグルは10代のときザ・フーのようなバンドを作るのが夢で、自身はピート・タウンゼンドになろうとしていた。ベースのスティーヴ・ガーヴェイが影響を受けたベーシストの一人はフリーのアンディ・フレーザー・・・・。もちろん、この知識は後付けであって、10代20代の私はそんなことなど知る由もなかったのだけれど、バズコックスと私が聴きこんできた音楽とは、しっかりと繋がっていたのだ。換言すれば、バズコックスは私の音楽判断規範の最大公約数的な存在なのである。昨年、ピート・シェリーの評伝『ever fallen in love』を読んでその思いに到達し、私の音楽の聴き方は首尾一貫するところがあったのだなと納得したのであった。

バズコックスとの出会いは、イーターの稿でも記した『ミュージック・マガジン』1986年6月号のパンク10周年記念特集においてである。それまでの私はパンクというと、ピストルズ(『グレイト・ロックンロール・スィンドルはまだ聴いていなかった』とザ付きの時代のスターリン、クラッシュ(あの時はまだ1stと3rdしか知らなかった)、ジャム(持っていたのは1stだけであった)しか聴いたことがなかった。ダムドもラモーンズも知らなかったし―名前だけなら、ピストルズのレコードに付いていたライナーや、遠藤ミチロウのインタヴューなどで知ってはいたが―、リチャード・ヘルもデッド・ケネディーズも、ことごとくこの雑誌でその名を知ったのである。パンク・アルバム100と題されたページに小さく載った『シングルズ・ゴーイング・ステディ』、高橋健太郎氏による紹介文。ここから始まったのである。
「ピート・シェリー率いるバズコックスは、ポップでスピーディーであぶないラヴ・ソングを歌うバンドだった」
(へえ、ラヴ・ソングを歌うパンクかあ)ザ・スターリンは別としてパンクと言うと、特にブリティッシュパンクは社会的・政治的メッセージを歌うものだという先入観が音楽雑誌を通じて刷り込まれていて、ラヴ・ソングを歌うなんて、と違和感を持ったことを白状しておかねばならない。当時の私は狭量なロック・ファン初心者(?)で、一見女々しいなりして非攻撃的な内容の歌詞なんぞ歌う、あるいは冷徹な内容でない(?)歌詞を歌う奴なんぞ、ロックじゃない、パンクだったらなおさらだという考えに凝り固まっていた。そのくせ自分はウジウジした日常を送っていたのだから、フカフカ・ソファー・パンクと何ら変わるところはなかった。
「今聞くなら、この76~79年のシングル集がベスト。全曲いかしてる」
(スピーディーか。ならパンクだろうな)18歳の、フカフカ・ソファー・パンク予備校生の私は短絡的にそう思った。その刹那まで、ラヴ・ソングを歌うなんて・・・・と蔑んでいたのが。根無し草の、まさに定見のない日和見野郎である。そのままレコード店に直行、とならなかったのはこれまた単純な話である。カネが、なかったからである。買いたいレコードは山ほどあり、しかるに恒常的金欠状態、どうせ手に入れるなら新品でなくてもよい、安売りしているセコハンで、ついでに歌詞の付いている国内盤で、と言う優先順位で、国内盤はとうに全部廃盤となっていると思しき―実際そうであった―バズコックスは後回しにしてしまった。
10代~20代初頭の私のレコード・コレクションは、満足に増えなかった。特にパンク関係は、国内盤を優先的に買っていたこともあって、お寒いかぎりであった。地元の中古盤屋の数は限られていて、その品揃えもほめられたものではなかった。パンク~ニュー・ウェーヴ関係は殆んどと言っていいほどなかったし、たまにあっても思わずため息を一反もついてしまう額であった。もうとっくにつぶれてしまったある中古盤屋でシャム69のセカンド『ザッツ・ライフ』のサンプル日本盤が帯付きで売られていて、おお!帯付きか、サンプル盤なら安かろうと思ったら・・・・。しかも私の場合、パンク以外にもいろんな音楽が聴きたくて、加えて古本あさりもしたくてあっちこっち浮気(?)をしていたものだから、パンク関係のレコードは、てんで増えなかったのである。
バズコックスの“音”をちゃんと聞いたのはその年の暮れである。地元ではなく、池袋の輸入盤専門店であった。何故池袋であったのか、憶えていない。どういう経路でその店の存在を知ったのかも全く記憶にない。ただ池袋であったことだけは憶えている。おそらく懐が温かかったから行ったのではなかったか。その店で、赤茶けた、荒っぽい画像のスリーヴ写真が印刷されたレコードに目が留まったのである。


『ロキシー・ロンドン・W.Ⅽ.2』と題されたアルバム。これもイーターの稿で掲載したが、1977年の1月から4月の間だけオープンしていたパンク専門のライヴ・ハウスで録音されたライヴ盤である、というのはいまさら説明する必要もなかろうが、聞いたことのないバンドばかり。なんかお得だ、しかもスリーヴのデザインが自分の勝手にイメージしていたパンク感覚そのままじゃないか、ということで購入することにした。値段はこれまた全く憶えていないが、当時の金欠野郎な私の事であったのだから、安売りされていたと思う。このアルバムのB面ラスト2曲を飾ったのが、バズコックスであった。ステージ写真に一番大きく映っている男を、私は最初ピート・シェリーだと思っていたのだが、実はスティーヴ・ディグルであって、ピート・シェリーはその隣の男であったという、冴えない話を記しておこう。




アルバムの音はどれも何だかガチャガチャしていて、いかにも混沌と言ったイメージ通りのたたずまいを見せているが、ああ、この猥雑さが新たなエネルギー誕生の証なのだよな、などとしたり顔して聴いていた。そんななかで、バズコックスの音は、これもガチャガチャしているようで、ちょっと違って聴こえた。そのメロディー展開は起承転結がはっきりしていて、ヴォーカルもいわゆるパンクな、がなり立てる唱法ではない。気取って歌いあげるといった風情でもない。ただ、耳に残るメロディーであり歌だと思った。ただ悲しきかな、この時はそこまでだった。バズコックスの単独のレコードを聴いてみたいと思いつつ、財布の中身が気になって仕方なく、そのままずるずる数か月が過ぎ去った。
バズコックスの出会いとは、かくの如きものである。なんてことはない、ありふれたものである。どこがドラマチックなんだということになるが、それが数か月後には、なのである。

ここに掲げたのはバズコックスの1st「アナザー・ミュージック」のスリーヴだが、私が当時手に入れたそれではない。2008年に出た2枚組CD版である。当時買ったレコードはさんざん聴いて潰してしまい、CDで買い直した時に売りはらってしまったのである。何故だかわからぬが写真はモノクロであった。当時解散していて、いわゆる「死んだ」バンドであったからという扱いであったからであろうか。しかし不思議に思うのは、あんなボロボロなレコードを店側が買い取ってくれたことである。スリーヴもクタクタで底が抜けていたくらいであった。それだけ需要があったのか。だとしたら売らなければよかったな、などと情けない思考に誘われる。それに、たとえ聴けなくなったレコードであっても。そのぼろさ加減が、私の歴史の一断面を照射するものであるなら、それは一つの証言を与えてくれるであったろうから、とも。これはあくまでも私の記憶の中だけで有効なのであり、説得力を持たない。いや、私の記憶すら大いに怪しい。フィクションと疑われても何ら弁解はできない。それでも語るのは、相手がバズコックスだから、というしかない。
それは87年の春。私が19歳を迎える年である。世の音楽メディアがレコードから一斉にCDに切り替わりそれがほぼ完了した年であったと思う。旧譜がことごとくCD化されると共にレコードは一気に消滅していった。ビートルズの国内産のレコードが一斉に廃盤になり、アメリカ編集盤とか日本編集盤とかが手に入らなくなったのも87年である。私自身、最初のCDプレイヤーを手に入れたのがこの年であったわけだが、実はCDを好かなかった。あのちんけなブックレットが嫌であったのだ。旧譜のCD版では裏スリーヴや見開きのアートワークがことごとく削除されてしまったブツが多かったのも理由の一つである。ハンブル・パイの『ロッキン・ザ・フィルモア』もそうであった。2枚組のレコードが1枚のCDで聴けたのはうれしかったのだけれど。だからアナログ2枚組のアルバムがCD化されたとき、CDがアナログ盤と同じ2枚組であった場合、CDの方がはるかに高く(レコードだって高かったが)腹立たしい思いをしたものであった。CDの値段があの頃は高かった。1枚ものでも3200~3300円はした。だからCDプレイヤーを買っても1年くらいはCDをほとんど買わなかった(買えなかった!)。やがてCDの値段が下がっていき、中古品も安く出回るようになってCDも買うようになっていったが、店からレコードが急速に姿を消していったゆえに必然的に、という側面もあったのである。
87年。たぶん一番たくさんレコードを買った年ではなかったか。世はCDばかりがもてはやされ、レコードは時代遅れの産物扱いされていったあの時代。私はなるべく安いレコードをセコク求めた。あの頃から、私は時代の流れから外れていたのだ。そしてその春の事である。
当時、私は家の近くのうどん屋でバイトをしていた。大学が春休みで、バイト先の上司が、「休みだし、人もいねえから、いいよな」と、シフトをたんまり私にあてがってきた。おかげで週6日、1日12時間労働な日々になった。昼の12時から、夜12時まで休憩ほぼなし。それを受け入れてまじめにやってる私もお人よしというべきか。その分、正社員の連中はのんびり夕方からやってきたり、途中で退勤したりしてぬくぬくとやっていた。奴等は私によく、「おまえ、4月になったら、時短になるんだよな。いいよなあ。俺も大学行きてえ」などと、嫌味をほざいていた。今ならコンプライアンスとかパワハラとかで大問題になるところなのだろうが、周りの奴輩は気にも留めなかった。私は私で、そんな連中の戯言を聞いている余裕もなかった。夜中にへたばり切って家に帰り、翌日の午前中は本を読み、買ってきたレコードを聴いた。週に1日の休みには疲れがたまっていても、無理やりに古本とレコードあさりに出かけた。なにせ春休みはカネがたんまり入るのだから、ついついいつもは堅い財布のひもが緩むのであった。そして休息よりひと文字でも多くの活字を、1曲でも多くの曲を脳髄に叩きこもうとした。そうすることが知的生産活動だと信じていたし、そうしなければ周囲の有象無象と同じ地平にまで堕落してしまうに違いないという強迫観念に駆られていた。実際の所は単なる自己満足に過ぎなかった。その証拠にあの当時読んだ本の中身も、聴いたレコードの中身も、ほぼ何も頭に残っていない。一体私は何をしていたのかというわけである。
そんなある休みの日。普段は見かけないレコードが目に留まった。
「この店で、これ。珍しい」
実は、そのバンドのレコードは、この店ではお目にかかったことがなかった。そして(輸入の)新品にしては安かった、そんな記憶だけがある。この店が地元にあった店なのか、新宿か神田、はたまた池袋にあった店なのか、まるで憶えていない。おそらくスリーヴがかなり傷んでいたゆえに割り引いていたのではなかったか。クローム色のバックに、黒いシャツを着た4人の男がぎこちない表情でこちらを見ているポートレートが載ったそのレコード。タイトルは「ANOTHER MUSIC IN A DIFFERENT KITCHEN」
「変なタイトルだな。別の台所にある、もう一つの、音楽?『ミュージック・マガジン』には載ってなかったな」スリーヴの写真を見ながら、私は『ロキシー』に写ったライヴの写真を思い出していた。
「ピート・シェリーは・・・・このハレぼったい眼をした奴か」実際のその男はスティーヴ・ディグルなのであった。
「右端の一番オトコマエの奴・・・・あのライヴには映ってなかったかな?」それはそうだ。あの時はまだメンバーでなかったスティーヴ・ガーヴェイだったのだから。当時の私はどれがピートで、どれがスティーヴか、てんでわからなかった。後にピートが一番オッサンな奴だったと知り、軽い衝撃を覚えたのであった。いや、その程度の衝撃で済めば今日、こんな雑文を書くことはなかったのだけれど。それにしてもこの写真、なんかさえない風情だ。ちっともパンク的じゃないと思った。それでいてそのデザイン、どことなくメタリックで暑苦しくない。ダサいんだがクール。これまでお目にかかったことのない、不思議な感覚であった。
「これは買う価値あるな・・・・。安いし」ガキの直感と言うやつか。
家に帰ってレコードに針を落とすと、ギターの単音が突き刺さってきた。もう1本のギターがジャジャジャとかき鳴らされ、ドラムとベースが入る。一瞬の静寂。今度はベースから入って、再び演奏開始、そして、声変りを拒絶したような声がかぶさってきた。
Fast cars/fast cars/Ihate fast cars
「へえー、かっけーじゃんか」たいして期待はしていなかった。それが見事に、いい意味で、裏切られた。ハードでスピード感たっぷり。けど、決して暑苦しくない。何だか情けないんだが、媚も売っていない。耳に残るメロディー。この絶妙な匙加減・・・・もちろん、これは今だから書けるのだけれども。この時は単純に、「かっけー」であった。
レコードをひっくり返し、B面のラスト。デカい音でドラムが響く。ザクザクとリズムを刻むギターが右から、じゃーんともう1本のギターがコードを鳴らす。そして、あの声だ。声変りを拒絶した声。
You said the things you did in the past
Where all because you are living too fast
この瞬間、体中の血が、逆流した。あほかと笑われるであろうが、そうとしか言いようのない感覚だった。これまで聴いたことのない音。文字通りsomething specialな瞬間だった。
「これすげえ」
間抜けな言語表現だが、すげえ、だったのだ。
後年、ピート・シェリーが評伝『ever fallen in love』の中で、この曲のドラムを‟あの音“にするためにジョン・マーは2回同じフレーズを叩いて録音したと語っているのを読んで、成程なあと感じ入ったのだが、この曲はバズコックスのバンドとしての総合力―バンド自身の演奏力だけではない。レコーディング・スタッフの力量も含めての―を見せつける最高のサンプルになりうる。「ムーヴィング・アウェイ・フロム・ザ・パルスビート」は未だに、私の生涯のベスト10に入る1曲である。
この日以降、私の家では毎日バズコックスのレコードが、ターンテーブルに乗るようになっていた。
バズコックスの、何がこうも私をのめり込ませたのであろうか。電気のこぎりbuzz-sawのようなギター。声変りを拒絶した声。耳に残るメロディー。パワフルなビート、それでいて暑苦しくない音、恋愛と人間関係に苦悩する歌詞、メカニカルで知性を湛えたアートワーク、メンバーの野暮ったさとクールさが奇妙に同居した佇まい・・・・。どのどれもが是、なのであったろう。一言でいえば、私との距離感が非常に近かったのだ。「なんだか、俺と変わんねえ」けれど、やっている音は超一級。それが良かったのだ。もちろんこの時点でバンドはすでに解散していたのだけれど、そんな時間差は気にならなかった。もちろん、リアルタイムでそのライヴに接することの叶わなかった悔しさはあったが、それとバンドの音楽との時間差への感覚とは、また別である。
それなのに、私は彼らの音楽作品以外の、本は別にして、例えば、彼らのキャラクター・グッズなどには、まるで興味を持たなかった。彼らが今どうしているのかは興味はあったが、積極的に知ろうともしなかった。あくまで音楽が聴ければよかった。そこがザ・スターリンへの態度とは明らかに異なる。バズコックスに関しては、いわゆるミーハーにはなれなかったのであろう。バズコックスに感じた、ある種クールな感覚。それと同じ―と私は勝手に解釈しているのだが―態度を、私は彼らにとった。彼らへの情報が知らされなくても、苦痛は全く感じなかった。だから現役当時の彼らが―特に解散間際、ドラッグ浸りになり、レコード会社ともめ、ファンの態度にウンザリしていたということは、知ろうと努力しなかったからずいぶん後になるまで知らなかった。知った時にも、何の感慨も得なかった。そのことと、彼らの音楽とは無関係だと思った。そういえば、やはりぞっこんであったダムドに関しても、私は同じような態度で接していた。例外はザ・スターリンであったが、これですら、キャラクター・グッズの類いは買わなかった。まあザ・スターリンの時には単に一層金欠で買えなかったのだけれど。つまらないファンというしかないのであろうが。
そのバズコックスが再結成するかも、という記事を見たのは88年の暮れであったろうか、あるいは89年の冒頭であったろうか。少々複雑な心境ではあった。昔の名で、というわけかと思ったりした。それが裏切られたのが少したってから発売されたライヴ・ヴィデオを見たときであった。実は動くバズコックスを観たのはこれが初めてであったのだけれど、見事な演奏に、ああこれは現役だなとうれしくなったものである。
当時のヴィデオの映像も、今では気軽にYou Tubeで観れる。あるのだな、ということで、貼り付けておく。この映像で判ったのだが、レコードでのキーは、実際の演奏より故意に全音高くミックスされているのだ。レコード・プロデューサーのマーティン・ラシェントの意向であったらしい。
しかし、この頃から、私はバズコックスを聴かなくなっていった。いやバズコックスだけではない。ロックはほぼ全般、聴かなくなっていった。たまに聴くのは戦前のブルース、それですらごく稀に、という有り様になっていった。たくさんの原因がある。それをいちいち挙げていくのも面倒であるし、だいいちつまらない。ただ、一言で済ますなら、私も世も、変わった、ということなのであろう。95年だったか、バズコックスの70年代のアルバムが日本で一斉に再発されたときはすぐ手に入れたが、何回か聴いただけで、棚にしまい込んでしまった。再結成後に出たアルバムも、出たのは知ってはいたが、買うことはなかった。90年代に入って何度か来日したことも、「ドール」を通じて知ってはいたが、観れなくて悔しいとは感じなかった。2018年、ピート・シェリーが亡くなったときは驚きつつ、そういえばずいぶんご無沙汰していたな、と頭の片隅でぼんやり考えたのであった。それが再びバズコックスが私の内なる肉に食い込むことになったのは―。
2022年の初頭の事である。前年にそれまで勤めていた職場を去り、心身の疲労から少しづつ、回復し始めた頃である。ひょんなことから知り合いになった方―これは「ever fallen on love」全訳の後記に記したK氏だが―とバズコックスのことで盛り上がった。
(そういや、もう何年も、聴いてなかったな)
もう20年余り、放り出しっぱなしになっていたバズコックスのCD。たまたま、本当にたまたま、70年代のアルバム3枚が、我が家に残っていた。他のロック、パンク~ニュー・ウェーヴ関係のレコード・CDの多くを散逸し、あるいは手放したのに、バズコックスのCDは手元にあったのである。プレイヤーにセットする。スピーカーから流れてきた、「あの音」私の中で、あの感覚がよみがえった。体中の血が逆流する感覚。
(ああ、そうなんだよ)
その音は、遥か彼方にある音ではなかった。ちゃんと目の前に鳴っていた。多くの音が、永遠の過去性の中で鳴っていたのに、バズコックスの音楽は、私の傍らで鳴っていることを、私は発見したのである。
私は夢中でCDを聴いた。こんなにも一生懸命音楽を聴いたのは、いつ以来であったろう。私自身、自分の行為にびっくりしたくらいであった。そして、うれしく思った。
「まだ、俺は生きてるんだよな」
あほなセリフだが、本当に、この言葉が口をついで出た。その日以来、家ではバズコックスの音楽がヘビロテで鳴るようになった。再結成後の作品を揃え、こんなにも作品を出していたのかと無邪気に感激したりしていた時、ピート・シェリーの評伝『ever fallen in love』の存在をK氏から教わった。もう何年も英語の勉強はしていない。辞書も押し入れの奥に突っ込んだままになっていた。体調の問題もあり、読める自信はなかった。
(まあ、いいか。英語の勉強をまた始めるつもりでやれば。しんどかったらやめればいい。これは強制ではないのだし。やめたところで誰からも責められるいわれはない)
たどたどしく、辞書を引きつつ、読み始めたところ、そのストーリーの内容に、ピート・シェリーの皮肉と反骨を湛えつつも品性ある語り口に、すっかり魅せられてしまった。さらに、著者のルイ・シェリーがバズコックスとビートルズとの間に深い親和関係があることを力説していること、ピート自身がビートルズから全てが始まったと発言していること、ピートとバズコックスの音楽的ルーツと私自身の音楽遍歴とがリンクする部分が非常に多いことも知ることができ、感動すること再三であった。そして私の音楽の聴き方に、それなりの太い線が貫かれていることを気付かせてもくれた。全ては私の中で繋がっていた。換言すれば、「品性を保ちつつ、己の内なる感情をテライなくさらけ出す音楽」と言えようか。バズコックスの音楽と、バズコックスのバンドとしてのありようは、それをわかりやすく知らせてくれる存在となっていたのである。この本の存在を知らしめてくれたK氏に感謝せねばならない。
私は『ever fallen in love』を読んだ証を形として残したいと思った。原著の全文を日本語に移し替えnoteに残そうと思った。著作権法も原著をきちんと明記すれば問題ではないようである。体調の問題、実家での諸々の問題も重なって無理だと最初は思ったが、
「俺がやりたいことだ。これは他人に言われてやることではない」
これが他人からけしかけられたら、私はウンザリして放棄し、逃げ出したに違いない。しかし私は本心からやりたいと思った。
その日から、日曜、盆暮れ関係なく朝3時から6時までの限定で作業にあたることを自らに課した。本を手に入れてから9か月かかってしまったが、どうにか年末には終わらせることができた。本音をいえば、もっと訳文を吟味し、独自の脚注もつけるべきであったけれど、時間がたつほどに訳文の、いや原著から受けるであろう鮮度がどんどん薄れてしまうことが怖く、さらには私自身の健康もどうなってしまうか判らなかったから、あのままの形で掲載することにした。
しかしである。ここまで一つのバンドに再度、何十年も経ってから夢中になるとは思ってもみなかった。人の心とはわからないものである。昨年秋にはバズコックスとして新作『ソニックス・イン・ザ・ソウル』も世に出て、それも含めて今もバンドの音楽を楽しんでいる。そしてこれがきっかけになったのか―単純に時間がたんまりできたからというのもあるが―他の音楽もゆっくり聴きかえせるようになった。ありがたいことである。
本稿を最初に記した時、この曲を貼り付けるつもりはなかったが、バズコックスは今を生きる(活きる)バンドであることを改めて記したく、ここに掲げる。アルバム『ソニックス・イン・ザ・ソウル』のキー・トラックであると共に、スティーヴ・ディグルからピート・シェリーへの挨拶であると思う。これからも俺はやっていくんだ、という意味の。
もう一言。バズコックスの来日についてつらつら考える。もし来日したとして、私はライヴに行けるだろうか。私を取り巻く事情から推して無理であろう。それでも、来日してもらいたいと思う。たとえその姿をこの目で見、耳で聴くことがかなわなくても、同じ日本の空気を、同じ時間に共有できる。その感覚を味わいたいと思う。ちっぽけな自己満足だとは承知しているけれども、今はそれが微かな望である。
