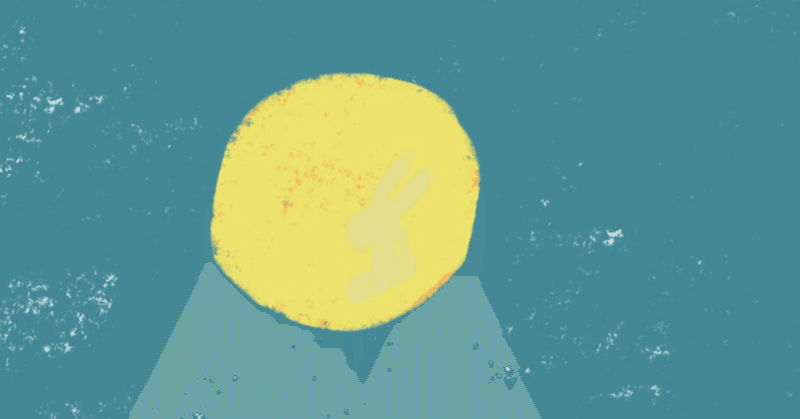
2000字掌編「小さな魔法使い」
目覚めたら、僕は、山手線の座席でヨダレを垂れながして、だらしなく横たわっていた。体を起こしたいけど、節々が痛むし、ひどい二日酔いのようで、頭を動かそうとするだけで吐き気がする。
陽の差し込む車内には、学生や会社員が身を寄せ合って立っているが、僕のまわりだけ、嘘のように人が居なかった。僕は相当、ひどい醜態をさらして眠りこけていたのかもしれない。記憶をたどろうとしても、ぼんやりとして昨日のことが思い出せない。僕はいつからここにいたのだろう?
「ねえおじさん。スーツがよれよれだね。」
こどもの声を聞いて、僕は視線だけを上にやった。黄色い帽子と眼鏡の小学生が、座ってこちらを見おろしていた。
「……二五歳はおじさんじゃない。」
答えたつもりの声は、のどがひしゃげているせいで、ただのうなり声のようだ。男の子は、白い頬を引きつらせて、くくく、と皮肉げに笑った。青いランドセルを背中に挟んでいるせいで、こどもは座席から今にもすべり落ちそうだ。
「ねえ、おじさん。かいしゃに向かってるの? ゆうがな出勤だね。ボク羨ましいなあ」
「……うるさいな。待て、今何時だ?」
腕時計は正午を指していた。完全に遅刻だ。血の気が一気に引いて、慌ててはね起きる。間髪いれず、がたいの良いおじさんが隣の席に大きなお尻をおろしたので、僕は小学生の隣に、小さくなって座りなおした。
僕が勤めるのは小さな会社だが、いわゆる体育会系だ。朝の集会で、昨日の営業成績ランキングを発表し、最下位はみんなの前で決意表明をさせられる。その集会に無断欠席でもしようものなら、鬼の部長が黙ったもんじゃない。恐る恐る携帯を見ると、部長からの不在着信が十二件もたまっていた。もう、取り返しがつかない。
「ボクはね、魔法が使えるんだよ。」
おもむろに小学生が口をひらいた。
「悪いけど、今それどころじゃないんだ。」
「いいからおじさんの悩みを教えてよ。」
「ご覧のとおり、会社に遅刻したことだよ。」
「それの何がもんだいなの?」
「……何がって、とにかく大問題なんだよ。部長に死ぬほど怒られる。」。
ただでさえ、昨日も、一昨日も、そのまた前も、朝の集会で僕の営業成績が最も振るわないことが指摘され続けていた。冷たい床に、額をこすりつけ、声を絞り出した記憶がよみがえる。今日こそは契約を取ります、今日こそは、今日こそは……。
「ぜんぜん大問題じゃないよ。おじさん知ってる? 地球の反対には遅刻して当たり前の国もあるんだよ。だからボクもこうして、」
「でもここは日本なんだよ。」
再び部長からの着信で震え出した携帯を握りしめて、僕は必死に考えを巡らせた。次の駅で降りてタクシーを拾えば、最短で会社に着くだろうか。
「やっぱりおじさんの言う通り、大問題かもね。ほら、おじさん、震えているよ。」
汗ばんだ小さな手で、無遠慮にぺたぺたと僕を触りながら、その子はなお、喋り続ける。
「ボク、魔法が使えるって言ったよね。ママに教えてもらったんだ。優しい人にしか使えない魔法なんだ。本当は誰にも教えたくないけど、おじさんにはとくべつだからね。」
こどもはマジックテープをはがして靴を脱ぎはじめた。座席に膝立ちになると、彼の分厚い眼鏡をかけた顔が、僕の顔よりも少し高くなった。この時になって僕はふと、正午の山手線に小学生がいる事の不思議さに気がついた。今は学校の時間じゃないか?
「おじさんはとくべつだよ。」
呟きながら、こどもは、細い腕で僕のぼさぼさの頭をだきしめた。
「おじさんのかなしさを、ボクが半分こしてあげる。」
視界がこどものボーダーの袖でいっぱいになって、それから頬が熱くなって、しばらくして僕は自分が泣いているのだと気づいた。
数字が全ての毎日。日々うるさく言われる営業成績。なんでもいいから契約を取らねばと、お年寄りの家まで尋ね歩いて、浄水器のセールスをするようになった。昨日はやっとおばあちゃんに契約書にサインをさせるところで、孫に警察に通報された。こんなこと間違ってると、ずっと分かってた。浄水器なんてくそくらえだ。営業成績なんてくそくらえだ。部長になんと言われようと、僕は、もう詐欺まがいの営業なんてやりたくない……。
「ボクは学校に行きたくない日は、こうしてずっと山手線をぐるぐるしてるんだ。おじさんも一緒にどう? 楽しいよ。」
僕は、震え続ける携帯の電源を、そっと落とした。明日のことは明日考えるとしよう。
「きみは、偉大な魔法使いだな。」
そう言うと、小学生はくくく、と笑った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
