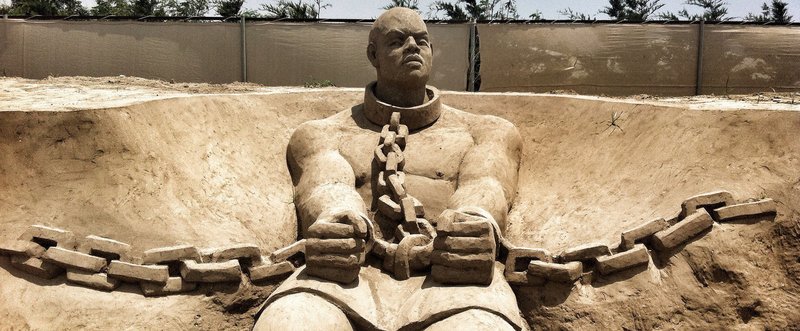
働き方のグラデーション
先日「IBM:自宅勤務制度の廃止」(2017年10月22日 Forbes)というニュースがSNSを賑わせた。大手としては2013年に米Yahooで同じように在宅勤務制度を廃止している。
ギルドは設立当初から、一ヶ所に固執しない制作スタイルをとっており、テレワークやリモート、ノマドといった働き方として注目されてきた。
やりたい仕事をやりたい時間に、やりたい場所で、やりたい分だけできるワークスタイルを目指して試行錯誤してきた。
そのためか、僕がテレワークやリモートワーク、ノマド、在宅勤務を推奨しているかのように誤解してる人も多いようなので、断じて違う!ということをここに宣言しておこう。
向き不向き
テレワークやリモートといった働き方は、そういう働き方が性格的に向いてる人向いてない人、向いてる業種向いてない業種、向いてる組織向いてない組織がある。
遠隔や在宅で勤務させることのメリット、デメリットは両方あって、取り上げられるのはメリットだけ。
会社という仕組みができてからこれまで、一度も会社に通って働くという制度が無くなったことは無いし、未だに大多数が、この仕組みで運用されているのは、通うことのメリットが大きいと感じてるからに他ならない。
これまで自然災害で交通機関が麻痺しようが、道路が閉鎖されようが、何とかして出社し、何とかして退社し、会社から来るな!と言われない限り、従業員は忠実に通ってきた。
東日本大震災は記憶に新しいと思うが、働く側も一定数は通うことに悦びや達成感みたいなものを感じ、平成の世も支配していることは間違いない。
ただ何となく今までの慣例だから、毎日通って、だらだら残って長時間労働を推奨する思考停止企業(通称 ブラック)などは、早く潰れろって思ってるだけで、どの企業に対してもテレワークサイコー!リモートサイコー!などと言うつもりは毛頭ない。
逆に言えば、テレワークやリモートに固執することもしていない。
ミス・コミュニケーション
毎日新聞のアンケートでは、約7割の企業が在宅やリモートの働き方を検討・導入する予定だと答えている。
ギルドが制度を導入しておいて言うのもなんだが「本気か?辞めておけ」と率直に思う。
先の2社以外にも、大手保険会社のエトナ社(Aetna)や家電量販店のベスト・バイ(Best Buy)も在宅勤務を廃止している。
また、日本マイクロソフト社が2016年に在宅勤務制度を廃止し、テレワーク制度に格上げしたとニュースになった。ここで言ってるテレワークに制度というのは、在宅勤務に限定していた制度をサテライトオフィスや遠隔地も含めて広範囲な制度にしたということで、実際のところは格上げか格下げか捉え方だろうけど、いずれにしても在宅による勤務形態がよろしくないという結論に達したということだろう。
そういう意味ではYahooもIBMも日本マイクロソフト社もその他の廃止した企業も1周先を走っている。
注目すべきは何でその制度辞めちゃうの?ってところで、出した結論はどの企業もほぼ同じ。
要するに、
コミュニケーション不足でチームワークの維持が難しく、業務に支障をきたす!
これには激しく同意する。所謂テレワークやリモートのデメリットの部分。文字だけでなく音声や映像を駆使して、様々なツールであれやこれややってみても、そのコミュニケーションはリアルなモノより薄まってしまう。共有すべき時間の感覚はズレるし、場の空気感も伝わらないので、スピード感や緊迫感、怒ってるのか冗談なのか、ギャグも滑っていたたまれない雰囲気時になったり、時にKY発言をしてしまうことも。
チームワークの重要性についてはチームラボの猪子氏も語っている。同社もノマドや在宅での就業は認めていない。スムーズなコミュニケーションが割と難しく、コミュニケーションが不足するのは実際にやってみないと気付かない点の一つだろう。
それともう一つ、帰属意識の問題。自分がどこの何者なのか?こういう意識も薄れる。毎日通っていれば、どこどこ社の何某って看板を背負って活動している自負を感じていられるが、テレワークやリモートだと他者と接する機会が減るし、毎日目にしてた自社の看板やロゴ、物理的に会社に通うことで切り替える境界線やトリガーみたいなものが存在しないので、在宅で呑気に過ごしてしまうことも多く、気を張っていない分どんどん帰属意識が希薄になる。
そこに社内で作業する者とのギャップが生まれ、「お前ヤル気あんの?」的なイザコザやイライラが募り、変な空気を創り出す 。
リモートや在宅勤務制度を辞めるという決断、そういう働き方がしたければ、そういう働き方ができる企業へ行けばいいという潔い決断を僕は指示する。逆に、そういう思想の人とは一緒に働けないという企業理念を堂々と示した形だ。何より実際に制度を導入し、効率的にも生産性も上がらないとなれば制度廃止もやむを得まい。
お前らに自由を与えてみたけどロクなもんじゃねぇなぁ
在宅勤務制度の導入を辞めた企業は、そう証明したに過ぎないかもしれないが、それだってやってみなけりゃわからなかったわけで、それなりに成果は得られただろうから正しい経営判断だと言える。
働き方の選択肢
テレワークやリモート、ノマドなど、在宅で仕事をしたいという人の意識も大切であることは、これまでも何度か書いてきた。一人でモクモクと作業をする類の業務には向いてる働き方かもしれないが、チームで仕事をする場合は他者とのコミュニケーションが極めて重要で、トラブルの殆どはコミュニケーション不足から起こることは間違いない。
上手く在宅で仕事をしたいのであれば、必要以上に意識的なコミュニケーションを積極的に取りに行く姿勢が働く側には重要だ。
また、企業はもう昭和の従属的で支配的な働き方を考え直す時期に来ているでしょう。勿論、従来通り通いたい人は相変わらずたくさんいるので、それも残しながら、テレワークやリモートなど在宅での働き方やサテライトオフィスやノマドでの働き方、今回は触れていませんが副業やパラレルワークなど、従業員の指向性やライフスタイルに合わせたフレキシブルな制度を取り入れて、0(ゼロ)か10のようにどっちかに振り切るのではなく、働き方の選択肢を、バリエーションを、用意することで職場環境や業務のやり方も変わり、近未来の在るべき企業イメージを確立できるのではないかと思うのです。
こコミュニケーションにおける最大の問題は
意思が伝わったと錯覚することだ
ジョージ・バーナード・ショー(アイルランドの文学者)
『働き方のグラデーション』ってお話でした。
弊社のクエストは「関わったら最後まで」。クリエイターやフリーランスの目指し方、働き方を提案。育成からマッチングまでを紹介するサポートマガジン || https://note.mu/aljernon
