
【その他】自分のことを自分で決めるって、どういうこと? ―第72回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国大会/第44回日本医療社会事業学会(大分大会)でワークショップを行いました
6月16日に、第72回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国大会/第44回日本医療社会事業学会(大分大会)が大分市内で開催されました。
くわしくはこちらからどうぞ☞
この大会は、全国規模で毎年開催されるもので、昨年は東京都、今年は大分県、来年は三重県の予定です。
今回の大分大会にも、全国から、実践現場の医療ソーシャルワーカーの方々をはじめとする医療従事者や学生さん方が参加されていました。
内容の充実はさることながら(当日のプログラムは、上記のホームページから確認してみて下さい)、参加者数は昨年の東京大会を上回った1000名を超え、大盛況のうちに終えられたそうです。
今回は、その大会で、私がワークショップの講師としてお招きいただきましたので、その様子を報告します。
テーマは、「緩和ケア・終末期医療における患者の意思決定支援について考える」です。
少し難しく聞こえるかもしれませんが、具体的には、緩和ケアや終末期医療において、患者さんが自分のことを自分で決めるってどういうことだろうというものです。
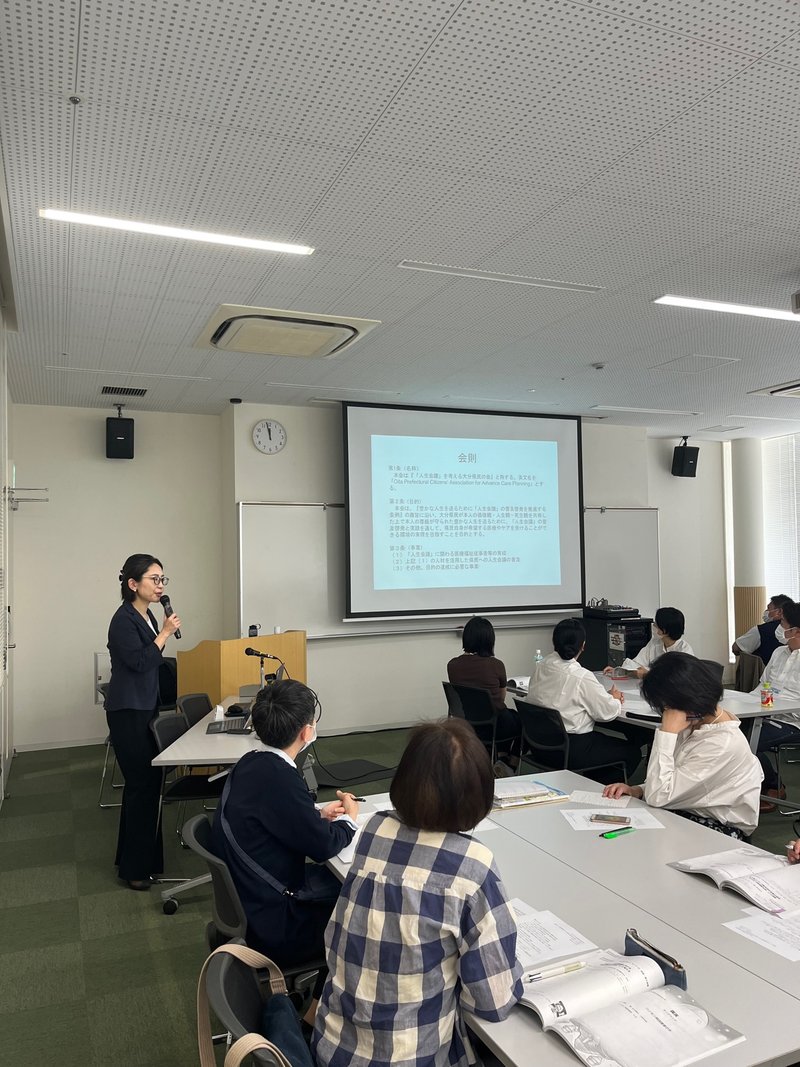
さて、ワークショップの内容を紹介します。
●患者さんの意思決定支援
医療の現場では、医療行為の方針の決定を、患者さんが医師から説明を受けたうえで決めることが原則として行われています。
そしてこの患者さんの意思決定には、いくつかの概念があります。
今回のワークショップでは、その概念のうち、インフォームド・コンセント(Informed Consent, 情報を説明したうえでの患者による同意)に加えて、最近話題になっている、シェアド・ディシジョン・メイキング(Shared Decision Making, 共同意思決定と訳されたりします)について紹介しました。
●アドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning; 頭文字をとってACPと表現します。)
上記のシェアド・ディシジョン・メイキングの一つの具体的なかたちであり、最近、緩和ケアや終末期で患者さんが意思決定をする考え方として、ACPがあります。
ACPの定義としては、「アドバンス・ケア・プランニングとは、必要に応じて信頼関係のある医療・ケアチーム等の支援を受けながら、本人が現在の健康状態や今後の生き方、さらには今後受けたい医療・ケアについて考え(将来の心づもりをして)、家族等と話し合うことです。」と紹介されているものがあります(詳しく知りたい方は、日本アドバンス・ケア・プランニング研究会のホームページを覗いてみてください) 。
●もしバナカードを使った演習
このACPを自分のこととして実感してもらうために、もしバナカードというトランプの形式のカードを使って、4人1グループによる演習をしました。
「いい人生だったと思える」「清潔さが保たれる」「私を一人の人間として理解してくれる医師がいる」「お金の問題を整理しておく」「ユーモアを持ち続ける」等の35枚のカードのなかから、「もし自分が余命半年だったら、なにを優先するか」を考えてもらい、自分が選んだカードについて、グループメンバーと意見交換をする演習です。
オンラインで手に入れられます。身近な人と、このカードを使って、もしものときのこと、つまり、現在の健康状態や今後の生き方、さらには今後受けたい医療・ケアについて考えて(将来の心づもりをして)、話してみるのもよいかもしれません。
●「人生会議」を考える大分県民の会
臼杵市医師会立コスモス病院の院長先生や大分県医師会の先生が中心になって、2023年から、大分県でACPを考える取り組みを行っています。ワークショップでは、その取り組みを紹介しました。
●ソーシャルワークにおける意味と課題
私自身の研究テーマとして、「緩和ケアや終末期医療において、患者さんの意思の確認ができないときの意思決定支援とはどのようなことか」というテーマがあります。
ワークショップでは、このことについて、ソーシャルワークにおける意味と課題をデータ等を踏まえて、紹介しました。
さて、ワークショップを終えての感想です。
ワークショップには、大ベテランの医療ソーシャルワーカーの方々をはじめ、看護師の方々、大学院生、学生の皆さんが、全員で60名近く参加されました。
講義には、熱心に耳を傾けてくださいましたし、グループワークではメンバー間の話に耳を傾けられている様子が感動的で印象的でした。
学生さん方も、大先輩たちにものおじすることなくでも真摯にディスカッションをされていて、その様子から、未来の世代に心強さを感じました。
そして、今回は、大分大学福祉健康科学部社会福祉実践コース4年の現役大学生2名にワークショップを手伝ってもらいました。
普段から、非常に優秀な学生たちですが、ワークショップ会場でもいかんなく力を発揮してくれました。
最後に、大学生たちのコメントです。
「終末期医療における意思決定支援では、ひとつひとつプロセスを踏み、進めていくこと、またそれを繰り返し行うことが重要であると学びました。
「人生会議」を考える大分県民の会等、取組が進められていることも知り、今後も興味を持って、人生会議や意思決定支援について学びを深めて行きたいとおもいました。」
「人生の最期の迎え方について、カードに描かれた具体例をみていくと、自分の今の価値観や大事にしたいものについて、整理することができ、最期の迎え方は「痛みがなければそれでいい」など決して単純なものではないと気づかされました。」
「終末期の意思決定において、支援者として、「第三者が決めることへの違和感」を持ち続け、何度も確認、話し合いを重ねることが重要であると学びました。」
もし高校生の皆さんがこの記事を読まれていたら、ぜひ、先輩たちのように、様々な視点でソーシャルワークを学び、学生のあいだから社会や世界に触れる機会を得てほしい、そして、こころの滋養をたくさん育んでほしいと、心から願っています!
(社会福祉実践コース 教授 上白木悦子)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
