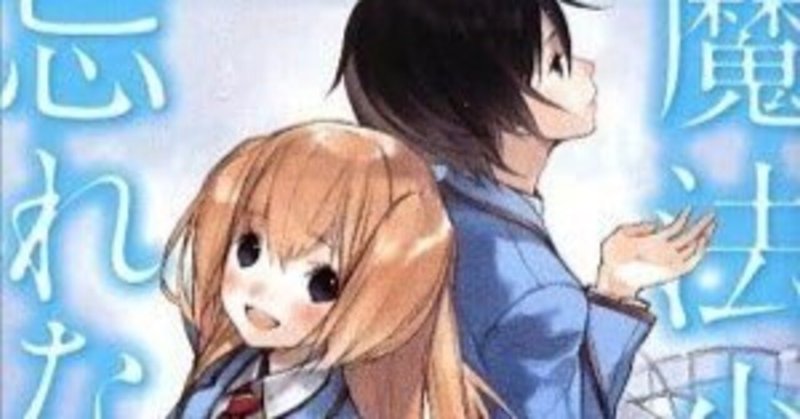
この単巻ライトノベルがすごい(かも)Vol.1 しなな泰之『魔法少女を忘れない』
・はじめに
単巻ライトノベルという言葉を正確に定義するのは意外に難しい。
現実的な話、続刊が予定されたのに諸事情で出版されなかったケースもあるし、応募時に完結している新人賞受賞作に続刊が出たりすることもある。後者の場合を単巻ラノベと呼ぶのは難しい気がする。だから新刊が出た段階で「単巻ラノベの期待作!」みたいに感想を言うのはなんか気が引けなくもない。なんか。
まぁそれはともかく、最初から単巻で締まっている作品」というイメージが手っ取り早いので、ふわっとそういう感じの作品を語ることにする。"1"とか"2"みたいにデカデカとナンバリングされていたらさすがに違うかなってなるけど関連作が出ている場合もゆるく含めていこうと思う。
ま、めんどい前置きはさっさとやめて本題に入るか。ようこそ単巻ラノベの世界へ……!
といきたいところですが前言撤回。もうちょっとだけ待ってもらって、前提として軽い持論を言わせてもらいたい。僕が興味を持つ単巻ライトノベルの名作には大きく分けると二種類あって、それは「青春路線」と「奇書路線」の二つである。
長々と定義論をするより、作品例を挙げるほうが分かりやすいだろう。たとえば前者の代表作は『ヴァンパイア・サマータイム』であり、後者の代表作は『インテリぶる推理少女とハメたいせんせい』である。
もちろん完全な二分法ではなく、奇書路線に近い青春(『ラン・オーバー』)や、青春路線に近い奇書(『消えちゃえばいいのに』)のようにスペクトル上に存在しているのだ。
これが、僕の考える単巻ラノベを語る上での序論だ。そして、その前者を考える上で見事な作品を見つけたので、まずはこの作品を紹介したい。
一冊目 しなな泰之『魔法少女を忘れない』
スーパーダッシュ文庫、2009年刊。
「――僕には、妹のことがわからない」ある日突然やってきた妹、みらいと共に過ごすようになって半年。高校生・北岡悠也は、まだ彼女との距離感を掴めずにいる。わからないことだらけの妹について、知っているのはたったひとつ――みらいが昔、“魔法少女”であったこと。自分の知らない世界を生きてきた少女に、兄として向き合う奇妙な日常。幼なじみの千花や親友の直樹、その助けを借りながら、季節は移ろい巡ってゆく。忘れ得ない大切な日々を分け合う、四人の少年少女の物語。悠也は魔法少女を忘れない。
※以下、後半の展開に触れます。ネタバレにある程度配慮していますがまっさらな状態で読みたい方は注意!!
現代的に解釈するなら、広義の妹もの(義妹もの?)と考えられるかもしれないが、ラブコメかと言われればそうではなく、また設定や終盤の展開でセカイ系とか泣きゲーみたいな側面もありつつそこまで振り切ってもおらず、よくいえばふわっとした、悪くいえば中途半端な作風。
……しかし、声を大にして言いたいが、僕はこの作品が好きである。
うまくいえないが好きである。
そしてそれは僕の考える単巻ラノベの魅力と繋がっているという予感もしている。だから、それをなんとかして言語化したいと思う。
まず、この作品において、「魔法少女」を巡る設定は、匂わされるだけでそれ以上の重要性を帯びていない。すべてはみらいが重い過去を持ち、やがて追い詰めるために用意された書き割りに思える。
一方で、もうひとつ激しいライトノベル的なテンプレートを意識させるのは、奇妙な喋り方をする幼馴染・千花である。他にもよくある悪友的ポジションの男友達や、男運の悪い個性的な女性教諭も登場し、この小説がラノベであることを声高に宣言しているようだ。しかし、やがて……
『魔法少女を忘れない』は、前者の(即席で、書き割り的な)"泣き"を呼ぶような残酷な設定と、ライトノベルのテンプレート的な人物配置がより現実的な高校生の青春ものに変化していくという、二つの側面が融合した作品ということになる。そして、後者にはボーイミーツガールだけでなく疑似家族的なニュアンスもある。このように考えていくと、いろいろな要素が曖昧に取り込まれてその一つ一つがふわふわとくっついた状態で『魔法少女を忘れない』という小説が存在しているように感じる。そのバランスは、人によっては中庸で刺激がないように感じられるかもしれない。
しかし、そのふわふわとした青春ファンタジーこそが、前者、青春路線の単巻ライトノベル特有の魅力ではないかと思うのだ。
文庫本一冊、たかが300ページほどで表現できるひとつの物語ができることは非常に少ない。その中でより大きかったり複雑なことをしたいとき、そこには技術的、作劇的な要請として、「中間項の欠落」と呼ばれるようなものが必要になってくる。最初は仕方なく飛ばしてくっついていたことが、やがて独自の効果を持った技法に変化していく。
僕は批評ではなく小説を読み、書く人間なので、セカイ系というのは厳然と作劇上の技法であると考えたくなるのだ。
それでいえば『魔法少女を忘れない』のセカイ系的な要素は要請よりも技法として使用されている面が大きいのではないか。魔法少女を深く説明しない、戦いは遠くで起きていることにする、主人公たちは元魔法少女の末路をどうすることもできない、その制度に異議を唱える力さえない。
さて、そんな世界の中で主人公たちは一介の高校生として生き、みらいと春夏秋冬の青春を送り、最後には高校生にできる範囲でみらいの人生に待つ結末を幸福なものにしようと努力する。
そして、そのために彼女――みらいを"ふつうの高校生"にひきもどすことになり、そこで千花は自分が主人公に抱いていた(そして、それがライトノベル的な言動を己に強いていた)心境を吐露し、主人公たちは高校生らしい恋愛問題を通り抜け、血の通った、ひとりひとりの少年少女たちとして、ライトノベル的なお約束(拘束でもある)の生活から一歩踏み出して、恋をする。
この物語が悲劇的に終わるであろうことは明らかだが、紙幅が別離を描くことなく終了する以上、読者にはそこで感じることがすべてになる。
終わりを描かない、という技法を使った作品として『魔法少女を忘れない』は非常に効果があり、一言では言えないような、胸の奥が痛むような、でもぬくもりも感じるような、そんな不思議な読後感なのだ。
ライトノベルという、穿った言い方をすればパルプ、その書き割りの世界に仕組まれつつも、喜劇からも、悲劇からも、その一歩前で立ち止まる――これこそが、僕が前者(青春路線)の単巻ラノベに惹かれる"中庸な"魅力なのだ、といえよう。
もしもこの小説に惹かれたら、ぜひ『銀色ふわり』(『REBOX』でレビューした)も読んでいただきたい。この二作はどちらも前者の単巻ラノベであり、似たような空気感を持っている(と勝手に思ってるだけだけど)。『魔法少女を忘れない』の電子書籍版はなぜかイラストが掲載されておらず、『銀色ふわり』に至ってはマーケットプレイス等の中古市場はさほど高騰していないものの絶版で電子化もされていない、簡単には入手できないが、僕の文章を読んで興味を持ってくれた方は絶対に失望させない自信があるし、こうして記事を上げることで少しでも単巻ラノベに光が当たり、より多くの人の手に届くようになる一助になれば……と先の長い妄想を語りたくなってしまったところで、そろそろ筆を擱こうかと思う。
つまり何が言いたいかというと……
妹萌え、いいっすよね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
