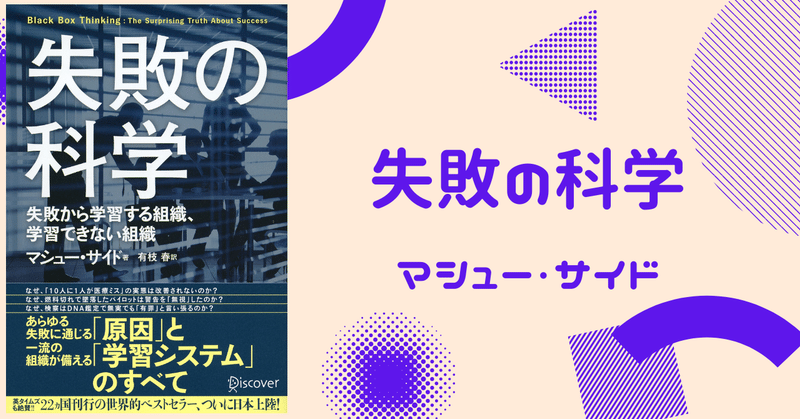
【要約】失敗の科学|成功したい全てのビジネスマンたちへ
「正しい失敗の活かし方を知りたい。。」
そんな方にぴったりの一冊を紹介します。
⬇︎こんなあなたにオススメ⬇︎
・正しい失敗の活かし方を知りたい
・いつも似たような失敗ばかり
・失敗したくない!
・失敗を恐れてなかなか挑戦できない
今回はマシュー・サイド著「失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織」について解説していきます。
この本の著者は、オックスフォードを首席で卒業した後、英タイムズ紙の第一級コラムニストやBBCのコメンテーターとして活躍した異才のジャーナリストです。
本書では、そんな著者が医療業界や航空業界、グローバル企業などあらゆる業界を横断し、失敗の構造を解説した上で、失敗を成功に活かすコツを解説しています。
本書は22カ国で刊行され世界的ベストセラーとなり、世界中多くの人に読まれています。
この本を読めば、失敗を成功に変える方法を学ぶことができ、もう失敗が怖くなくなります。一緒に学んでいきましょう!
なぜあなたはいつも同じ失敗を繰り返すのか
なぜ人は失敗から学ぶことができないのか。それは人間の持つ自分の失敗を認められないという特性に原因があります。
人間がなかなか自分の失敗を認めないのには「認知的不協和」と「非難」という2つの理由があります。
原因その1: 認知的不協和

認知的不協和とは、自分の信念と事実が矛盾していることによって起こる不快感やストレス状態を指します。これが生じると、人はこの状態を回避するために自分に都合の良い解釈をつけます。
例えば、12月21日に世界が滅亡すると預言した預言者の信者たちは、実際に世界が滅びなかった際に認知的不協和が生じ、自分たちの信仰する預言者を詐欺師と批判するのではなく、我々が信じたことによって世界は救われたという自分達に都合の良い解釈をつけました。
この信者たちは都合の良い解釈をつけることで失敗から目を背け、失敗から学ぶ機会を失っています。
原因その2: 非難

人は誰でも失敗を犯します。しかしそんな時、悪意のないミスを毎回責め立てられていたら、誰も自分の失敗を報告したがらなくなります。
失敗を繰り返さないためには、まずその失敗自体を報告してもらう必要があります。ところが失敗に対して非難されたり、懲罰があったりすると、その報告数は激減してしまいます。
ではどうすれば失敗から学べるようになるでしょうか。
あなたは成長マインドセット?それとも固定型マインドセット?

失敗から学ぶための1つ目の方法は、「成長マインドセットを持つ」ことです。
失敗には2つの考え方があります。
<失敗に関する2つの考え方>
・成長マインドセット:失敗を自分の力を伸ばすために欠かせないものだと考える。
・固定型マインドセット:失敗を自分に才能がない証拠だと考えている。なぜなら成功には生まれつきの才能が必要だと考えているから。
成長マインドセットを持つ人は、失敗を自分の力を伸ばすために欠かせないものだと考えるため、失敗を伴うような大きな困難にも何度も立ち向かうことができます。
これは失敗を繰り返すことで自らが成長し、成功につながるという考え方であり、固定型マインドセットの「成功には生まれつきの才能が必要」という考え方とは対照的です。
失敗を成功に変える方法

失敗から学ぶための2つ目の方法は、「失敗をデータの山と捉える」です。
失敗を単なる失敗として終わらせるだけでなく、失敗をデータの山と捉え、それらの原因を分析し対策することで、失敗を減らして成功に変えることができます。
例えば、あなたが転職活動の面接に落ちたとします。その際、失敗は2パターンに分けられます。
<失敗の2パターン>
・なぜ落ちたのかわかっている場合:とっさに質問に回答できなかった
・なぜ落ちたのかわかっていない場合:受かっている気満々だった時
そして、あなたがどちらの状態にいるかで対処の方針は変わってきます。
<失敗への対処法>
・なぜ落ちたかわかっている(とっさに回答できず面接に落ちた)場合
→システムを改善する
例)本番さながらの練習をする。予期しない質問への対処法を用意する。
・なぜ落ちたかわかっていない場合:
→テストする
例)身だしなみを整える。声のトーンを上げてみる。
なぜ落ちたかわからない場合は、原因としてあり得そうなものを改善しながら真の原因を探る必要があります。
このように失敗は、行動や戦略をどのようにアップデートすべきか教えてくれます。
こうして私はたった3年で弱小チームを優勝に導きました

失敗から学ぶ最後の方法は、「マージナルゲインを積み重ねる」です。
マージナルゲインとは、「問題を小さく分解して、一つ一つ試行錯誤を繰り返しながら改善することで将来大きな成果を得る」という考え方です。
この考え方に沿って、1%の小さな改善を毎日続けることで、1年後にはなんと38倍の結果を得ることができます。1.01の365乗ということです(≒38)。
例えば、あなたが仕事の生産性を上げたいとします。生産性は様々な要素がかけ合わさって向上していきます。そこで生産性に影響を及ぼす要素を分解し、一つずつ改善していきます。
<仕事の生産性をあげたい場合>
✔️朝の集中力向上のため、就寝前1時間はブルーライトを遮断する
✔️複数のタスクに追われて判断力が低下しているなら、シングルタスクを徹底する
✔️脳の機能をアップさせるために、栄養価の高いナッツを食べる
このマージナルゲインの考え方はGoogleやメルセデスベンツなどの大企業も採用しています。
マージナルゲインは非常に強力な手法ですが、使う際に意識すべき点が2つあります。
注意点その1: 試行錯誤の精度を上げる

高い精度の検証を繰り返さないと「成功か失敗か」の判断がつきません。本書では精度をあげる手法として、ランダム化比較試験が紹介されています。
先の例で簡単に説明すると、ナッツを食べて仕事の生産性が上がったとしても、それがナッツのおかげかは分かりません。もしかしたら他の取り組み・要因で上がっただけの可能性もあります。
それを知るためには「ナッツを食べるグループ」と「ナッツを食べないグループ」とに分けて再度生産性を比べてみる必要があります。もしかすると生産性は変わらないかもしれません。
注意点その2: 量をこなす

試行錯誤の精度を上げたら、あとはとにかく量をこなします。
本書では陶芸クラスの例が紹介されています。クラスを量で評価する組と質で評価する組に分けて作品を作らせたことろ、量で評価される組の方がたくさん作ったのはもちろん、作品の質も高かったそうです。
初めから完璧を求めて頭で考えるよりも、作りながら試行錯誤する方が質も上がります。やる前から頭を悩ませすぎてはいけません。
まとめ
今回は、マシュー・サイド著の「失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織」について解説しました。
著書ではこの記事で書かれている内容を、あらゆる業界での失敗の実例を数多く取り上げながら、より詳しく説明しています。少々ボリュームはありますが、読んでいてとても面白く、スラスラ読み進められます。
「失敗を無駄にせず、成功に変えたい!」という方は実際に手に取って読んでみてください。
タメになった・面白いと思った方は、いいね、フォローお願いします!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
