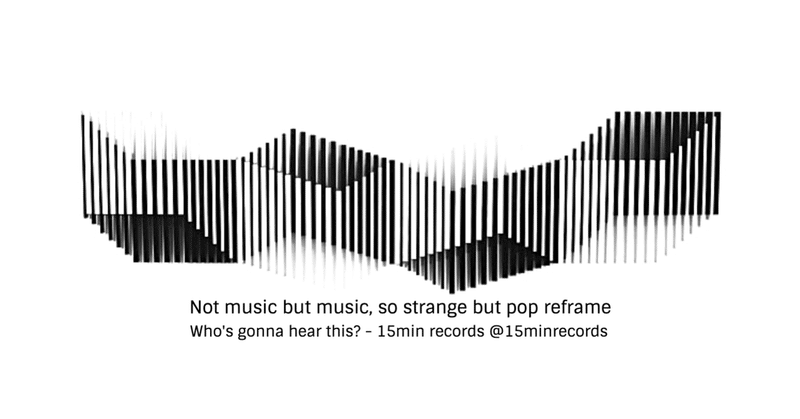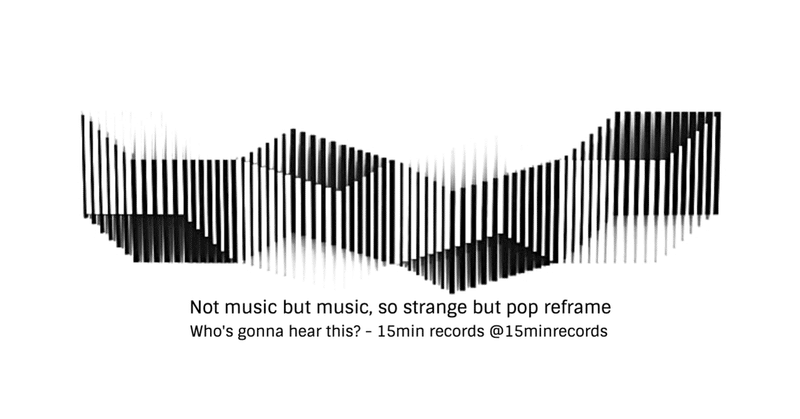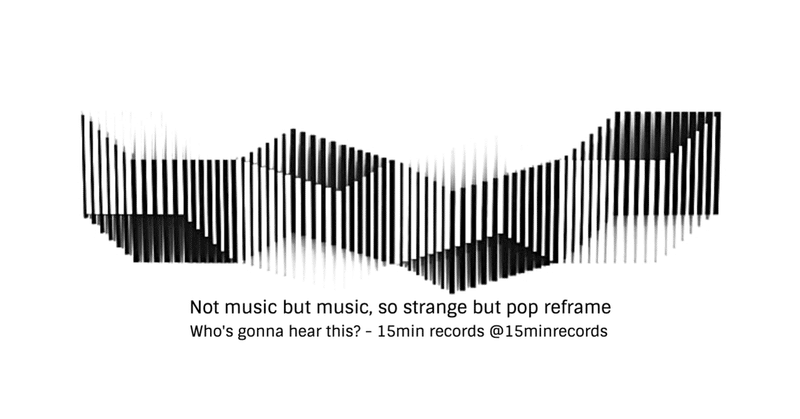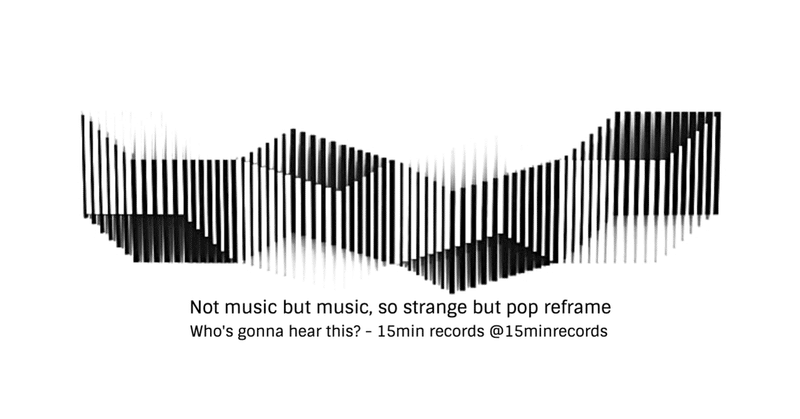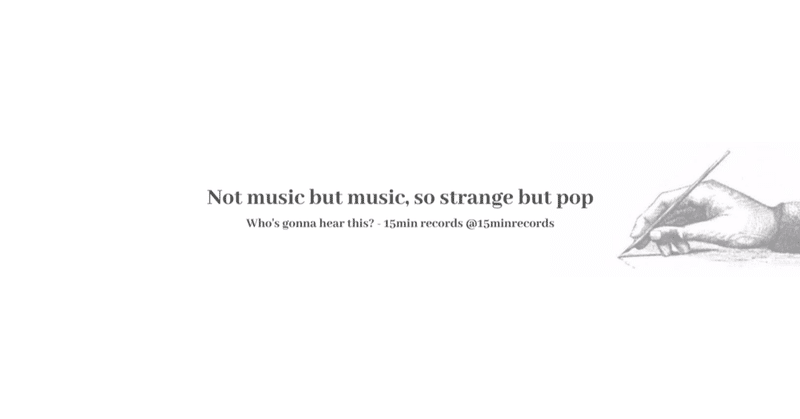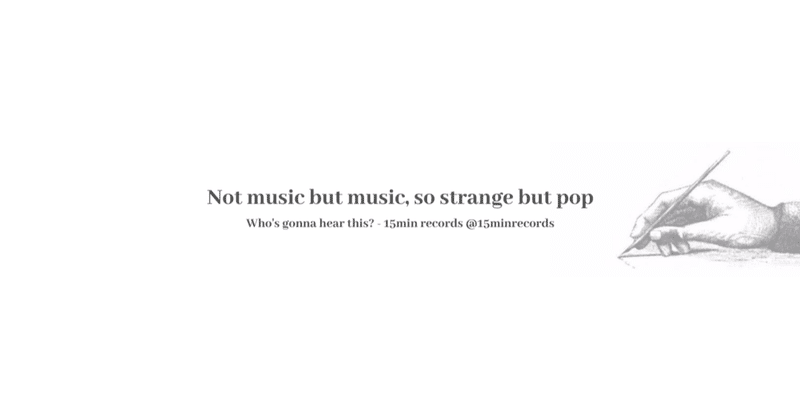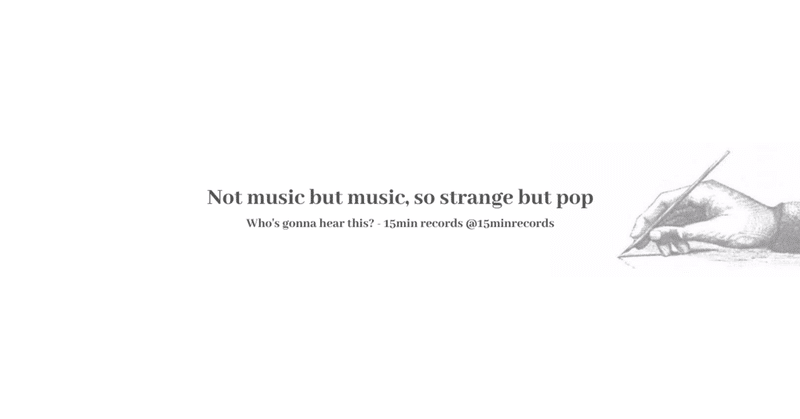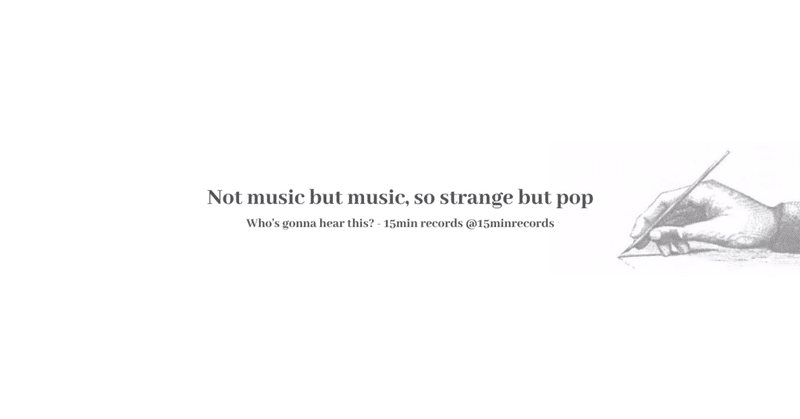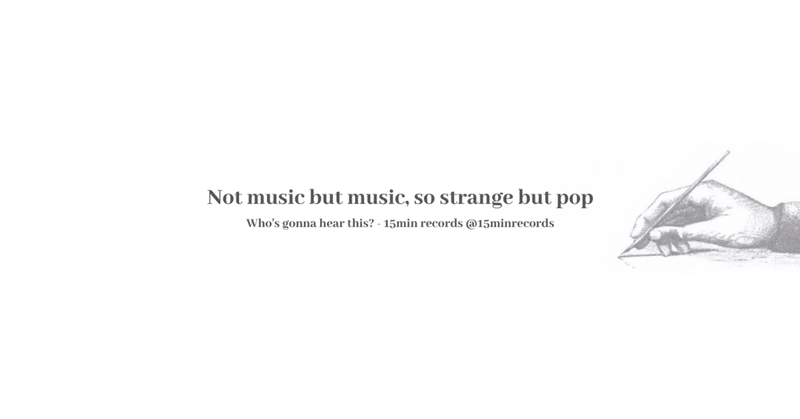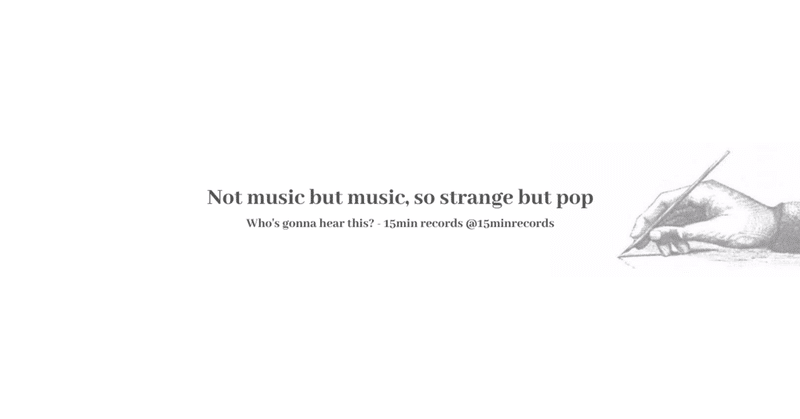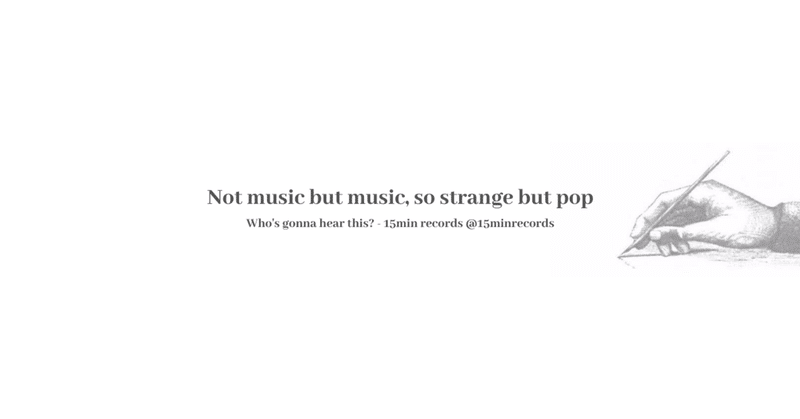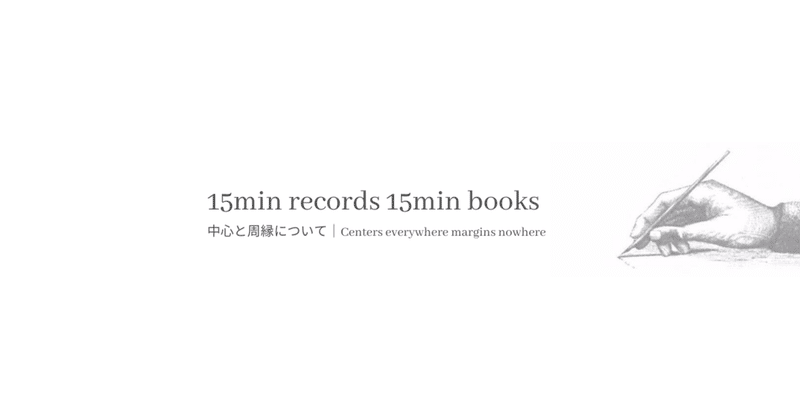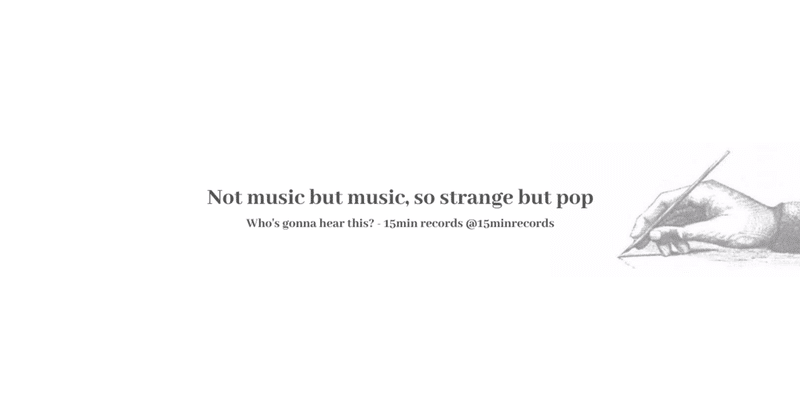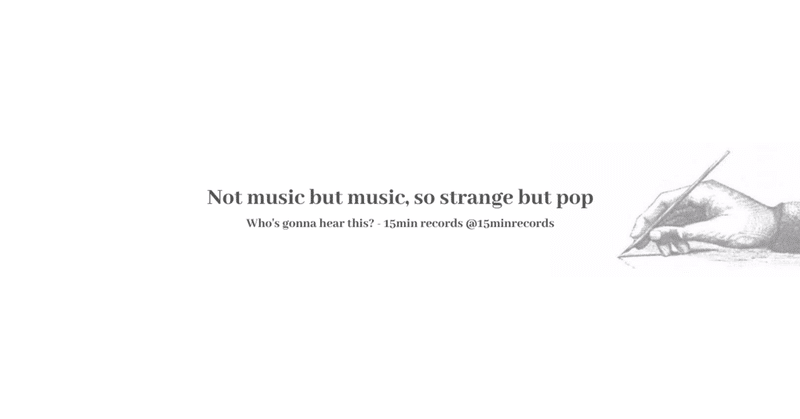- 運営しているクリエイター
#15minrecords
Not music but music, so strange but pop
バッハの「ゴルトベルク変奏曲」には、カイザーリンク伯爵が自らの不眠を解消するために作曲を依頼し、それを受けて作られた作品だと言う逸話がある。すなわち、眠るためまたは眠れなさをやり過ごすための音楽である。これを覚醒の音楽に変えたのがグールドの演奏だ。グールドはシートミュージックでは解釈できない演奏のニュアンスを含めて録音芸術として作り上げてそれを提示した。結果、彼は眠るための音楽に潜んだ眠れぬ要素に
もっとみるNot music but music, so strange but pop
マチューナス最後の作品は1977年のFlux Cabinetであるとされている。それはフルクサスに賛同した各アーティストの作品群をアンソロジー化したいというマチューナスの願望の集大成とも言える作品だ。一般的に、販売のためにマチューナスに譲渡された一連の作品やパフォーマンスを指してフルクサスという。そのフルクサスの集合体としてのあり方は興味深い。マチューナスは芸術共同体とクリエイターの創造性を訴えた
もっとみるNot music but music, so strange but pop
不意に視界が広がるということがある。しかしそれは一瞬の出来事で再びまたもとに戻ってしまう。それをどうにかしてとらえようと試み、あるいはリアリティというものを意識の観点から追求し続けたとされる脳科学者、ジョン・カニンガム・リリー。あらためて彼の研究に想いを馳せている。オルダス・ハクスリーの影響を受けた彼の研究は脳神経の研究にはじまり、イルカとのコミュニケーションなどいずれも20世紀のオルタナティブな
もっとみるNot music but music, so strange but pop
フーゴ・バルが1916年に発表した”Karawane”は最初の音響詩と言われる。彼はその作品の発表に先立ち「言語を一切放棄、言葉の最深部の錬金術に引きこもれ、言葉を見放して、文学の神聖な領域を守れ」と発表の意図を自ら示している。そして音響詩がはじまる。言葉に潜む音と意味を分離させ各々元の居場所に置き直すその試み。それは今もって未完である。
ところで、the future is certain,
Not music but music, so strange but pop
Facing the past - 15min records
“The future is certain, the past is unpredictable”
過去はうつろい、今は未来を照らす。今、今。不確かなものは不確かなまま、朴訥なものは朴訥なまま。Whisper words of wisdom, let it be、あるがまま、あるがまま。
Not music but music, so strange but pop
トマス・ヤングのダブルスリット・エクスペリメント。光源からの光は平行な2つのスリットを通り衝立上に干渉縞を生じさせる。光は粒子と波動だ、という訳だ。この光の縞こそがラスタ走査線に繋がるのではないかと妄想する。その妄想はさらにサウダージへと飛翔する。光は波であり粒子である。粒子はランダムでありながら文様を浮かび上がらせる。干渉縞はそこに何も宿るはずのない現象であろうが、その現象の美しさに心が揺さぶら
もっとみるNot music but music, so strange but pop
デュシャンが掲げていたとされる「傑作など無い」という言葉はまさにデュシャン自身のマスターピースが語られる場面でしばしば引用される。そうであったとしても、つまりマスターピースがそこに存在していたとしても、コンテンポラリーでありながら傑作であるという両立は極めて難しいという思いには十分共感できる。
そう考えていた時に規範と逸脱という言葉を目にした。規範から逸脱すること自体が規範であるとされる集団の中
Not music but music, so strange but pop
ノーマンメイラーは自作”The Naked and the Dead”の作中に「コーラス」というタイトルで登場人物たちの会話を挿入した。その会話は本来は物語の外に置かれるべきものだ。特に示唆するものもなく流れていくやりとりがエコーのようでもあり、また、確かにコーラスのようでもある。しかし挿入されたコーラスは確実に読者を揺さぶる。彼が最大級の賛辞を送ったバロウズもまた、彼のコーラスに揺さぶられた者の
もっとみるNot music but music, so strange but pop
トーマス・J・ワトソン・リサーチセンターにて、つまりIBMの研究部門にて、マンデルブロはフラクタルの概念を発表した。私は正直なところ、マンデルブロ集合というものを正しくは理解してはいない。それでもその概念に触れると、そこで描かれ無限に発展してゆく一連のフラクタル図形にマンダラを連想してしまう。そして同時に私はなぜかどうしても実際的であるはずの経済学が、より空想的であり思弁的であるマンダラに踏み込ん
もっとみるNot music but music, so strange but pop
ペレアスとメリザンド。メーテルリンクとドビュッシー。関係は必ずしも良好的とは言えない。しかし、それであっても流麗な旋律は物語が紡ぐ悲劇を一層感情豊かに膨らませることに成功している。しかし「今は小声で話さないといけない」。だからこそ通奏のあわいを縫って時に溢れ出る起伏は我々を十分に揺さぶるのだ。今でも!
さて、このあわいというのはなぜ我々を揺さぶるのか。杉本博司の”Theaters”は、あらゆる映