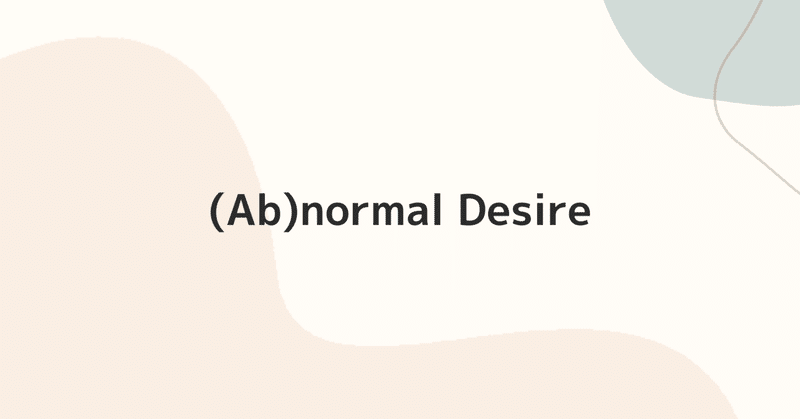
『正欲』と「強制的性愛」
内容を正確に思い出せなくとも「読んだ」ことを決して忘れない本がある。続きが気になって貪るように読んだ本、見落としていた気持ちに光を当ててくれた本。そのような本に出会った興奮は日を跨いでも続き、何回も反芻することによって自分の思考の一部となっていく。
朝井リョウの『正欲』は、私が先を急ぐように読み進めた本の一つである。この本は半年以上前に読み、それ以来再読していない。しかし、強く心が動いたことは鮮明に覚えている。普段から漠然と考えていたこと、私が他人から「理解されることはない」ことを再確認した。
ここでは、半年前の記憶を頼りにして『正欲』を読んだときの印象を記してみたいと思う。今、あえて再読することはしない。もちろん間違いが含まれている可能性は否定できないが、あくまで当時の記憶を優先することにする。
理解されることのない感情
『正欲』を読んで、特に、水に性的な興奮を覚える二人の主人公に親近感を覚えた。「親近感を覚えた」という表現は適切ではないかもしれないが、彼らの感情や行動は、私が普段感じているものと似通っているように思えた。
自分が他者と決定的に違うことを自覚し、他人から理解されることは無い、そして自分が多数派の行動を理解することもできない、という諦めに似た感情。
どうせ否定されるのだからと、他者との関わりを前もって避けるような行動。
それでいて一人で生きるのは心細いという矛盾。
彼らは、幼児性愛に関わる写真を撮影したとして取り調べを受けていた。ただ水の飛び散る写真を撮っていただけなのに、巻き添えを食らう形で幼児性愛者として扱われることになる。
当然ながら、幼児性愛に関わる写真を所持することは犯罪である。その犯罪を容認し正当化するつもりは毛頭ない。しかし、彼らの感じたであろう窮屈さは、より普遍的に、誰もが経験しうる形で存在しているのではないかと思う。
他者から押し付けられる自分
私たちは、他者から様々な期待を受けながら生活している。そのような期待はときに、自分の経験を豊かにしたり、ほどよいプレッシャーとして能力を向上させたりすることがある。
しかし「当然こうあるべきだ」という期待が過剰になると、自分の主体性を失ってしまったり、失敗することを恐れるあまり思うような行動を取れなくなってしまったりする。
もし誰かからの期待が、その人にとってはあたりまえすぎて「当然」と思える、無意識のものであったらどうであろう。『正欲』を読んで私が共有した窮屈さは、他者、それも「多数派」の期待から逸脱してしまった場合の無力感である。
その一例として、唐突ではあるがセックスについて考えてみる。ここでは、性に関する多様な行為を含むセックスではなく、異性間での性交という狭い意味でのセックスについて言及する。
何事もセックスを中心として回っているこの社会では、「正常」な人間ならば「当然」セックスに興味があるように扱われ、異性のことを性的に見るのが「当然」とされている。裏を返せば、セックスしない人間は「異常」である。性格に問題があるのではないか?モテないことが原因で強がっているだけではないのか?という詮索をされることになる。
しかし、誰かとセックスをしたいと感じたことが無い場合には、そのような規範を前提として話をされるのは窮屈なのである。「多数派」の信念というものは固定的なものであり、そのたびごとに訂正する必要があったり、否定される可能性が高かったりすることを考えれば、黙っている方が良いと考えるのも当然である。
それでも生きるために
水に対して興奮を覚える二人は、最終的に一緒に住むことに決めた。相互に理解し合える(少なくとも否定されることのない)関係を結べたことは非常に小説的で、不幸中の幸いといえるかもしれない。皆がそうなれば話は早いが、現実的ではない。
理解されることのない感情を抱いて心細く思っている場合、何ができるだろうか。ありふれた結論ではあるが、やはり「ありのままの自分でいようとする」ことが重要なのではないだろうか。
多数派とされる性癖を持っていなかったとしても、それは自分が欠けていることを意味しない。「私は~が好き」「~と一緒だと落ち着く」といった内なる感情を大切に、自分がしたいこと、なりたい自分を目指して生きていくことが大切なのだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
