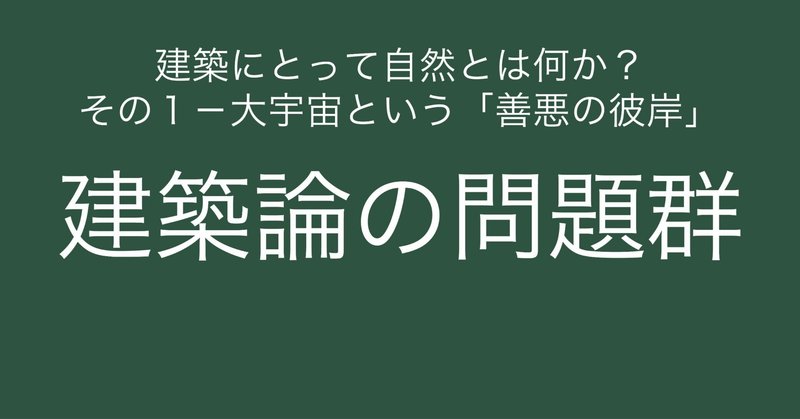
建築論の問題群04〈自然〉 建築にとって自然とは何か? その1-大宇宙という「善悪の彼岸」
田路貴浩(京都大学大学院教授)
自然に外部はない。まずこれを命題としてみる。
人間は自然にあらがい、対抗し、操作し、自然には存在しない世界を創り出そうとしてきた。そうした営みが〈建築〉だと理解することもできる。しかし、はたして人間は自然の外部に飛び出すことができるのだろうか?人間は自然の一部ではないのか。自然の外部に飛び出すことができるという意識自体も、自然の内部でのことではないだろうか。
『西遊記』に登場する孫悟空のひとつのエピソードが思い出される。孫悟空は筋斗雲で疾駆し、5本の柱が立つ世界の果てまでやってきたと思ったが、それはお釈迦様の手のひらの中だった。人間にとって自然とは、どこまで行っても飛び出すことのかなわないお釈迦様の手のひらのようなものではないだろうか。
かつて京都大学には、哲学的な建築論で知られた増田友也という建築家がいた。丹下健三の1歳年下で、戦後復興の1950年代、高度経済成長の1960年代、オイルショック後の1970年代に活躍した。その増田が考え続けた問題のひとつが〈自然〉だった。増田は、夢窓疎石が作った西芳寺の枯滝石組を「本然なる自然」の象徴だと解釈している(増田友也『家と庭の風景』)。「本然なる自然」とはお釈迦様の手のひらのようなもので、外部のない大宇宙と考えても良いだろう。夢窓が作った石庭は、お釈迦様の手のひらを自覚させる大宇宙の象徴なのだ。
人間は大宇宙の果ての外に出ることはできない。当たり前のことである。しかし、人間はこの当たり前をすぐに忘れてしまい、自然を逃れて自由に〈建築〉できると考えてしまう。その結末が地球温暖化だ。
地球温暖化は人類が引き起こした危機的な結果ではあるが、考えてみれば大宇宙の法則が作動したにすぎない。作用が大きければ大きいほど、その反作用も大きくなる。CO2の排出量が増えれば、地球の気温が上昇する。すべては地球のシステムの内部で生じる現象にすぎない。そこには善も悪もない。ニーチェのひそみに倣って言えば、大宇宙は人間的な「善悪の彼岸」にある。
人類は自然に手を出し、自己の生存に都合良いように改変してきた。しかしそれも度が過ぎれば、かえって不都合な反作用を招いてしまう。そうすると自然とどこかで折り合いをつけなければならないことになる。反作用の悪影響が顕在化しないバランスポイント。和辻哲郎はそれを「風土」として発見し、人為と自然の均衡状態を理想化した。そして、増田友也はそうした風土の眺めを「エスノスの風景」として論じた(『増田友也著作集Ⅰ』)。それはある民族集団が自分たちの居住域と折り合いをつけ、意味を与えた全体的なイメージのこととされていた。
自然と折り合いをつけるためには、まず自然と折り合いをつけようと思わなければ始まらない。そのためには大宇宙の認識が前提となる。悟空のようにお釈迦様の手のひらなど関係ないと思っているかぎり、自然との折り合いという発想は生まれてこない。
夢窓疎石の石庭は大宇宙の象徴として作られた。それは観る者を大宇宙の直観あるいは観相へといざなう仕掛けではある。とはいえ、それを磯崎新のように「つくりもの」、あるいは「始源のもどき」と偽悪的に呼ぶ必要はないだろう。たしかに人為的な石組みは、万物の根源なり大宇宙に対してはささやかな「つくりもの」であり、「もどき」でしかない。しかし重要なのは、そうしたつくりものを踏み台として大宇宙を思念することである。
人は日常生活で大宇宙を忘れている。ハイデガーは「存在の忘却」という難しいことを論じたが、ハイデガー自身の用語を使って、「存在」をむしろ「自然(ピュシス)」に置き換えてみてはどうだろう。人はふだん自然を忘却しているのだ。「大宇宙の忘却」と言ってもよい。
建築は自然からの自由を求める。重力にあらがって石を積み、柱を立て、ピロティで建物を持ち上げ、超高層ビルを立ち上げる。建築が地球上にどんどんはびこっていく。そして自然からその反動を受ける。ただそれだけのことでしかない。エコロジーと言っても、生物多様性と言っても、動物のための建築と言っても、それはあくまで人間の都合によるものでしかない。人間の動物や植物に対する責任や倫理という思想も、所詮、人間が地球上で快適に生存し続けるための方便でしかない。どこでどのように自然と折り合いをつけるかという問題は、「人間的なあまりに人間的な」問題なのだ。だからこそ動物のためとか、植物のためとか言わずに、人間が人間自身のために責任もって考えるべきなのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
