
死神ですが、なにか?第一話 #創作大賞2024 #漫画原作部門
以前より成瀬家は死神と関わりを持っていた。
1.成瀬梓が会社で思わぬ罠にはまりそうになり、あるビルの屋上でその気持ちを発散させる。
死ぬことも厭わないその姿を見て死神が現れる。死神はその解決のために知恵を授け、梓はそれに従い新たな出発をする。
2.死神と成瀬家の因縁は母が取引をしたのが発端だった。母はある日突然病気になるが、幸せを感じながら死んでいく。父・義正にその秘密が明かされる。
3.長距離トラックを運行する会社に転職した梓は、スケジュール管理を任される。
心やさしい運転手がある日、オーバーワークが祟って事故を起こし、積み荷の賠償を求められる。梓がトイレで願うと死神が現れるが、何もできないと言った。
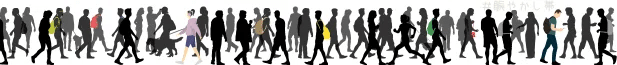
主な登場人物
成瀬 梓 (なるせあずさ)
義正(梓の父)
竜弥(梓の弟)
死神
第一話 林課長
第二話 梓の母
第三話 タケさん
死神ですが、なにか?
第一話 死神がやってきた
晴天の屋上に女性がひとり佇んでいる。正午を回ったこの時間に、何をするわけでもなく。
フラットな屋上から突き出したペンキの剥げた白い塔屋には錆びた梯子がある。その上に、切っ先を天に突き刺すように避雷針が立っている。
梓のデスクからこの塔屋がよく見えた。古臭くて不恰好なそれが自分に似ているようで嫌な反面、自分を象徴するもののようで気になる存在だった。
雲が太陽に掛かると梓は靴を鳴らし始めた。そうせずにはいられなかった。
どうせ誰も見てはいない。梓は制服のタイトなスカートを腰までたくし上げた。
梓の耳に匂い立つフラメンコギターの音色が聴こえてくる。それは時間を経てますます激しさを増し、その舞踏はもはや野生のものとしか見えなかった。
梓は隣のビルで働くOL。入社以来経理を担当している。
キーを叩く音、紙をめくる音、咳払い、ヒソヒソ声、たまに電話の話し声、小さな所帯の経理課はそんな日常だった。
会社はいちおう総合商社。商売になりそうなものなら何でも扱っている。タピオカのような食品から、工作機械までその種類は数多に及んだ。
従業員300人少々の小さな商社は、それはそれで居心地がよかった。この厳しいご時世にブラックなところがないのは奇跡のように思っていた。新しい経理課長が来るまでは・・・。
現経理課長の林は営業畑の人物で、経理の経験はなかった。前任者が定年で退いた際、経理課には管理職の適任者がなく、大学の商学部出身ということで、営業部の林に白羽の矢が立ったのだった。
営業というところはラフなところらしく、社外の人間に会う時以外はネクタイも外すし、なんなら草履を履いている者までいた。つまり体育会系のノリ。
営業とは切っても切れない経理に身を置く梓も、以前からそういう人物を相手にはしていた。
しかしフロアの違う営業部とは日常的に触れ合うことはなく、空気感まではわからない。それはそれ。自分に影響が及ばない限りはよしとしていた。それでも生温い水を飲んだような気持ち悪さは感じていた。
その営業のスタイル、空気を林課長は持ち込んできた。
お堅い前課長と比べてしまうせいもあるだろうが、林課長の仕事は怠慢を極めた。出社も帰社も適当で、捕まえるのが難しい。そのせいで仕事が捗らず、承認を繰り延べることも増え、そのストレスは溜まっていった。
梓はフラメンコと合気道を習っていた。合気道は幼いころからで、すでに黒帯。大抵の暴漢には負けないだけの実力はあると思っている。
一方のフラメンコは大学の卒業旅行で行ったスペインで見たのがきっかけだった。その激しい情熱の発露が梓の性格に合っていた。
しかし梓は小柄で顔立ちも質素。したがっておとなしいと見られがちだった。実際、自分を主張することは少なかった。
トラブルは日々の小さな積み重ねから、ある日今そこで突然生まれたかのように大きく膨らんで爆発する。
問題は出張費の前渡し金だった。
一般社員の場合は一日五千円と社内規定で決められている。これは交通費・宿泊費などの経費とは別で、社員への小遣いのような性格のもの。そこで課長は馴染みの顔からの要請があると増額して渡していた。
ある日のこと。出張から帰ってきた営業部社員が過剰にもらい受けた出張費の返還を拒んだ。
「君島さんが出張費の精算に応じてくれません。何とか言ってくださいませんか」
「そのうち払ってくれるだろうから、今日のところは、会議費にでも潜りこませといてくれ。余裕あるだろ?会議費」
「ありますけど、それって面倒なことになるんじゃないですか?」
「そんな硬いこと言わなくていいよ」
「では課長、この件はよろしくお願いします」
「これは上司の指令。わかるね」
そんな捨て台詞を吐きながら、課長は窓際の自分の席のブラインドをピシャリと閉めた。
私が手を付けないそういった処理は誰かに依頼したのだろう、いつの間にかどこかに消えていた。
梓のおとなしく見える容姿は、時に損な役回りを押し付ける。
学校でもそうだった。何かとクラスの役割が回ってきて、うんざりすることは度々だった。それに文句も言わず受け入れていた自分もよくなかった。
小学校の四年生になったとき、三年までは2クラスだったものが1クラスになった。生きもの係は四年生が朝早く登校して、餌やりをすると決まっていた。それまではクラスが交代でこなしていた餌やりを必然的に1クラスで受け持つことになる。上に兄弟のいない梓はそんなことは知らなかった。「生きもの係」それくらいならクラス委員よりいいや、と引き受けたが、毎朝早く登校しなければならなくなった。
いつの間にか空は暗くなっていた。空を見上げても太陽は見えない。
凪いでいた屋上に風が生まれ、それは強さを増していく。
つむじ風が目に見える渦巻きを生み、辺りの塵や埃を集め、さながら洗濯機の中にいるような、その中に引き摺り込まれそうになって、梓はグッと身を屈めた。
渦は真ん中に収束し、さらに高速で回り出す。
そこに人影が見えた。と思う間にそれは形を成した。
黒いスーツに黒いハット、黒い靴。
「誰?」
「あははは、驚かなくても大丈夫。風の精です」
「風の?」
「ここで何をしてらっしゃるのかお訊きしたい」
「ここの管理人さんですか?」男はニヤけた顔を向けた。「初夏の風を楽しんでいるとお答えしたらいいですか?」
「あんなに激しく?私はあなたに怒りを感じた。あまり風流な楽しみ方とは言えないな」
「あなた、何者?」
「だから・・・まだ名乗っちゃいないでしょ」
梓はサッと半身(はんみ)に構えた。
「まぁ待て。私は風だ。私を打つことはできないよ」
「できる。確信がある」
「どうして」
「自分の足元を見てみろ」
男の足元にはくっきりと黒い影があった。
「わかっただろ?影があるということは実体があるということ。どんな手品を使ったのか知らないけど、おまえは倒せる」
「わかった。まいった」
そう言い終ったときには梓の手は男の手首を掴み、己の身を翻し地面に組み伏せていた。
「参った。参りました。どうか落ち着いてくれ」
「落ち着いていますけど?」
「わかった。さっきの質問に戻ろう」
「じゃぁ正直に言いなさい。あなたは誰?」
「ふーっ、あなたがここで命を断つんじゃないかと心配になりましてね」
男は立ち上がって、さして汚れてもいない服を両手ではたいてみせた。
「そんなヤワじゃないわよ。ほっといて」
実際、梓の胸にそのことが去来したのは確かだった。いっそ死んでしまったらどうだろうと考えなかった訳ではない。
出張費の不正使用が会社幹部の知るところとなり、部長室に呼び出された。
その他にも、出張費の水増し分を遥かに超える額が消え、会議費や福利厚生費として記帳されていた。
梓は経理担当だが会計の責任者ではない。末端の事務処理を担当しているだけ。到底会計全般を俯瞰することはできなかった。
しかし会社幹部はその発端を出張費の水増しと見たらしい。それは本当なのかもしれないが、梓にはわからなかった。
課長の一歩後ろに従っていく。課長が部長室のドアを叩くと、ドアの向こうからくぐもった声がした。
「失礼いたします」課長に続いてそう告げた。
部長は二人を一瞥すると体を窓と平行に、横に向けた。
「何が言いたいかわかるね」ドスの利いた低い声はお腹に響いた。
「この度はたいへんご迷惑とご心配をおかけしました。私もたいへん心を痛めております」
私「も」?他人事?あちら側?首謀者は誰なのよ!そんなことは決して口にしない。しかしその言葉が梓の鼓動を早め、滾る血が体を駆け巡った。
「ちゃんと調査してレポートを提出してくれ。レポートは監査を通さない。いいね。以上」
上気した梓の顔を課長が横目で見ていた。
そんなレポート、筋書きだけ伝えて誰かに書かせ、梓の目に触れることなく提出されるに決まっている。それを部長が上に上げて幹部全員が知るところとなり、最終的にはシュレッダーにかけられて終わり。梓のレッテルだけが残されることになる。
横領なんかしてはいないし、不正にも関与していない。そんなごくごく当たり前な、言い訳がましい言葉が梓の胸にわだかまった。
しかし、もう決着したも同然のこの件。そのレポートで終止符なのだから、梓はデスクに一筆残していっそ死んでやろうかと思った。
そんなにしがみつきたくなるほどの命ではない。課長の不正を暴いて、目覚めを悪くすることができるなら、こんな命はくれてやる。
「あなた、誰なのよ」
「死神ですが、なにか?」
「ふふ、やっぱりね。なんかそんなんじゃないかと思った。・・・この大嘘つき」
「いや、本当だ」
「じゃあ、証拠を見せなさいよ」
「そんなものはありゃしない。私は正真正銘の・・・」
梓がまた男に向かって一歩、二歩と迫っていく。
「待て。待てって」
男はハットを取って見せた。その頭のてっぺんに平らで不格好な角がべったりと横に裾野を広げている。
「何それ」
「いちおう角ですが・・・」
「ははは、冗談でしょ?そんな弱そうで、べっちゃりしたのなんて見たことないわ」
「言ってくれますね。これ、帽子の邪魔にならないからけっこう気に入ってるんです」
「あははは、カッコわるっ」
「そんな画に描いた鬼みたいな角なんてどこにもありませんよ」
「驚いた。本当にいるんだ。いちおう信用してあげるけど、でもあなたは死神には見えないわ」
「この格好がよくないのかな?」
「服、パリッと新調したらどう?」
いちおうスーツの体を成してはいるが、よれて萎れてだらしなく映る。
死神は自分のへそを覗き込むように自身の服に目をやると、首を振りながらスーツの前ボタンを留め直した。
「あなたの手首に触れたとき、妙な違和感があった。この世のものではないような」
「その通り。私はこの世のものではない。しかしこの世のものでもある」
「どうでもいいけど大歓迎よ、死神さん。この命、持ち帰ってくれたらいい」
「あなたは何か勘違いなさってますね」
死神はそう言って空を見上げた。その視線の先に白い雲がおもちゃ箱を散らかしたように広がっている。もう先ほどまでの暗い空はどこかに消えてしまっていた。それを見て、空が翳ったのは男が現れたときだけだったことに梓は気づいた。
「死神は死を司る者ではありませんよ。私に命の与奪権はありません。ただ、追い詰めることはできますがね」
「なに?じゃ見物しに来たってわけ?私がここから飛び降りるのを」
「私は死の専門家です。すぐに匂いを嗅ぎつける。しかし今のあなた、そんな状態で死ねますか?」
「死ねるわよ。思い残すことなんてない」
「あなたの、ご自分のお父さんやお母さんのことを思っても?」
「母はもうずいぶん前に死んでいる」
「あなたはまだ死なない。あなたが死んだくらいでは、林課長は何の影響も受けませんよ。葬儀に出席するのを面倒だと思うのが関の山」
「よく事情はご存知のようね。遺書を書いたから。遺書っていうんじゃないけど、事の顛末を事細かに書いておいたから」
「もう削除されてますよ。あなたのブログ。その辺はできる課長さんだ」
「まさか」
「確かめてみればいい。私も末席とはいえ神なんでね。嘘はつかない。たまにしか」
「え?結局嘘つくんだ。あはははは」
「今、あなたが自ら命を投げ出せば、あなたに全てを押し付けてお終いになる。当然の結末だ。療養施設のお父さんに会社が賠償を求めることにもなりかねない」
梓はスマホを操作した。
「嘘じゃなさそうね。ブログは消えてる。毎日せっせと書いたのに」
死神はそれ見たことかと言わんばかりの顔をした。
「じゃ、あなたの望みは?何しに来たの?」
「さっき言ったでしょ。匂いがしたと」
「死の匂いを嗅いだって?それで私がここから飛び降りるのを阻止しに来たって?それ反対じゃないの?」
「私はどういう訳か、あなたの家族と縁が深い。どういう訳か」
「家族に何かしたの?」
「しましたよ。いろいろと・・・」
「誰に!何を!」
「そんなに心配しなさんな。ちゃんと生きてらっしゃいますから」
「嘘はあまりつかないって言ったよね」
「はい。つきませんよ。ほとんど。ほんの少し。本当にたまに」
「父と弟に電話してみるわよ」
職場にいるはずの竜弥にはLINEを入れた。
―なにかかわったことない?―
すぐに返信
―ねえよ なんだよ 仕事中なんだから―
―何もなけりゃいいのよ。ごめん―
LINEの送信時間が午前10時30分になっていた。もうお昼過ぎ。ランチタイムのはずなのに。
「竜弥君はお元気でしょ?」
「どうして名前・・・ああ、もういい」
父の入所施設への電話の呼び出し音が5回ほど鳴って、受話器を上げる音がした。
「もしもし、お世話になっております成瀬義正の娘の梓です。父に変わりはありませんか?」
「ええ、こちらこそお世話になっております。今日もご機嫌はいいですよ。安心してください」
「ああ、突然すみません。ありがとうございました」
発信時間を見るとこちらも10時30分。
「何もないでしょ?」
「ない。それはいいけど、どうして時間が10時30分なの?」
「何のことですか?」
スマホのLINEの発信時間と父の療養施設への架電時間を見せた。
「え?電話の故障でしょ?」
「そんなこと・・・。じゃあ、あのふたりに何をしたの?」
「三人でしょ?お母様も」
「母に何を・・・まさか・・・」
「それはあなたご自身が確かめたらいい。私が言っても信じない。どうせ自分で確かめることになるんだから」
梓は母が病死だったことに思い至った。しかし死神の発言は生前に母親と何か関わりがあったということを示唆していた。
「で、ここには何しに来たんだっけ?」
「そもそも、あなたはこの屋上に何をしにいらっしゃったのですか?」
「私はぁ、そのう、もしかしたら死んでやろうと思って」
「それは思い留まってくださったと思っていいですね」
思い留まるも何も梓にはそれほどの決意があったわけではない。
「でもねぇ、もう会社にはいられそうにない」
「では転職すれば?会社なんて星の数ほどありますよ。転職先も砂の数ほど」
「簡単に言うのね」
「簡単なことですから。辞表書いて、一発喰らわして辞めちゃえばいい」
「一発喰らわして?」
「このままじゃあなたも困るでしょう。転職先まで付いて回るかもしれない。悪い尻尾はなるべく根元で断ち切る。それが賢い生き方だ」
「簡単に言うのね」
「簡単、じゃないかもしれませんが」
「そう。簡単じゃない。ことは私の知らないところで進行してるんだから」
「では少しだけ知恵をお貸ししましょう」
「どうやって?」
「それを今、明かしてしまったら面白みがない」
「信用しても大丈夫なの?」
「私は末席とは言え、神ですよ」
「ああ、わかったよ。死神だけどね」
「私は誇りをもってこの仕事をしているんですけどね。今のところ転職も考えていない」
「へえ、転職なんてできるの?」
「できますよ。地獄の門番とか。退屈な仕事です」
「そんなのがいるのなら会ってみたい」
「いずれ機会があればお引き合わせしますよ」
「へぇ、たのしみ」
「今の門番の彼はすごく綺麗な角を持っている」
「ふーん、羨ましいんだ」
「そんなことはありません。ただうつくしいものはうつくしい。それだけです」
「まぁいい。じゃお手並み拝見させていただくわ」
死神は少し微笑んだ、ように見えた。そして帽子の縁を舐めるように指を滑らすと、黒い煤のような影となって風に吹かれて消えてしまった。
聴いたこともない音楽が鳴りやんでハッと気がつくと、空に浮かんだ雲が勢いよく東へ流れていくのが目に入った。
梓は屋上に寝ころんでいた。
時計を見ると、まだお昼休みの終わりまで25分あった。
「急がなきゃ」
ちょっと遅刻したが、オフィスは何事もなかったように静かな空気が流れている。
課長が廊下から梓を手招きした。
「君、辞表は提出してくれるだろうね」
「そんなことを心配なさってたんですか?もちろんです。私の担当で起きた不始末です。責任は取ります」
「いつ?」
「一週間以内に」
「一週間か、もう少し早く何とかならないか」
「では5日では?」
「まあいい。それで頼むよ」
「お詫びはなしですか?言っておきますが、私は損害賠償や欠損金の穴埋めには応じませんよ。裁判になれば、とことん戦います。隅々まで調べれば証拠が挙がってくることは課長もご承知ですよね」
「ああ、わかっている。そっちは私が何とかする」
梓は会社が表沙汰にする気がないのは百も承知。
「レポートの提出期限は?」
「一週間」
「ああ、それで。私にいられては困るわけですね」
「まあ、さっさと荷物をまとめて出て行ってくれ」
「かしこまりました。ここには未練の欠片もありませんので」
「ん?」
課長は微妙な顔を梓に向けた。
「どうしてこんなことになったのか、わかってらっしゃいます?同じことをすれば同じ結果になりますよ」
「あとのことは心配せんでいい。この場だけ凌げればいいんだ」
「あ、あと。これまでの会話、全部録音してありますから。もちろんこれも」
ベストのポケットからボイスレコーダーを取り出して、再生ボタンを押した。
―あとのことは心配せんでいい。この場だけ凌げればいいんだ―
再びレコードを押した。
「見くびってたよ」
「でしょうね。首を洗っといてください」
「首を?何様のつもりだね」
「介錯の刀が首の骨で止まって、頭がだらーんと肩にぶら下がったらおいやでしょ?」
課長の顔がなんとも言えない歪み方をした。
「変なレポートが提出されたらこれ、部長のポストに入れておきます。あなたが消されたブログ記事と一緒に」
「勘弁してくれよ、さっさと消えてくれ」
「ああ、雑誌社に持って行く準備もしてありますから」
梓は踵を返して席に着いた。
いつの間にか課長が梓の背中に張りついていた。
「それ、譲ってもらう訳にはいかないか」
「しっかり退職金がいただければすべて削除しますよ。このご時世、ものを渡したところでコピーなんていくらでもできるんです。私の言葉を信じていただくしかないですね。退職金次第」
課長の汗が落ちて来そうで、梓は立ち上がった。
「いくらほしいんだ?」
「誠意の金額。足りないと思ったらそのまま返金します。雑誌社の方が高く買ってくれるかもしれないし。最後くらいは気持ちよくお取引できたらと思います」
課長は口を半開きにしたまま、すごすごと引き下がった。
そんなのハッタリに決まってるじゃない。そんな証拠があったらもっと早く、もっと簡単に片づけてる。
梓は死神の顔を思い浮かべた。あいつ、なかなかいいセンスしてる。
第一話 終わり

第二話
第三話
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

