
わたしのイカイ地図⑩ #創作大賞2024
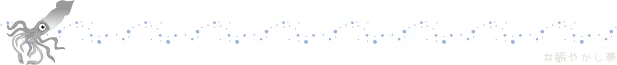
第十話
翌日、B氏の部屋の側まで行って問いかけると、今日は看護師がいるからダメだということだった。完全看護というのは大袈裟だとしても、ちゃんとケアはされているらしい。
ふらふらと誰もいない地上の道を歩くのは気分がいいもの。もっと早くから、こうすればよかった。
翌日、B氏を訪ねるといくぶん元気そうに見えた。一昨日よりもちゃんと座っている感じがあるし、声がしっかりしている。
「こんな黒い私といるのは気持ち悪くないですか?」
「どうして?黒くても青くても全然平気よ。ああ、そうね。私にはバイアスがないの。白でなきゃならないっていう」
「ミカさんの滞在歴が短くてよかった」
「私ね、ほんの3日間だけど自宅軟禁されてたから、ここの言葉をマスターしようと思ったのよ」
彼は軽く笑った。
「むずかしいでしょう。ここの言葉はたぶん私たちの種しか話せません」
「諦めたわ。ねぇ、ちょっと変なこと訊いていい?」
「はいどうぞ。なんでも」
「あなたたちはどうやってセックスするの?イヤだったら答えなくていい」
「私はラボの職員ですけど、同時に生物学者ですよ。セックスの方法はこの手の先、だいたいは左手の先端です。因みにですが、この手が切れると再生しません。他の手足は再生するんですよ。それを相手の頭の下、つまり座っている部位ですね、そこに差し入れます」
「ふーん、いやちょっと気になったけど、他の人には訊けないと思って」
「はい。微妙な事柄ですからね。あなたはメスですから、お尻の下ですね」
「やだ、メスなんて失礼です。女性と言ってください」
「ああ、すみません。こちらにはそのような区別がないものですから、そうした微妙な言葉遣いが難しいんです」
「私たちのような異種でそのような交流は可能でしょうか」
「それはわかりませんが、子孫は残せませんよ。遺伝子が違いすぎる」
「そうね、その辺に病気の治療の役に立つ何かがあるんじゃないかって思ったりしたんだけど」
「どういうことですか?」
「私は無理だけど、男性が精子を注入すると何か化学変化みたいなことが起きるんじゃないかって考えたり、それは良くも悪くもだけど」
「それは実際にしてみないと何とも言えませんが、何も起きない可能性が一番高いです」
「それから精子や卵子そのものが役に立つとか。どちらも一個の細胞として、生体を離れても生きてるっていう特別な存在でしょ?」
「はい、そうですね。そこに目を向けたことはありませんでした。ミカさんには言ってませんでしたけど、ここにはもう一人、人間界の人がいるんです。男性です」
「え!どこの方?」
「ウズベキスタンです。ご存知ですか?」
「行ったことありませんけど、知っています。どこにいるんですか?」
「それは私も知りませんし、会ったこともありません。上層部は人間について、かなり詳しい研究をしています。人間という種は一人だと大人しいが、複数になると凶暴になるとされています。どう思います?」
「そういう心理は確かにあると思います。でもみんながみんなそうじゃないし、必ずしも凶暴にはなりません。むしろ稀です」
「やはりそうですか。この世界でもそういう傾向はあります。複数だと気が大きくなるというんですか。群れの心理は共通しているのかもしれませんね」
「過去の研究から、そういう間違った結論に至ることってよくありますよね。歴史は再々書き換えられています。未知の社会だと尚更かもしれません」
「どうです?海には行かれましたか?」
「いいえまだ。行けるのかなぁ」
「行けると思いますよ。そんな連絡が私が倒れた日に来ていました。行けるならエレベーターのドアが開きますから立ってみて・・・」
彼の体の動きがその時、急に荒くなった。
「お願いがあります。私の体を海に埋葬してください」
「そんなことできるんですか?」
「できます。あなたを私の子どもとして申請します」
彼は揺れる体をテーブルに預けるようにして、そこをしきりにタップした。その必死の形相が伝わってくる。
「おそらくこれでできました。養子縁組は簡単なんです」
彼は自分のチップを胸から取り出して、私に渡してきた。
「これ、持ってたらいいのね」
「死ぬのは構わない。でもあなたと離れたくない。なんてそんな臭いセリフは吐きませんよ。あなたの言葉を必死で勉強したんです」
「もっともっと生きててほしい」
「ふふ」
彼の体を支えている私の腕にはもう彼の体温は伝わってこなかった。
「この感じ。もうすこ・・・」
その冷たい体は、それから動くことはなかった。私は彼の体を横たえ、それを強く抱きしめた。
夜になって、さらに朝が来た。
クローゼットから服を取り出して上から被せた。
「黒いの、気にしてたもんね」
でもどうしてあの時、紫外線を浴びる危険を冒してまで、地上から役所まで私を案内したの?私が寄り道したからより時間がかかったのに、あなたは何も言わなかった。
部屋の中から手稿がたくさん見つかった。植物学に関するものらしい手稿を手に取った。
あなたの書いたものが読めたらいいんだけど、私にはまだ無理。でもいつか読めるようになりたい。
医師なのか検視官なのかわからないイカたちがやってきたので、私は娘だと名乗ってチップを見せた。
外に出るように促されて、私は葬儀屋に向かうと告げた。他に何も、どこも思い浮かばなかった。
葬儀屋の店主は私の問いかけに、体内から骨だけを取り出して火葬する。そして体は乾燥させると言った。
彼の遺体はもうあらかじめ決まっていたかのように手際よく葬儀屋に到着し、二種類のオーブンで荼毘に付された。
いたたまれなくなって地上に出た。
こんな日がくるなんて・・・
こんな日がやってくるなんて・・・
そんなことばかりが頭をめぐる。
葬儀は形式、でもそれは文化の表象、そんなことを話してくれたっけ。もう何年も何十年も前のことのように思える。
私は彼の子どもにはなれた。その証、胸の中に収まるほどに小さくなった彼を抱えて、私は家路に就いた。
つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

