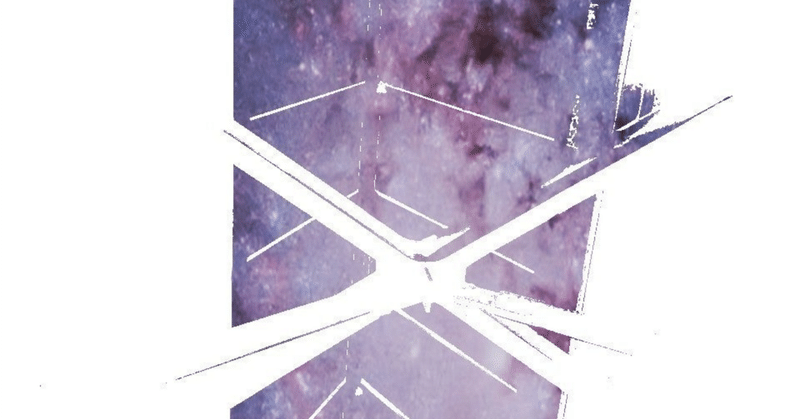
すい星列車がやってきた!(2)
「第37回 福島正実記念SF童話賞」一次選考落選作品
いつの間にか黒い雲はどこかにいってしまったみたいだ。
すい星列車の窓の外には、いちめんにビーズを散らばしたようなみごとな星空がひろがっている。
「――ありがとうございます」
わたしはそういって、となりにすわる星子さんにおじぎをした。
「パンケーキ、おいしかったです。おみやげまでもらっちゃって」
「いいよ、それくらい」
星子さんは笑って言う。
「それに」
「それに?」
「――なんか、楽しかったです」
「……そう」
星子さんはそう言ってもう一度笑った。今度はさっきとはちがう、ちょっとはにかんだような笑顔だった。
「この列車に乗るのは、はじめて?」
星子さんの質問に、こくんとうなずいて答える。
「……星子さんは、よくくるんですか?」
「そうだね。常連とまではいかないけど、何回かね」
テールと話している時も、星くずパンケイクスにいる時も、星子さんはとても慣れている感じだった。ふしぎなお金も持っていたし。
「――テールには、なんて言われたの?」
聞かれた言葉に、首をかしげる。つけたすように、星子さんがつづけた。
「一番さいしょに、なんて声をかけられた?」
「えっと……たしか『なにか悲しいことがありましたか?』って」
「そう……」
星子さんは、窓の外の星空の、うんと遠いところを見ながら言う。
「辛いとき、悲しいとき、さびしいとき……私は何度もこの列車に助けられた。――だから、きっとこの場所は、あなたのことも守ってくれるよ」
星子さんはそう言って、まるでつぼみがゆっくりと花開くように笑った。すごくきれいで、やさしくて、なんだかなつかしい笑顔だった。
そんな顔で見つめられるとくすぐったくて、けれどふしぎとうれしくて、わたしはぽりぽりと鼻の頭をかいた。
星子さんはそんなわたしの様子をみて、ふふふと小さく笑っている。
ピンポンパンポン。
「きんきゅうじたいが発生したため、一時停車します」
テールのアナウンスのあと、プシューッという音をたてて列車がとまった。
「何があったんだろう……」
「いってみよう」
星子さんはそう言って、わたしの手をひいた。
向かったのは先頭の車両だ。
一歩入ると、そこはもう客車とはぜんぜんちがう。
たくさんのくだやメーターにかこまれた部屋のまんなかに、ぽかんと大きな穴がひとつ。その向こうでは、青白い炎のようなものがゆらゆらとゆれていた。
「――困りましたねぇ」
頭をかかえたテールが、うーんうーんとうなっている。
「どうしたんですか?」
星子さんがそう声をかけた。
「おふたりとも。急にとまってしまってすみません。それが、このとおりでして……」
「やめろ! こら! 羽根をつまむな~!」
テールの手の中で、なにかがばたばたとあばれている。
よく見ると、それは小さな人間のような姿をしていた。
「……妖精?」
そう。まるで絵本で見た妖精みたいだ。
背中には虹色に光るトンボの羽根のようなものがついていて、そこからわずかにきらきらと光る粉がまっている。
「《星食い》ですよ」
テールはそう言って、足もとに転がっている箱をつん、とつま先でつついてみせた。
「この列車の燃料である星くずは、《星食い》の大好物なんです。見て下さい。この箱いっぱいに入っていたのを全部、この子が食べつくしてしまったんですよ」
テールがそう言ってはぁっとためいきをつく。
「どうしましょう。このままでは燃料がつきて、この列車は動かなくなってしまいます」
「それって、このまま家に帰れなくなっちゃうかもしれないってこと⁉」
わたしがびっくりして声をあげると、《星食い》は気まずそうな顔でうつむいた。なんにも言わないけれど、「悪いことしちゃったかな」って顔に書いてある。
そもそも、どうしてこの子は盗み食いなんてしたんだろう?
足元の箱は、わたしが両うででやっと抱えられるかどうかという大きさだ。これにいっぱい入っていた星くずを、残らず食べつくしてしまったなんて……。
「よっぽどおなかがすいてたんだね……」
わたしがぼそっと言うと、《星食い》の肩がぴくりとふるえた。
「――そういえば、おかしいですね」
テールがそう言って、手の中の《星食い》をのぞき込む。
「あなたたち《星食い》は群れで生活すると聞いたことがあります。ひとりでは生きていくことがむずかしいと――」
「おれだって、好きでひとりでいるんじゃねーよ!」
《星食い》はそう言って、テールの手の中でばたばたとあばれた。
「――つまり……迷子ってこと?」
わたしの言葉に、もう一度《星食い》の肩がふるえる。
「迷子って言うな!」
《星食い》はそう言って、テールの手から脱出するとわたしの頭の上をくるくると飛んだ。
「父ちゃんも母ちゃんもリリもミミも……、あいつらが迷子なんだ。おれじゃねぇ!」
《星食い》の言葉を聞いて、星子さんが言う。
「いるよねぇ、こういう迷子」
「だから迷子じゃねぇ!」
ぎゃんぎゃんと文句を言う《星食い》を見て、テールはなやんでいるみたいだ。
「どうしましょう……。ご家族の居場所は、ほんとうにわからないのですか?」
《星食い》はうつむいたまま答えない。
テールはさっき、《星食い》はひとりで生きていけないって言ってた。ということは、この子はこのままだと死んでしまうのだろうか。
「――……せんか」
そう思ったら、口が自然に動いていた。
「この子の家族を、さがせませんか」
テールは顔をあげて、わたしのことをじいっと見つめた。
「――私には仕事があります。この列車を動かすために、まずは新しい燃料を用意しなくては」
「……」
テールの言葉に、わたしはぐっとだまりこむ。そうだよね。だってテールはこの列車の車しょうさんなんだから。
「じゃあ……」
ぐっとこぶしをにぎりしめながら言う。
「わたしが、この子の家族を探します」
わたしは思い出していた。お父さんとケンカして、お母さんにも会えなくて、まるで世界にひとりぼっちでいるような気持ちになっていた時のことを。
この子ももしかしたら、そういう気持ちなのかも。いや、本当にひとりぼっちになってしまったぶん、あの時のわたしより辛いかもしれない。
「いいね」
そう言ったのは星子さんだ。
「私も手伝うよ。その子の家族探し」
にっこり笑って、わたしの肩をぽんと叩く。
「い、いいのか。おれ……」
「あなたが食べてしまった星くずについては、ご家族が見つかったらどうするか考えましょう」
テールはそう言ってひげをなでた。少し笑っているようにも見える。
「この列車はここにしばらく停車しています。《星食い》はひとりではそんなに長く飛べません。ご家族はきっと、そう遠くないところにいるでしょう」
テールはそう言って、肩からさげているカバンをごそごそとあさった。
出てきたのは丸くて白い、電球のようななにかだ。はじっこからは短いひもがたれている。
「この列車の近くに、インスタント太陽を置いておきます。戻ってくるときには、これを目印に」
テールはそう言って窓のそばまで歩いていくと、インスタント太陽のひもをえいやっと引き抜く。とたんに丸い球が強く光った。
「ほいっ」
その球を窓の外に放り投げたテールは、
「これでよし」
と言って、くるりとわたしの方を向いた。
「よろしくたのみましたよ」
わたしと星子さんは、顔を見合わせたあとうなずく。
「それじゃあ、しゅっぱーつ!」
最初に列車からとびだしたのは星子さんだ。
その勢いのよさにびっくりしながらも、わたしと《星食い》の子はすぐに後をおいかける。
「うわぁっ」
そうだ、忘れてた。ここは空の上だから、足をつくところがない。
だけどなぜだか体がふわんとういて、下に落っこちることはなかった。そういえば、すい星列車に乗る前もこんな感じになったっけな。
「――大丈夫かよ」
《星食い》は、ぶっきらぼうな口調で言った。
「大丈夫。ありがとう」
にっこり笑いかけると、《星食い》はくるりとわたしの方をむく。
「――おれは、ピピ」
不愛想な自己紹介は、きっとピピなりの「よろしく」だったんだろう。
「わたし、まひろ」
「私のことは星子って呼んでね」
そう言ってわたしたちはピピにこたえる。
ピピは照れくさそうにフンと鼻をならすと、わたしの頭の上に飛んで行ってしまった。
「それにしても、まぶしいね」
そう言ってわたしはぎゅっと目を細めた。すい星列車の真上にあるインスタント太陽の影響で、この辺りだけまるで昼間みたいだ。
「そうだね。これなら目印としてばっちりだよ」
星子さんはそう言って、すいすいっと空を泳ぐ。
「ピピくん、それじゃあここらで君のお話をきかせてもらおうか」
「話?」
「君、ほんとうにどこから来たのかわからないの? あっちの方とか、こっちの方とかも?」
星子さんは、ピピに問いかけながらくるくると空を泳ぎ回っている。
「……」
聞かれたピピは、少し悩んでから答える。
「それも、わかんねぇ」
「となると、何か事情があるね」
星子さんの目がきらんと光った。
「みんなで一緒にいたはずなのに、なんかすごいのがぶわわわわーってきて、ごごごごごーってなって、気づいたらひとりになってたんだ。そんでもうだめだーって思ったときに、あの列車から星くずの光が見えて……」
わたしにはピピが大変な目にあったことぐらいしかわからなかったけれど、星子さんは何かピンときたようだ。
「ピピくん、それ、もしかして星嵐じゃないの」
「ほしあらし?」
わたしがくりかえすと、星子さんはこくんとうなずいた。
「星もね、たまに不機嫌になるんだよ。それで爆発したりする。どっかーんってね」
星子さんは両手を大きく広げて説明する。
「その衝撃で生まれるのが星嵐。ものすごい勢いで、なにもかもを吹き飛ばすって聞くよ」
両手をもとにもどして、ピピの方を向く星子さん。
「ピピくん、『ぶわわわわーっ』ってなった時、もしかしてめちゃくちゃまぶしくなかった?」
「まぶしかった!」
ピピの答えに、星子さんはこくりとうなずいた。
「天気予報を見てみようか」
そう言ってワンピースのポケットからスマホを取り出す星子さん。
「この近くでさいきん星嵐が発生したのは……あっちの方みたい」
星子さんが指さした先に、もしかしたらピピの家族がいるのだろうか。
「いってみよう!」
わたしのひと声で、みんながいっせいに動きだす。
星子さんは平泳ぎで、わたしはバタ足で、そしてピピは背中の羽根でとびながら、星嵐があった方に向かって、空を泳いでいった。
「当たりかもね……」
星子さんがそう言ってにやりと笑った。
「だんだん前に進みづらくなってるの、わかる?」
そう聞かれて、わたしとピピはこくんと頷いた。
「星嵐の影響だと思うんだ。たぶん、近いよ」
星子さんがそう言った次の瞬間のことだった。
急に強い風が吹いて、体ががくんとかたむいた。
「うわっ!」
一番最初に吹き飛びかけたピピを、ぐっと腕の中に抱く。
そのまま片手で空をかきながら必死にこらえるけれど、たぶんもう限界が近かった。
星子さんも、わたしたちをかばっている余裕はないみたいだ。
どうしよう。どうしよう。どうする⁉
「――さよなら、わたしの星くずキャンディ!」
星子さんの言葉とともに、何かがぱあっと辺り一面に散らばった。
きらきらと輝く色とりどりの砂糖菓子――。星くずパンケイクスで買った星くずキャンディだ。
でも、ばらまかれたキャンディはあっという間にふきとばされ、どこかにいってしまう。
「星子さん、なにを……」
「さぁて、うまくいくかな……」
星子さんの呟きをかきけすように、どこかでオォォォォォン、という音がした。いや、声……だろうか? 地響きのような『それ』はどんどん近づいてくる。
「オォォォォォォォン」
次の瞬間目の前にあらわれたのは、夜空の色をした、大きな大きな何かだった。
「オォォォォン」
丸い瞳と、目が合う。
それはわたしの知っている生き物によく似ていた。
でもわたしが知っているのは空を飛ばないはずだし、さすがにここまで大きくはない、と思う。
「ソラナガスクジラじゃねぇか! なんでこんなところに!」
腕の中のピピが大声をあげた。
「この子、キャンディが好物なんだ。さぁ、いまだよっ! 乗って‼」
星子さんに腕を引っ張られて、ぐいんと体をもっていかれる。
「わっ!」
お尻をついた先に、ひんやりした感触。
なんと! わたしたちは空飛ぶクジラのうえにまたがっていた。
そのはるか下には、星空と、ぐるぐる渦巻く何かが――。
「ひょっとしてあれが、星嵐?」
「たぶんね」
星子さんがそう言ってうなずいた。
「ピピの家族は……」
ここから目をこらして見ても、下の様子はわからない。
どうやってピピの家族を見つけたらいいのだろう。
ピーーーピピッ。
とつぜん、空気を切り裂くようなするどい音がなりひびいた。
指笛だ。
腕の中のピピが、親指と人差し指を口にくわえて、何度も何度も必死に音を鳴らしている。
「届け……!」
わたしは両手を組んで必死に祈った。
星子さんも同じポーズをとって目をとじている。
ピーーーーピピッ。
ピーーーーピピッ。
ピーーーーピピッ。
ゆっくりと移動するクジラの上から、何度も何度もくりかえし指笛を鳴らすピピ。
「……‼」
バッとピピが顔を上げて、動いた。
「あっちだ‼」
指さしたのは、わたしたちの右斜め前あたり。
「あっちから、母ちゃんの指笛の音がした!」
わたしたち三人はおたがいの目を見て、こくんと頷いた。
「行こう! 二人とも、しっかりつかまっててね」
星子さんはそう言って、ぐっと体を低くする。
そしてポンポンポン、とクジラの頭を三回たたいた。
「オォォォォォォォン!」
星子さんの合図に応えるように、クジラがひときわ大きい声で鳴く。
勢いをつけるようにぐんっとはねあがったクジラは、そのまま急降下して、下へ、下へ。
このままいくと星嵐直撃コースだ。
大丈夫なんですか、とたずねようとしても、風が強くてうまく口がきけない。
でも、星子さんはわたしの不安そうな顔をみて、勇気づけるようににっこり笑ってくれた。そしてずっとにぎりしめていたこぶしに、優しく星子さんの手がかぶさる。
ピーーーーピピッ。
ピーーーーピピッ。
わたしのうでの中、どんどん強くなっていく風に負けじと指笛を吹き続けるピピ。
ピーーーーピピッ。
ピーーーーピピッ。
プーーーーププッ。
「見つけた!」
ピピの指笛に応えるように、かすかに聞こえたその音色。
「あそこだ!」
ピピが叫びながら指をさした。
その先には、小さい小さい四つの影がある。
「オッケー! まかせて‼」
星子さんはそう言って、ポポン、と短くクジラの頭をたたいて、合図を送った。
ぶるるるるん。
大きくふるえたクジラは、体を左にかたむける。
「オォォォォォォン‼」
どんどん近づいてくる四つの影。
この距離ならわたしの目から見てもわかる。少し大きい影が二つ、それよりも小さい影が二つ。どれも背中にはピピと同じような羽根がはえていた。
どんどん風が強くなっている。いまにもクジラの背中から振り落とされてしまいそうだ。すごい勢いで渦を巻いている星嵐まで、あともうほんの少し。
「今だよ!」
星子さんの声を聞いて、ぐうっと、できるかぎり手を伸ばす。
「みんなぁーーー‼ おれだよぉぉぉぉ‼」
ピピがわたしの腕からとびだして叫ぶ。
「わっ!」
吹き飛ばされかけたピピをあわてて抱きとめながら、もう片方の手にふれた『それら』を必死でつかまえる。
「やった‼」
ぐいっと引き寄せたのは、ひい、ふう、みい、よぉ。よっつの影。
「――た、助かった……」
聞き慣れないその声は、なんとなくピピに似ていた。
「みんな……‼ よがっだぁぁあぁ」
ぽろぽろと涙をこぼすピピとその家族に、もらい泣きしそうになったのもつかのま。
「ごめんね! 今はしっかりつかまってて!」
星子さんの言葉が聞こえたすぐあと、大きい力に押しつぶされそうになった。クジラがぐいいいいっと大きくカーブ……いや、Uターンしているのだ。
「オォォォォォォン」
ひときわ大きな声で鳴いたクジラは、星嵐に背をむけるとそのままぐんぐん空をのぼっていく。いくつもの雲をつきぬけて、いつも見上げている夜空よりもっと高いところへ。
「うわぁ……‼」
そこに広がっていたのは、星の海だった。
数えきれないほどの星たちがちかちかとまたたき、まるで空全体に光のさざ波がたっているようだ。
プシュウゥゥゥゥ。
わたしたちの背中側から、水がふき出すような音がした。
「わっ、潮だ!」
星子さんの声と共に、冷たい霧みたいなものが上から降ってくる。それは星の光を反射しながらきらきらきらきら輝いて、まるでこの世の全部が星空になってしまったみたいだった。
「オォォン」
短く鳴いたクジラが、今度はゆっくりと下に向かって泳いでいく。
目指しているのは、インスタント太陽のあの光だ。
わたしたちはあっという間にすい星列車のそばまでたどりついた。
「はい、とうちゃく! ありがとうね」
星子さんはそう言ってクジラの頭をなでると、ふわんと夜空におりたつ。
「……ありがとう」
わたしはそう言って、ごそごそとパジャマのポケットから星くずキャンディを取り出した。
「これ、お礼」
そう言って袋を開けると、クジラは嬉しそうに目を細めてから、ぱかっと大きく口を開けた。
一袋あったキャンディは一瞬で消えてしまったけれど、クジラは満足したようだ。
「オォォォン」と嬉しそうに鳴くと、背びれで空を蹴りながらどこかへ泳いでいってしまった。
「本当に、ありがとうございました……‼」
そう言って頭を下げているのは、多分ピピのお父さんとお母さんだろう。
「あのままでは危ないところでした。なんとお礼を言ったらいいか……」
深々とおじぎをされてどうしたらいいかわからないわたしは、おろおろとピピの家族と星子さんとを順番に見る。
「お気になさらないでください」
星子さんは、やっぱり大人だ。
「みなさんがご無事でほんとうによかった。ピピくんも、ひとりにならなくてすみましたから」
そう言ってにっこり笑うと、今度はピピの方を見る。
「父ちゃん、母ちゃん、おれ、このひとたちにめちゃくちゃ助けてもらったんだ。それに……」
ピピは言葉を詰まらせながら、すい星列車の方を見た。燃料の星くずを食べてしまったことを、お母さんたちになんて言おうか考えているのかもしれない。
「みなさん、よくご無事で。お疲れでしょう。どうぞお召し上がりください」
列車の中から顔を出したのは、大量の星くずが入った箱を抱えたテールだった。
「そんな! これ以上何かしていただくなんて」
「困ったときはお互いさまですよ。さぁさ、どうぞどうぞ」
テールにそういわれて、さいしょはためらいながら、けれどすぐにがつがつと、《星食い》の家族たちは星くずを食べ始めた。よっぽどお腹がすいていたんだろう。
「ピピ、あんたは大丈夫かい?」
お母さんに尋ねられて、ピピは困ったような顔でもごもごと何かを言いかけていた。
「ピピくんには、ひと足先にたくさんごちそうしましたよ」
テールはそう言って、ピピにウインクをして見せた。
「言ったでしょう。困ったときはお互いさまだって」
「!」
どうやらテールは、『自分が燃料の星くずをピピにごちそうした』ことにして、全てを水に流すつもりらしい。
「車しょうさん……‼」
ピピは声を震わせながらそう言うと、ぴゅーんとテールのまわりを飛び回る。
ピピの家族は、箱いっぱいだった星くずをあっというまにたいらげてしまった。
「ほんとうに、ありがとうございました……!」
そう言ってもう一度深々とおじぎをするご両親。
ばいばい、と言って手をふってくれるかわいい弟と妹。
「ほんとうに、ありがとう。また……今度は、いっしょに遊ぼうな!」
そう言ってにかっと笑ったピピは、くるりとわたしたち――わたしと星子さんとテール――のまわりを一周した。
はらはらとおちてきた金色の粉は、たぶんテールの羽根についていたものだろう。
「《星食い》の粉を浴びた者には、幸運がおとずれるって言われてるんだぜ!」
「みなさま、どうか良い夜をお過ごしください」
ピピのお母さんはそう言うと、家族を連れて夜空へ飛び立っていく。
「ばいばーーい!」
「また会おうね!」
わたしと星子さんは、四人の姿が見えなくなるまで、ずっと手をふっていた。
「ちょっと応援してやろうかな」と思って頂けたのなら、是非サポートを!あだがわの心の糧となります!
