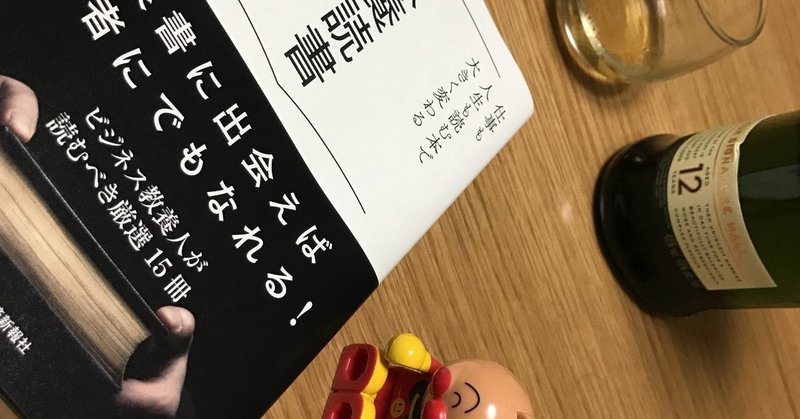
これからの読書の提案(#006:『教養読書』)
2020年のオススメは『3D読書』!
あけましておめでとうございます。
2020年、皆様はどんな本と出会い、
何を思い、何をしていくのでしょうか。
良き本に出会い、良き1年をお過ごしになりますようお祈り申し上げます。
さて、今回はこの『教養読書』の感想文の書き直しとして、
この2020年オススメの読書法をご紹介します☆
名づけて『3D読書』!
やや面倒な読書法ではありますが、
そもそも…
効率、スピードと理解度ってそんなに大事ですかね?
そんなにカリカリ、セカセカしなくても…。
そんなことよりも、もっと。
その本を読んで、何を感じたか。
その本を読んで、何が変わったか。
そっちの方が大事じゃないですか?
「何分で読めました!」ってナゾの報告とか。
「あなたの言いたいことはつまり…」って頼んでもいない解説よりも、
シンプルな感想が知りたい。
自分が著者ならそう思います。

まずは『教養読書』の感想。
読んだ直後の感想は、インスタにもあげたんだけど…
そのシンプルな感想は、一言で「悔しさ」。
なぜかというと…
読んでない本ばかりが「読むべき本」と紹介されていて、
だから、悔しかった。それが第一の感想。
で、これを書くために少しだけ読み直したら…
読んでいる最中に「共感」だったり「納得」もしていたことが分かった。
そう分かる部分にチェック・マークがしてあった。
「悔しさ」の対極のような、感情体験もしていた。
具体的には…
“読書は人の生存にとっての必需品ではないが、人生の必需品なのだ。”
“本の選択とは、自分が何を読むかを編集することだ。そして、本を読んでしまえばやがてそれらの本によって編集された自分が出てくる”
“いわゆる「書友」をたくさん持つことは人生にとっての財産になるのだ。”
“ビジネス教養人は併読せよ、他分野の知は力だ”
これは…
今年度からやるようになったイベントの趣旨とも、
今のおれの本の読み方とか楽しみ方、吸収の仕方とも
重なること。
ちなみに…
イベントは
「子ども関連業種のための交流読書会」というもので、
「LAP」という名前です。
Liberal Arts for Professionalの略で、専門家のための教養という意味です。
そして、個人では併読もしています。11冊。
話を戻して
初めの感想とチェックやマークが「解離」してたっていう話。
これは、読んでいる最中と呼んだ直後の
「自分」のコンディションの違いだと思う。

同じ「人間」(自分)でも、
「時間」(タイミング)が違えば、
感想(リアクション)がこうも違う。
でも、逆に言えば…
時々で感想が違っても、基本的には、
その本と「自分」との関係性。
そういうことだと思う。
読書メモをつくろう~パレートの法則~
そしてもうひとつ。
でも基本的には、それ以前に…
多分、我々は、
本に何が書いてあったとしても、
どんな思いが込められていたとしても、
・知ってることしか分からないし、
・自分にあるものしか感じられない。
先の
“ビジネス教養人は併読せよ、他分野の知は力だ”
という記述であれば…
「やっぱり!」と思っても
基本的には「知らなかった!」と大差なくて。
でも
「ビジネス」とか「教養人」とか「併読」とか。
それを知っているから読めるし。
多少なりは「自分」がそう思っていたから、
「やっぱり」って思える。
だから、実は…
本を読むということは、
「本に映し出された自分を見ている。」ということ。
著者なり、記述なりと重なる部分の「自分」を見ている。

「本は鏡である」と言える。
だから、今回のこの本との向き合い方、つき合い方の
反省というか、課題というか…。それは、
「読書メモをとっておけば良かった。」
ってことなんだけど。
要点だと思う部分、
感情体験がある部分
そんなところが「メモ」だったり、
チェック、マークの対象になる。
それに関連して、
「パレートの法則」というものがある。
これは…
ざっくり言うと
「全体の影響の8割は、全体の2割からなる」
そんな法則で。
前に取り上げたドラッカー先生の本でも取り上げられている。
まあ、現実は…
そうかっちりいかないことの方が多いだろうから、
「だいだいの影響は、一部分によるもの」
その程度に把握していればいいと思う。
イメージとして…
白紙の上に「文字」があれば、
その「文字」の方が領域が狭いのに「影響」は強い。そういうこと。
▲▲△△△△△△△△
△△▲▲△△△△△△
△△△△▲▲△△△△
2割の「黒丸」を目で追ってるでしょ?
これは本に対するチェック・マーク、
メモのための抜き出しも同じで、
だいたいチェックしているのは「ごく一部」のはず。
チェックだらけになると分かりづらくなっちゃうし。
そして、そのチェックが「自分」と重なる部分というのは、
先述のとおり。
そのチェック(部分)を見れば、
「だいたい」のことを思い出すことができるし、
本に対する感想みたいなものは、だいたいそこからきている。
チェックが示しているのは、
本あるいは著者と「自分」との関係性のエッセンスだ。
その「抜き出し方」とか「解釈」が問題になるのは、
「試験」のときくらいじゃない?くだらない。
本の「立体化」
そして、ここがポイントなんだけど…
実は、「8割の影響を与える2割」
そのなかにも「8割の影響を与える2割」がいる。
そしておそらく(絶対!)
さらにその中にも「8割の影響を与える2割」がある。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
