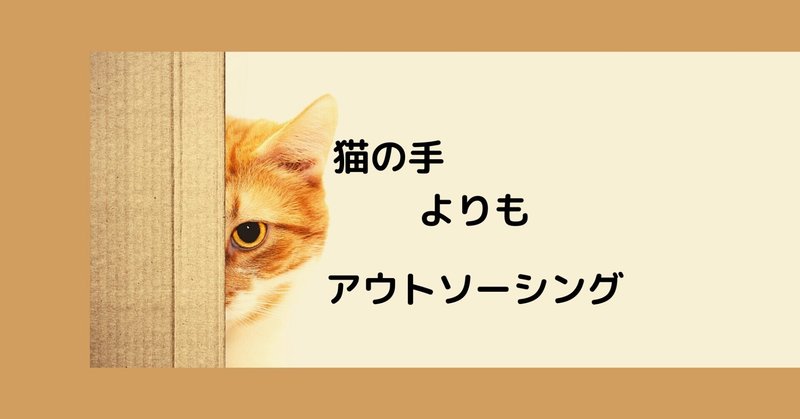
猫の手よりもアウトソーシング #ポスドク総研
いよいよ2021年後半に突入しましたね。大学教職員の方々にとっては、期末が近づいてきました。通常にも増して忙殺され、授業準備に採点に学務に雑務に明け暮れる毎日…せっかく科研費を獲得したのに、研究が思うように進まず、猫の手も借りたくなっている方もいるのではないでしょうか?
そんな中で考えていただきたいのが、アウトソーシングです。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆
アウトソーシングとは
横文字にするとかっこよく聞こえるかもしれませんが、簡単にいうと業務の一部を外部委託または外部発注することであり、特段に新しい概念というわけでもありません。近年では、情報学分野をはじめとする産業界においてアウトソーシングは活発になってきており、またその対象が業務単体委託から部門委託まで拡大するといった変化もあり、アウトソーシングという概念が改めて脚光を浴びることになりました。
一方、研究界隈では、例えば生物学の研究者がDNAシークエンス・サービスを外部の会社に委託するといったアウトソーシングは日常的に行われてきました。他にはリサーチ・アシスタントや研究補佐者を雇用し、一部の業務を分担してもらう形式が取られることも多くなっています。
何のためのアウトソーシングか
上のDNAシークエンス・サービスの例のように、自分の研究室にだけ調達するにはコストがかかりすぎるような、高価な機材が必要な分析をアウトソーシングすることは、よく見られるアウトソーシングの形です。この場合、アウトソーシングは設備投資などのコストをコントロールすることにつながります。
一方、リサーチ・アシスタント雇用のような場合は、金銭的コストを支払うことで比較的に単純な作業をやってもらい、研究者自身の時間と体力を買うタイプのアウトソーシングになります。限られた研究時間の中、いかに時間を効率よく利用し、研究の着想・論文の執筆・科研費申請書の作成といった他者に代え難い仕事内容に時間リソースを投入できるかが重要になってきます。そのため、時間と体力の節約に繋がるアウトソーシングは積極的に行われるべきだと、筆者は考えています。
例えばオンライン実験を行いたいと考えている研究者がいるとします。自分で勉強すれば2週間程度で会得することができるかもしれませんが、日常業務をこなしながらその時間を取るのはとても大変になります。それよりも、プログラム言語に長けている人に数万円で外注して、自分は科研申請書や論文執筆に打ち込む方が、より生産的かもしれません。
プログラミングはまだ「大きな仕事」の部類に入ります。研究者の日常には他の細々とした仕事も満ち溢れています。例えば文章の校正・参考文献資料の収集と選別・データの初歩的な整理などがあります。
「こんなことくらいは自分でできる」と思う人もいるかもしれませんが、できるかどうかの問題ではなく、そこに時間と体力を取られることが「割に合うかどうか」の問題です。研究費が全く足りていない若手研究者なら体力勝負に出ざるを得ないこともあると思いますが、多少の研究費の余裕があるときには「金で解決できる問題は全て無問題」(中国の流行語)に従い、「お金で解決できない問題」に集中するのも一つの選択肢になります。
ただし、多少の経費上の余裕はあっても、ポスドクや長期で研究補佐者を雇うほどの財源がない場合も多々あります。その際には、単発または短期間のアウトソーシングの依頼を出すことになりますが、その対象となるのは学生やフリーランスの方になります。
「面倒くささ」に打ち勝つ
筆者の観察に偏りがあるかもしれませんが、日本の研究者は欧米の研究者ほどアウトソーシングに積極的ではないように見えます。それには研究費の潤沢さの違いや「研究とは何か」に関する哲学の違いなど、さまざまな理由があると考えられますが、大半は「面倒くさい」の一言にまとめられてしまいます。
以下ではその「面倒くささ」に何が含まれるか、そしてどういった対策が可能であるかについて述べます。
記事の続きを読む
株式会社アカリク(https://acaric.co.jp/)は「知恵の流通の最適化」という理念の下、大学院生やポスドクを対象とした求人情報の提供やキャリアセミナーを開催しています。また、現役大学院生から大学院修了者まで幅広く対応したエージェントサービスも提供しています。他にもLaTeXの環境をクラウド化できるサービスも運営しています。
【運営サービス一覧】
◆就職ナビサイト「アカリク」
◆アカリクイベント
◆就職エージェント
◆アカリクキャリア
◆Cloud LaTeX
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

