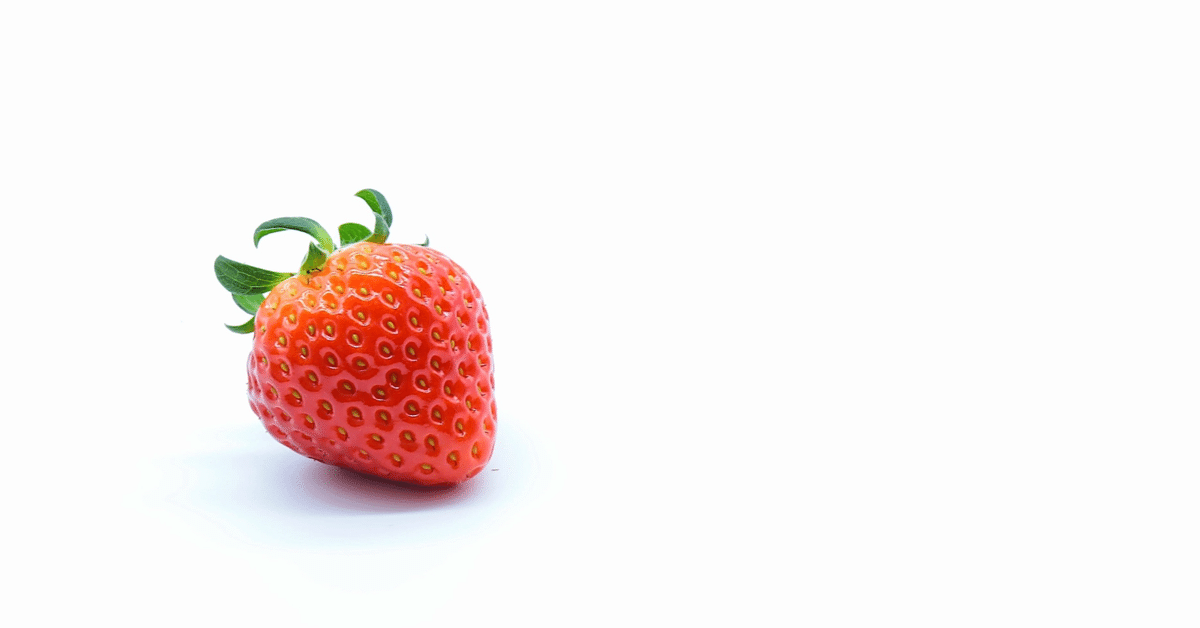
三島由紀夫「苺」
もうやめにしないか。そう言いたくなる作品がこの世にはいっぱいある。悲しいことに。
それで一つ無駄話をさせてほしい。
筆者はこの前「ザ・マミー/呪われた砂漠の王女」という映画を見た。
トム・クルーズが見たくて見たが、これが信じがたい駄作。
一時間五十分のうち、面白いのは冒頭十分。
あとは行き当たりばったりの、中身のないCGお披露目会(と謎のゾンビ)に付き合う羽目になる。
本題。
筆者は三島由紀夫(と遠藤周作)の書く、女性が嫌いだ。
彼らの書く「女性」は、男の持つ非現実的―理想的な願望を決して理解できない、あくまで現実とかまぼこ板のようにくっついた、想像力のない存在として書かれる。
少女の目には矜(ほこ)りがうかんだ。自分の写真が真治を守ったと考えたのである。しかしそのとき若者は眉を聳(そび)やかした。彼はあの冒険(筆者注:台風のさなか命綱をブイに繋ぐ作業)を切り抜けたのが自分の力であることを知っていた。
これと似た表現は遠藤周作にも見られる。
いっそ、
「人非人でもいいじゃないの。私たちは、生きていさえすればいいのよ」
ここまで書くなら文句はない。
女性の生の熱を、三島遠藤両氏はなぜそこまで貶めるのか。
「苺」は三島本人による「潮騒殺し」のような小説だ。そして、女性の書き方は醜い。
小説は三部構成。一、二部では「潮騒」を思わせる恋人、龍次と友江の物語が語られる。
三部では、それ以前にちらっと出ていた居候の画家、矢倉の手紙が置かれる。
まず、この作品は二重の侮蔑に汚れている。
ひとつは、矢倉の手紙の内容。彼はこの漁村の祭りを「絵画的見地からは、一顧にも値ひしない」と(おそらくは無意識に)下に見る。
手紙のなかで友江の姿が描かれるが、ここでも矢倉は友江を無意識に見下している。
また、恋人たちの書き方は「潮騒」を思わせるが、その欠点もそのまま持ち越している。作中、友江は龍次の乗る屋台を追いかける。誰もが酔っている、龍次が大ケガしたらどうしようと不安になって。
この、「男の後を追う女」の構図には、良い読後感は持てない。
この二人の恋模様は、それでもそれなりに微笑ましい。だがそれも矢倉の手紙の存在が相対化してしまう。
とにかく、安上がりのニヒリズムだと思う。
全体として、途中で投げ出したような印象を残す短編。読まなくていい。
発表年1961年。三島36歳。
