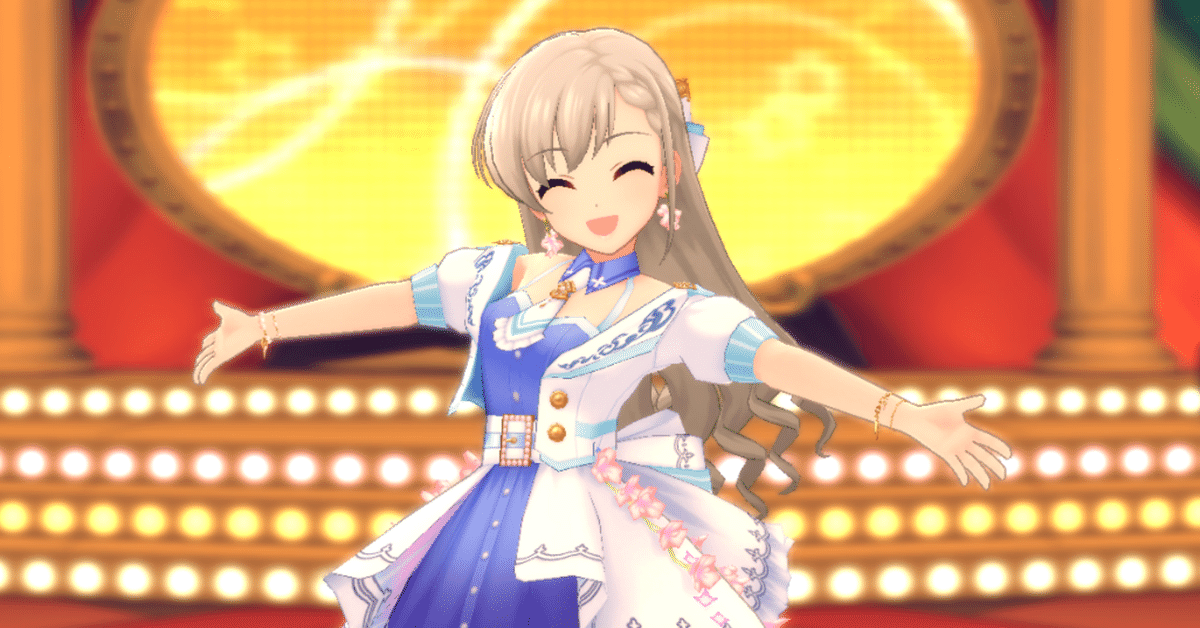
久川颯ちゃんの意思決定
颯とプロデューサーは黙ってパソコンのモニターを見ていた。モニターにはステージ上でギターをかき鳴らしながら歌うひとりの女の子が映っている。
女の子のギター演奏と歌唱力は最高レベルの出来栄えだ。ギターのフレットの上を素早く動き回る女の子の指。疾走感あるメロディ。澄んだ歌声。ステージの向かい側にある観客席からは大歓声が沸き起こっていた。颯とプロデューサーが見ていたのは最近話題になることの多い女の子――某Lという歌手のライブDVDの映像だった。
一通りライブの様子を見て、プロデューサーが言った。
「リッチー・ブラックモアみたいにギターを弾くんだな、この子」
「誰それ? プロレスラー?」と颯。
「若い子はディープ・パープルなんて知らんか。そういう凄腕のギタリストがいたんだよ」
「ふーん。確かにLさん、ギターうまいし歌もうまい。かっこいいね」
モニターの中ではLがステージから去り、まもなくライブDVDも終わった。プロデューサーがパソコンを操作してDVDのディスクを取り出す。颯はプロデューサーがそのディスクをケースに仕舞うのを目で追った。
颯の人気はここのところ上昇傾向にあった。颯のアイドルとしての技術も上がってきたし、さまざまなメディアを通じて颯のことを知る人々も増えてきている。ここからさらなるサクセスが始まりそう、というときに突如現れたのがLだった。
Lはいつもひとりでステージに立つ。そして自分が作詞作曲した曲を美しい声で唄い、超ハイレベルなギター演奏を披露する。美声に乗る歌詞は明るく、強く、優しい世界を想起させる。ライブの段取りや演出もすべてLの独力で組まれていた。たったひとりですべての仕事をこなし、それを大成功に導くLのスタイルはたちまち人気を集めた。
Lはしばしば独りで仕事をすることの大切さをメディアで語った。超一流のクリエイターに仲間は必要ない。全部自分でやるから全力を尽くしてやりきれる。群れるのは弱い奴ら、強い者はなんでもパーフェクトにできる。これぞ究極の歌手であり、自分はそれを極めるために活動する。こうした発言をしても嫌味に聞こえないほどLの持つ技術とカリスマ性、フットワークの軽さ、あらゆるものをそつなくこなす器用さは見事なものだった。たったひとりで戦い続けるLのファンはどんどん増えていき、Lが手掛けた楽曲は凄まじいスピードで売れていった。
颯はそんなLを見るたびに思う。ひとりでなんでもできるのはすごい。颯にはそんなことはできないから。ギターをかっこよく弾いたり、自分の仕事を完璧に管理しつつ良い結果を出すことも颯はできない。でも、それが究極にすごいものなのかな。颯は言ってみた。
「Pちゃん、Lさんの言っていることが正解なのかな。全部、ひとりでできちゃうほうがいいのかな。誰かに頼ってたら、ダメなのかな」
プロデューサーは腕を組んで返事をした。
「ひとりであらゆることを解決していくのは、確かにかっこいいよな。だけど仕事観、世界観、人間観なんて人それぞれだと思うよ。Lにとって楽しくて正しいことが、颯にとって気持ちのいいこととは限らないだろう。LはLですごいけど、颯だってすごいアイドルだよ」
ようするに自分のスタイルを持てと言うことか、と颯は思った。
颯の次の仕事はCDショップを会場にしたミニライブだった。ミニライブといっても関わってくる人間は多い。会場を抑えて、ライブをやります! といろいろなところで宣伝し、スタッフが高級な機材をライブ会場に持ってきて、颯に美しい衣装が用意される。颯を含め様々なスタッフがそれぞれの仕事をがんばって果たし、ライブ本番を迎える。
ライブは楽しい、と颯はステージに立つたびに思う。集まったお客さんの前で思いっきり歌うのは本当に楽しい。
ライブの最中、颯はニコニコして、華麗なダンスを舞いながら思う。Lはひとりでこの楽しさを味わっているのだろう、と。Lがひとりで作るものを、颯はひとりでは作れない。だから颯が劣っているとも言えるのかもしれない。物事のスタートからゴールまでひとりで組み立てる技術を持っている奴はなかなかいないだろう。完璧にすべてを自分の力でやり切るLの能力、それは強烈で、かっこよくて、才能があるように見える。
しかしLのやり方が最適解なのか、颯にはわからない。単独で周囲を圧倒するLのスタイルが正義で王道でグッドなものなんだろうか。
ライブは終わり、観客から拍手が颯に送られた。颯はまだまだいっぱいライブしたいなと思いながらステージをあとにした。
それから数週間後、とある音楽雑誌の最新号にLのインタビューが載っていると知った颯は書店に走った。音楽雑誌を手に取ってレジに持って行き、自分の部屋に帰るとページを素早くめくってLのインタビュー記事を読みはじめた。
なぜLさんはひとりで仕事を進めていくのですか、という質問に対し、Lは100パーセント自分の手で仕事をしていかないと、自分は成長できないから、と答えていた。単独で仕事をするのはきつくないですかと聞かれると、「きついですけど、自分が考えているアイデアを全部自分の思った通りに具現化したほうが楽しいじゃないですか。誰かから影響されるんじゃなく、自分だけのオリジナルなものを作り続けることが楽しいんですよ」と返している。
颯は長いインタビュー記事を読み終わり、雑誌を閉じた。Lの気づいていないところに、楽しいことがあったりしないのかな。
「ダンスの練習会? はーがダンスの先生役をやるの?」
「そうだ。小学生のアイドルを集めて、ダンスの技量向上を目的とした練習会を開く。その講師として颯が選ばれた。すごいことですなあ、ガハハ」
「はー、まだ十四歳だよ。もっとベテランの人が教えるべきじゃないの」
「颯の技術が評価されて講師役に抜擢されたんだ。年齢は関係ない。颯は使える人材だということだよ」
話があるから事務所まで来い、とプロデューサーに呼び出された颯は、小学生アイドルにダンスを教える講師になれと告げられたのだった。
となると、自分はほかの人に力を与えるということだ。それはなんだかうれしいなと思い、颯は講師役を引き受けた。
そして練習会の日。練習会はプロダクション内部のレッスンスタジオで行われることになった。集まった小学生アイドルは八人。デビューしたての子ばかりだったが、練習が始まると熱心に颯の話を聞いて、颯がお手本として踊った振り付けをなぞっていった。
みんながんばってるな、はーもしっかり教えよう、と颯は講師役を張り切ってやった。
「踊っているときは、身体が作る線を意識してね。線がまっすぐしていないと美しくなくなっちゃう。猫背にならないよう、身体全体でラインを作るんだ」
「動かしているほうの足に気を配るのは当然だけど、動いていないほうの足の角度にも注意して。お客さんはアイドルのいろんなところを見ているよ」
「ゆっくりダンスをするときもあれば、一気にスピードを上げて身体を動かすときもあるよ。逆に急に止まってポーズを作ることもある。次にやる振り付けを意識して、速度に気をつけよう」
「本番では衣装を着るけど、衣装の色と調和したダンスを踊れるとかっこいいよ。覚えておいて」
「難しい振り付けだと感じたら、アクションを分解してダンスをひとつずつ区切ってみよう。分解したものをマスターしたら、それをくっつけていけばいいからね」
そんなふうにしてダンスの練習会は終わった。颯も小学生アイドルもいっぱい汗を流した。小学生アイドルたちは疲れた様子だったが充実した顔つきをしていた。はーの力、伝わったかな? と思い、颯は小学生アイドルたちがレッスンスタジオを出ていくのを見送った。
練習会が終わって一ヶ月ほど経ったころに、プロデューサーはまたしても颯を呼び出した。ダンスの練習会に参加した小学生アイドルたちのライブが動画配信サイトで視聴できるから一緒に見よう、という誘いだった。颯はプロデューサーのもとへ直行し、いつかLのライブDVDを見たときと同じようにパソコンのモニターの前に座った。
動画が再生された。ライブは陽気なムードで進み、キラキラした衣装に身を包んだ女の子たちが一生懸命に歌って踊っている。そういう人間を見るのは楽しかった。
そしてライブは終わった。最後に小学生アイドルたちは満面の笑みを浮かべて言った。
「今日は楽しかったです! またぜひ私たちのライブに来てくださいね!」
あの笑顔をあらわすのに、颯はいくらか貢献できただろうか。それはわからないけれど、彼女らは楽しくライブをやった。見ていた颯も楽しいライブだと思った。自分と他人とのあいだに楽しさが流れていた。
Lは自分が創る楽しみを極限まで追求する。颯は他人に楽しさを伝えたり、伝えられたりするのがおもしろいと思う。それが颯のスタイルなのかもしれない。
「いいライブだったな。左から二番目の子、結構おっぱい大きかったし」
プロデューサーがそうほざいたので、颯は大きなため息をついた。
「Pちゃんはそういうところを見てたの? ライブをもっと楽しみなよ」
「おっぱいを見るのって楽しいだろ。男にとっては重要なファクターだ」
「嫌なオヤジだな〜」
プロデューサーの楽しみ探しはおっぱいに関連しているらしい。それならば颯としては、どこを探そうか。楽しさはいろいろなところに流動するし、形も様々だが、探すこと自体も楽しそうだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
