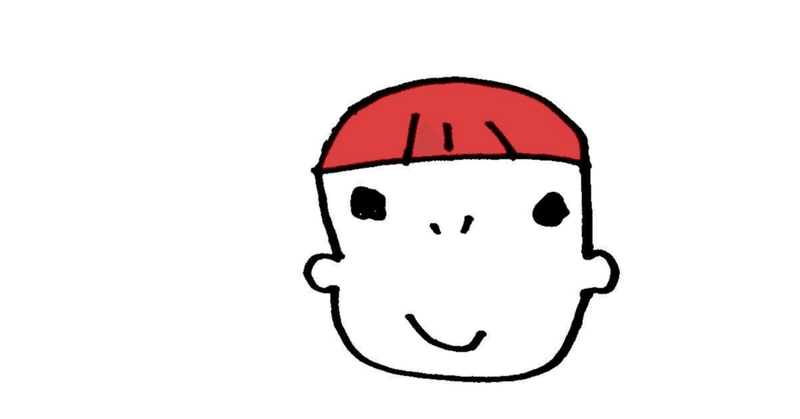
小5息子の「激太り」と「生活習慣の変化」と「自主性」と「自信」。vol1
『信じて、「必要な時」にサポートすること』
母親との「共依存関係」に散々振り回されてきて、さらに「過保護・過干渉」で育てられてきた「自分の問題」に取り組み続けているわたしにできる子育て。
●こどもたちを「信じる」こと。
●こどもたちが「困っているとき」にサポートする努力をすること。
●こどもたちと「人として対等に」関わる意識で接すること。
こういう事を今特に一番大切にして
娘と息子との関わりを「貴重な時間」だと感じながら過ごしています。
そんな意識的な変化もある中
わたしの生活習慣や生きる姿勢が
否が応でもこの数ヶ月で大きく変わったことで、
こどもたちの「生活習慣」にも明らかに変わってきています。
まずは息子。
3年半という長い期間での施設生活。退所をきっかけに、本人の希望で不登校に。そして偏食気味な息子が、これまで「嫌なものも我慢して食べてきた」ことをおもうと、「食べたいものを、自由に食べさせたい」気持ちが私にあり。
運動不足&食事の変化により、当たり前ですが「激太り」しました。
わたしはもちろん気づいていましたが、
「デブになった事」を本人は全く気にしていなくて。
「やりたいことを、やっている」ということもあったと思います。
とにかく、元々基本的に明るいし、不登校でも毎日楽しく過ごしている。
デブになはなっているけど、本人は「困ってない」状態でした。
息子はとにかく、ごはんを「美味しそうに食べる」のです。
わたしが作るものに対して「んまい!!」と言って美味しそうに食べてくれる。苦手な味、イマイチな時も、隠さず正直にリアクションしますが、美味しい時は、本当に食べっぷりがよく。
「おかわり!」と幸せそうに言われると、どうしても「もうそれ以上食べないほうがいい」とは言い辛く。満足するまで自由にさせていました。息子は「ラーメンが特に好き」なので、カップラーメンも好んで食べていましたし「夜食」にもしていました。
この1年半の間に、
もちろんその状況を「野放しにしていた」わけではありません。
不登校のこと、カラダの重要性、生活習慣など。小学校高学年の男児ということを考慮しながら、「成長する上で必要だと感じること」については要所要所で「話すこと、話しあうこと」はしてきました。
だけど「本人が困っていない」「本人に実感・自覚がない」ので、
見守ることを続けていました。
だけど、
そんな状況から、だんだん「デブであること」で日常生活の中で「困ること」が出てきました。そこから徐々に息子が「自覚」をもつようになってきて。いろんな毎日のことで「意識的になる」言動が増えていったのです。
その「意識的になったこと」の結果として
大きくあるのが、3週間ほど前から始めている「有酸素運動と筋トレ」です。
運動については、これまで何度も自分で「やる」と言ったタイミングがありましたが、なかなか続けられず。本人も「それでいいや」「仕方がない」と思うようなところがありました。
が、
今の彼は違って。
体重はまだ大きく変化はしていないけれど「見た目」が変わってきています。そして、少しずつ「基礎体力」がついてきました。
なにより「毎日運動する習慣」が、確実についています。
娘とわたしも一緒に運動をしていますが、
わたしがタイミングを合わせられなかったり、一緒にできないという時でも、自分から娘(姉)に声をかけて「今日はやらない」ということがありません。
食事の方も、明らかに変わってきていて。
わたしが食事内容を意識していることもありますが、自ら量と質を考えたり「腹八分目」でおさえられたり。以前は、1回の食事でお茶碗にモリモリ2杯はご飯を食べていましたが、今ではよほど「気に入った味のおかず」じゃなければ1杯で終わり。「すごい量が減った。胃袋が小さくなってきた!」と本人も喜んでその変化を感じています。またそれが「運動のやる気」につながるようで。
相互作用で「食事と運動」は、息子のなかで今しっかりとリンクしているようです。
自分のカラダに興味関心を抱くようになった息子にとって
もう一つ起こった「良い変化」として「本を読む事」があります。
息子は「国語が苦手」「活字・多くの文字を読むのが苦手」なので、普段ほとんど本を読む習慣がありません。
学校でもかなり「無理をしていた」ようで。
今でも時々、急に「国語の授業」や「国語の先生」のことを思い出して、その話題を出してきます。突然、さらっと話題に出すので、こちらとしては「今??急に思い出したの??」とビックリしますが。本人が「気にしていること」が、そんな風に、なんでもないタイミングの時に「言葉になって、出てくる」ということがあります。
これまで色々と話してきたこともあり、本人は今「笑って(明るく)話している」状態ですが、内容としては「嫌だった」「我慢していたこと」で。リアルタイムでの実際の「その出来事のとき」は、本人辛かったと思います。
そんなこともあり、
彼の「国語」「言葉」「本を読む・読まない」は
ずっとわたしも「気になっていること」ではありましたが「本を読む事」を強いたりすることはありませんでした。
そんな状況でしたが、
今回息子が「自分のカラダ」に興味関心を抱くようになったことをきっかけに、わたしが図書館で適当にみつくろってきた「写真や数値・図がたくさん載っている」栄養や糖に関する本を渡してみると、興味深く読み始め。「本をよむこと」に自然と時間を割いていました。
これも本当に「自分の興味関心」のたまものだなぁと感じるのですが。
「本を読む習慣がなかった」息子にとっては、
プラスのきっかけ&自信に繋がった経験になっています。
つづく
今後、母子共に「自分らしい幸せ」を諦めず、希望をもって生きていけるための具体的なサポート活動を拡げていきます。そのための活動資金にしますので、ぜひお気持ちいただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。
