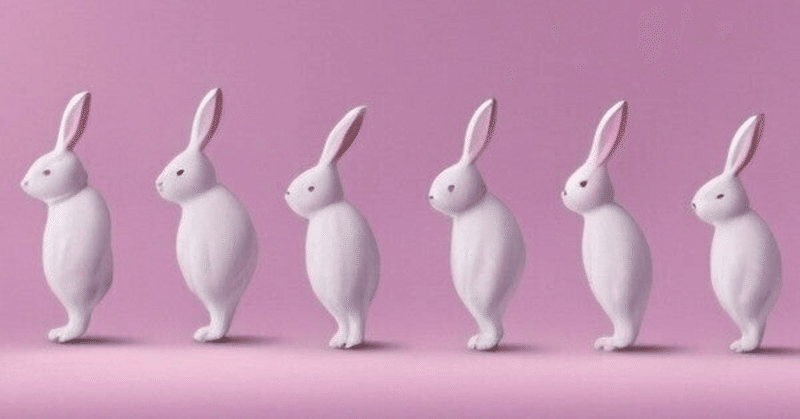
この世でいちばんギャルの多い歯医者 前編
白く清潔な部屋、消毒液の匂いと耳障りな機械音。泣き喚く子どもたち。そう、歯医者である。
みなさんは歯医者は好きですか?
好きじゃないですよね。わかります、同じです。わたしも歯医者が好きじゃないです。
好きという人はとりあえず、そういう人もいるんだねと思いながら読んでいってください。
歯医者の何が嫌って、シンプルに痛いし、怖い。
ドリルのようなもので歯を削られると、頭頂部から口内が地鳴りのように響くようで気分が悪くなる。けたたましく鳴り響く「ウィィィーーン」というあの音、めっちゃ嫌だ。
歯医者は好きではないものの(負けた気がするから嫌いとは言わない)、歯はとても大事なものなので渋々通っている。しかし、高校生までは、「痛くなったら歯医者に行く」という最悪な習慣だった。
痛くなってから行くということは、大体が非常にまずい状況にある。神経を抜くかどうかという究極の選択を迫られることだってある。「そんな判断能力ないのに、委ねないでよ!」という感じである。
そんなわけで、あれは高校2年生の冬。奥歯がひどく痛みだし、何年かぶりに歯医者のドアを叩いた。
そこの歯医者は、当時のアルバイト先と同じ駅の構内にあった。「立地最高!」と思い、そこにしてみた。当時は口コミというものをよく確認するという習慣がなかったし、今ほど詳細な情報が書き込まれてもいなかった。
数年ぶりの歯医者はドキドキだ。
問診票を記入し、席へと案内される。うがいをする。
やたらと待たされるので歯科助手の女性に、「あとどれくらいですか?」と聞くと、強い口調で「待ってもらえます?」と言われた。待ってもらえますの「ま」の前に小さく「は?」って聞こえた気がするけれど、気のせいだと思い込むことにした。この世にそんな高圧的な歯科助手はいない。絶対そう。歯科助手の人ってみんなやさしいはずだもん。
さっきの高圧的な女性は、テキパキを超えた乱雑な手振りで準備をしてくれている。ガチャガチャと音が鳴る。“え、怒ってる?”と思うほどである。
わたしは、さきほどから感じていた違和感に気づいた。
歯科助手の女性、全員ギャルじゃね?
みんな普通体型よりも痩せ型で手足が長い。金髪で睫毛はバサバサ、ポップティーンモデル並みの黒々としたつけまつ毛が揺れている。バリバリのギャルメイクだ(※2009年当時)。
なんだか無性に不安になってきた。ギャルは嫌いじゃないし、ギャルの友達もいっぱいいる。でもギャルの歯科助手ってこの身を委ねるには、心細い。きらびやかすぎる。やさしく抱きしめてもらいたいくらいなのに。せめて、やさしいギャルにしてほしい。歯医者って不安なんだ。
てか1、2人ならまだしも、やたらいる歯科助手10人くらい(全スタッフ)が全員ギャルってどうなの?逆に凄くない?院長の趣味もろわかりじゃん。
待てど待てど、治療をしてくれるはずの院長は登場しない。バイトの時間が迫りつつあるが、これ以上ギャル助手に何か言おうもんなら反撃にあうこと間違いないし、H Pは極限まで減らされてしまうだろう。ままよ!そう思い、治療用の椅子で静かに待った。
しばらく待ってから院長は「は〜い」と言って、登場した。は〜いって何やねん。「お待たせしました」とか「すみません」くらいないものか。でもJKのわたしには当然のことながら威厳がちっともない。舐められてしまうのは致し方ない。この時点で気持ちはかなりゲンナリしていた。
ようやく治療がはじまるようだ。
「では、口を開けてくださーい」
院長はわたしの口内を見てすぐ言った。
「ひどい虫歯だね。よし、神経を抜こう」
えっ即決? そんな一瞬見ただけで神経って抜く判断していいものなの? 神経だよ?
母からすぐに神経を抜こうとする歯医者はやばいと聞いていた。どうしよう。どうしよう。
わたしの緊張と葛藤をよそに院長は素早い動きで麻酔の準備をしている。
「えっ本当に神経抜くんですか?」
「どうにもならないもん。抜くしかないよ。麻酔するから痛かったら教えて。いいね?」
専門家にそんな勢いで迫られて「はい」と言わない女子高生はいるだろうか。もしかしたらいるかもしれないが、さきほどからギャルにもHPを削られていたわたしは圧倒されていて、闘う力が残っていなかった。
されるがまま麻酔が注入される。初めての口腔内麻酔。え、痛くない? 痛すぎる。
少しの間、どう考えても痛い気がしたがそういうものなのかもしれないと思い、我慢してしまった。さすがに我慢できないほどの尋常じゃない痛みを感じて、手を挙げた。凄まじい痛みだ。無理ですと必死の形相で伝えた。今思えば時すでにおそしである。
「あ、痛かったの? もっと早く教えてよ」
なんだその軽いノリ。ふざけんなよ、くそ痛いわ。悪態をつきたいくらいだったが、命を握られてるもの同然。わたしは静かに中止の要請をした。
何かよくない間を感じさせながら、院長は手を止めた。
わたしはこの院長に任せてはわたしの歯が大変な目にあってしまうと直感した。現に大変な状態に片足を突っ込んでる。麻酔の針をされた歯肉がジンジン痛む。
わたしは慌てて、「あ、もういいです! 神経を抜くのは今後検討します!」と高らかに宣言し(本当は歯肉が痛すぎて声にならないような声をあげて)、脱兎の如くギャル助手と神経即決院長の歯医者を後にした。
その後、アルバイトをしたのは覚えている。だが、何をしたのかが記憶にない。歯が、歯肉が、尋常じゃないほどの痛みを訴えている。もともと虫歯で痛かったはずなのに、そんな痛みをはるかに超えるほどの凄まじいパワーで痛みを感じる。歯肉が熱を持ち、メラメラと燃えているようだった。
わたしは歯医者に行ったはずだったのに、なぜ更に痛みが増しているんだ?
ギャル助手の冷たく高圧的な態度も、あっけらかんとした様子で即決で神経を抜こうとした院長にも怒りがわいてきた。しかし、怒りをもったところで痛みは引かない。ちゃんと確認せずに駅構内の歯医者なんて選んだ自分がばかだった。そう後悔してももう遅い。歯肉が痛いはずなのに、もはや口腔内全体が痛いような感覚におちいり、頭痛と吐き気までしてきた。震えてくる。このままでは死んでしまう、そう感じるほどの痛みに襲われていた。
わたしは子どもの頃に通っていた、やさしいで有名な亀の歯医者に行くことを決意した。
後編へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
