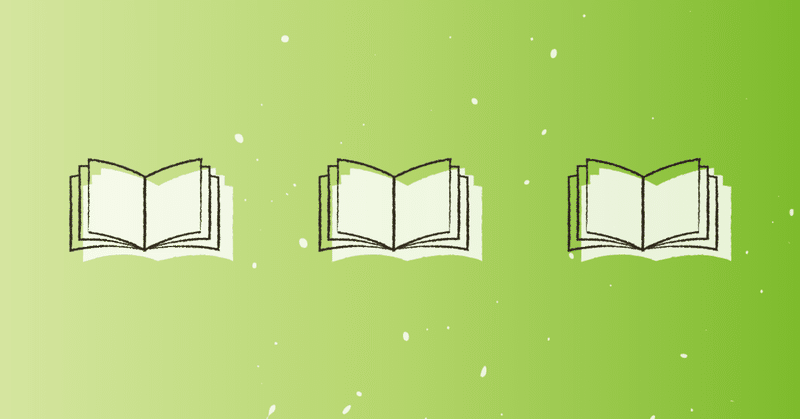
少子化で考える、子供の教育機会
少子化による問題が良く取り上げられる。一方、数10年前は人口増加が問題とされていた論調から考えると本当に大きな問題なのかだろうか。加えて、今の地球環境を考えると、ある程度の人口減は良いのではとも考える。
経済の観点では、需要側は、国内需要の減少は問題だが、海外の需要増を取り込めれば問題が緩和するとも考えられる。一方、供給側は、最近のロボット技術の急激な進展から作業人口減少は問題にならず、ロボットをフル活用し、生産能力の維持、生産性の向上が可能と考える。しかし、若者の母数が減ることで経済を牽引する優秀な若者が減少することは課題ではなかろうか。そこで、母数が減っても、その中から優秀な若者が出てくる比率が高くなれば、これも乗り越えられると考える。そこで、現在、十分な教育を受ける機会が少ない子供たちにその機会があれば、解決の一助になると考える。ここでは、所得と地方という観点で、良質な教育を受ける機会を整備することで伸びしろがあるのではとの点についてポストしてみたい。
所得格差による教育への影響
所得格差が教育格差につながっていることは、参考文献を読むと実証分析の結果として証明されていると思う。私は教育格差は、一つは良質な教育を受けるための費用が大きいことと、もう一つは教育に対する環境(含:親の言動、行動)がある。
まず、所得については、参考文献に詳細はゆずるが、教育へかけるお金と学力に相関が強いことがあげられる。東京大学進学者の親の年収が高いことも事実としてある。卑近な例でも、歯科医師の子息がインターナショナルスクールから米国留学をしていたり、小学校から名門の学校に行っているのを目の当たりにすると実感もある。この解決策としては、大阪府政で検討されていた目的が絞られた補助(教育バウチャー)が効果があるのではと考える。
もう一つは、親の日々の行動の影響である。子供が親を見て育つと考えると、親が向学意欲や教育に興味があると、子供が学習に向かう確率が高く、ひいては子供の学力に反映されるのではなかろうか。そのような親の行動は、心と時間にゆとりがないと難しい側面もあり、所得や労働環境に恵まれているとそのようなことに時間がさける。これに対して、親に関係なく子供は伸びるということも間違いではないし、経営者の中でもそのような人の自伝などを見聞きするが、統計的には親の日々の行動や考えに相関していると考えられる。少人数制で小学校や中学校の先生がフォローできれば良いが、実態は雑務が忙しく難しいのが現実だろう。その時間を確保するため、例えば、小学校の講義は授業のうまい講師の映像を見て、それのフォローを学校の先生が行い、雑務はその専門職を雇い、先生の時間を確保することも施策としては可能性があると考える。これについては、慣性ではたらく義務教育の変革方法について暗中模索の状況である。比較的難易度が低い方法として、いろんな専門の大学教員が学校の勉強と社会課題の解決への応用について週替わりでクラスを持ち、子供に学習の楽しさを伝える方法はどうであろうか?
地方との情報格差による進学機会の不平等
以前、私の同僚(東京有名私立大卒)で北関東の地方出身者から聞いた、優秀な生徒が地元の大学入学を強く勧められる環境が地方にはあると聞いた。その後、もう一人と最近読んだ参考文献でも指摘されている。もちろん、地方にも良い大学があるし、地元への貢献も重要(私も地元に帰ってきた)だが、優秀な生徒は関東や関西の有力大学や特徴ある大学で高い能力を持つ学生と切磋琢磨し、自身の能力向上に専心されてはと思う。その後、地元で活躍したいと思った時に地元の貢献すれば、地元も高い能力を持つ人材が戻ってくることでさらに活性化するとも考える。確かに、関東や関西圏の住宅事情を考えると莫大な費用がかかるが、特に大学院からは十分な支援プログラムもあるため、是非チャレンジしてもらいたいし、そのようなコースがあることを伝える活動を大学側も実施する必要がある。これにより、現状よりは情報格差が低減できると考える。
才能のある子達に機会を
最近の若い子達の多彩な方面での活躍は目覚ましい。音楽、芸術やスポーツなど枚挙にとまない。昔と今で、日本人の素質が変化がなければ、特化した領域に時間を割ける豊かさを享受できる人が増え、その子達を引き上げるルートが確立されているからではなかろうか。サッカーの下部組織や卓球やバドミントンなどの若年層からの選抜合宿など、やはり、才能がある子たちには若いころから特別な機会が必要ではなかろうか。では、”勉強”の世界はどうか?平等の名の下、飛び級はなく、その子達が選抜されて才能を伸ばす機会も多くない気がする。才能に平等はない。世の中の子達が多くの機会に触れ、社会がいい意味でのえこひいきを許す成熟した社会になれば、能力がある子達が社会をけん引してくれると考える。その中から勇気があるアントレプレナーが沢山出てきて、社会の課題を解決していくのではと考える。
自分にできる、学ぶことの楽しさや社会との繋がりを伝えて、少しでも学ぶことに興味を持つ子が増えるように、高校生や中学生向けの出張講義から始めてみようと思っている。
まとめ
まとまりがないが、大事な点は”勉強”や"事業"の世界でも、音楽、芸術やスポーツの世界のように、個々の才能を高く評価し、その人たちがもっと頑張りたいと思う世界観が重要なのだと思う。嫉妬が少なく、才能がある人たちが生きやすい世界を望みつつ、子供たちに学ぶことの楽しさやその先の未来について伝え、その子たちが活躍することに貢献できればと思った。子供の徒競走と踊りの2つしかない体育祭を見ながら。
前回はこちら:
参考文献:
記事を書くときの素材購入の費用などにさせてもらえればと思います。
