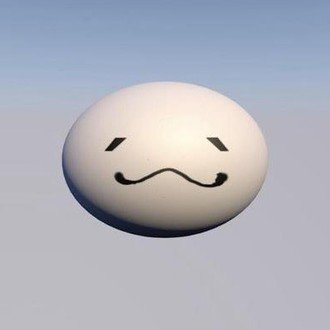完全3DCGアニメ『ドラゴンボール超 SUPER HERO』の映像的進歩、そして鳥山明にとってナメック星人とは何だったのかという話
新作アニメ映画『ドラゴンボール超 SUPER HERO』を見てきました。今作の最大の特徴は、過去の手描き作画に対して、全編フルに3DCG化したということだと思います。 CGアニメというと『トイ・ストーリー』や『アナ雪』などのディズニー、進化版人形劇のような映像をイメージしますが、セルアニメの質感に合わせたトゥーンレンダリング、セルシェーディング(言い方はさまざまですが)で、違和感のない、というか素晴らしい出来になっています。もともと鳥山明という人の立体デッサン力が圧倒的で、3D化に矛盾がないということも大きいのかもしれませんが、ものすごく上手く立体化できている。
映画を見た感触として、東映および集英社のチームは、ドラゴンボールコンテンツの世界進出戦略の一環としてこの3DCG化をテストしているのではないかと思う。鳥山明原作がもともとどこかアメリカンな乾いたタッチのある絵ですが、アメリカンコミックとジャパニメーションのいいとこ取りみたいな映像になってるんですね。
じゃあ手描きアニメはなくなり、アニメーターは失業してしまうのか、というとそんなことはなく、ドラゴンボールの3DCGというのは、おそらく過去の作品の手描き絵を忠実に参照しながら構図やモーションを作ってるのではないかと思います。
3DCGの初心者は「モーションキャプチャーがあれば簡単にどんなキャラでも動かせるのでは?」と思いがちですが、実はモーションキャプチャーで記録した人間の動きというのはめちゃくちゃに「その人のクセ」が出てしまいます。美少女アバターの中におっさんが入って動かすと、「あっ中身はおっさんだな」と1発でわかるほどおっさんくさい動きになります。逆もしかりです。こういうのは新しい技術が出てきて初めて気がつくところもあるのですが、人間の動作というのは本人が思っている以上に個人個人のクセが強く、情報の塊なんですね。なので、アニメキャラを適当にモーションキャプチャーで動かすとしばしば違和感が出ます。
別の作品になりますが、山﨑貴監督がルパン三世の3DCG化に挑戦した『ルパン三世 THE FIRST』という作品がありました。これも大変に出来がよく好評だったのですが、よくよく見ると、おなじみのルパン一味とゲストキャラの美少女・レティシアにはっきりと動きの差があるんですね。その理由を推理すると。ルパンたちの動きというのはモンキーパンチ、そして宮崎駿らが作り上げてきた手描きアニメという「お手本」があるのですが、ゲストキャラにはそれがないからなのではないかと思います。予告編の映像を見るとわかるのですが、むろんモーションキャプチャーは下敷きとして駆使する前提で、アニメ特有の「強調した動き」「現実の人体には難しいアクション」は過去の手描きアニメを参照してると思います。
今回の『ドラゴンボール超 SUPER HERO』でもそれは同じで、過去のドラゴンボールアニメをすごく丁寧に参照している。こちらも予告編のYoutube動画をリンクしますが、
最後30秒のところでピッコロが「いらーん!いつオレがそんなもの…」と振り向いて指差すところ、こういう動きってモーションキャプチャーの自然な動作ではなく、東映のアニメーターたちが蓄積してきた「一番リズムの気持ちいいタイミング」を参照してると思うんですね。パンも可愛いんですよ。小さい子どもの動きなんてモーションキャプチャーだけでは描けないと思います。
アニメーターの技術というのは、単に絵を描くだけではなく、「動かす」ところにその本質がある。どういうタイミングで、どう動かしたらかっこよく、あるいはかわいく、小気味よく見えるのか。ディズニーの CGアニメも過去の自社手描きアニメをよく研究して作っていますが、ドラゴンボール CGは東映というアニメの老舗に蓄積された日本アニメのタイミング、動きをよく消化できていると思いました。3DCGでドラゴンボールが作れてしまう、というのはある意味ではショッキングなことでもあるのですが、願わくば、ただでさえ良くないアニメーターの労働環境が3DCGによって「合理化」されるのではなく、彼らが持っている偉大なノウハウ、そしてそれを未来に引き継ぐための人材育成に生かされることを願ってやみません。そうでなければ、日本アニメはかけがえのない大きな遺産を失うことになると思うので。
さて、映像面のことをまず話しましたが、今回のストーリー面での特徴は、原作の鳥山明氏が脚本を担当し、ピッコロがほぼ主役のようになっている点だと思います。鳥山明先生本人がコメントで「一番好きなキャラはピッコロ」と語るように、
ピッコロはドラゴンボールという作品の中で不思議な役割を果たしてきました。純然たる悪役だった初代ピッコロから、生まれ変わりの二代目として天下一武道会で対決し、そしてサイヤ人を迎え撃つ仲間へ。昨日の敵は今日の友、それは少年ジャンプの王道的展開ではあります。でもナメック星でのフリーザ戦を経て同じサイヤ人のベジータが「クールなライバル」として仲間になった後は、本来ピッコロというキャラクターはその役割を終え、その他大勢のキャラクターに埋没していってもおかしくはないのです。しかしそうはなりませんでした。セル編、ブウ編とその後もピッコロはドラゴンボールという物語に不思議な形で関わり続けます。
改めて単行本を読み返すと、鳥山明という作家は最初は単なる大魔王として出したピッコロというキャラクターに、『ナメック星人である』『もともとは神様と表裏一体の存在である』『龍族の天才児であった彼が地球に流れ着き、作ったものがドラゴンボールである』という、『ドラゴンボール』という作品のタイトルに関わるような設定を次々と付加していくのがわかります。ドラゴンボールといえば誰もが悟空、そしてサイヤ人の物語というイメージを持つでしょうが、読者の目を奪うサイヤ人の物語の裏側で、鳥山明は『ナメック星人の物語』を延々と語り続けてきたのです。物語上の最大のクライマックス、「本当はあそこで終わらせる予定だった」と語られるフリーザと戦う舞台に、鳥山明はナメック星、ピッコロの故郷を設定しました。そこに住むのは戦闘民族サイヤ人とは違う、平和を愛し、傷を癒やし潜在能力を引き出す不思議な力を持つナメック星人たちでした。水だけで生き、神の力を持ち、性別がなく、古い知恵を持つ彼らはまるで僧侶のように見えます。
ドラゴンボールは本当はあそこまでバトル一辺倒になるはずではなかった、というのはよく語られることです。さまざまな要素が混在していた悟空の少年時代から、ピッコロ大魔王と戦うシークエンスによってドラゴンボールはバトル漫画へと変貌していきます。そしてどんどん「戦闘民族」の血に引き込まれていく悟空たちサイヤ人とは裏腹に、ナメック星人であるピッコロは不思議なことに別の変化をしていきます。悟飯を守って倒れるピッコロに、共に死にゆく神様が残す「ピッコロは最後の最後で神であるわたしを超えた、うれしいぞ」という名台詞。セル編で神と大魔王が再び一体化した時につぶやく「もう神でもピッコロでもない、本当の名前も忘れてしまったナメック星人だ」という、ドラゴンボールとしては異質なほど詩的で、哲学的なセリフ。パワーと戦闘に傾斜していくストーリーにカウンターを取るように、大魔王として登場したピッコロは奇妙にもその知性、徳のようなものを獲得していくのです。
ここからは今回の『ドラゴンボール超 SUPER HERO』のネタバレに関する内容なので、月額マガジンになります。ここまで読んで、もし興味を持ってくださった方は、加入して頂けると他の記事も読めますので、よろしければ投げ銭のつもりで読んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?