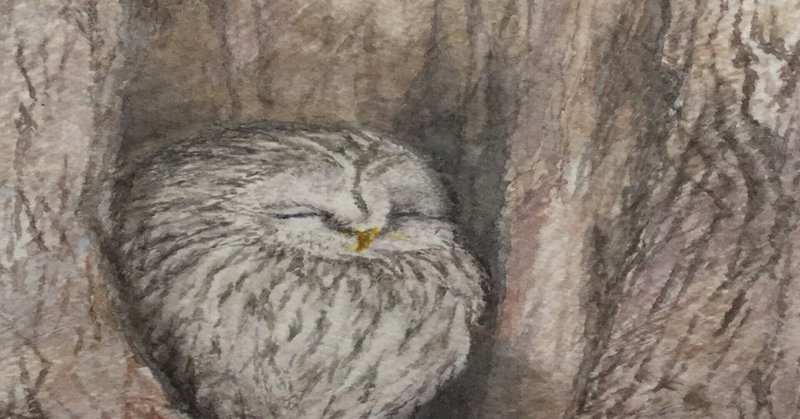
幸田露伴の小説「望樹記① おばあさんのこと」
望樹記
「年を取るとケチになる。」
この言葉は誰から聞いたのか、また何時(いつ)おぼえたのか、その由来は甚だ不明であるが、何でもその由来が忘れられたほど遠い過去に、そしてその由来が思い出されないほど何気なく受取った言葉に相違ない。それがどうしたことかこの一二年、時々頭を擡(もた)げて来る。ちょうど石塊(いしころ)や瓦片(かわらかけ)の下になった雑草が、そこに物が有ると気づかない長い日数が経った朝、どうした雨や露や風や日の具合かによって、至ってかすかな青みを現すことがあるように、どこかで至ってかすかに、
「年を取るとケチになる。」
と囁くことがある。無論古い記憶が新しい機会に出て来て、「ここにこういうものが控えておりました」と名乗るに過ぎないので、「そうか」と答えればそれで済んでしまうことなのである。
ある時、何かの拍子に、またこの「年を取るとケチになる。」という言葉が聞こえた。そこで寸時を我知らずに割(さ)いて、一応その言葉と自分との交渉を考えて見た。しかし誰から何時(いつ)聞いたのか分からなかった。もっとも余り立派でない生活をしている佐藤さん加藤さんも、系図をただして見れば天之児屋根命(あめのこやねのみこと)の子孫であったり、片田舎の里人でも厳然として皇胤(こういん)から出る者があったりするように、この言葉も、濁り川のその水源をただして見れば、萩の下露・篠の露・岩下清水・苔清水の清い流れであるように、多くの人が偉大・高明と尊崇している人の言葉から系図をひいているものかも知れない。栗原柳庵は人に依頼されれば、巧みにその人の出自(すいじ)を、調べ出すのか作り出すのかは知らないが、何しろ立派な系図にまとめたと聞いているが、多分それは虚言妄説であろう。この言葉だってそういう調子で調べたならば、おありがたい御本尊様から糸をひいているのかも知れないが、そういうことをして、何に曰く云々(しかじか)と似かよったものを列べ立てて、証拠裁判から云えば成り立ちそうな案文をこしらえたところで、おかしくもおもしろくもない。嘘には証拠が必要だが、事実は自然が語る。何でもこの真実は勿体らしい本を読んだりして、その中の字句から「年をとるとケチになる」という現語訳をして、そしてそれを記憶したのでは無い。今になると多少想像を加えないでは思い出せないが、凡そは次のようなことであるらしい。自分がまだ年の若い頃、活発に放縦に、今日を過ごせることが幸福であるとも意識しないで、幸福に暮らしていた時分、自分等と同じ年頃の無駄口友達・・・無駄口友達というのはおかしいが、漢学者風に云えば談敵(だんてき)即ち話し相手で、実際若い者は自分の為にも他人の為にも学問の為にも芸術の為にも、職業や利益生活や又は社会の為にも、何にもならないような会話、即ち無駄口を交換することを悦ぶもので、会話の為の会話、強いて弁護すれば趣味興味の為の会話を交換する友人達を持っていない者は無い。が、それらの会話から良いことが生まれることは勿論稀で、大抵は山の木の葉が風に動くように彼等の舌が動くだけで、そして山の木の葉は動いたが何の結果も齎(もたら)さないように、何もなく終わるのが常であるから、その実質に適切な名称としては無駄口友達が適当である。・・その無駄口友達と会話して、その絮説、縷説、連綿語、突発語、奇句、警句、罵倒の言葉、叱咤の言葉、或いは悲憤慷慨、或いは滑稽突飛、種々様々の無駄口興味ともいうべき、しかも浅はかな、偉そうな、しかもくだらない、超脱的で実は平凡な、気焔が強く且つ足元のおぼつかない、つまり世間の青少年共が為すところの会話を為して、その月並みな興味にひたっているのを良いとしていた時分に、誰だかは忘れたがその仲間の一人が、若い自分等とはソリの合わない老人を冷評して、「年をとるとケチになる」と云った。それを覚えていたのではあるまいか。或いは又無駄口仲間の雑話交換の有様をかいた小説雑書の中で、この言葉を見て「これは一寸おもしろい」と思ったのではあるまいか。どうも二者の中では前者のようであり、また重苦しい書物の中から受け取った言葉では無いように思えた。
○
この言葉の最初について思い出したことはこれだけであった。しかしまだこの言葉について思い出したことがあった。それは今から十数年前、或る一人のお婆さんについて、フトこの言葉を自分の心中に浮かべて感じた事のあった事であった。
そのお婆さんは可なり多彩な履歴をもった人で、随分気の強い、我の強い、若い時は突き詰めた事情から身を投げようとした事もあれば、また女だてらに荒々しい振る舞いをして愚かな男を懲らしめたり、また安政の大地震に際しては紀文(きぶん・紀伊国屋文左衛門)もどきの投機的商売をしたという事であるが、自分の知った頃には、もう髪を切ってしまって、神仏に帰依奉仕するような事だけを、道楽と云っては悪いが、まあ道楽的にやっていて、倅たちから贈られる小遣銭を貧困の人の為やなんぞに遣うのを仕事としている結構な身分のお婆さんであった。
しかしお婆さんは、手足も達者、口も達者で、中々シャキシャキしたお婆さん振りを発揮し、まるで上等な時計の秒針のように、正確に不断に、どんな時でも進行を忘れずに勤勉な生活を続けていた。江戸に生まれて、江戸・東京で育った人にも似ず、材料さえ見つければ直ちに銘仙の糸を抽く、一二寸の短いのでも丹念につないでコロコロした毬のようなものをつくる。反故紙は貰い溜めて、かなり溜まると丁寧に長めに四ツに折って、鋏を櫛の歯のように入れ、そして切り余しの部分を一ツ置きに引き破ると全紙が紐のようになる。それを揉んで糸車にかけると造作なく長い紙縒(こよ)りになる。これらの物を溜めては織屋に渡して、或いは銘仙を織らせ、或いは雑色彩糸(ぞうしきあやいと)の美しいものを織らせ、或いは紙を緯(よこ)にした一種の丈夫で瀟洒な紙布(しふ)を織らせる。そして何ぞの場合には、お婆さんはその御手製品に、報徳宗(二宮尊徳の教え)を御天狗が布教するような談話を添えて・・しかしその談話を江戸子式にチョッピリと、まるで小さなノシ位の割合にしてくれるのは、流石苦労した人であると思わせた。
こういう達者なお婆さんが、或る時自分を訪問してくれた。その用件は例の紙布か何かを呉れて、そして反故紙か何かを徴発して行こうという、此方(こちら)にとっては誠に有難く、彼方(あちら)にとっては寧ろ苦労な事に定まっていた。例のようにシャキシャキと、例のように意気旺盛で、例のように雄弁哄笑をほしいままにして、先ず「こんにちは」という冒頭の一句から、「御不養生をなさらないそうでいつも御丈夫で結構です」という二の句に、もうお婆さん独特の威圧的な何物かを含んでいる。「お婆さんもお達者で」と挨拶すると、「ええ、有難うございます。まだ神様が働けると思っていて下さるそうで達者でございます。ソレニネ」と一寸人の顔を見て、「図に乗って後(あと)ねだりして二日酔いをする、ソンナ神様にお手数をかけるようなことは、こう枯れてしまって致しませんからネ。お婆さんの方が若い方よりナラシで云ったら強いとこがあるかも知れませんよ、ハハハ。その代わり神様が、もうお前は卒業させてやるよ、とおっしゃった日には、待て暫しは有りゃしません。南無阿弥陀仏、ゴクリッというッきりで、明日はお寺で卒業式ですよ、かわいそうなような、おめでたいようなものです。アハハハ。だから年寄りは可愛がっておきなさい。ハハハ。可愛がられりゃ年寄りだって情が無い訳じゃないから、きっとお礼心に憎まれ口ぐらいは云って行きますわ。笑いごとじゃありませんよ。為を思えば年寄りですもの憎まれ口でもきくより、ありゃしません。ハハハ。」というような調子でまくしたてられる。抑揚がある。頓挫がある。はたき込みも打っちゃりもあれば、時には逆手もあるような快活な話し方なので、とても太刀打ちは出来ないから、平静な柔らかな心持ちになって、ただその言葉を聴いている他(ほか)はなかった。
会話も良いほどに闌(たけなわ)になった時、お婆さんは鼻紙か何かを出そうとして、その常に携帯している手提げ袋の口を解いて、中の物を抜き出した拍子に、コロコロと転げ出したのは、例の糸くずを紡(つむ)いで毬のようにしたものであって、それは別に自分の注意を惹きはしなかったが、なおその他に半分ばかり見えたのは、赤と緑との糸の縒り合された紐のようなものであった。お婆さんがまた何かやり始めたのか知ら、と思ったので、「その赤と緑との紐は何です」と問うと、するとお婆さんは直ぐにそれを抽出して示した。一目して自分にもはっきり分った。それはお婆さんの手製になったと見える下駄の鼻緒の前坪(まえつぼ)であって、その材料たるものは各商店でその頃より大いに使われ始めたところの糊固めした括り糸で、それを縒って芯としたのへ有り合わせの小切れを被(かぶ)せて無造作にこしらえたものであった。ハハアお婆さんこれを持って居て、往来で鼻緒の切れた人を見かけた時、モシモシ持ち合わせましたからこれをあげましょうと与えるのだナ、と直ぐに合点ができたので、
「お婆さん、また一ツ新規の事をはじめましたネ。」
と別に深い意味も無く、ただ一通りの挨拶に云った。
「ナアニ、もう余ツ程前からして居るのですよ。今度からこの糸も溜めて置いて下さい。座敷から庭に掃き出し、庭からごみ箱へ掃き込んでは、何ぼ何でも勿体ないことですから。」
「ハイ、ほんとにそうです。溜めて置いてさしあげましょう。今でも少しは溜まって居りましょう、私も家内も冥利(みょうり・お蔭様)ということは知っていますから」
「ああ有難い。男は少しぐらい無理な喧嘩をしてもいいが、米一粒でも半紙一枚でも無駄にするようじゃ民百姓の上に立つ器量じゃ無いッて云いますからネ。」
「お婆さん、権現様の御腫物(おでき)の膿の紙じゃありませんか。(徳川家康は、腫物の膿を拭った紙を捨てずにとって置いたと云う)」
「ハハハハ。しかし世の中は小癪になりましたネエ。どうでしょう。一寸買い物をしてもこんな糸で括ってよこすなんて、むかしは藁縄ばかりで済んだものです。買い物するには風呂敷を持ってゆきますもの、一々紙で包んでこんな物で括るなんてことは、実に無駄な手数、無駄な物遣い。ですが、御体裁好きの不精な人には気に入りそうな事なので、どこでも仕無いところはないようになりました。この糸だってどうでしょう遠くの国の百姓がこしらえた綿を、エッチラオッチラ石炭を焚く船で運んで来て、それから外国ごしらえのすばらしい機械にかけて、年がら年中、芝居の雪に降られた石灯籠みたいな女工さんの手を煩わせた結果が、やっと世の中の用に立つのでしょう。考えてごらんなさい、あだやおろそかにしては勿体ないじゃありませんか。」
老人というものは、まんざら無茶は云わないものだと思った。しかし、今しみじみと極々少しばかりの糸の事を論じているのを、このお婆さんが若かった時の溌剌とした行為が伝わる種々の話から考えると、この人にしてこの言葉あるかと思わざるを得なかった。勿論紙布にしろ、屑糸織にしろ、銘仙つくりにしろ、皆おなじ系統の事であるが、足に履く泥下駄、その下駄の鼻緒、その古鼻緒を生かすための前坪、その前坪を直すデイデイ屋(今はほとんど見かけないが、下駄の鼻緒が切れなくなった訳では無い、おもしろい世態の変化である。)は、江戸の風俗では賤しいものとされていた、ということを知らない筈の無いお婆さんが、人の為とは言え手提げ袋の中にこういうものを持って歩くのを見ては、新たに一寸感じさせられるものがあったのである。それはとにかく、お婆さんの言葉は、尚古的な感情のほかには、非とすべきものは無いのであったから。
「ほんとに仰(おっしゃ)るとおりです。」
と答えた。お婆さんは答えに満足して、
「ですからこんなものをこしらえて、この糸屑だって力のありったけは世の中の役に立たせようと思ってし始めたのですよ。この婆アだって、卒業までは何かしら勉強しますからネ。アハハハハ。どうです。世間のやくざ野郎や、のらくら者、下駄の前坪にでもしてやりたいような奴もたんと有るじゃありませんか、だがそんな奴は前坪にもなりやしないのですネ。アハハハハ、わたしなんぞも学は無いし、時世おくれ、人間の屑にゃあ違いないが、せめて糸の屑ぐらいにゃあ役に立ちたいと思ってるんです。」
半ばまでは平静だったが、後半は少し激しているように思えた。
「どうしてお婆さんなんぞは屑どころじゃあ無い、第一今日を気持ちよく送って、そして人の為になることを始終心掛けて居るなんて・・」
「オット、そんな挨拶は若い女にしておやりなさい。女ッていうものは意気地のないものでネ、好い話を一ツしてあげましょうか、お聞きなさい。メッカチの男が来る、女は厭なメッカチが来ると思いながら澄まして行き違ってしまう。四五間離れてから、メッカチが心底から感心して、マアなんて髪の美(い)い女だろうというと、女がそれを聞いて腹の中で、あの人は眼がいい。アハハハハ、若い中はほんとにその位のものですが、婆アになっちゃあ、気に入るようなことを云う奴があると、厭な奴だな此奴(こいつ)、無心の足場でも掛けていやがるのじゃ無いか知らん。アハハハハ、そんなもんですよ。」
「わたくしは御無心しませんよ、ハハハ。」
「じゃあ、ほんとに褒めて下すったの。マア嬉しいこと、お礼を申しますよ。しかしネ、正直のところを申しますと、褒められて嬉しがった齢にもう一度なりたいくらいのもので、アハハハハ。嘘じゃありませんよ、今にお分かりになるでしょうがネ、新沢庵をパリリとやった味なんかも、歯がいけなくなっちゃあ二三割どころじゃあ無く、割減りが立って来るようなことでネ。全くのお話ですが、年をとると魂(たましい)にも皺でもよるせいですか知らん、新しいゴム毬が一寸突かれてもポンとあがるように、ほんのお世辞を言われても真に受けて嬉しがるというようなことは無くなりますよ。つまり毬なら気が足らなくなってハズミが悪くなるのですネ。子供なら大人に脱け変わろうという時分、おさらいで長唄の一ツも気を入れて唄ったあとで、みんなの惜しいッて声もほんとに実が入っていて、そして他所(よそ)のお師匠さんに褒められたなんて、そんなわずかの事にも嬉しくってハチ切れそうになるのは、一体嬉しいっていうのが罪の無いことなので、罪の無いのが嬉しいっていう事なのか知りませんが、何でも嬉しいというものは若い中(うち)のことですネ。」
「ハハハ、分かりましたよ。嬉しかったんですネその時。その時分はお婆さんも左様(そう)さ、色白の、小柄な可愛い娘さんで、パッチリとしてはいないが気の勝った眼つき、紅だの浅黄だの身の・・」
「下らない。何を云っているんです。嘘をおつきなさい、まだ卵にもなっていなかったくせに、あてずい(当て推量)な。」
と喝破されて、引き下がった。
「オヤ、つい御心安立てにとんだ失礼を申しました。しかしほんとにわたしは音曲の方は出来もしなかったし、また好きでもありませんでした。今のはただ物の道理のお話が横丁へ深い入りしたので・・」
此方(こちら)も皆まで言わせるほどまどろっこしくはない。
「アア、それは分かっていますよ、私も余計なことを申しました。で、本筋の方の・・。ナゼ、お婆さんは自分のことを糸屑だなんぞというのです。」
「だって、本当にそうだから仕方ありませんや、今日たった今、此方へ伺う途中のことですがネ。どうです。こういう厭な奴にぶつかったのですよ。水戸様の前の川ぶちを通りかかりますと、子供を負ぶったおかみさんが、しかも内職かなんぞの品物を問屋へ持ってでも行くという姿で、嵩高(かさだか)な風呂敷包みをかかえてやって参ったのです。この頃の雨続きに下駄の鼻緒は腐り勝ちですもの、かかえたり、負ぶったりでは、足もおかしく力を入れて突っ張りますから、忽ちポッツリとなって、これはと当惑した様子なのです。そこで、もとよりそういう時の為にもと持っていた前坪ですから、モシおかみさん、お困りでございましょう。丁度持ち合わせがありますから、どうぞお使いなすって、と袋から出してやりますと、おかみさんは一寸びっくりして、それから大層喜びました。しかし子供は負ぶっているし荷物はあるというので、手も碌(ろく)には自由に使えませんから、わたしが荷物を持っていてやると、おかみさんは礼を云い云い鼻緒を立てるという訳で、それはほんとに嬉しがってくれましたから、なにも恩に着られようといって酔狂なことをしているのではないんですが、此方だってそう云われれば悪い気持ちはしません。そこでもうすっかり出来たところで、おかみさんはまた改めて礼を云う。此方はどう致しましてと挨拶する。北と南へ分かれようとすると、通りかかった二人連れの男、余り感心しない洋服に、安いステッキ薄ッ髭、ぶらぶらと鷹揚に勿体ぶって歩いて来かかりましたが、一人が行き過ぎながら、わたしの方を見て、「御安直な慈善行為サネ」と言うと、もう一人が振り返って見て、フンと云って、「慈善でも無いサ、と言って義侠と云う程でも無しカ、ハハハハ、ハハハハ」と行ってしまいました。行為ッてのは何です。」
「行いということです。しかし失敬な奴ですネ、お年寄りに対して・・」
「ヘエ、年寄りで無ければさげすんで貰ってもいいのですか。」
と余憤なお盛んにお婆さんは、その時の忌々しさを吐く。同情せずにいられない。
「誰に向ってだって、御安直だなんて、侮蔑の意味を含んでいます、失敬千万な。タンボ道の泥濘(ぬかる)なんぞで其奴(そいつ)の鼻緒が切れて弱った時、ヒョックリお婆さんに出遇わせて、お婆さんの親切を貰わせてやりたい。」
フト漏らしたこの言葉は、大いにお婆さんを緩和させる効果があった。お婆さんの余怒はもう名残(なごり)無く晴れた。
「ナアニ世間によくある型のあんな奴を相手にする程若くはありません、あんな奴でも困っていたらば全く親切を惜しげもなく呉れてやりますは。ただああ云う奴が世の中にウヨついていると、どれ程人が真面目に善い事をしようと思っても、機先を挫いて縫い針の先を悪くするようなことをするか知れません。デモマア好うござんす。人さまは人さま、わたしはわたし、貴婦人とか何とかいう御大層な方々の真似は出来ませから、自分の心持と自分の手業とで出来る分の事をして気が済めばそれで好いのです。御神楽(おかぐら)に出て来る外道のような奴に褒められたいからッて何をするのでもありません。どうせ大したお金持ちというのでは無し、学問や身分があるというのでは無し、コウ意気地なく年を取って、使いからした糸のようになっているのですから、身体(がら)相応のケチな事でも何でもして、働けるだけマメに働いて、人間の奉公を奇麗に済ます積りなのですよ。何だか自分だけの自惚れでは、御礼奉公も済ましたつもりなのですが、まだ勤め方が足らないと見えて、極楽で一軒新店(しんみせ)を出させて下さるというところにはならないと見えます。ハハハハ。いづれその内に出させていただきますから、店が出来ましたらどうぞお立ち寄り下さい、いづれ遅かれ速かれ、あちらへお出(い)でになりましょうから、ハハハハハハ。それともお路(みち)がちがいますかネ。」
困らせる軽い洒落だ。しかたが無い、ただ、
「ありがとうございます。」
と笑った。お婆さんも面白そうに笑った。
「マア冗談は冗談、いくら年寄りだってお天道様が太っ腹なことを良い事にして、のらくらと食いつぶしばかりして居ては勿体ないことですからネ。」
と勿体ないという言葉に力を入れて言った。実にこのお婆さんの宗旨は、もったいないという一語にあった。もったいない、というのは、妄(みだ)りに天の恩恵を被(こうむ)ることは恐懼の至りに堪えない、ということであるが、この一語から導かれた道理で、他人の悦ばない残飯でも余り汁でも、このお婆さんは「もったいない」の真言(しんごん)を唱えながら食べてしまう。貧者が借家の陋隘を嘆いても、このお婆さんは「もったいない、働きさえすればこのお住居(すまい)でも結構好い心持で御休みになることが出来るじゃありませんか、いずれその中にお天道様が何とかしてくださりましょう、むだに光っておいでなさる訳でもありませんから」と慰める。廃紙を紡織するのも、糸くずを鼻緒にするのも、皆この勿体ないから割り出されたことなのである。
この勿体ないの一語、即ちお婆さんの生命であり信仰であり祝詞(のりと)であり咒詞(じゅし)であり教条である、その勿体ないの一語が自分の胸に強く響いた時、このお婆さんの若い時の溌剌とした生活を聞き知っている自分は、済まないけれども、当時読んでいた本の議論に尤もな節(ふし)もあると思っていたせいか知らないが、「臣従道徳!」という声が何処からともなく聞こえて、そして再び済まないけれども、「年をとるとケチになる」というが、真(まこと)に「年をとるとケチになる」と思った。今にして思えばお婆さんの所謂「もったいない」ことではあったが、口にこそ出さないがそう思って感じたのは事実であった。
そのお婆さんは、お婆さんの所謂お天道様の命令を受けて他所(よそ)の世界に新店を出すために出発してからもう長い月日になる。おそらくは相当な店が出来ていることであろうが、訪問をすることは小野篁(おののたかむら)でも無いことであるから、まず御免をこうむっている。
この頃自分が何事かを言ったり思ったり行ったりする時、たまさかであるが、「年をとるとケチになる」という言葉が、何処からか聞こえる。これはどうしたものであろう。そこで一応自分とその言葉との交渉を考えて見ると、この通りであって、その他には何も無い。その中(うち)お婆さんとの件は、記憶を辿れば辿るだけ分明になって来るが、この言葉の発頭のところは考えれば考えるほど不明になって、むしろその朦朧とした霧の中に、何かの神祠(しんし)の千木(ちぎ)か鳥居か、仏寺の山門か堂の屋根でも見つけるように古い歴史上の学者や詩人の言を見出して、そしてこれから出ていたのであった、ハハハと云って悦びたいような気がするのみである。しかし諸子百家などの著述の類から同意味の言葉を見出したとしても、それからこの言葉を得たので無いことは疑いも無い事である。(望樹記②につづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
