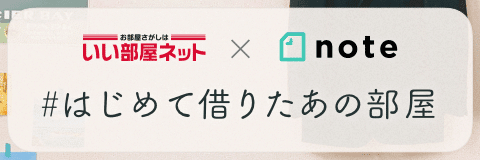おじさんと僕
おじさんと僕。それまでまるで、と言ったら語弊があるけど、あまり関わりの無い関係だった。普通の「おじさん」と「甥」。どこにでもある関係性だ。おじさんは遠くに住んでいたし、会うとしたら正月くらい。それに、変わった人だった。会社に勤めてはいるけれど、長期の休みを取っては海外(一般的な観光地ではなく、〜スタンとかが多かった)を放浪していた。そして、独特な画風の絵を交えて手記を書いてみたり、現地の植物や動物に異様に興味を持ち、図鑑を作ってみたりするのが趣味だった。そのどれも、クオリティがめちゃくちゃ高くて、母はいつも「お兄さんすごいわあ。大学の教授にでもなればいいのに。」と言っていた。家に来ても、外国の芸術家の話や昔の中国の王朝の話、思想家の主張の話なんかをしていて、興味の無いぼくはただふんふんと受け流していた。頭が良過ぎて、マニアック過ぎて、ついていけないのだ。おまけに早口で、ガーっと捲し立てる様に話すから、気分も話し方もいつもフラットな僕とはペースが噛み合わない。どちらかというと兄と馬が合い、熱く語り合っているのを、テレビを見ながら意識の端っこの方でぼくは聞いていた。
「健二郎は、もう高校も卒業か」
「そうだね」
「あっという間だな」
「うん」
「お年玉ももうすぐ終わりだな」
「あはは、そうだね」
トイレに行く時、おじさんはぼくに申し訳程度に話しかけ、また兄との会話に戻っていった。本当に、それくらいのやりとりしかない、おじさんと僕だった。
高校卒業を控え、埼玉の大学に進学が決まった僕は、まず、通学について頭を悩ませることになった。実家から通えない事もなかったが、毎日2時間以上かかる。かといって、一人暮らしはうちの家計にとっては大ダメージだ。どうしたものか、やはり毎日早起きか。そんなとき、
「兄貴のとこに住まわせてもらったらどうだ」
父はいつもの調子で事も無げに言った。
「それは悪いわよ。お兄さん、中学を卒業してからずっと一人暮らしでしょう。今さらこんな大きい子どもと二人暮らしなんて。」
母はうーん。と眉毛を下げた。
「別におれはいいけど。一人暮らしがいいとか、こだわりないし。」
「健二郎がよくたって、お兄さんがよくなきゃだめでしょう。」
「とりあえず、兄貴に聞いてみるか。」
父はスーパーポジティブな人で、本当にフットワークが軽い。おまけに、言動も。父が話すと、何でも簡単なことのように思える。
そんな父からの話だったためか、おじさんは僕と住むことをあっさりオッケーした。母はすごく感謝して、何度もお礼を言っていた。そして、家賃とか生活費とか、そういった事を話し合って、一ヶ月一万円という破格の値段で住まわせてもらえることになった。僕はというと、そんなに特別な事だとは思わなかった。なんなら、住まわせてもらって当たり前のような気さえしていた。だって家族なんだし。じーちゃんはおじさんの事をよく理解しているからか、僕がおじさんちに転がり込むことに最後まで渋い顔をしていた。でも、当の本人がいいって言ってるんだから、もう決定だ。僕は父に似たのか、ちょっとコンビニ行ってくる。くらいな感覚で家を出た。
「ここが健二郎の部屋な。ここが。トイレはこっちだな。うん。」
一人暮らしなのに、広い家だ。改めて僕は思った。なのに、足の踏み場がない。至る所が本で埋め尽くされていた。歴史、経済、自然科学、心理学、芸術、文芸書、詩集、あらゆるジャンルの本が所狭しとひしめいている。きっと、本が好きな兄だったら興奮してただろうなぁ。そんな事を思いながらうん、ありがとう。と返事をする。
「めし、食べるか」
「うん」
その日は2人で近くのファミレスに行った。男2人、きっと、他愛の無い会話をしたんだと思う。新しい環境だとか、新しい生活だとか、そういったことに特にテンションが上がるわけでもなく、ごく自然に、今までもここに住んでいたかのように、おじさんとの生活が始まった。
おじさんと生活し始めて分かったこと。やっぱりおじさんは変人だ。
テレビを見てると、政治家顔負けの鋭いツッコミを入れるし、芸人に負けじとオヤジギャグを炸裂させて一人で笑い転げてるし。かと思えば、外国の古い映画を観て、尋常じゃないくらい泣いてることもあった。何事も極端なのだ。おじさんは。生活にも変なこだわりがあって、サラダには必ずブロッコリーを入れるとか、朝起きたらまずは香水を振り掛けるとか、寝る前の30分は写経タイムだとか、お風呂のお湯は42度以上でも以下でもダメ(一度、良かれと思っておじさんが仕事から帰る前にお湯を溜めておいたら、ぬるい!と怒られた。)だとか。これまで生きてきて、特にこだわりも無ければ、強い意思も主張もない僕からしたら、おじさんと一緒に住むことは異文化交流だった。よくもまあそんなにこだわれるよなぁ。おじさんと僕、足して二で割ったら丁度いいかも。いや、おじさんの方が圧倒的に強いか。そんなことを考えながらも、軟体動物のように変幻自在な僕は、変人のおじさんとの生活にすぐに慣れた。
人当たりが良いことだけが武器の僕は、大学でもたくさん友達がいた。そうなると、お互いの家に行き来することも勿論ある。おじさんの家だが、今は僕の家でもあるのだ。自由に友達を呼んだって構わないだろう。そう思って、僕はどんどん家に友達を連れ込んだ。今思えば、おじさんこそ異文化交流だったに違いない。ヘラヘラしたフーテンの寅さんみたいな僕、と、愉快な仲間達。雑誌の読者モデルをやってるコーキやユータ、陸上の全国大会で優勝経験のあるアスリートの茂木くん、強面だけど、めっちゃ歌がうまくて歌手を目指している祐希、趣味がマニアックなスポーツ観戦で、高校野球とか高校サッカーにあり得ないくらい詳しい内藤、おじさんと似ていて、考古学とか歴史が大好きな竹ちゃん、ハーフで芸術家肌のアリソン。(アリソンはアルパという小さなハープみたいな楽器を、男の僕でもうっとりするくらい綺麗に弾いた。)こんな面々を毎日のように連れ込んで大騒ぎする僕に、ある日おじさんはキレた。
「いい加減にしろお!」
シンプルだが、最もなお言葉だ。僕は調子に乗りすぎていた。おじさんの城にズカズカ入り込んで荒らしまくっているのだから、そりゃあ怒られるよな。僕は素直に反省し、それからは、適度なペースを守って友達と付き合うようになった。おじさんの方も慣れてきたのか、段々と僕の友達と交流する様になった。趣味が合う竹ちゃんや、同じくマニアックという点で馬が合う内藤とは、僕そっちのけで熱く語り合うこともあったくらいだ。その光景を眺めながら僕は、こういうの悪くない、と思った。変人で偏屈なおじさんがすごく楽しそうだった。
あっという間に大学4年間は過ぎた。
埼玉は好きだし、友達も沢山いたけど、僕は地元に戻って就職することを決めた。卒業式は平日で、休みが取れない父に代わって、母とおじさんが参加することになった。別に、卒業するからって何か特別なことは無いけどなぁ、と僕はいつもの調子で思っていた。けど、おじさんにとっては違ったようだった。2週間前にはスーツをクリーニングに出して準備万端。前日に散髪を済ませ、当日にはとっておきのネクタイとチーフを身に付けて出陣するという気合の入りっぷり。
「一生に一度だからな」
そう言うおじさんの目が、少し潤んで見えた。
3月の中旬。春らしい天気の日だった。
「また、帰ってくるよ。」
「おう、気をつけてな。」
いつも家を出るときの様に、ごく自然に、おじさんとの共同生活は終わった。
翌年の正月、おじさんが我が家にやってきた。
「おう、健二郎。元気か。」
「元気だよ。」
一緒に住んでいたのが嘘かの様に、僕たちはまたただの「おじさん」と「甥」に戻っていた。
夜になって、おじさんは父と兄と一緒にお酒をガバガバ飲んで、また昔の中国のことなんかについて熱く語り合っていた。僕はケータイをいじりながら、意識の端っこの方でふんふんと聞いていた。
トイレから戻ってきたおじさんは、いつも申し訳程度に話しかけるのとは違い、僕の隣にどっかと腰を下ろした。もうベロンベロンだ。
「だいぶ酔ってるね」
ぼくは笑った。
すると、酔っ払いながらも真っ直ぐに僕を見て、おじさんは話し始めた。
「健二郎、おじさんはな、不器用で変人で、今まで人と関わらないように生きてきた。最低限の人間関係だけでいいと思ってた。周りの人にも冷たくしてきた。でもな、垣根がない健二郎の人柄のおかげで、健二郎のおかげで、職場の人にも優しくできるようになったんだ。健二郎と一緒に暮らしたおかげだよな。健二郎ありがとうなあ。」
おじさんは泣いていた。
「おじさん違うよ。おじさんとだからやってこれた。」
気付いたら、言葉が溢れていた。
「おじさんとだから4年間あの家で一緒に暮らせたんだよ。俺も、おじさんと暮らしてさ、色んなこと、思ったよ。嫌になることもあったけどさ、楽しかったよ。」
気付いたら、僕も泣いていた。
「そうかあ。それは聞いたことなかったなあ、ちゃんと話したことなかったなあ。」
おじさんは更に泣いていた。オイオイ泣いて、ボロボロ涙を流していた。父と母、兄もこちらの様子に気付いた。
「何やってんだ2人共。」「あらやだ、どうしたのよ、2人してそんなに泣いて。」「なんだなんだ?」
僕は段々笑いが込み上げてきた。大の大人が2人、ボロボロ泣いていることがおかしくて、僕は死にそうなくらい笑い転げた。
僕がはじめて借りた、おじさんと過ごしたあの部屋は、一生忘れない。きっと、忘れられないだろう。
この記事が受賞したコンテスト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?