
『「瞑想」から「明想」へ 〜真実の自分を発見する旅の終わり~』書籍出版記念講演会②
師匠山本清次の出版記念講演会を開きたいと考えた場合、まず最初にしなければいけないのが師匠のスケジュールをいただくことです。師匠のスケジュールがないとそもそも成立しません。師匠のスケジュールをいただき、日程を決めることから始まります。「1月17日の出版日以降でちょうどいい日程をいただきたいです」とお願いしました。出版記念講演会ですから、書籍の出版以前に開催することはできません。かと言って出版から1年も2年も経ってから開催するというのもおかしな話です。ですのでちょうどいい間隔の日程をいただきました。師匠に少々無理なお願いをしたかもしれませんが、快諾してくださいました。
2022年10月2日 発起会から始まりました
今回の出版記念講演会の主催は一般社団法人愛光流ではなく愛光流認可指導室と愛光流師弟会です。一般社団法人愛光流にもお世話になりますので、まったく関わりがないということはありませんが、でき得ることなら認可指導室と師弟会が中心となってものごとを進めて行きたい。
10月2日は記念すべき日となりました。この日は師匠の出版記念講演会に向けて最初の日。認可指導室が一堂に会して話をする発起会と題された会でした。ちなみに若いスタッフの誕生日でもありました。
10月4日は本格的に会議という名の会議がスタートしました。オンライン上ではありましたが。議題はもちろん講演会です。
講演会の日程や当日の師匠の動きなどを確認します。会場となる候補地、予算案など細かな今後決めていくべきことを列挙し、まとめて行きます。後々でも決めていける部分もありますが、決めていくべきことや確認しておかなければならないことを書き出しておくことは優先順位をつけたり、ものごとの手順を考えるのには適していると思います。
中でも重要なのが目的と進め方です。目的が決まると進め方も決まってくるようにも思います。目的に応じた進め方をしていきたいです。進め方の選択も目的に応じたものでなくてはなりません。目的自体も細かな部分では変更可能であっても、言葉や表現を変える程度で大筋は変わってはいけないのだろうと、今の私は考えています。とにかくいろいろと動き始める前にも決めなければいけないことが抽象的な部分から具体的な部分までたくさんあるものだという印象でした。
目的・進め方
目的を確認します。さまざまな意見が出る中でも目的を明らかにすることで全体像が見えてきます。会全体の方向性も明らかとなってきます。
【目的】
・明想を中心にした愛光流の活動を一般の方々へ広く、知っていただく。
・閉鎖的なものではなくOPEN な講演会となる。講演会は誰が来てもいい(普段、愛光流は入会された会員さまのみが様々なサービスを受けることができる)。今回の講演会は非会員さまの参加も可能。
・基本的なコンセプトはお祭り。来られた方々に楽しんでいただくことを考えよう。何か面白そうという雰囲気を作りたい。
・講演会は愛光流認可指導室主催、愛光流後援とする。
いくつか目的と手段とがごちゃ混ぜになっている部分もあるかと思いますが、具体と抽象を行ったり来たりしていく中でまとまってきたものでもありました。
そして目的を形にするためにどのように進めていくかです。愛光流認可指導室と師弟会を合わせると15名。
講演会にお越しになられたみなさまが「楽しい」と思って下さるには、私たちも「楽しい」と感じる必要性もあると思います。
【進め方】
・愛光流認可指導室・愛光流師弟会メンバー間で共に作っていけるような形にしたい。
・報告・連絡・相談、まとめ役。リーダーが必要。
⇒人選しました。
・目的を共有し、意志を合わせる。
・講演会に向けて実働していくのに必要なグループを作り、実働はグループで進めていくことをベースとする。
はじめての師弟会全体での集まり
講演会についてのはじめての師弟会全体での集まり、話し合いは大阪師弟会の日に師弟会が終了してから行われました。
各地から集まってきている師弟会ですから、事前に主旨を伝え、時間の許す限り集まっていただきました。鳥取県倉吉市を拠点とする師弟会もありますので、全員が全員その場で参加できるということではありませんでしたが、大阪に来れない師弟会もオンラインで参加し、これから始まる「お祭り」に向けて意見を交わしました。
師匠の出版記念講演会を愛光流認可指導室と師弟会が中心となって開催したい、講演会の日程、実働していく担当グループ、リーダーの人選、グループ分けなどなど。いろいろと決めることもあり、長時間にわたりました。「新幹線の時間に間に合わない」と途中退席する師弟会もいました。振り返ったらそれだけの長い時間が経っていました。みんなの熱を感じました。
リーフレット・チケット・受け付けフォームを担当することになりました
私は倉吉師弟会をひとつのグループとする担当グループのリーダーになりました。私のグループは講演会のリーフレットの作成、チケットの作成、お申し込み受け付けフォームの作成、運用を担当することになりました。
私たちのグループは担当する部門の特徴もあり、他のグループよりも早く実働していくことになります。リーフレットやチケット、お申し込み受け付けフォームなどは講演会自体の告知の際に必要となるものですから、皆さまに告知する以前に完成しておかなくてはいけません。そして諸々が完成した後も講演会当日までお申し込みの状況を把握して対応しなければいけません。
私の担当グループは早期から長期にわたり運営に関わってもらうことになります。その旨をグループの皆さまお伝えし、了承いただきました。
みなさまのお伝えしていく方法案
講演会に限らずですが一番肝心なことは多くの方にご参加いただくことです。私たちもできるだけ多くの方に会場にお越しいただきたいと願っています。そのためには多くの方に講演会自体を知っていただかなくてはいけません。どのようにしたらより多くの方に講演会の存在を知っていただけるのか?いろいろと意見を交換しました。
「講演会の存在を知らなかったので参加することができなかった!」「お伝えできていなかった」ということがないようにできうる限り多くの方に知っていただくようにSNSなどインターネットを活用するだけではなく、直接お会いできる方にはお会いしてお伝えしていきましょうとなりました。
まとめ
講演会の開催に向けて本格的に動き出しました。考えていくといろいろと準備しなければいけないことが想定するだけでもたくさんありました。ひとりの力ではなく愛光流認可指導室・師弟会の力を結集すると目的でもあります講演会にお越しになられたみなさまが「楽しい」と思って下さる講演会ができるのではないかと思っています。


日本全国あちこちで活動しています愛光流認可指導室・師弟会です。一堂に会して話し合うこともありますが、オンラインでは日夜ミーティングを重ねて、お越しいただいた皆さまに「来てよかった」と思っていただける講演会ができるよう意見を交わしています。

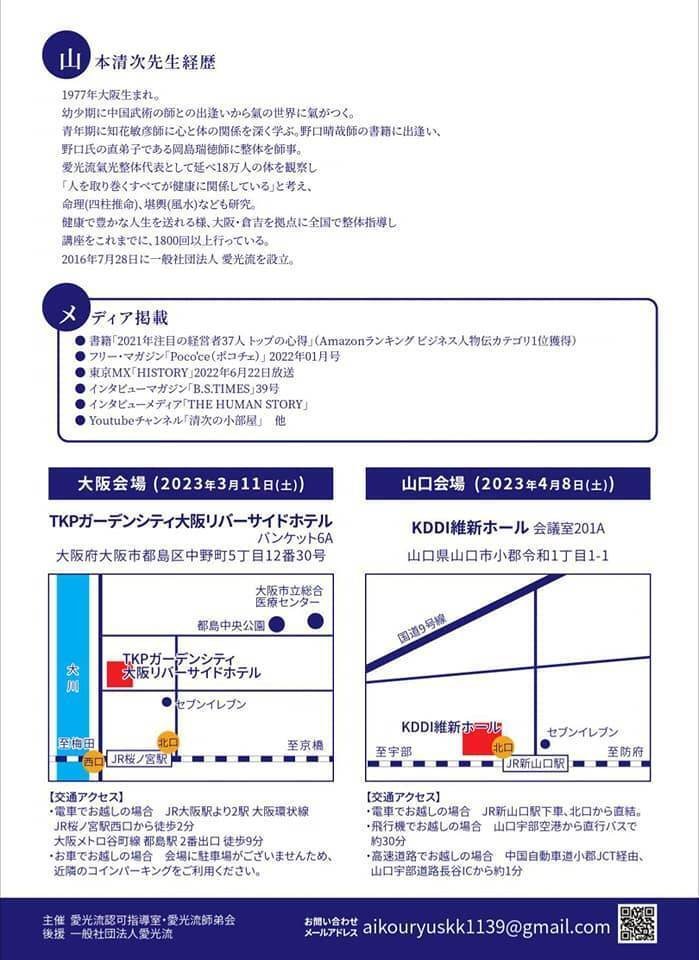
これは私たち弟子が師匠の出版記念講演会を開きたい!と願い、模索していく物語です。
これからも講演会開催までの間、更新して行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
いいなと思ったら応援しよう!

