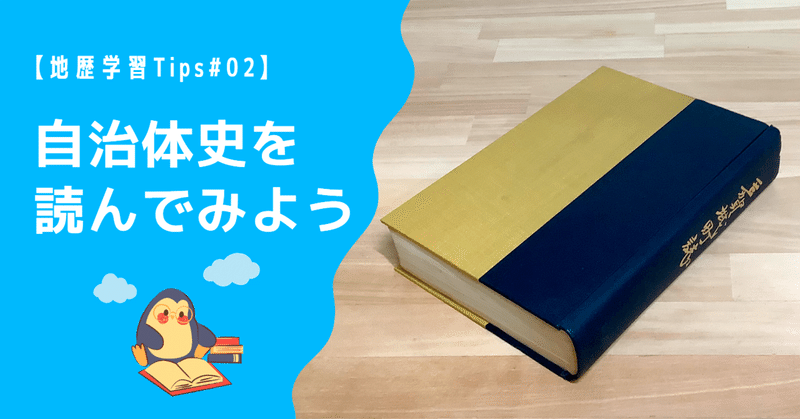
【地歴学習Tips#02】 自治体史を読んでみよう
町史や市史を読んでみよう
住んでいる自治体に『〇〇町史』や『〇〇市史』という本があることをご存知ですか? これを自治体史と言い、地方自治体がその自治体の歴史を編纂したもので、都道府県史・市町村史などがあります。自治体における古代史から近代史、天災の記録、寺社仏閣、文化財、産業などを詳細にまとめ、何巻かに分けて刊行されています。巻末に祭りや方言、資料集などを掲載しているものもあります。
もし刊行されていれば地元の書店や役所で販売されますが、内容が豊富で分厚く高価なため、市・町立図書館でも読めるようになっています。
自治体史のでき方
1989年に全国に市町村制が施行され、まず1901年に大阪市史、翌年に東京市史稿の編さんが始まりました。
自治体史が編さんされるタイミングは、村が合併して町になったり市政施行の時などが多く、それ以前の行政区のあり様を記録して残そうという意図が含まれます。区切りの良い〇〇周年事業として計画されて、編さんをアップデートする場合もあります。
自治体史を作る際には「編さん委員会」や「編さん室」が編成されます。委員会は首長をはじめとして役場職員、郷土史家、歴史学者などで構成されます。何年、と目標が決められ数年かけて編さんしていきます。
自治体史のすごさ・面白さ
大まかな歴史は風土記などにももとづいていますが、地域の蔵などから出てくる数多くの歴史・文化・自然資料や碑などは記録され、現地で伝承者などに聞き取り調査されて、最終的に掲載するかどうか判断されます。行政記録が公文書として残されて整理されて掲載される項目もあります。
編さん後は編さん室が残ることはほとんどありません。しかし自治体史をもとにして「私たちの〇〇町」などといったタイトルで、地元の歴史を知るために学校用の教材が作られることがあります。
国立国会図書館 NDLオンライン でも調べられます
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【行政Tips#02】成長に合わせた学生用の副教材を
行政側からすれば地元をよく知って将来にむけて活動してもらうためにも、誇りを持って成長してもらいたいという目的で自治体史をもとにしてわかりやすい学生用の教材を作成するのは有意義だと思います。
副教材は小学生・中学生のどちらかだけでなく、成長に合わせた編集が必要だと思います。またそれをもとに地元の地歴を歩いて確かめる機会を作る取り組みがあればと思います。
東京都では高校生用に2012年『江戸から東京へ』という教材が刊行され配布されています。高校では在住する地歴と、進学や仕事で関わる可能性のある首都や政令指定都市などの地歴を学ぶ機会があれば、将来への不安も取り除けるのではないかと思います。
【行政Tips#02】
自治体史をもとに、成長に合わせた学生用の副教材を
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
