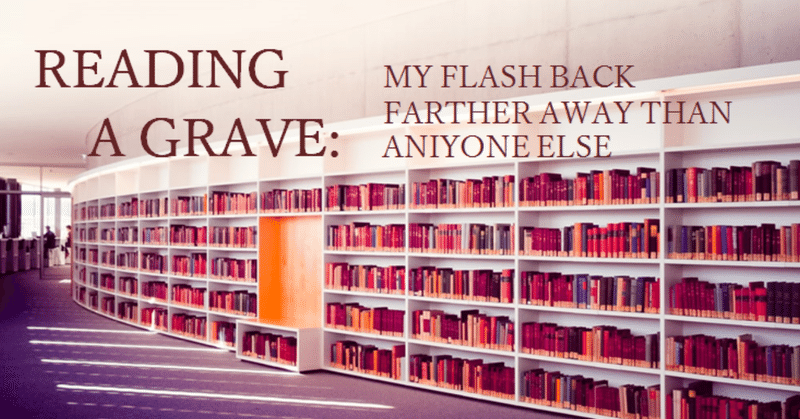
死人めくり
図書室の空気は重いと人は言う。それは周囲の本たちが否応なく死を意識させるからか、来客が皆等しく人の死に接しているからか。私は違う。私は本が好きで、この図書室という空間を愛している。そんな自分がマイノリティであることは、もちろんわかっている。中学の休み時間、祖父の本を読む私は明らかに浮いていた。でも、その時の自分を否定しなかったからこそ、私は今、この職に就いている。
■■■
「九相図をご存知ですか」
口の重い来客だった。四十頃の女性。結婚指輪。暗い表情。デスク上の本の由来は、父親か夫か。
「死後、人が綴じられる過程を九段階に分けて描いた絵画です。膨張し、崩れ、体液が文字に皮膚が頁に骨が表紙になり、変色し収縮し、纏まり綴じられる。人は死ねば本になる。それは残酷な理ですが、とても優しくもあります。そこに記されたお話を読むことで私たちは故人と再会できるのですから。もちろん、知りたくもないことを知ってしまうこともある。最近はそれを嫌い、蔵葬ではなく焚葬を選ぶ人も増えています」
それでも、遺された者はやはり読んでしまうのだ。愛する人が、憎んだ人が、本心では何を思っていたのか。その人の物語の中で、自分はどんな役目を果たす登場人物だったのか。どうしても知りたい、どうしても読みたい。その衝動を我慢できる人は少なく、そして実際に読んでショックを受ける人も少なくはない。
「私たち死書は、あなた方が故人の本を正しく読み解く手伝いをする者です。誤字脱字に勘違い、それどころか意図的に誤読を誘う捻くれた故人の方もいらっしゃいます。主観で書かれた文章ですからね。どうしても……」
「違います」
初めて聞く彼女の声は、震えていた。
「夫の本は主観で書かれていないのです。自分の視点が一つもない。ずっと三人称で、屋根の上から私たちを見下ろして」
彼女は顔を上げ、私に問うた。
「私の夫は、神様だったのでしょうか?」
【続く】
