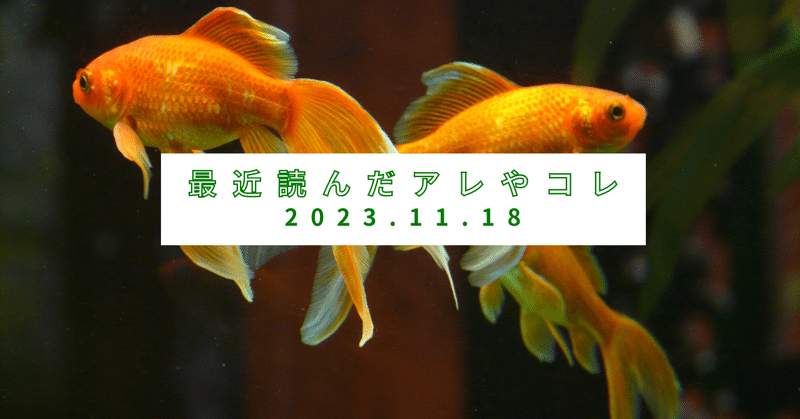
最近読んだアレやコレ(2023.11.18)
気温の変化に弱く、季節の変わり目には必ず風邪を引き、最低1日仕事を休みます。この「必ず」は誇張表現ではなく、本当に100%であり、職についてから1度の例外もなかったはず。タイムスケジュールも固定化されており、土日に体調の崩れを崩し、月曜日にやや低めのコンディションで仕事をし、その夜から翌朝のどこかで発熱して火曜日に休みをとり、水曜日には復調して職場に戻るという流れを、ほぼ毎回辿ります。ただ、今秋は2度やられました。大体、冬に切り変わる1回だけのことが多いため、これは珍しい。桜は狂い咲き、クワガタが秋に出て、私が2度風邪をひく。異常気候を測るバロメータとして今後もがんばっていきたいと思います。
■■■
時計館の殺人/綾辻行人
鎌倉、時計館。108の時計を収め、針のない時計塔の建つその館で、降霊会が開かれた。呼び出されたのは夭逝した主の娘。彼女の声はペテンか真実か……いずれにせよ過去の死は呼び起こされ、停まっていた時間が動き出す。それは、凄惨な連続殺人の開幕を意味していた。館シリーズ第5弾。
4度目の再読。邦ミステリを代表する傑作であり、その普遍的な価値は疑いようもないでしょう。しかし、それ以上に「館」という内輪の連続性・文脈上において、非常に大きな位置づけの作品であると思います。題材的には1度完結し終えたシリーズの「続き」を作るにあたり、新しいテーマや応用編に取り組むのではなく、「これまで書いた全てを、これまで書いた以上の完成度で新しく完成させる」という正面突破を試みるスピリッツは、創作者としてあまりにも格好がいい。思考と実践の繰り返し。「シリーズもの」というPDCAの理想形こそが本作であり……端的に表現するならば、ここまでの総決算ということになるでしょう。人の形を拡大し、大きな囲いを建てることで館は生まれる。時空や虚実すら隔ててしまう、巨大な人形の内に収まるものを探偵は”悪夢”と呼ぶ。「推理小説とは何だろう?」…… その単純な問いを真直ぐに見つめ、臆さず言葉に変えてゆく。綴られる謎と解決に微塵も逃げがなく、それを語る物語にも一切の安易が混じらない。これが傑作でなく、なんなのか。また、連続殺人終盤の真に迫った疲労と退廃は、身につまされるものがあり、読んでいて暗い喜びを覚えます。推理小説のテンプレートでありながら、どこかホラーの血脈も感じるのは、綾辻行人のオリジナルでしょうか。何度読んでもめちゃくちゃおもしろい。
(Amazonリンクは新装版になっていますが、私は旧版で読みました。旧版は上下分冊ではないため、感想文も1つにまとめています。)
黒猫館の殺人/綾辻行人
記憶を失ったその老人に残されたものは2つ。「鮎田冬馬」という名と、その筆名で記された手記。そこには黒猫館と呼ばれる屋敷で起きた殺人事件の顛末が記されていた。相談を持ち掛けられた推理作家・鹿谷門実は、隠された館を見つけ出し、”悪夢”を暴くことができるのか。館シリーズ第6弾。
再読。『時計館』の感想で書いた応用編に該当する作品。「枠組」で囲うことを描く上で、副作用として生じていた「隔てること」に焦点を当てている点や、館をその内に収められた”悪夢”からではなく、外側から解体してゆく点などに、シリーズ内での特殊な位置づけが強く表れていると思います。連続推理小説を続ける上で必然的に発生した支流を束ねた作品であり……ある種の脇道でもあるのですが、実は推理小説として最も地力が高いのはこの『黒猫館』ではないか、と読み返して思いました。初読が10年以上前なこともあり、インパクト抜群な大ネタしか記憶していなかったのですが、むしろその大ネタを成立させるための下ごしらえの部分に秀逸さがあるように思います。ただ伏線が多いというだけでなく、その仕込み方の堅実さと鮮やかさのバランスが絶妙で、真相に向かう動線も整然と揃えられており、丁寧です。着想と実践の両輪がいずれも頑丈であり、抜群の機能性によって語るべきものを語っています。また、おおいにその非人間性を発揮する鹿谷門実の存在感も個人的には癖(へき)でした。社会規範の外に立ち、正義や必要性ではなく、ただ戯れに館を開いては悪夢を啜る折り紙の悪魔。
無貌伝 ~綺譚会の惨劇~/望月守宮
探偵・御堂八雲が開催した豪華列車での談話会。「綺譚会」と銘打たれたその集まりの出席者は、いずれもが怪盗・無貌にまつわるエピソードを持っていた。語られる綺譚を全て聞き終えた時、探偵見習いはそこに解決編を付け加えることができるのか。〈無貌伝〉シリーズ第4巻にして、短編集。
探偵譚・怪盗譚のクライマックスを間近に控え、すいとお出しされた箸休め……では決してなく。シリーズ中でも随一のボリュームを割いて描かれるのは、探偵でも怪盗でもない、彼らの物語に行き遭い、巻き込まれた一般人たちのお話です。収められた8編の中にはヒトデナシが主でないものも含まれており、やはりこのシリーズの中心は、「無貌伝」と題される通りに「貌(かお)のない者」たちにあり、ヒトデナシという特殊設定自体はそれをより強く描くための補助輪に過ぎないのだなと再確認することができました。自らの貌を得るために、探偵は推理によって世界と向き合い、怪盗は他者からそれを奪い去る。では、いずれの力も持たないただのヒトが、貌のない自分と向き合わざるをえない状況に陥った時、何が起こるのか? 救いなきフリークアウトや、扉を打ち壊すカタストロフィ……そして、まだ見ぬ「楽園」。どこか哀しく、そして不吉な8編を読み通した時、それに対する解答がきっぱりと示されます。そのミッシングリンクが示すものは、本作全体のミステリとしての大ネタでもあり、探偵見習いが挑むべき次の命題でもあるでしょう。短編単位で語るなら「末期の酒」がスリリングで好きです。あと表紙の猫が絶妙にかわいくなくて、好きです。
結界師(1~35巻)/田辺イエロウ
烏森の城は妖を呼び寄せ、その力を増幅させる。家が滅び、かつての城が学校に変わっても、その土地の特性は変わっていなかった。一方、妖を滅する技術体系も「結界術」として2つの家に引き継がれていた……。夜の学校を舞台にして、2人の学生結界師が繰り広げる知恵と工夫の攻防戦。
体調不良時に、まとめて再読。少年漫画にあるまじき「渋さ」がとても好きな作品であり……読み返して、よりその印象を深めました。装備と環境を固定した上で、手を変え品を変え新たなシチュエーションを繰り出してくるのは、コンセプト重視のパズルゲームを攻略してゆくかのような趣があります。また、最終決戦において一切戦闘に参加しない主人公、主人公の兄と同調するように強者としての格が剥げてゆく組織「裏会」、スケールが矮小に縮まってゆく黒幕の等身大の真意と、少年漫画的な盛り上がりの全てに逆風を吹かせるような「渋さ」はやはりオンリーワンの魅力を持っていますし、何よりそれらの展開がただの奇の衒いではなく、「結界」という題材への真摯さから生まれているのが素晴らしい。役割に殉ずる暗愚な安堵になびいてゆくドラマや、烏森が迎えるビターな結末、そしてヒトを越えた神の在り様や、全てが思い通りになる世界すらもが、システマティックな技術体系として解体されてゆく無常……大きく逸脱することはあれど、決して破られることない檻の中に我々はいる。それを諦念ではなく「世界を恨むな」と結ぶからこそ、この物語は『結界師』なのだと思います。また、抑制を効かせて淡々と描写することで、異物感を強く引き立たせている悪人たちの造詣も非常に好み。中でも松戸さんは私のベストフィクション悪人の1人です。
