
ΠΡΟΔΟΣΙΑ No.13 車窓より
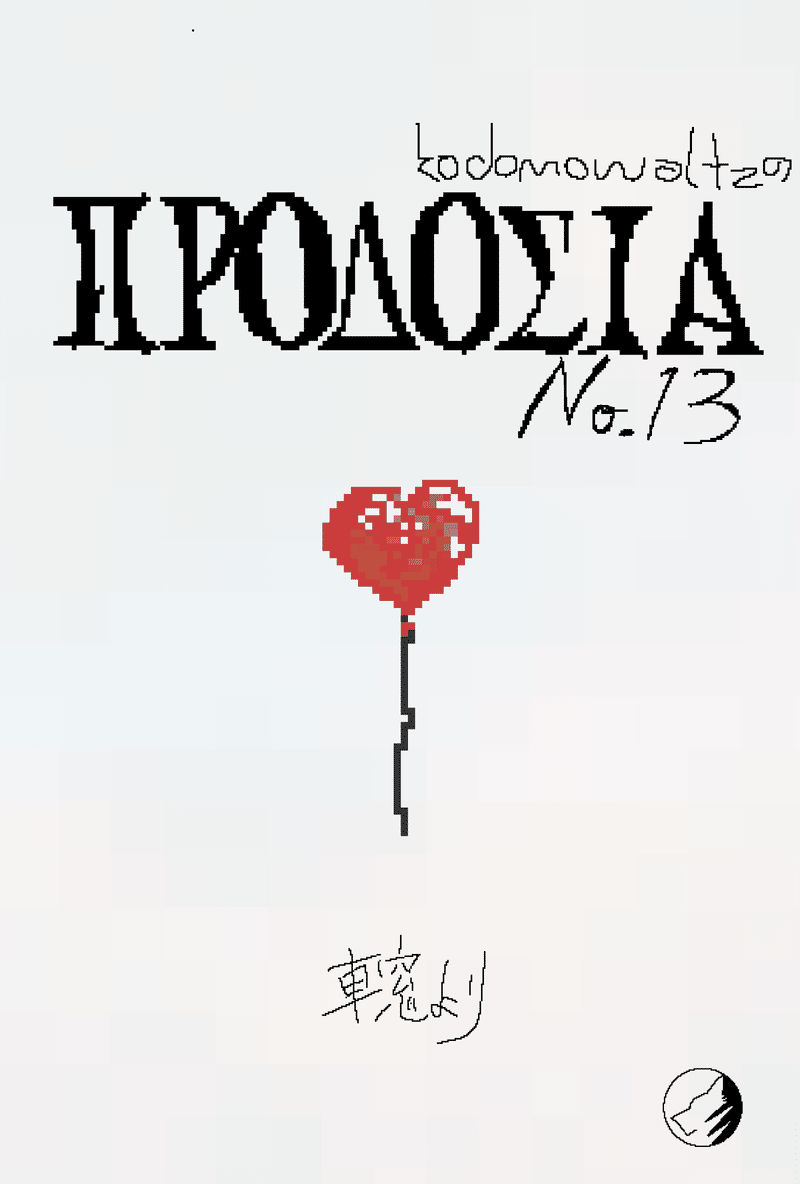
東京へ向かう電車の中にて。目前の小さな荷物置きにインスタントカメラと本を積み、場違いなグミの袋ととおにぎりを広げ、僕の目は車窓の外と本とを往復している。
片耳には椎名林檎の「モルヒネ」を再生しているイヤホン。手元にはジッドの「地の糧」。度々車窓の外へ意識を飛ばすと田舎の風景の中に確かに荒廃感と最新感を感じる景色が広がる。
今、僕は高校最後の一大イベントのような感覚で全国大会へ向かっている。
音編集で手伝った班が全国大会へ出場するということで、その付き添いも兼ねてやって来た。
勉強道具を持ってきたので東京へ着くまでは勉強しようとしていたが、下を長時間向いているとすぐ酔ってしまうので、手持ち無沙汰に外を見たり本を読んだりする。消毒された布の匂いがするため、なんだか保健室や病院の待合室にいるみたいな感覚。
特急列車に乗るというのは今日が人生で三回目だ。
車窓から眺める景色ほど贅沢なものは無い。今日の様な晴れて澄み渡る空気を感じられる日においては尚更だ。
僕は車でドライブに行く時など、窓の外に映る景色と自分の中の空想とを重ねて、そこに住む人の暮らしや考え方を想像してみる。丁度このエッセイでも以前書いたのではないだろうか?(臭いテディベアのはなし)
向こうの山の上にある大企業の社員寮、誰かが大事に育てている緑色の田んぼ、木漏れ日の中の森の奥深く、トタン屋根の安そうな空き家。そこに住む人や動物を想像する。
今僕が聴いているヨルシカの「第一夜」をその人が聴いたらどう感じるのだろうか、とか、駅前のロータリーに泊まっている車の中にいる人と、さっき想像した人との間に希薄な繋がりを見出してみたり、とか。静かな丘の上の赤い屋根の別荘らしい建物に住む作家の書いた小説のキャラクターとか。そうした想像の中にこそ、全てのクリエイティビティは種を宿すのでは無いか、というようなことを最近よく考える。
この電車に乗っている、全く知らない誰かの人生を想像する。いつしかその想像は現実と溶け合って、僕の目の前に突然現れることを夢見る。
気が付くと、すぐ横の山の影から、とても大きな入道雲が伸びている。空の青は少し薄い色をしていて、景色は開けてきた。
日常生活の中で僕が蓄えてきたどんな知見だって、想像力の前では無力に値する。そうして揃えてきた僕の心の中の書物が、このまま順当に大人になっていくうちに埃をかぶって行って、人並みの生活を送るようになるのなら、僕の書庫の本は余すことなく焼き尽くされる気がする。無駄になる、ということほど悲惨で不幸なことは無い。
日々覚えていかなきゃならないことばかりで忙しいが故に、忘れていくことがとんでもなく多いということさえ忘れてしまっている。
忘れたくないことばかりだ。
電車は緑の茂る山の中へと突入した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
