
2022年BESTアルバム50
1. Rival Consoles / Now Is

イギリスはロンドンのサウンドプロデューサーによる作品。情景的なメロディを重視したアンビエントテクノだろうか。寄せては返す波のような、止むことのない大粒の雨のような、またそれらに侵食される砂岩のような光景。年齢は37歳とベテランというわけではないが既に確固たる作風を確立させていると言えるだろう。本作は近年の社会情勢等を反映して作られているらしく、例えばコロナ禍における孤独感などが発想の根底にあるらしいがそのへんは聴いている限りではちょっとよく分からない。この手の電子音楽は作者のパーソナルな部分が直接的に表現として結実されているというのもあるのだろう、第三者がその意図を判別するのはやはり難しい。とは言えそれぞれのトラックの完成度は凄まじいものがあり、聴けば聴くほどその音楽世界に深く入り込むのは必至であろう。(山根)
2 . Vladislav Delay / Isoviha

フィンランドの電子音楽家の作品。昨年は前作「Rakka Ⅱ」を取り上げたが本作も基本的な路線は同じ。リズム、メロディ、ノイズが四方八方から襲ってくる言わば電子ブラックメタルだ。強いて言えば前作ではまだそれぞれのパートが独立して鳴らされていた(ロックミュージック的であった)が本作はそれらがより一体化していてインダストリアル・アンビエント色を増している。タイトルは18世紀の大北方戦争時にロシア帝国が一時的にフィンランドを占領した時期から取られており、こちらもまた現在の世相が反映されていると言える。そういう背景を知ると戦場に鳴りわたる銃声にも聞こえ、果てしなく続く泥濘の光景が浮かび上がってくる。
3. Kangding Ray / ULTRACHROMA

フランスに生まれ、現在はベルリンにて活動するサウンドプロデューサーの作品。これまでの作品はかなりインダストリアル的なヘヴィさに重点が置かれていたが、本作はそれに比べるとより(ジャケットからもわかるように)色彩豊かで正統なクラブミュージックとして作られている感がある。硬質さという「質感」から触覚を介さぬ「光」へと移ろいゆく中で野太いキック音のみが物質的存在を繋ぎ止めているかのような。しかしながら後半に進むにつれて次第に低音が中心を占めるようになり、言うならばトリップ状態からシラフに着地かのするような感覚を味わえる。
4. John Roberts / Wrecked Exotic

米国出身のJohn Robertsはプロデューサー、DJ、ピアノやバイオリンの演奏家など音楽家として幅広く活動しているが、それ以外にも写真や映画、その他多用なメディア媒体で作品を発表するアーティストとしても知られている。本作においても彼自身が演奏するピアノが中心に置かれ、そこに民族音楽的パーカッションや電子ノイズ、そして環境音などが配置されており、音と音の「間」を重視した作曲となっている。限りなく現代音楽に接近したハウスミュージックと言えるかもしれない。
5 . Dubokaj & Lee "Scratch" Perry / Daydreamflix

不思議なことに日本では(海外でも)ほとんど誰も言及していないアルバム。スイスのダブエンジニアであるDubokajと言わずと知れたダブのオリジネーターであるLee "Scratch" Perryとの合作(?)。2017年にスイスの山奥で行われたDubokajとUpsettersのセッションをもとに21年にかけてミキシングなどを行ったものらしい。リー・スクラッチ・ペリーは2021年に亡くなっているのでほぼ遺作と言ってもいい作品かもしれない。作風としては古典的なダブレゲエとアンビエントダブ・エレクトロニカの折衷といった感じでもちろんクオリティは非常に高い。これだけ話題になりそうな要素がある作品なのに音楽メディアはもちろんSNSでもほとんど誰も言及しないのは何故なのだろう?事情を知ってる方がいたら教えてください。
6. Carmen Villain / Only Love From Now On

ノルウェー系メキシコ人のサウンドプロデューサーCarmen Villainは音楽家として以外にもファッションモデルとしての顔も持つ。本作はジョン・ハッセルによって提唱されたいわゆる「第四世界」的なジャズを基調としたダブ・アンビエントであり、そうした系統の音楽に興味がある人は絶対に聴いた方がいい。
7. Michel Banabila / Monochromes

80年代から活動するオランダの電子音楽家による作品。ヘヴィなドローンからコラージュを多用した実験音楽までが収録されている。ノイズも多用されるがアンビエントに仕上げられているのでおおよそ耳触りは良い。この作品もまた「第四世界」的な発想を下敷きにしているようだ。
8. Caterina Barbieri / Spirit Exit

現代の電子音楽シーンを語る上で絶対に外せない一人であろう、カテリーナ・バルビエリ。5枚目となる本作は昨今の混沌とする世界、終末論、ポストヒューマン的な思想に触発され作られたのだそうだ。だがにも関わらず本作に収録されている楽曲は過去の作品に比べてメロディもはっきりしていて構築的であり、良くも悪くも「普通の音楽」という感じである。正直なところ初視聴時にはそうした点から今一つ物足りなさを感じたりもした。ただよくよく聴いてみるとこれまでの作品が「音」そのものに鮮烈さが内包されていたのに対し今作では(ともすれば凡庸ですらある)メロディを配置し反復させることによってそこに特異性を生み出そうという壮大な試みをしているのかもしれないと、そんな気にさせられる。哲学的な、精神の(故に表面的には必ずしもそれを感じさせない)ミニマル・ミュージックと言えるのではないだろうか。
9. Lamb of God / Omens

NWOAHMのオリジネーターとも言われるLamb of God。本作でも畝るようなグルーヴメタルを展開している。ビートダウンを取り入れたりとハードコア的な曲展開でありながらギターソロではブルース色を垣間見せたりもする。そういった器用さを持ちながらもそれを前面に出さずあくまでパワーと凶暴性でごり押すのが良い。結成から20年以上ともはやベテランの粋に達しつつあるバンドだが未だにシーンの最前線に立っていることがわかる。
10. Gaika / War Island OST

英ヒップホップクルーのボーカリストとしてそのキャリアを開始したGAIKA。現在は実験音楽から音楽以外の分野まで横断的な活動を展開している。本作はGAIKAによる同タイトルのインスタレーションのためのサウンドトラックとして制作されたものである。本作は過去作以上に低音部が心地よくて良い感じである。
11. Deliluh / Fault Lines

カナダのトロントにて結成され、現在は欧州を中心に活動するポスト・パンク/アートロックバンドによる作品。スポークンワード的な1曲目に始まり、ローファイなノイズロック、no waveを聴かせる。ところどころにジャズっぽい要素もある。カナダ出身ということもあってかやはりアメリカーナな音。70年代後半から90年代初頭くらいのジャンクサウンドが好きな人にはおすすめできる。
12. Prurient / Creationist

Dominick Fernowのプロジェクトの一つであるPrurient。昨年は確かVatican Shadow名義の作品がランクインしたはずだ。Vatican Shadowではやや実験的な作風が採られているがPrurient名義ではよりストレートなノイズ、インダストリアルサウンドが展開される。本作はPrurient名義の作品としてはわかりやすいパワエレというよりはドローンやダークアンビエントの色も強く出ているのでドゥーム・スラッジ系が好きな人にもおすすめ。
13. Nadja / Labyrinthine

カナダのドローンメタルデュオによる作品。本作はこれまでの彼らの作品の中ではややエクストリーム・メタル色が強い。ゲストボーカルもOLD、Khanate、Gnawなど数々のバンドで活躍したAlan DubinやFull of HellのDylan Walkerと非常に豪華で彼らからの影響も感じさせる。
14 . Croatian Amor / Remember Rainbow Bridge

Croatian Amorはデンマークの音楽家Loke Rahbekによるプロジェクトの一つである。本作はコンセプトとしては少年が大人になっていく、その成長の過程を題材にしていると言うらしいが、うーん言われればそんな感じもしなくもないが、どうだろう?ただ環境音やビート、電子音などが「配置」されたような楽曲群は家庭用のビデオフィルムを編集したような感覚があり、そういう意味において「一人の人間の成長記録」のメタファーなのかもしれない。本作には軽快なビートのアップテンポな曲からややダークアンビエントのような曲までが収録されているが、これも人生にはさまざまな局面が存在するということなのだろう。
15. Whatever The Weather / Whatever The Weather

Whatever The WeatherはLoraine Jamesの別名義プロジェクトである。Loraine James名義ではブレイクビーツやグリッチなどを用いた作風で知られるが、本作はそれに比べると若干アンビエント的な要素が強くなっている。ジャケットからも伺い知れるように原色というよりは淡色っぽいサウンド。
16. Huerco S. / Plonk

昨年度はPendant名義での作品がランクインしたHuerco S.。Huerco S.というと従来はハウス的な4つ打ちを特徴としていたのであるが、本作ではリズムがやや複雑化しハウス・テクノの文脈から逸脱した楽曲が多く見られるようになった。また同じく彼の特色であったダブ要素も希薄化し雅楽やアジアの民族音楽の要素が前景化したようなIDMといった趣きとなっている。Pendantを通過することで生じた変化なのかもしれない。
17. Oval / Ovidono

90年代初頭から活動するOvalはドイツにて電子音楽バンドとして出発し、現在はマーカス・ポップのソロ・プロジェクトとして活動している。本作は帝政ローマ時代の詩人オウィディウスと小野小町からインスパイアされたらしく、それぞれの詩を引用し朗読するポエトリーリーディングアルバムでもある。このうち小野小町を朗読するのはマーカスとともにSoというユニットで活動する豊田恵里子。しかしながらそれら朗読はグリッチやリバーブなどの処理がかけられ、「音」と「言語」の間をどちらともつかずに彷徨っている。電子音やノイズ、ピアノなどもふんだんに使われているがそれらはあくまでも伴奏といった感じであり、あくまでも声(ボーカル)が主体となった作品。まさに幽霊の声やねこれは。ええ意味で。
18. Not Waving / How To Leave Your Body

Not Wavingとはロンドンを拠点とするALESSIO NATALIZIAによるソロ・プロジェクトである。バックボーンとしてはEBM(エレクトロニックボディミュージック)があるようだが、一聴したところ特段そういう曲調ではない。いずれもややポップさすら感じさせる楽曲が揃っているがそれぞれがバラエティに富んでいてその脈絡のなさにどことなく不穏さを感じさせる。
19. James K / Random Girl

ニューヨークを拠点に活動する電子音楽家の作品。昔Earthというバンドが自分たちの音楽性をパワーアンビエントと称したことがあるが、本作はまさに「パワーアンビエント」と形容すべきだろう。どことなく宅録っぽいチープさが漂っているのもまたコレはこれで良い。CoilのDrew McDowallが参加している曲もあるが確かに両者は音楽性が通じるところがある。
20. Alex Banks / Projections

DJ、サウンドデザイナーとして活動するAlex Banks―。ミュージシャンとして活動する傍ら、映画やテレビ、さまざまな広告などに使用される音楽も手掛ている。本作はイギリスはブライトンにある彼の個人スタジオにて2021年初頭から制作されたものである。フローティングポインツを想起させるようなサイケデリックでメロウさを伴ったテクノ。
21. HEALTH / DISCO4 :: PART II

カリフォルニア出身のインダストリアル・ノイズロックバンドによるコラボアルバム。前作「DISCO4」のパート2という位置づけ。ゲストミュージシャンはNine Inch Nails、先にも紹介したLamb of God、Backxwash、HO99O9 、Street Sectsなど非常に豪華で新旧インダストリアル勢が集結している。音楽的にもいわゆる懐古趣味に走るのではなく現代的な形でのインダストリアル・ロック・メタルを模索している感じ。
22. Worriedaboutsatan / Bloodsport

Worriedaboutsatanはイギリスにて元々ポストロックバンドとして活動していたが現在ではギャビン・ミラーによるソロ・プロジェクトとなっている。ドラムンベースからドローンまで幅広い要素を持ったIDM。筆者は彼(ら)の過去作を聴いたことがないのでそれとの比較はできないが、ただやはりバックボーンにあるのはヘヴィメタルなのではないだろうか。全体を通して重々しいサウンドに貫かれている。
23. Minami Deutsch / Fortune Goodies

日本のクラウトロックバンドによる作品。ボーカルは現在ベルリンに居住しておりそれ以外のメンバーがいる東京と二拠点で活動しているらしい。執拗かつミニマルな楽器隊の反復にリズミカルで小洒落た詩や具体音のサンプルなどが乗るような感じ。70’sっぽい懐かしさもあります。
24. Roméo Poirier / Living Room

フランスのアンビエント作家による作品。彼もまた第四世界系として知られている。彼の作風と特徴としては他の第四世界系アーティストと比較するとやや都会的なニュアンスが強いということ。そのためその世界に身一つで没入するというよりはリゾート観光的な感触があったりもする(前作や前前作のジャケットもまさにそういうイメージを表している)。またそうした模倣的なコマーシャリズムにはヴェイパーウェイヴ的な懐かしさも内包されているといえるだろう。
25. Pablo's Eye / A Mountain Is An Idea

Pablo's Eyeとは創設者であるAxel Libertを中心に流動的なメンバーで活動するベルギーのバンド(本人らはバンドと呼ばれることを否定しているらしい)。80年代末から活動をしているが90年代の末から活動を停止しており、2018年ころ再始動したようだ。本作はそんなバンドの22年ぶりとなるアルバム。当初はトリップホップ系の音楽をやっていたそうだが本作に関しては全体としてはドローン、ダークアンビエントに近く、またサウンドコラージュ、ポエトリーリーディング、クラシカルなどの要素も併せ持っている。
26. SHXCXCHCXSH / Kongestion

SHXCXCHCXSHはスウェーデンの音楽ユニットだ。結成以来メンバーの素顔はおろか名前や年齢性別など何もかもが不明の匿名ユニットとして活動している。作風はインダストリアル色の強いダブテクノ。非常に重々しく歪んだ音像だが不思議と耳障りさはなく聴きやすい。
27. Cremation Lily / Dreams Drenched in Static

Cremation LilyことZen Zsigoはノイズアーティストである。これまでパワーエレクトロニクス系の作品を発表してきた彼だが、本作においてはそうした従来の路線にエモラップやブラックメタルの要素をプラスしている。また曲構成としても静的なパートが増えている。要するに音楽的な引き出しが多くなったということなのだがこれが今後吉と出るか凶と出るか。
28. Hainbach / Tagwerk

Hainbachはベルリンの電子音楽作家。YouTuberとしても活動しており実験音楽の作成テクニックを解説した動画でドイツでは高い知名度を得るに至ったらしい。特に近年は非常に多作で知られ2022、21年にはそれぞれ3枚のアルバムを発表している。タイトルのTagwerkとはドイツを中心に古くに用いられていた面積を表す単位であり、一日に耕作可能な田畑の広さを基準としているそうだ。そういったこともあるのか本作もレトロかつ必要最小限の音数を用いたミニマルなアンビエントミュージックとなっている。
29. Slikback / K E K K A N

ケニアのプロデューサーによる作品。こちらも非常に多作で知られる人物であり、2022年だけでもいくつものアルバム、EPを発表しており、しかもそのどれもが高クオリティでもある。本作はジャンルとしてはインダストリアルテクノに分類されるのだろうが到底それに留まらない広がりがあり、グリッチ、ヒップホップ、コラージュ、ドローンなど様々な要素がdeconstruct(脱構築)されることにより楽曲として形成されている。
30. Kardashev / Liminal Rite

アメリカのアトモスフェリックデスメタルバンドによる作品。アトモスフェアを重視したデスメタルバンドとしてはUlcerateなどが有名だがKardashevの場合はよりポストロックやシューゲイザーに接近している。またクリーンパートを重視したスタイルはOpethなどとも共通しているがこちらはどちらかというとデスコアやブルデスをバックボーンとしているという違いがある。本作はLost manという年老いた男が、認知症やそこからくるせん妄によってその自己を解体しつつ死の足音を聴く様を描いた1時間近いコンセプトアルバムであり、こうした創作スタイルは往年のプログレッシヴロック・メタルを想起させたりもする。とにかく暗くて救いのない雰囲気の作品。
31. Author & Punisher / KRÜLLER

現役の工業エンジニアでもあるトリスタン・ショーンによるソロ・プロジェクト、Author & Punisher。その作風はインダストリアルとドゥーム、スラッジ、ドローンメタル、さらにはダブステップを融合したもの。本作では従来からの無機質性は継続しつつ90年代のグランジやオルタナティブ・ロック、トリップホップなどの燻ったダウナーな側面が顔を覗かせている。それはゲストミュージシャンとして参加しているTOOLのメンバーやポーティスヘッドのカバーなどにも現れているだろう。またアルバム全編を通してAs I Lay DyingのギタリストであるPhil Sgrossoも参加しており、トリスタン・ショーンによるボーカルも「歌唱」的な要素が増していることからもよりロック的な方向に接近していることが伺える。
32. Vein.fm / This World Is Going To Ruin You

米国はボストン出身のニューメタルコアバンドによる作品。ニューメタルコアとはニューメタルにグラインドコアやハードコア・パンクを融合させたような音楽で数年前よりアメリカ中心にやや流行しているようだ。Vein.fmは以前はVeinというバンド名で活動しており、かねてより凶悪なサウンドが持ち味であったが本作ではそこにエモやポストハードコアの要素が入り若干ながら人の血が通ったような作風となっている。そこは賛否両論かもしれませんね。本作ではターンテーブリストが正式にメンバーに加わったわけではあるが前述の通り前作よりもむしろ機械的な要素は減じており、また同時に本作を以て脱退してしまったようだ。
33. Björk / Fossora

世界で最も有名なエレクトロニカ系アーティストかもしれないBjörkの、10枚目に当たる作品。2018年に母親を喪ったことを始めとして彼女自身の人生の転機が反映された作品となっているらしい。本作はこれまで同様にクラシカルなアヴァン・ポップの要素を持ちながらそこにガバの要素が持ち込まれている。これは共同プロデュースを手掛けたインドネシアのガバ・モーダス・オペランディによるものだそうだ。
34. Sofie Birch / Holotropica

Sofie Birchはデンマークにて主にモジュラーシンセを使用した作品を発表している電子音楽作家である。本作は不協和音等も多用した実験的な作風でありながら根本的にはどこかポップな要素があり意外と聴きやすかったりもする。こちらも所謂第四世界系に含めても良いかもしれない。
35. Brian Eno / FOREVERANDEVERNOMORE

グラムロックから出発しアンビエントミュージックの大家となったブライアン・イーノの作品。アンビエントミュージックでありつつもレオ・エイブラハムズのギターを前面に出し、イーノ自身の弟や姪などがボーカルで参加していることからもロック、ポップス的な側面を持っている。しかしながら軽快さや明るさはなく雰囲気はむしろ陰鬱。本作は昨今の気候変動などに対する危機感から制作されたアルバムであり、それがロック・ポップスという「何かを物語る音楽」というジャンルへの接近を選択させたのだろう。
36. Kaitlyn Aurelia Smith / Let's Turn It Into Sound

Kaitlyn Aurelia Smithは幼少期からクラシック音楽を学びバークリー音楽大学に進学、スティーブ・ライヒを私淑するというサウンドクリエイターである。初期にはクラシックギターやピアノを用いて作曲を行っていたが現在ではモジュラーシンセを主に使用した楽曲を発表している。と、このようなバイオグラフィーからはどうしても難解で衒学的な作風をイメージしてしまいがちであるが、本作はあくまでも(もちろん多重録音やサウンドコラージュのような実験的側面はあるものの)ポップソングであり、かつダンサブルですらあるかもしれない。またどことなくヘンリー・カウなどカンタベリーロック系にも通じるものがありそういった音楽が好きな人にもおすすめできる。
37. Chat Pile / God's Country

米国はオクラホマ出身のノイズロック / スラッジメタルバンドによる第一作目となるフルアルバム作品。音楽性としてはToday Is the Day、Buzzov•en、Fudge TunnelなどのスラッジメタルバンドがBlack FlagやBig Black、Flipper、さらにはRudimentary Peniなどのスローなハードコアに若干先祖返りしたような趣を持ちつつ、90年代に流行したグランジやニューメタルなど、よりメジャーな音楽からの影響も語られている。バンドの出身地オクラホマは元々鉱山開発が盛んであり、バンド名のChat Pileとは「ボタ山」的な意味があるそうだ。また犯罪率なども非常に高い地域でもあるらしい。そのような環境下でたくさんのマリファナに囲まれて育ってきた彼等の音楽には、ジャケットの変電所が物語るようなボルテージ高い暴力性と悲嘆、脱力感が同居している。
38. KMRU / epoch

ケニアのサウンドプロデューサーによる作品。先に取り上げたSlikbackもそうだが近年の電子音楽界ではケニアが密かな発信地になりつつあるようだ。ただし本作はSlikbackの作風とは正反対のドローン・アンビエントを主軸としており、どことなく東洋的な侘び寂びの心を感じさせたりもする。
39. Rachika Nayar / Heaven Come Crashing

ブルックリン在住の作曲家、ギタリストによる作品。そういった経歴もあるのだろう、電子音なども多用されてはいるが楽曲の中心にあるのはやはりギターであり、フィードバックなどを多用したポストロック的な作風となっている。また彼女は2021年にデビューした後Loraine Jamesと知り合い交友を深めたらしく、そういった影響もあってかブレイクビーツやクラブミュージックなどの要素も散見される。アルバム通して多面的な要素を持ちつつもコンセプトの芯はぶれていない。
40. TENKA / HYDRATION

冥丁名義の作品で有名な広島出身のアンビエント作家の新名義による作品。本作は山林の中で生活を営む中で構想されたということ、また「水分補給」というタイトルからもわかるように水のせせらぎや風のざわめきなどがモチーフとなっているのであろう、具体音と電子音を細やかに組み合わせたフィールドレコーディングに近い感触の電子音楽となっている。
41. Backxwash / HIS HAPPINESS SHALL COME FIRST EVEN THOUGH WE ARE SUFFERING

Backxwashはザンビア出身、現在はカナダにて活動しているラッパーである。本作は基本的には2013年ころから勃興し始めたトラップメタルというジャンルにあたるのだろう。そこで展開されるトラックはヒップホップ、ヘヴィメタルの他にインダストリアルや宗教音楽、さらには古典的なポップソングなどを内包し、そこに力強いラップが重ねられる。リリックは彼女自身がこれまでの人生で体験した宗教的虐待やドラッグ依存などがテーマとなっており、それらを乗り越えるためのセラピーとして制作された側面があるそうだ。
42. Klein / Cave in the Wind

ナイジェリア出身、現在はロンドンにて活動をしているKlein。ジャネット・ジャクソンに憧れてキャリアをスタートさせた彼女の音楽性はサウンドコラージュとR&Bをバックボーンとしたダークアンビエント、ポストインダストリアルである。制作スタイルとしてAudacityという無料の音楽編集ソフトを用いることで知られており、その作品からは粗削りかつ大胆な独自性を感じ取ることができるだろう。本作は2022年におよそ50年ぶりに覆された「ロー対ウェイド判決」に関するニュース報道などの音声素材が用いられている。作者的にはおそらく怒っているであろうテーマ選定であり、実際の音像も不気味なダークアンビエントとなっているのではあるが…どこかシュルレアリスム絵画を見たときのような「ありもしない郷愁」のとでも表現するしかない感覚に襲われる。後半の短め(?)の2曲は比較的ストレートなインダストリアルミュージックでこれはこれで良い。
43. Ho99o9 / SKIN

Ho99o9はニュージャージー州で結成されたヒップホップユニットであり、後にブラックフラッグの元ドラマーが加入したことによりラップコアやメタルコア、デスインダストリアルなどより多様な音楽性を見せるようになりました。本作は2017年に発表された「United States of Horror」と比べますとハードコアパンク的な直線的なノリを捨て去ってはいないまでも、よりヘヴィさやカオティックなノイズに重点が置かれ、さらによりスローテンポな楽曲ないしパートが増加しています。コリィ・テイラーやソウル・ウィリアムズなど、ゲストもなかなかに豪華なアルバムです。
44. Moor Mother / Jazz Codes

Moor Motherはフィラデルフィアを中心に活動する実験音楽家、ラッパーである。30代半ばから本格的に音楽活動を始めたらしい彼女の音楽性はヒップホップを基調としつつもおよそそこには収まらぬユニークなものだ。本作の作風を一言で言うならば「ジャズホップ」ということになるのであろう。しかし実際にはそんな単純なカテゴライズを拒むかのように即興、コラージュ、さらにはポストロックやエレクトロニカのようなアトモスフィアまでが散りばめられ、さらにそこにMoor Motherのポエトリーラップが乗る。ブルース、ジャズ、R&B、ヒップホップ、そして電子音楽。そうした近代以降のアメリカ黒人音楽の歴史を概観した上でそれを彼女自身のカオティックな主体によってぶち撒けた、そんなようなアルバム。
45. Marina Herlop / Pripyat

Marina Herlopはバルセロナ在住のアーティストでありピアニスト。大学でクラシックを学んだという経歴らしい。本作はピアノと声楽を中心に構成され、南インドの民族音楽にインスパイアされたということもあり、ダンスミュージックとも現代音楽ともまた違った毛色を持つ。タイトルのPripyatはウクライナのチェルノブイリ原発に近い都市の名であり、原発事故後街全体が廃墟化したという経緯を持つ。恐らく本作に通底する非通俗的な躍動感は人間が放棄した土地で息を吹き返した野生、もしくはかつてそこで暮らしていた人々の残留思念(幽霊)の表象なのであろう。
46. deathcrash / Return

deathcrashはロンドンに拠点を置くスロウコアバンドである。本作「Return」は彼等の2作目のアルバムに当たる。2作目で「Return」とつくとなんとなくキラー・トマトが想起されるのは筆者だけだろうか。本作は全体としては90年代のCodeinやLowを想起させる懐メロ的なスロウコアなのではあるが、ところどころにドゥーム、スラッジメタルからの影響を感じさせるダークな要素がちらつき90年代より「ガチさ」が増しているように聴こえる。これはVenomの『Black Metal』というパーティロックの影響によってノルウェーやフィンランドでマジモンのブラックメタルが生み出されてしまったようなものかもしれない。
47. bonsai2004 / Sleep Installer
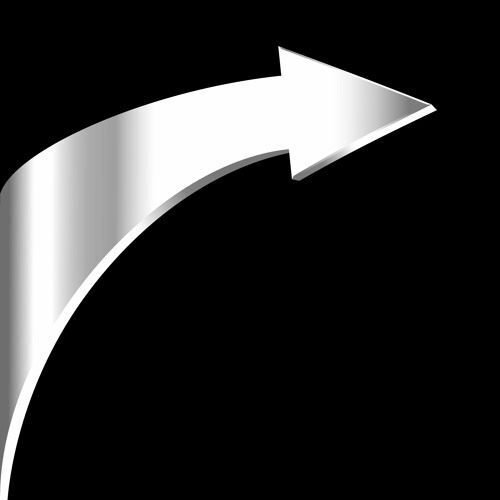
「2004年生まれの日本人」ということでつけられた名前がbonsai2004ということらしい。作風は深淵なドローンアンビエント。ドローンアンビエントはDTMerが誰しも一度は作ってみる、通る道ではあり、作者の年齢が若いということもあってそういう作品なのかと思いきや、本作は恐らくそうではなくかなりの音楽的な背景を持った人物が作っているということを伺わせる。敢えて言うならBruce Gilbertのソロ作に近い感じ。
48. Kelly Lee Owens / LP.8

Kelly Lee Owensはイギリスの音楽プロデューサー。元々エレクトロポップバンドのメンバーとしてその音楽キャリアをスタートさせたことからもわかるようにポップ・ミュージック的な方向から徐々に実験性の高い音楽性へと移行してきたという経緯がある。本作『LP.8』はスロッビング・グリッスルに触発されて制作が始まり、またエンジニアとしてハーシュノイズ等のシーンで活動するLasse Marhaugが参加していることからもかなりノイズ・インダストリアル色が強い内容となっている。しかし一方で彼女の元からの志向であるポップな要素が完全に消えたわけではないのでそれほどとっつきにくい感じというでもない。
49. Cult of Luna / The Long Road North

スウェーデンのポストメタルバンドの作品。バンドのボーカル兼ギタリストが故郷であるスウェーデン北部に戻り、そこの文化や風土を追体験することで着想を得た作品だそうだ。基本的には重々しいアトモススラッジにハードコア由来の咆哮が乗るスタイルなのだがところどころに北欧的な叙情性を覗かせる。一曲一曲はそれぞれ(アルバムタイトルの如く)長めでなのであるが曲の構成などかなり緻密に練り上げられていることもわかる。ただ非常によくできた作品ではあるのだが、個人的には同一の系譜にあるという前作のほうがもっと好きだったりもする。
50. house of care / Perila

ロシアのアンビエント作家による作品。昨年には前作『How Much Time it is Between You and Me?』を取り上げたが本作もまた良い。元々は150枚ほどの限定カセットテープとしてリリースされたもののようだ。ピアノとフィールドレコーディングっぽい音にところどころウィスパーボイスが乗る。癒し系のアンビエントだがどこか不穏さもあり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
