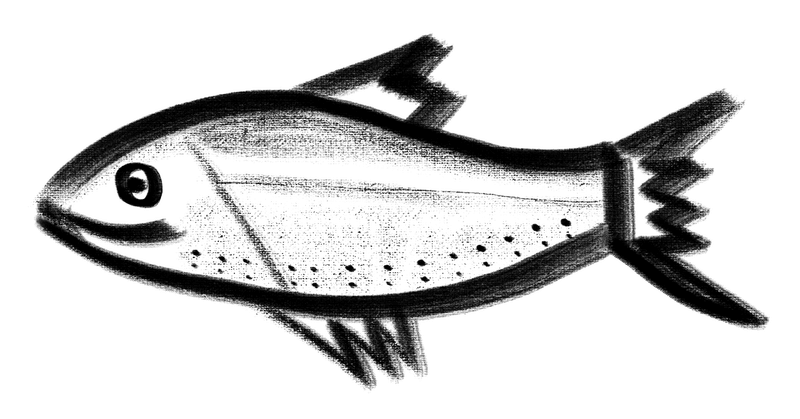
恩返しのはなし
魚心あれば水心とか申しますが、ご恩に報いたいと思うのは人も魚も変わらぬようでして 一席そのようなおはなしを。
むかしむかし。
在所のお堀近くの街にゴモチって男がいた。そいつは随分と不信心でやんちゃな輩で、人混みに紛れちゃスリをして、失敗して見つかりゃ喧嘩沙汰を起こした。警察のご厄介になったのも一度や二度じゃない。特に悪かったのは、大きな水害に見舞われた年のこと、街中水浸しの瓦礫まみれで大勢死人が出て、みんなして助け合わないことにゃどうもならん。それでもゴモチはその隙に不用心になった民家に忍び込み食い物やら金品やら、まぁ盗みをはたらいたりなどした。こういうしんどい時に人のつらみを踏みつける真似をするってえのは尾を引くもんで、いよいよ恨みを買って殺された。
さてそれでもこのゴモチ、生きてるうちにいっぺんだけ善行を働いたことがあった。
ちょうど先のはなしにあった水害の時期、水たまりに取り残された一匹の魚を助けたのである。
魚は増水に連れられてどこぞの水辺から飛ばされてきたようだった。今にも干上がりそうに背びれは空気へ出てしまい、小さな水たまりで藻掻いていた。ゴモチはそいつをみて、食うにはちいせえしと手ですくい上げ、逃げ足で鍛えられた疾さで急ぐと、近くの川にそいつを放してやったのだった。
そんなこんなで、大勢から恨まれて殴り倒されたゴモチだったが、今は川辺をずうっと歩いていた。魚を放した川辺じゃあない、死にかけた時に見る川の岸に来ている。だが死んだ後のことなんざゴモチの頭に無えもんだから自分が死の淵に来てるのにも気付かない。雲の中を歩くような山奥にも似た景色をながめ、はあ不思議なことになってんなとため息をつく。向こう岸は美しい花をつけた並木が川沿いにどこまでも続いている。
大きな川だ。澄み切っているのに水は底がわからず、空は白い霞に何層にも覆われ見通せず、向こう岸は遙か遠い。足元しかわからんようなこの岸から美しい向こうの岸へ渡りたいもんだ、と思った折
「お、橋がある」
白い景色の向こうにぼんやり、橋が架かってるのが見えた。明るい木肌の色をした広々と立派な橋である。
こいつはいいと近付いて渡ろうとするが、一向にその橋へは辿り着けない。目測の距離を歩いても歩いても、遠ざかっていくのだった。「なんだなんだ、おいおい ちっとも距離が縮まらねえじゃねえか」
これはおかしいと大抵の者ならば悟るところである。
橋を渡ってゆけるのは生前とくに善い人間だった者だけだが、ゴモチは不信心もの、自分が橋を渡れねえこともどうやら知らないので、あれ霧の向こうにたどり着けない橋に向かって、追いかけるのをしばらく続けた。
畜生、なんだってんだクソッタレ、と悪態ついてかかとを蹴ったところで、ようやく見切りをつけ、のどが乾いて河原に降りた。川原は妙にごつごつといびつな形を保ったままの石が積み重なりながら散らばっており、平らかに広々とした川の流れに不似合いに見えた。上流の岩を無理に砕いたらこんな破片になるだろうか。慌てれば足に怪我をしそうだ。
ゴモチは慎重に川の縁まで寄り、そこで船があるのに気付いた。
こいつはいい、今度こそアレで向こうへ行けるぞと手を打ったが、船着き場が見当たらない。漕いでいる船頭は濃い霧の奥でこちらに気付いているかもわからず、仕方なしに川の底があるあたりをざぶざぶと船まで歩み寄った。ほとんど胸元まで水に浸かりながら「おうい、乗せてくれ」と声を掛ける。
と、ゆるり振り向いた船頭は被り物の影で表情を隠したまま、「六文」と呟いた。
「あ、なんだって?」
「六文」そういってゴモチをじっと待っている。
「おいまさか金を取るのかよ」
さほど信心深くなくとも六文銭で川を渡ることはよく知られているはずなのだが、ここはゴモチのことで、案の定知らない。船頭も呆れたのかふいと向きを変えて、船ごとつつぅーと離れて行ってしまった。
「あっおうい、待てや、このやろう薄情者め」
追いすがろうとして川底の石のとがりに足を置いてしまい、飛び上がりながらゴモチは悪態をついたが、痛みに跳ねた拍子にずるりと深みへ足を踏み外した。
「あっ!」
踏ん張ろうにも足は底につかず、みるみる身体が水に沈む。慌てて水面に顔を出そうと藻掻けば、突然足をぐいと引っ張られた。
「な、なんだなんだ」思わず足元の水底を覗き込む。すると、目が、合った。
なんとどこまでも澄んでいたはずの川の底にはいつの間にか陰った死者がうようよといて、幾本も膨れ爛れた腕が伸びゴモチの足首を掴もうと手を伸ばしてきていた。悲鳴を上げてもう片方の足で蹴り離そうとするものの、逆にそちらの足も掴まれてしまい、とうとう頭の先まで水に引きずり込まれる。
うわあああたすけてくれえ、と叫ぶにも叫べずブクブクとゴモチが沈んでいこうとしたその時、
ざぷんと大きな波が立って、ゴモチを川岸へ一気に引き上げた。
「へ、へ?」
「ああ、会えてよかった。お久しぶりでございます」
ペッペッと川の水を吐き出しながら濡れた視界を拭ってみると、なんとそこには美しい人魚がいた。
「…こいつぁ…どうしたこった、さっきの腕のお仲間かよ」
「おやまだ動じてらっしゃるようだ。彼等に尾びれはございませんよ。水に溺れ続けておるのです。私は自らの意思で、この川に留まっております。この鱗、このヒレの色に見覚えはありませんか?」
言われて、持ち上げられた魚の部分をじっと眺めるが、人間の覚えもあやふやというのに魚の鱗まで覚えているわけがない。首を傾げていると「私は雨に流された折に、土の囲いに閉じ込められて、そこで死ぬかと思われたとき、あなたに助けられたのです」と、人魚の方から語り始めた。
「あの日は暑く、干上がるばかりの浅い水のなか死を待つのは酷く恐ろしいことでした。貴方が施してくださったことは、まさに天のたすけ。川へ返していただいたのち、私は天寿を全うすることができました。貴方様とは生き物の命の長さが違いますから、ご恩を返す間もなく、先にこちらへ来ましたので、ここでお待ち申し上げておったのです。待っている間にこのような姿にまでなりました。ここを渡れずお困りならば、私が向こう岸までお連れいたします。今こそ、あの時のご恩を返させてくださいませ」
ゴモチは水害の日のことなどさっぱり忘れていたので、人魚の言うことはほとんど何のことかもわからずろくに聞いちゃなかったが、「向こう岸までお連れする」と都合のいいとこだけ耳が拾った。仮に他人の善行とて、人魚がここで自分を恩人と思い込んでいるなら構やしない。内心ほくそ笑み、神妙にうなづいて「そうかそうか」と調子を合わせた。
「そいつぁなによりだ、恩返しとは義理堅いねえ、だがそのおかげで俺は助からあ。ほんとに渡してくれるのかい?あとで金払えってったって、俺は一銭も持ってないぜ」
「滅相もございません。さあ、どうぞ私の背につかまっておくんなさい」
人魚が岸に手を差し伸べて、ゴモチはそれに捕まりながらつるりとした背にまたがった。背びれや鱗が引っ掛かりめくれたが、人魚は微笑んで「では参ります」と泳ぎだした。
こうしてゴモチは霧深い岸から並木道の岸へ渡ることができた。
ところでこいつもよく知れたことだが、死にかけてるときにみる川ってのは渡っちゃならない。それは三途の川っていって、手前で引きかえせば現で目を覚まそうってもんだが、此岸から彼岸へ渡っちまったら、そいつはもう戻ってこれなくなる。
しかしゴモチは不信心もの、川を渡る意味もどうやら知らない。自分が助けた魚のおかげで、まんまと死んじまったってわけだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
