
嫉妬につける薬はなくて、妬みが世界を駆けめぐる 第2話【創作大賞2023】
答えるバッハさんの声が震えていた。
「弊社の製品、速乾洗剤フイールの主原料です」

フイールの原料は公開されていない。XKZという液体は、乳白色で確かにフイールと似ている。おそらく新物質なのだろう。
銃を向けられているからなのか、秘密を明かしたからなのか、バッハさんは異様なくらい落ち着きがない。
「その通りだ。そして、もうわかっただろう。この青い液体がアロルウム溶剤だ」
アロルウム溶剤は工場などで使われる一般的な薬品だ。
「やめてください!」
バッハさんが叫ぶと、ワトキンスさんが愉快そうに笑った。
「次の質問だ、XKZとアロルウム溶剤が混ざると何が起きる? さあ、答えろ」
バッハさんの唾を飲み込む音が聞こえた。
「ば、爆発します」
「え?」
わたしはのけぞって驚いた。

「正解だ。私がこの二つのガラスボトルを床に落とせばこんな古いビル。すぐに吹っ飛ぶ」
ワトキンスさんが脅すように二つのボトルを振ると液体が激しく揺れた。吹っ飛ぶ、ってどれほどの威力なのだろう。爆発の炎に巻き込まれるイメージが頭に浮かび、身体がすくむ。
バッハさんが恐る恐る口にした。
「そ、それでは、あなたも助かりませんよ」
「いいんだ、わしはどのみち死ぬ気でここへ来てるんだ」
ワトキンスさんは、通信機に映るアーサーさんに向けてボトルを突き付けた。
「そういうことで交渉人、言うことを聞かなければ、このビルごと爆破する。わかったら、早く社長とロットリンダを呼べ。映像でのやりとりはここまでだ、あとは音声のみにする。防犯システムを全館オフにしろ」
「わかりました」
静かな声でアーサーさんが応じた。
天井に設置されていた防犯カメラの電源が落ちた。
「交渉人、社長とロットリンダが来たら、音声スピーカーで連絡を入れろ」
それだけ言うとワトキンスさんは、通信機のスイッチを切り、窓のブラインドを下ろした。
* *
コッペリ社の地下一階、警備室のモニターが一斉に真っ暗になった。
「まずいな」
通信機の前のアーサーがつぶやいた。
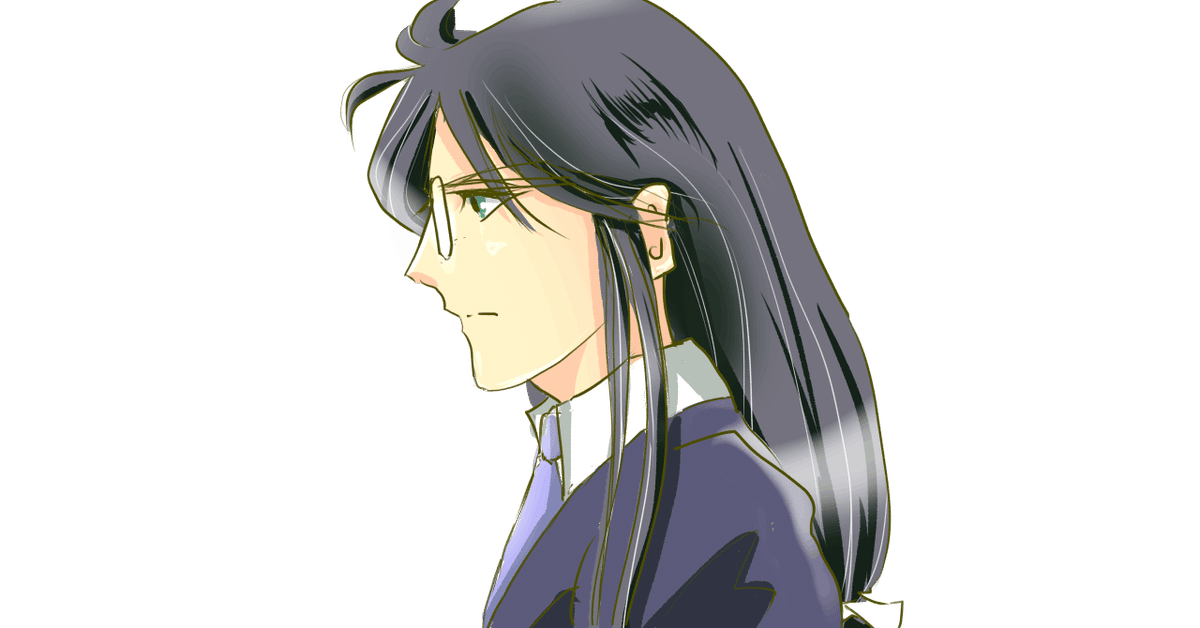
「おい、なんだよあの液体は?」
レイターがたずねる。
「XKZは十年前に発見された新物質だ。ワトキンス氏の持つ液体がXKZとアロルウム溶剤だとすると、二つが接触した瞬間、このビルは吹き飛ぶ」
「何い? 液体爆弾かよ」
アーサーはカルロスが用意した報告書のタブレットペーパーを、常人では読めないスピードでスライドさせた。
「ワトキンス氏はハルタナ社でXKZの研究をしていたようだ」
「はったりじゃねぇ、ってことか……」
警察の責任者であるバルダンに、アーサーが丁寧な口調で指示をした。
「バルダン隊長、ここから半径一キロに避難命令の措置を取ってください。我々もいったん退避し、警察署に前線本部を置きましょう」
「わかった」
「ちょっと待て、俺はここから動かねぇぞ」

レイターが不満げな声で言う。
「死にたければそうしろ。さて、コッペリ社の方、社長とロットリンダさんは、どちらにいらっしゃいますか?」
コッペリ社の担当者が青ざめた顔で答える。
「社長は出張中で、ほかの星系へでかけています。ロットリンダは、郊外の研究所です。とりあえず警察署へ向かわせます」
レイターがアーサーに小声で話しかけた。
「アーサー、あいつの目的はカネじゃなくて、社長とロットリンダを殺すことだろ。心中覚悟だな」
「おそらく」
「じゃあ、早いところ、ワトキンスを殺るしかねぇだろ」
「どうする気だ」
「生体反応照準器を使って、ティリーさんに当たらないように隣のビルから、頭ぶち抜いてやる」
「お前の腕ならできるだろうが、ワトキンスがボトルを床に落としたら爆発するんだぞ。ティリーさんを救う策があるのか?」
「それを考えるために、あんたに天才の頭がついてんだろがっ」
二人のやりとりを見ながら、バルダン隊長が苦笑した。

「お前ら、ガキの頃から全く変わらんな」
* *
フェニックス号の居間で、サブリナは携帯通信機の画面を何度もスクロールしていた。情報が更新されていないか、ネットワークのアップデートを繰り返す。

何かをしていないと、不安に押しつぶされてしまう。
ウウウウウウ……
テレビの中から響くサイレンの音に驚き、顔を上げてモニターを見る。
中継先で記者が慌てていた。
「避難命令です。コッペリ社から半径一キロの住民に、避難命令が出ました。立てこもり犯は強力な爆薬を持っているとのことです。我々はここから撤収します。皆さんも逃げてください」
「ええっ?」
ティリー先輩はまだコッペリ社の中だ。

ホストコンピュータのマザーが言う。
「ここは、コッペリ社から三キロ離れているので対象外です。問題ありません」
問題ないはずがない。
頭の中がパニックを起こしている。
ティリー先輩が事件に巻き込まれているのは、わたしのせいではない。けれど、先輩の仕事はわたしの契約から始まっているのだ。
わたしは耳をふさいで身体を縮めた。間違った選択をしたら父にぶたれる。なのに、手持ちの選択肢がない。吐き気がわたしを襲った。
*
厳格な父は潔癖症で、しつけと称して母とわたしに年中手を上げた。
些細なことだ。スプーンが曇っていた、とか、洗濯物にシワがあった、とか。強く殴るわけではない。頬の腫れはすぐに引いた。それでもわたしは怖かった。
どうしたら父の機嫌を損ねないか、物心がついた頃から考えながら生きていた。家では息を凝らして父の様子を観察し、出来る限り先回りした。間違ったらぶたれる。
そんなわたしにとって、学校の先生の意図を汲み取るのは容易なことだった。
低学年のころは、よかった。
よく気のつく優等生だと、教師にも近所の大人たちにも褒められた。
高学年になると状況は変わった。わたしは相変わらず教師の受けが良かった。でも、それは、同級生の間では別の言葉で語られた。「えこひいき」と。誰が言い出したかこの言葉は、子どもたちの間に一気に広まった。自分の何がいけないのか、今もよくわからない。
同僚から妬まれ、上司に受けがいいのは今も変わらない。先回りをする性分のわたしは、妬まれやすい体質なのだ。ティリー先輩を見ていて思う。羨ましいことに、あの人は、人から妬まれたことなどないのだろうな。
通信機が鳴った。彼氏のジョンからだ。

ダメだ。この通信に出たら「ここへきて欲しい」と口にしてしまう。ジョンの出世に悪影響を与える訳にはいかない。間違った選択をしてはいけないのだ。わたし自身のためにも。
着信音を無視した。これが正しい選択だ。
震えているわたしに、コンピューターのマザーがカップを差し出した。
「どうぞ」
ホットココアだった。一口すする。甘さが身体に染み渡り、少しだけ気持ちが落ち着いた。
* *
コッペリ社十五階の総務部。
犯人のワトキンスが、オフィスに設置されているテレビをつけた。慌てた記者の声がモニターから響く。
「避難命令です。コッペリ社から半径一キロの住民に、避難命令が出されました。立てこもり犯は強力な爆薬を持っているとのことです。我々はここから撤収します。皆さんも逃げてください」
ティリーはモニターを見つめた。
警察が住民を避難させている様子が映し出されていた。現地対策本部も一キロ以上離れた警察署内へ移動した。アーサーさんもレイターもこの近くにはいないということだ。なんだか見捨てられた気分だ。
わたしはバカだ。レイターが助けに来てくれるんじゃないかと、どこかで期待していた。

ちょっと考えればわかる。レイターは、警察官でもない民間のボディーガードだ。この状況で、ここまで来られるわけがないのだ。
そもそも、レイターは今回、わたしのボディーガードではなく、サブリナのボディーガードだった。サブリナは無事契約を終えただろうか。わたしにはバチが当たったんだ。

厄病神の船で出かけて、サブリナの契約がうまくいかなければいい、なんてことを願ったからだ。
アンタレスの神様は、わたしの肩の上で『行いの書』を書き続けている。人の不幸を望んだことへの報いを受けたんだ。
わたしはここで死んでも天国へは行けず、アンタレスの地獄の炎に焼かれ続けるのだ。

故郷の両親の顔が浮かんだ。パパ、ママ、ごめんなさい。
立てこもり犯のワトキンスさんが、イライラしながら通信機の音声スイッチを入れた。
「交渉人、社長とロットリンダはまだか?」
アーサーさんの落ち着いた声がした。今のわたしにできることは、ワトキンスさんとアーサーさんとの交渉を見守ることだけだ。
「ワトキンスさん、お待たせして申し訳ございません。社長は出張中のため、到着に時間がかかっているそうです」
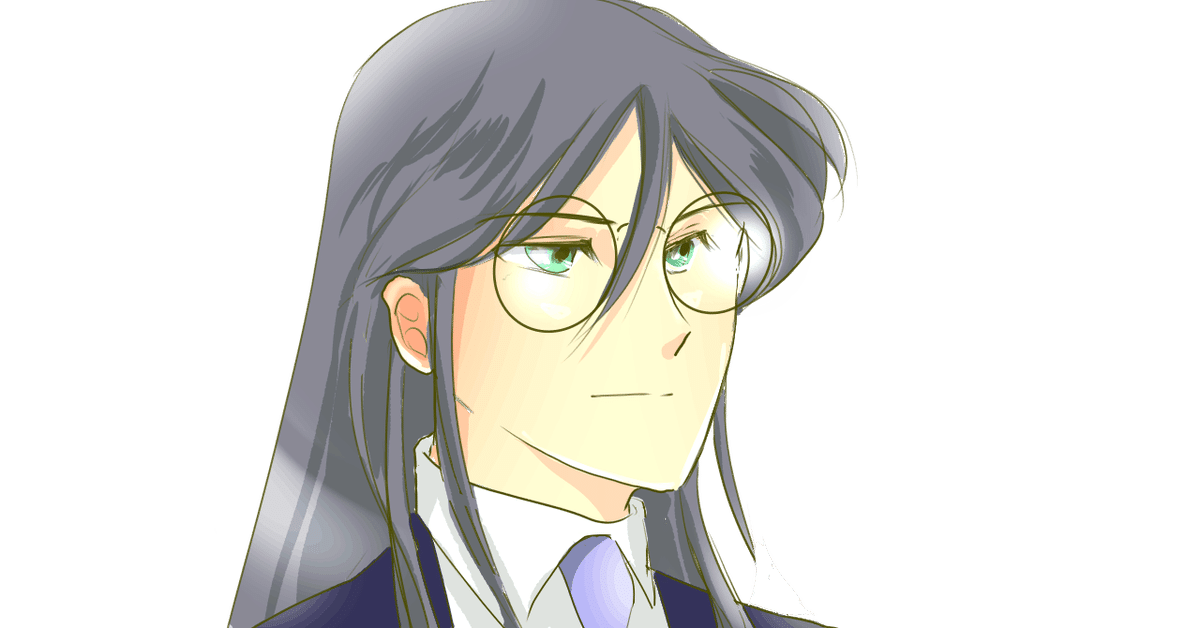
「ロットリンダはどうした?」
「今、研究所からこちらへ向かっております。ただ、避難命令が出ている中、そちらへ向かわせることには、躊躇がありまして」
「人質がどうなってもいいのか!」
怒声とともに唾が飛んでくる。わたしの身体が固まる。
「いえいえ、とんでもありません。ワトキンスさんは、ロットリンダ研究員に謝罪を求めるということでしたが、まさか、危害を加えるおつもりじゃないですよね」
「そんなことわかるか!」
「……」
アーサーさんが黙った。
沈黙が怖い。
ワトキンスさんが怒鳴りだした。

「ロットリンダは、殺されても仕方がないほどのことをしたんだ! わしの実験結果を、命より大切なデータを盗んだ産業スパイなんだ」
知らなかった。
「ワトキンスさんはそのことを、社会に明らかにしたいというお考えでいらっしゃるんですね」
「その通りだ」
「お気持ちはよくわかりました。そのためには、ロットリンダ研究員に、きちんと謝罪させた方がよろしいですよね」
「もちろんだ」
「脅された状況の謝罪では、ワトキンスさんのご主張を証明できなくなってしまいますので、フラットな状態で、謝罪をさせないといけないですね」
「あ、ああ……」
「では、ロットリンダ研究員には危害は加えられない、という約束でそちらへ向かうように説得してみます。少々お時間を下さい」
そこで、アーサーさんの通信がいったん切れた。
ワトキンスさんは、口の中でブツブツつぶやき、反論しようとしたけれど、うまく言葉にできないでいた。
* *
アーサーたちが現場を離れ警察署へと移動した後も、レイターはコッペリ社地下一階の警備室に残っていた。
特殊部隊に借りた対刃防弾の戦闘服に着替える。犯人のワトキンスを刺激させねぇように、防犯システムのスイッチを落としたから、ズラリと並ぶモニターは死んでる。十五階の状況を把握するため、悪いがティリーさん、盗聴させてもらうぜ。

ティリーさんは携帯通信機を手首につけている。その通信機に盗聴ソフトを送り付けてリモートで立ち上げる。
つながった。
ティリーさんの通信機のマイクを通して、くぐもったアーサーの声が聞こえた。感度を上げる。
「フラットな状態で、謝罪をさせないといけないですね」
アーサーの奴、訳の分かんねぇこと言って、犯人を言いくるめてやがる。
「では、ロットリンダ研究員には危害は加えられない、という約束でそちらへ向かうように説得してみます。少々お時間を下さい」
ワトキンスとの交渉がいったん中断した。
* *
十五階の部屋に再び沈黙がおとずれた。
ティリーは犯人のワトキンスの隣で小さくため息をついた。フイールが、盗まれた情報で作られていたとは知らなかった。コッペリ社のバッハさんと若い男性社員はうつむいている。
ワトキンスさんは、わたしに銃を向けながら説明を始めた。
「わしは、XKZの発見当初から十年に渡り研究していたんだ。その性質が、速乾洗剤に使えることをわしが見つけ、ハルタナ社で研究を重ねてきた。だが、わしの部下だったロットリンダが、その情報をもってコッペリ社に引き抜かれたんだ」
「そうだったんですか」
イケメンすぎる研究者の、さわやかな笑顔が頭に浮かんだ。

人は見かけによらないものだ。ロットリンダ研究員は誠実そうな人に見えた。うちの課の契約を、スルリと横取りしたサブリナの面影と重なった。悪人が悪人面をしているとは限らないのだ。
「そして、コッペリ社は、わしより先にXKZを使った洗剤の特許を申請した。産業スパイの裏切りにあわなければ、高速速乾洗剤は本当はハルタナ社から売り出せたんだ」
「それは違います」
バッハさんが口を挟んだ。

「何が違うんだ? コッペリ社はXKZについて研究をしたこともなければ、着想すらしていなかった。ロットリンダが転職してから開発を始めたんだ。間違っているか?」
ワトキンスさんが唾を飛ばしながら怒鳴る。
「い、いえ、その通りです」
バッハさんが下を向いた。
「わしが研究にかけた十年の時間も、会社の資金も、すべてコッペリ社のフイールにかっさらわれた。汚い産業スパイのせいで、研究所にわしの居場所はなくなり、わしはハルタナ社を辞めざるを得なくなった」
若いロットリンダ研究員は、時代の寵児ともてはやされていた。
頭が良くて、格好良くて、フイールが売れて、商品番付で一位を取って、お金も名声も得た。
その裏で、ワトキンスさんは泣いていたのだ。癇癪持ちのさえないおじさんにしか見えないけれど、ずっと頑張ってきたに違いない。
ぼんやりと考える。新型船七隻の販売で、サブリナは部内表彰をうけるんだろうな。
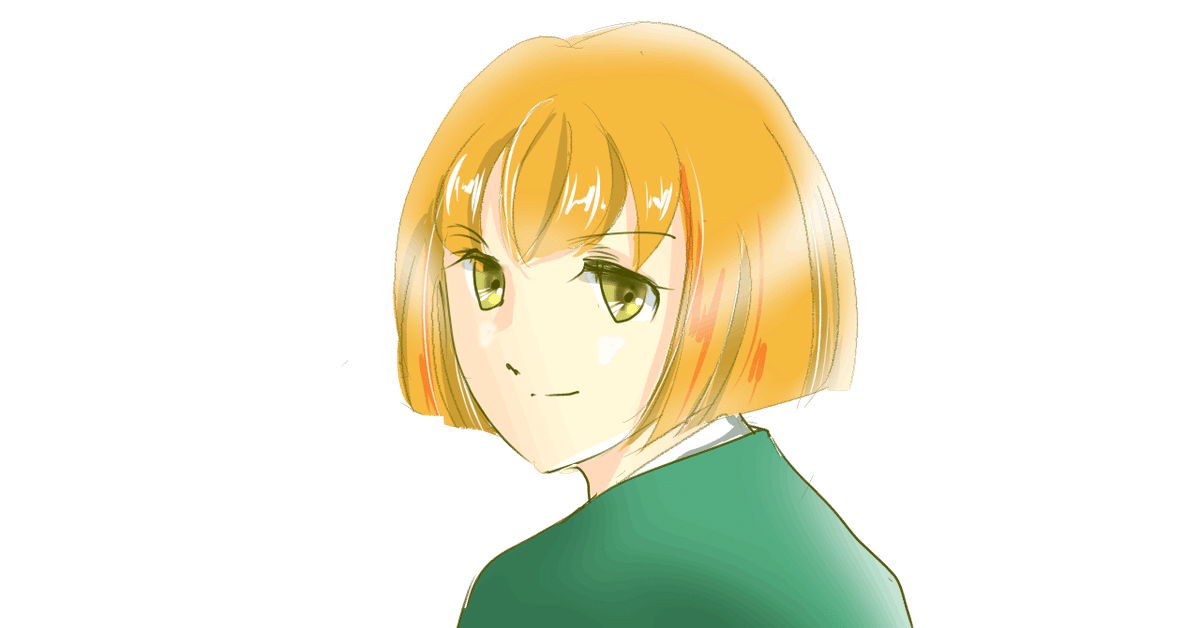
わたしはここで死ぬかもしれないのに。
どこにでも要領がいい人はいる。卑怯な人がおいしい思いをする。世の中は理不尽だ。
「お辛いですね」
自然に言葉が出ていた。
「わかるか」
「はい」
情報を盗んだロットリンダ研究員も、それで大儲けしたコッペリ社もひどい。ワトキンスさんに同情する。
「わしはその事実を、もっと多くの人に知ってもらいたいんだ」
「お気持ちはわかります。でも、このやり方はよくないと思います」

「うるさい!」
怒鳴られてわたしは肩をすくめた。
* *
おいおい、ティリーさん。頼むから犯人を刺激しねぇでくれ。俺の心臓に悪い。これだから真面目なアンタレス人には参るぜ。

コッペリ社の地下一階警備室で、現場の音声を盗聴していたレイターにアーサーから連絡が入った。
「レイター、七階へ行け」
「七階? 立てこもりの十五階じゃねぇのかよ」
「今、リアルタイム動画を送る」
アーサーから送られてきた映像を携帯通信機で再生する。
午前中に俺が張り付けた、集積カメラの映像だ。コッペリ社の防犯システムとは別だから、きちんと機能していた。さすが俺の仕事だ。きれいに撮れてる。
全員退避したはずの本社内を、男が二人うろついていた。
七階にある耐火ロッカーを開けようとしている。フイールの開発資料が入ったロッカーだ。
「あいつらがアリオロンの盗人ちゃんかよ。誰もいなくなるのを待って火事場泥棒ってか」
敵ながら、効率いい仕事だ。
年中稼働している防犯システムがワトキンスの要求で切れていて、しかも、仕事途中で社員が避難したから、普段は三重のロッカーの鍵も今は暗証番号のみだ。
「レイター、この窃盗犯を捕まえてくれ。ワトキンスはアリオロン軍と連携している。彼らの目的がわかった」
「あん?」

「フイールの技術を盗み、XKZ液体爆弾の制御に応用するつもりだ。フイールの非公開技術を使えば、爆破時間の調整ができる」
使い勝手のいい液体爆弾が作れるってことかよ。
「資料を持ち出されたら、連邦軍に甚大な被害が出るってことだな。こいつは特別手当をはずんでもらわねぇと」
俺の要求をスルーして、アーサーは続けた。
「ワトキンスは現在無職だ。アリオロンに亡命して、液体爆弾開発のためXKZの研究を続けるつもりなのだろう。アリオロンの工作員が七階で情報を入手したら、ワトキンスと合流し逃亡する手筈とみられる」
「ってことは、泥棒ちゃんが資料を盗み出すまでは、ワトキンスは爆破しねぇな」
「安心はできない。ワトキンスが勝手にXKZを起爆させる可能性はある」
「んなことしたら、味方もろとも死ぬぜ?」

「ワトキンスは、興奮し精神不安定な状態だ。死んでも構わないと考えて、衝動的に他人を巻き込む恐れがある。中の人質が彼の機嫌を損ねないことを祈るのみだ」
「まじかよ」
ティリーさんは、すぐに地雷を踏むぞ。
* *
サブリナは爪を噛んでいた。落ち着かないときの癖だ。

警察は公式に発表していないけれど、情報ネットワークのまとめサイトによれば、どうやら、立てこもりの犯人はライバル社の元研究員ノア・ワトキンス氏。ワトキンス氏はフイールの開発者ロットリンダ研究員を、産業スパイと告発しているようだ。
情報が無いと不安。でも、いくら情報があっても今の自分には何もできない。
その時、誰かがフェニックス号の居間に入ってきた。レイターさんが帰ってきたのかと振り向いた。
「サブリナ」
驚いた。そこに立っていたのは、正装に身を包んだ彼氏のジョンだった。

「ジョン?! どうして?」
「どうしてじゃないよ。君がフェニックス号にいるとレイターから聞いて、飛んできたんだ。どうして君は、僕に連絡を入れてくれないんだ。僕の通信も無視して」
わたしはあわてた。
「だって、あなた、きょうは授賞式でしょ」
時計を見る。ちょうど式が始まる時間だ。
「サパライアン所長に頼んできたから大丈夫だよ。式場とここヨマ星系が近くてよかった」
のんびりとした笑顔がわたしをいらつかせる。研究所のサパライアン所長はジョンの上司。

でも、この賞はジョンのものだ。
「この授賞式がどれほど大切か、わかってないの?」
ジョンは、浮世離れしている。きょうは若手研究者の登竜門、ザルダック財団賞の授賞式だ。ジョンが見つけたバローネ理論がその大賞に選ばれたのだ。授賞式にはマスコミもたくさんくる。
そこで語った抱負が記事になり、注目され、さらに大きな賞へと結びついていく。
世界的権威のキンドレール賞だって、狙えるかも知れない。ジョンにとっては、この先の人生がかかった大事な日だ、というのに。
「ジョンが、学生時代から続けてきた研究が世界に認められたのよ」
ジョンは緊張しながらも、きょうを楽しみにしていた。その晴れ舞台を、サパライアン所長に渡してしまった。
「でも、サブリナの方が大事だよ」
だから、恋は嫌なのだ。人生を踏み外す。
*
大人になって家を出たわたしは、何度も母に言った。
「父とは、別れなさいよ。わたしと一緒に暮らそう」
母は、困った顔でわたしに言った。
「サブリナ、わたしはやっぱり、あの人のことが好きなのよ」
暴力による支配は愛ではない、といくら伝えても母は理解しなかった。母は父に尽くすことに生きがいを感じていた。
恋は盲目、とはよく言ったものだ。
この世界に男性は沢山いるのに、なぜあの父を好きだ、と言うのかわたしにはわからない。
母は愚かだ。わたしは父の側に立ちたい。愛されれば支配する側になれる。愛したら人は負けるのだ。正常な判断ができなくなって、目の前のジョンのように、人生の大事なチャンスすら、棒に振ってしまう。
レイターさんのお節介のせいだ。
今日の授賞式がジョンにとってどれだけ大切か、あの人はわかっていた。わたしたちが祝勝会を開くことも知っていたのだ。
「レイターさんが、わたしの居場所をジョンに知らせなければよかったのに」

「どうしてそんなことを言うんだい?」
ジョンが小さな目を見開く。
「だって、わたしは怪我もしていないし、立てこもりに遭ったわけでもないのよ。人質に取られているのはティリー先輩で、ジョンが来る意味がないわ。ジョンの将来にとって、人生にとって大事な授賞式なのよ。比較したらどっちが大事か考えるまでもないわ」
わたしは感情的になって声を荒げた。
「サブリナ、君はいつも、正しい答えを出そうとする」

「そうよ。間違ってはいけないのよ」
間違った選択をしたら、父にぶたれてしまう。
*
ジョンと出会ったのは、新入社員の頃だった。
たまたま、社員食堂で隣の席になった。わたしは本社で働くほとんどの人の顔と役職を覚えている。
ジョン先輩は研究所の有望株だ。わたしからあいさつした。
「新入社員のサブリナです。ジョン先輩はすごいですね、今年も早々と特許を取られて」

情報も集めているから雑談も得意だ。わたしは近くにいる同僚は不愉快にさせるけれど、少し距離があるお客さまや上司からは好感を持たれる。
何度かあいさつするうちに、気がついた。ジョン先輩がわたしのことを好きだということに。
わたしは情報を集約し計算する。先輩と付き合うことのメリットを。そして、デメリットと比較する。容姿は冴えないけれど、そこはわたしは気にしない。彼には才能がある。のんびりし過ぎているけれど、わたしが振り付ければ、出世もまちがいない。いい人だ。優しく、そして、何よりわたしを愛してくれる。
愛される側が決定権をにぎる。
父のように、人生をコントロールする側になれる。ジョン先輩を彼氏にする選択は、正解だ。
告白したのは、わたしからだった。
「先輩、わたしとつきあって下さいませんか?」
ジョン先輩はまるでプロポーズのような返答をした。
「ぼ、僕は君を幸せにすることを誓うよ」
週末にはデートをした。ジョンは気の利いたお店も何も知らなかった。わたしは、自分の行きたい映画やイベントにジョンを誘った。彼は興味があろうがなかろうが、何一つ文句を言わず、笑顔でついてくる。都合のいい男性だ。
つきあわせたお礼に、わたしはジョンの家でご飯を作った。料理作りはわたしの趣味のようなものだ。彼は、何でも美味しそうに食べた。わたしが支配する側。ジョンと過ごす、計算の必要がない時間は楽しかった。
ジョンは宇宙船レースを観るのが好きだった。つき合って見ているうちに面白さにハマった。就職活動の際、わたしはクロノスのほかに、ベンチャー企業のライネッツ・スチュワート社から内定をもらっていた。

若き経営者が生み出す、最先端の情報産業は面白そうだった。倍率は高く、クラスメートには羨ましがられた。
けれど、わたしは計算した結果、クロノスへの就職を選択した。人生を預けるにはスチュワート社は事業の成否にムラがあり危険だ。でも、思い入れはある。そんな縁から、宇宙船のS1レースではチーム・スチュワートの船を応援した。
*
「サブリナ、君はいつも、正しい答えを出そうとする」
ジョンの言葉に、否定的なニュアンスが含まれていた。こんなことは初めてだった。
わたしは反論する。
「そうよ。間違ってはいけないのよ」

一生懸命に情報を集めて、正しい解を導き出せば、人生に幸せが待っているはずなのだ。DV男はきちんと排除する。不安定要素の多い就職先も避ける。
「わたしは今回、あなたの将来の邪魔になった」
「邪魔じゃないよ、サブリナ。僕が自分でここへ来たかったんだ。だって、君はとっても怖がりじゃないか。サブリナを一人にしておきたくなかった。この選択は、僕の中では正解だ」
「……」
ジョンが来るまでの間、わたしは恐怖で何度も嘔吐した。
ジョンは気がついていた。わたしが極度の心配性で、耐えられないほどの不安に陥っていることに。
* *
さて、あいつらをどうするか。階段をのぼりながらレイターは動画を見ていた。
コッペリ社七階の開発管理課で作業を続けるアリオロンの盗人。大柄と小柄の男二人組。全身を対刃防弾スーツで覆って、コメディアンのコンビみたいだぜ。
頭部はヘルメット仕様。銃も刃物も致命傷は負わせられねぇな。肉弾戦か。

アーサーの奴は、窃盗犯を捕まえろって言ってたが、証拠隠滅のためにワトキンスに爆破命令を出す恐れがある。ティリーさんを守るためには、殺すしかねぇ。
身体のでかい方は見張りだ。もう一人のチビがロッカーの暗証番号キーを解読して開けようとしている。
首絞めてる時間的余裕はねぇな。一撃で首の骨を折る。楽しい仕事じゃねぇが、しょうがねぇ。しかし、二人同時は無理だ。見ればわかる。訓練された動き。あいつらだって素人じゃねぇんだ。
俺の存在が気づかれてねぇアドバンテージを、最大限まで生かさせてもらうぜ。
*
七階の構造は頭に入ってる。
さっき案内された奥の会議室の横に、あいつらの視界に入らないドアがある。防犯システムが切れてるお陰で無施錠だ。音を立てずに部屋へ忍び込む。しゃがみ込み、オフィスの机で身を隠して近づく。
二人を目視で確認した。もう少しでロッカーの鍵が開きそうだ。時間がねぇ。俺は机の影に隠れて、腕に着けた携帯通信機の短縮ダイヤルを押した。

PPPPPP……
俺の二メートル先にある卓上通信機の呼び出し音が、大音量で鳴り出した。二人がビクッと音のなる方を振り向く。
俺の想定通り、オフィスの中をロボットが近づいてきた。さっき、俺とサブリナさんを案内した旧式の受付ロボットだ。人工アームで机の上の通信機の受話スイッチを押す。
「はい、こちらコッペリ社でございます。現在、担当者は席を外しております」
盗人の二人は、自分の仕事に戻った。俺は続けざまに通信機を操作する。
受付ロボットの近くで呼び出し音が一斉に鳴り出す。ロボットが一つずつ通信機をオンにして対応する。俺がループで架け続けているから、切っても切っても鳴りやまない。
PPPPPP……PPPPPP……
「はいこちら、コッペリ社でございます」
PPPPPP……
盗人たちも様子がおかしいことに気づいた。見張りの大男がゆっくりと受付ロボットに近づく。もう一人のチビは背中を向けて解錠作業に集中している。
さあ、大男が俺の間合いに入った。
男の背後から飛び出し、大男の太い首に腕を巻きつけ、口をふさぐ。
PPPPPP……
着信音が隠れ蓑になる。チビの奴は作業に必死で気付かない。俺のシナリオ通りだ。ここで、とどめを刺す。その時、
「レイター、殺すな」
アーサーの声が耳の無線機から聞こえた。俺の身体が一瞬固まる。敵はその隙を見逃さなかった。一気に反撃してきた。俺の完璧なシナリオが崩れる。不意打ち失敗。次のシナリオへ移行だ。
ちっ。大男の奴、想定より力が強い。俺の腕を引きはがしにかかる。アーサーの奴が余計な情報を俺に入れる。

「ワトキンスと彼らの通信は遮断した。爆破指示の恐れはない。安心して捕まえろ」
安心じゃねえよ。こいつらは俺を殺す気だ。あんたは遠くの警察署で俺が張り付けた集積カメラの映像見てるだけだから、悠長なことが言えんだよ。
接近戦、大男の馬鹿力で俺の優位性が崩れる。
バスッ。
胸に強烈な痛みと衝撃が走った。肺が潰れる。息ができねぇ。
争いに気付いたもう一人のチビが、銃で俺を撃った。この戦闘服は防弾仕様だ。死にはしねぇが、銃弾は人力を上回る破壊力だ。
意識が飛ばねぇようにするので精一杯だ。
俺の力がゆるむ。形成が逆転された。
怪力大男が両手で俺の首を絞めにきた。すげえ握力。息ができねぇ。目の奥がチカチカする。やべえ。
もう一人のチビが再度、背後から俺を撃とうと狙ってやがる。もう一発撃たれたら終わりだ。俺は間違いなくこの怪力大男に絞め殺される。
苦しい。のどがつぶされる。脳に血が回らねぇ。
右手で相手の指の隙間を探す。
左手で腰に付けた電子鞭を握った。
叩くんじゃない、大男の両足首に巻き付けて引っ張る。投げ縄の要領。自動巻き取りモードにしてある。電子鞭から手を離す。
いくら怪力でも機械の力には勝てねぇ。
大男の右足と左足が、くっつくようにしてそろい、バランスを崩す。
今だ。大男の指の隙間に俺の指をねじ込む。隊長のバルダンなら指をつかむだけで人を殺せる。
大男の奴、不安定な体勢になりながら、さらに締めてきた。俺の指がちぎれそうだ。一体どこからこのパワーが出てきやがる。
銃を持ったチビが、あわてて援護射撃した。
俺はぐっと力を入れ敵の薬指一本を引きはがしながら、身体の軸を回転させた。くるりと俺と大男の向きを変える。
バスッ。
大男が盾となり、銃弾が奴の背中に当たる。
「ぐあっ」
同時に、思いっきり大男の首筋に側面から手刀をあてる。脳震とうを起こして大きな体が倒れる。
はあ、はあ。酸素を思いっきり肺に吸い込む。

怪力大男の足に巻き付いた電子鞭は、簡単にははずれねぇ。一人目、捕獲終了。
その時、ロッカーが開く音が聞こえた。あわてて振り向く。
デジタルペーパーを手にしたチビが走り出した。まずい、フイールの機密資料を取り返さねぇと。
速い。
大男はパワー。チビはスピードか。チビは足に履いたブースターブーツで空中を移動始めた。銃でチビの背中を撃つ。衝撃は与えたが、あいつも訓練されている。資料を落としたりしねぇ。このまま七階の窓をぶち破って外へ飛び出す気だ。
チビの奴が窓に飛び込む。やべぇ。間に合わねぇ。逃げられる。俺の特別手当が……
* *
コッペリ社の十五階で、ティリーは、立てこもり犯ワトキンスの話を聞かされていた。
爆発的に売れた速乾洗剤フイールは、ワトキンスさんの研究が盗まれて作られたものだった。
ワトキンスさんが怒るのも無理はない。
「お気持ちはわかります。でも、このやり方はよくないと思います」

「うるさい!」
怒鳴られてわたしは身体をを縮めた。
つい、本音を言ってしまった。でも、こんな立てこもりじゃなくて、人に迷惑をかけない方法というものがあるはずだ。
ワトキンスさんが、わたしに顔を近づけた。こめかみに青筋が浮かんでいる。
「お前、やり方が良くないと言ったな、わしが何度コッペリ社に抗議文を送ったと思ってるんだ。どれだけ言っても、当方に問題はない、の一点張りだ。直接出向いてみれば、そこの若造に木で鼻をくくったような対応をされて、わしの悔しさがわかるか!」
ワトキンスさんが怒鳴りながら銃を人質の若者に向けた。
「すみません」
男性社員は震えて下を向いた。まずい、今にも引き金を引きそうだ。
やり方が良くない、と言ってしまったわたしのせいだ。何とかしなくては。
「け、警察に訴えてみてはどうでしょうか?」
「被害届は出したが、受理されなかったんだ」
「じゃあ、メディアに告発してみるとか」
「告発状をマスコミ各社に送った。だが、誰も取り上げてくれない。他にどうしろというんだ?」
経済スパイ法違反の事件だと言うのに、警察もマスコミも動かなかっただなんてひどすぎる。
その時、いいアイデアを思いついた。
「告発文書を、情報ネットワークにあげてみてはどうでしょうか」
情報ネットなら、誰でも世界に発信できる。弱者の武器だ。世論を味方にできれば公的機関だって動かせる。
「情報ネットワークか……」
ワトキンスさんの目が細くなる。
「わたしと同じように、おかしいと感じる人は必ずいます」
「そうだよ、わしは何度も何度も情報をあげて、ようやくネットワーク上の良識ある人たちの間で話題になった」
口元が笑っている。笑顔ってこんなに怖いものだっただろうか。
「その結果を教えてやろう。ロットリンダは名誉毀損だと警察に届け出た。あいつは今や有名人だ。そして、わしの投稿は削除されたんだ。さあ、わしは次はどうすればいいんだ?」
打つ手がない。
やり方が良くない、と言ってしまったけれど、ワトキンスさんはいろいろ考えて、実行していた。それを、みんなが無視したせいで、立てこもりという犯罪にたどり着いてしまったんだ。
これは、おかしい。
何かがわたしの中で弾けた。死ぬ前に、一言言わずにはいられない。わたしは、人質のバッハさんに顔を向けた。
「バッハさん、どういうことなんですか? そもそもコッペリ社が産業スパイをしたっていうのは」
「いえ、それは、あの……」

バッハさんが口ごもった。
「大体、フイールが危険な成分でできている、ってことを隠して販売するなんて、倫理的に問題じゃないですか」
「そう言われましても」
コッペリ社は、フイールの危険性を一言も告知していない。
わたしは速乾機能を喜んで使っていたけれど、こんなビルを吹き飛ばす爆発力を持っているなんて知らなかった。原材料が危険なことを隠すために、企業秘密として一切公開しなかったんだ。消費者への裏切りだ。
「売れればいいんですか。そんなコッペリ社もおかしいですけど、ワトキンスさんの勤務先だったハルタナ社はもっとおかしいです」
「ん?」
ワトキンスさんがわたしを見た。
「だって、情報を盗まれたのなら、ワトキンスさんを責めるんじゃなくて、正々堂々と、社としてコッペリ社に抗議すべきです。ワトキンスさんが十年研究していた企業秘密を盗まれたんですよ。それを、社員一人の責任に負わせるなんて、おかしいじゃないですか。ワトキンスさんの居場所を奪うなんて、もってのほかです!」

怒りが恐怖を上回っていた。わたしは逆切れしているのかも知れない。けれど、間違ったことは言っていない。
ワトキンスさんが声を震わせた。
「その通りだ。わしはずっと真面目に研究してきたんだ。速乾洗剤が完成しなかったのは、産業スパイのせいだ。それなのに、どうして、こんな目にあわなくちゃいけないんだ」
契約を横取りした後輩のサブリナが、売買成立という日に、わたしは雑用仕事で、どうして、こんな事件に巻き込まれなくちゃいけないんだろう。
世の中の不公平に腹が立つ。
「理不尽です」
わたしの心からの言葉に、ワトキンスさんの表情が和らいだ。
「わかってくれるか、わしの無念を」
「はい」
その時、わたしは気が付いた。
「ワトキンスさん、テレビを見てください」
記者が最新情報をリポートしていた。
「ワトキンス容疑者の要求について、情報が入ってきました。コッペリ社の社長とフイールの開発者ロットリンダ研究員を呼ぶよう求めています。ワトキンス容疑者は、ロットリンダ研究員が産業スパイだ、という主張しており、謝罪を求めているとのことです。ワトキンス容疑者が研究してきた速乾洗剤の研究データを、ロットリンダ研究員が盗み出しフイールを完成させた、と訴えている模様です」
「ワトキンスさん。あなたの主張をマスコミが取り上げて流していますよ」 ワトキンスさんが、テレビを食い入るように見つめた。
「本当だ……」

「きっと、このニュースで銀河中の人にわかってもらえます」
ワトキンスさんのとった手段は正しくない。でも、社会の不正はようやく表にさらけだされた。と、その時だった。
ワトキンスさんの身体が硬直した。
そして、手からガラスのボトルがするりと落ちた。えっ?!
あれが床に落ちたら、爆発する。
二本のボトルの落下がスロー映像のようにくっきりと、わたしの目にうつる。
突然のことに身体が動かない。レイター、助けて!

視界が真っ白になった。
* *
コッペリ社七階の開発管理課。電子鞭でしばった怪力の大男は床にのびている。もう一人の背の低い男が、速乾洗剤フイールの開発資料を手に逃走した。レイターが追いかける。
速い。大男はパワー。チビはスピードか。ブースターブーツで身体を浮き上がらせ、窓から外へ飛びだそうとしている。
あのチビ、ワトキンスを置いて逃げる気だ。フイールの資料さえあればワトキンスがいなくても、アリオロンの科学者がXKZ液体爆弾を成功させるにちがいねぇ。
やっぱ、生け捕りじゃなく殺しときゃよかった。俺のせいじゃねぇ、アーサーの面倒な捕獲命令のせいだ。

半径一キロは警察も誰もいねぇ。あいつは悠々と逃げのびる。やべぇ。間に合わねぇ。逃げられる。俺の特別手当が……
と、その時だった。
窓の手前で黒い大きな影が、チビにタックルした。
ダンッツ。
音を立ててチビが床にひっくり返る。
ブースターブーツの噴射を超えるパワー。戦闘服の男が、チビを押さえ込む。
「窃盗犯を現行犯逮捕」
バルダンの声だ。
相変わらず、すげぇな。対刃防弾スーツの上から急所を指一突きかよ。チビがぐったりしている。乗り込んできた特殊部隊の奴らがフイールの資料を回収する。バルダンの部下は手際よく、大男とチビに拘束着を着せた。
「遅せぇよ」
文句を言う俺にバルダンは、怪力大男の赤く腫れた薬指を見ながら言った。
「ふむ、俺の教えた通りに働いたようだな」

「ちげぇよ、あんたの教え通りに戦ったら、殺すしか選択肢ねぇだろが」
「俺は今、警察官だ。悪い奴を捕まえるのが仕事なんだ」
ガキのころ、俺と一緒に戦艦アレクサンドリア号に乗ってたバルダンは、白兵戦部隊を率いて敵を倒しまくってた。あの頃とは違うってことかよ。
チビも死んでなかった。
「さて、もう一人の悪い奴を捕まえに行くぞ。動けるか」
「当たり前ぇだ。上に俺のクライアントがいるっつったろ」
大きな声を出すと胸が痛む。撃たれたところだ。肋骨やられたか。
「お前、十五階の部屋を盗聴してるんだろ?」
「よくわかったな」
「アーサーが言っとった。突入のタイミングはレイターに任せろと。お前に指揮権をやる。部隊をしっかり動かせ」
「アイアイサー」
俺たちは十五階へ向かった。
*
十五階の構造は面倒だ。ワトキンスが立てこもっている経営総務課へ入るためのドアは正面の一つしかない。
ワトキンスから丸見えだ。ワトキンスは素人だ。どこかに隙がでる。それを狙って突入する。ティリーさんの携帯通信機を通じて、俺の耳に室内の音が聞こえる。
ワトキンスとティリーさんが会話している。やばい。ティリーさんが興奮して怒ってる。頼むからワトキンスを逆上させるな。
「社員一人の責任に負わせるなんておかしいじゃないですか。ワトキンスさんの居場所を奪うなんて、もってのほかです!」

あん? 何だか、すげぇ会話だ。ティリーさんの怒りの方向が、ワトキンスと同調している。
「理不尽です」
「わかってくれるか、私の無念を」
「はい」
被害者特有のストックホルム症候群? いや違うな。
ティリーさんは、純粋にワトキンスに同情して共感している。天然の傾聴力。ワトキンスはティリーさんが自分を認めていることを感じて、憎悪の攻撃性が緩んでいる。
「ワトキンスさん、テレビを見てください。あなたの主張をマスコミが取り上げて流していますよ。きっと、このニュースで銀河中の人にわかってもらえます」
今だ。
ニードルガンのスコープがワトキンスの首筋をとらえる。俺は突入の指示を出した。
バルダンたち特殊部隊が白い煙幕を張った。正面ドアから音を立てずに一気に侵入する。さあ、生き残るかお陀仏か。
俺は、テレビに見入ったワトキンスに、即効固定剤の注入針を打ち込む。

プシュッツ
ワトキンスの身体中の筋肉がこわばり、動きを止めた。
液体爆弾の二つのガラスボトルがするりと手から滑り落ちる。
この記事が参加している募集
ティリー「サポートしていただけたらうれしいです」 レイター「船を維持するにゃ、カネがかかるんだよな」 ティリー「フェニックス号のためじゃないです。この世界を維持するためです」 レイター「なんか、すげぇな……」
