
緑の森の闇の向こうに 第4話【創作大賞2024】
その時、ダルダさんの手首で携帯通信機が光った。
「おっと失礼」
メッセージが届いたようだ。ちらりと送信元の名前が見えた。『レイター』と出ていた。
わたしは思わず扉の方を振り向いた。レイターがにやりと笑った。
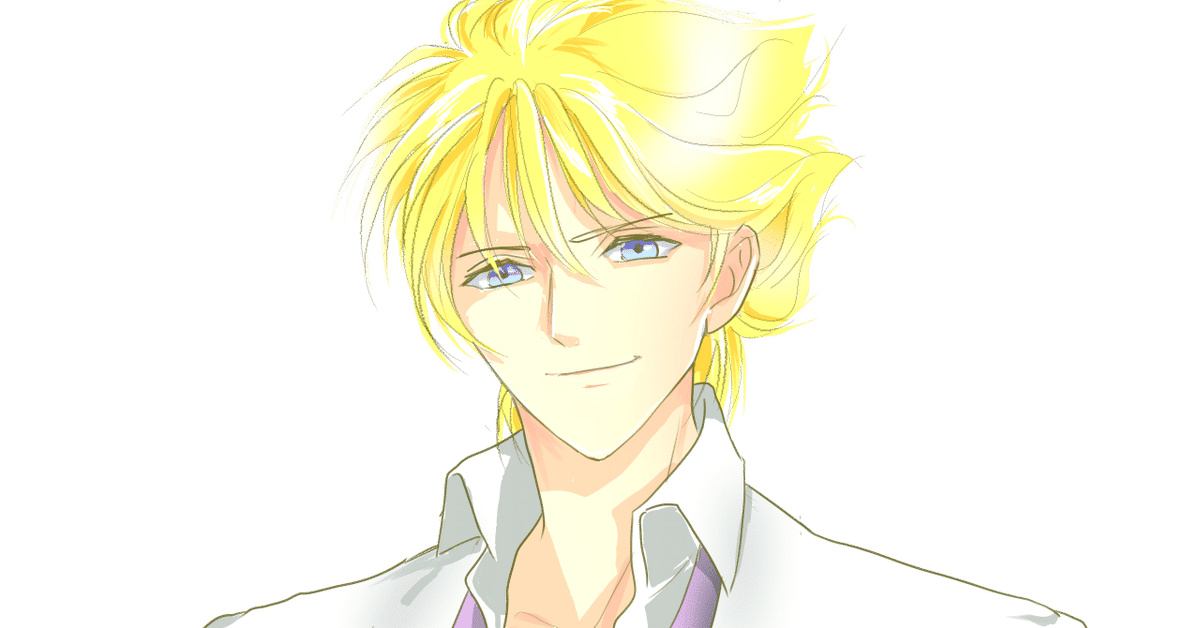
携帯のメッセージを見ながらダルダさんがゆっくりとうなずいた。
「ふむ、移転先ではパキの木の九十ニパーセントが枯れているらしいな」
「……そ、その数字は」
狐男が細い目を見開いた。
「九十二パーセントをたまたまとか一部とは言わないだろう」
「問題ございません。次の移植先も確保しております」
「俺の実家は農家でね。土にはうるさいんだよ。九割が植え替えに失敗して、検証もなしに代替地は見つからんよ」
「……」
狐男が黙った。
「政府は隠蔽しているようだが、いずれにせよ本社が入って調査すればすぐにばれてしまうことだ。物価スライドと同時に、工場拡張の是非も本社の検討議題にあげるから、ちゃんと反対派の動向についても情報をあげてもらいたい」
「はい。かしこまりました」
狐男は丁寧に頭を下げた。本心かどうかはわからない。
「ところで、パキールというのはそんなにおいしいのかね?」
ダルダさんがたずねた。
「ええ、生でも火を入れても食べられまして、私達パキ人にとってはなくてはならない食材です。人工栽培技術も進んでおりますので、栽培物でも十分おいしいんですよ。反対派が言っていることは極端なんです」
「ぜひ、食べてみたいものだな」
「はい、本日は、パキ星でも最高のお店をご用意いたしました。パキールもお楽しみいただけます。政府の要人もお呼びしておりますので、何卒お付き合いをよろしくお願いいたします」
政府は工場を誘致したいのだ。狐男はわたしたちを要人と引き合わせ、接待で懐柔するつもりだ。逆にその場を利用してもっと情報を得ることもできる。この会食は緊張したやりとりになりそうだ。と考えたその時、
「いや、結構。食事は予約してきた」
ダルダさんが工場長の誘いを断った。食事の予約? そんな話は聞いていない。誰かとアポイントを入れていたのだろうか?
狐男があわてていた。
「お伝えしておりませんでしたが、実は産業担当の大臣に予定を空けていただいているのです。短いお時間で結構です。お顔を出していただけないでしょうか?」
これまで本社からの視察と言えば、高級ホテルに泊めて、美味しい食事を出して、要人に会わせて、とパターンが決まっていたのだろう。
「悪いがこちらも忙しいんだよ。ガハハハハ」

ダルダさんの笑い声の前に、狐男が茫然としている。その様子を見るのは痛快だった。けれど、大臣との会食を断って大丈夫なのだろうか。
帰りは後部座席のダルダさんの隣に座った。確認しておかなくては。
「この後はどなたと食事をする予定なんですか?」
「誰って別に予定はないが」
答えの意味が分からない。
「え? さっき先約があるって、断りましたよね」
「嘘に決まってるだろ」
「う、うそ?」
「ああでも言わないと、あいつ、しつこそうだったろ。嘘も方便という奴だ。レイター、俺は現地の人が行く店でパキールが食べたいんだよ。お前、現地語しゃべれるだろ? 案内してくれよ」
「あん? 工場長に連れて行ってもらえばよかったじゃねぇか」
「あいつが行くところと言えば、銀河共通語が通じて連邦資本が入った店だろ。そんなところにロマンとスリルはない。それに、折角の出張なのにあんな食事のまずくなる奴と食いたくないだろが」
「あんた、これは仕事か? プライベートか?」
「プライベートさ、俺がおごる」
「あんたの仕事はいっつもこうだ」
「ちょ、ちょっと待ってください」
話の流れについて行けない。

「大臣との会食をキャンセルしたんですよ」
ダルダさんが驚いた顔をした。
「ティリー君、君、行きたかったのかい?」
「いえ、行きたいとか、行きたくないとかじゃなくて、行くべきだったんじゃないですか?」
先輩がダメ社員ということを忘れていた。アシスタントとしてもっとしっかり予定を把握しておけばよかった。
「どうしてだい? 折角の出張だよ、楽しもうじゃないか。ガハハハ」
出張を楽しむと言うのは、それは仕事がうまくいった後の話だ。今からでも狐男に連絡を入れれば大臣の日程変更に間に合うんじゃないだろうか。でも、わたし一人で行くわけにはいかない。ダルダさんを説得しなくては。
運転席からレイターの声がした。
「ティリーさん、あせんなよ。ダルさんが食事を断った時の工場長の顔、最高だったよな。会社で一番接待に釣られない男を派遣したところで、すでに本社の勝ちだった、ってわけだ」
「ガハハハハ。会社も俺の使い方をわかってきたな」
わたしたちの仕事の目的は生産の遅れの原因を探ることで、その要因は大体把握できた。これまで正確な情報が取れなかったのは、狐男の策略ともてなしに引っかかっていたからだ。下手にパキ政府と交渉をして、取り込まれたりしないほうが賢明なのかもしれない。
気持ちが落ち着いてくると、急にお腹が空いてきた。
「食事にご一緒していいですか?」
「だ~め。俺の仕事が増えるじゃねぇかよ。ガキはホテルでお留守番してな」

「わたしはガキじゃありません。それに、わたしはレイターじゃなくダルダ先輩に聞いたんです」
ダルダさんはにっこりと笑った。
「もちろん、構わんよ」
その答えにレイターがあわてた。
「おいおい、あんた子どもを連れてく気かよ」
「大丈夫だ、俺は純粋に食事に行く」
「あんたが?」
バックミラーに映るレイターが、いぶかしげな顔をした。
「ガハハハハ。歓楽街は逃げないさ」
二人の会話からレイターがわたしを連れていくのを嫌がった理由を察した。いつもは男の人が楽しむ夜の街へ繰り出しているということだ。
「ティリー君の分もおごるよ」
「ありがとうございます。でも、大丈夫です割り勘で。お金もカードに入ってます」
「信じらんねぇ」
レイターが驚いた声を出した。
「何がよ?」
「ダルさんがおごるって言ってんだぜ。自分で払うことねぇじゃん」
「わたしはあなたとは違います」
「あんた、ダルさんの一億の小遣いの話、聞いてなかったのかよ?」
「その話とわたしとは、関係ないでしょうが」
わたしたちのやりとりを見ていたダルダさんが、笑いながら言った。
「ガハハハハ。レイターにとって俺は、単なる金ヅルだからな」
「よくわかってんじゃん」
「ティリー君、先輩としておごらせてもらうよ。後輩の指導は先輩の仕事だ。きょうはよく働いてくれたから、ねぎらいたいんだ」
そう言われると断る理由がなかった。「よく働いてくれた」と言われるとうれしい。狐男を相手に自分でもよく戦ったと思う。
でも、その時気づいた。ほとんどレイターがくれた情報を武器にしていたことに。
ダルダさんが提案した。
「ロマンとスリルは電車にある」
「ったくあんたの警護はボディーガード泣かせだぜ」
「仕事じゃない。プライベートだ。文句があるなら夕飯代は自分で払え。ガハハハハ」
「ちっ」
ぶつぶつ文句を言いながらもレイターはパキ語で切符の手配をした。 旧式の電車に揺られながらわたしはレイターに聞いてみた。
「ねえ、どうしてパキ語が話せるの?」
「あん?」
ダルダさんが笑顔を近づけてきた。
「こいつらは、ほとんどすべての星系の言語を叩き込まれてるんだ」
「すべての言語?」
驚くわたしにレイターが笑顔で声をかけた。
「アンドリューム、マルバトーレ?」

反射的に『元気です。あなたはいかが?』と返事をしそうになった。故郷のアンタレス語で『ご機嫌いかがですか、お嬢さん?』というあいさつだ。驚いたのはその発音のよさだ。レイターってこんなにいい声をしていたっけ。
「ま、八年も前の話だから、あいさつぐらいしか覚えてねぇけど、おかげで銀河中の女性と仲良くなれるからな」
銀河共通語で話すレイターは軽薄で、品も柄も悪くて相手にする気がしない。けれど、アンタレス語で話すレイターの声はまるで別人のように心地よく耳に響いた。
「レイターと一緒だとどの星へ出張に行ってもナンパができるから助かるよ、ガハハハハ」
この二人は出張先で一体何をしているんだか。それにしても、語学が得意なことは間違いない。
「レイターはどんな学校に通ってたの?」
わたしの質問にダルダさんが答えた。
「こいつ見かけによらず皇宮警備官だったんだ」
「えっ、皇宮警備ってあの王室を警護する?」
声が裏返ってしまった。皇宮警備といえば、ドラマにもなる連邦軍のエリート集団だ。各星系の王室を守る皇宮警備なら、すべての言語を身につけていても不思議ではない。運動能力や体力だけでなく、知力や人格が秀でた人が選抜され、さらに厳しい規律で有名なのだ。このだらけた態度とはまるで結びつかない。
「ダルさん、俺は皇宮警備官じゃねぇっつったろ」
「ガハハハハ。お前が皇宮警備って話は女性に受けがいいんだよ。人生はスリルとロマンとジョークに満ち溢れているということさ」
わたしは肩を落とした。驚いて損をした。語学力をナンパに使う皇宮警備なんて、ありえない。全然面白くないジョークだった。
*
「ここらで降りるか」
ダルダさんが気まぐれで決めた適当な駅で降りる。大通りを離れ、雑草が茂る住宅街の路地を歩いた。
「よし、ここにしよう」
ダルダさんが足を止めたのは、本当に地元の人しか入らないであろうと思われる小さな店だった。
「お店について調べなくていいんですか?」
「調べるって何をだい?」
「評判とか、情報ネットで見れば、当たりはずれがわかりますよ」
「当たりかはずれかわかっていたら、ロマンもスリルもないじゃないか」
飛び込みで知らない土地のお店に入るなんて、不安しかない。
「大丈夫さ、きのこ料理の匂いがする」
とレイターがドアを開けるとおいしそうな香りが漂ってきた。
「こんばんわ、三人だ。パキール料理が食べたい」
ダルダさんが銀河共通語であいさつしたけれど、店の人には全く通じていない。
「おい、レイター『こんばんわ』はパキ語で何ていうんだ」
「カルデロ」
「は~い、カルデロ」
ダルダさんが手を振る。若い女性スタッフがとまどいながら丸テーブルへと案内した。レイターが現地語で話しかけると、彼女はホッとした表情を見せて現地語で応じた。レイターはにっこり笑って彼女の手を握った。

彼女はうれしそうに肩をすくめて顔を赤らめた。何を言ったかわからないけれど「町一番の美人さんに会えて光栄だ」とか大体そんなところだろう。
「よろしく、よろしく」
にやけた顔のダルダさんも一緒になって握手をしている。
じわっと浮かんできた不機嫌な気持ちを振り払って、メニューをのぞき込む。画像はなく文字だけが並んでいた。数字も現地語で価格もさっぱりわからない。
「パキール料理は何がある?」
ダルダさんの質問にレイターが指で示す。
「パキールのスープ、焼き物、炒め物、この辺が定番だな。珍しい生食もあるぜ」
わたしには記号にしか見えない文字を、ちゃんと読めていることにあらためて感心する。
レイターはあいさつ程度しかできないと言っていたけれど、店員たちと普通に会話をしていた。フェニックス号で現地語のラジオを聞いていたことを思い出した。彼は耳を慣らしていたのだ。
この記事が参加している募集
ティリー「サポートしていただけたらうれしいです」 レイター「船を維持するにゃ、カネがかかるんだよな」 ティリー「フェニックス号のためじゃないです。この世界を維持するためです」 レイター「なんか、すげぇな……」
