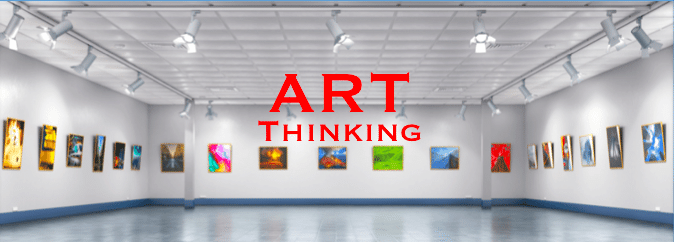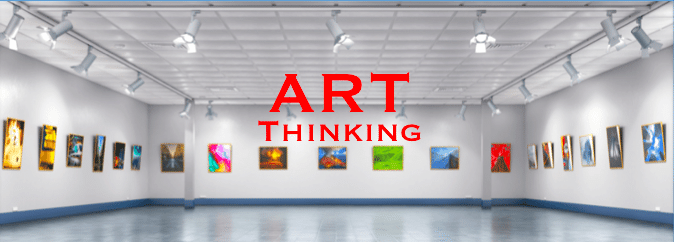【アート×テクノロジー×スピリチュアルの統合】
NAKED, INC.の「ネイキッド占い」やデジタルアートとサウナの「TikTok チームラボリコネクト」の様にアート×テクノロジー×ライトなスピリチュアルだったり、”ととのう”マインドフルネスが若者の人気スポットになっています。これはZ世代の価値観が外在的な物語ではなく内発的な欲求としてマインドフルネスに向いてる傾向をいち早く場にとして表現しているのではないかと勝手に思っています。
20代はどこにリアリティーを求めているのでしょう。
正解が見えない世の中で、彼らは肌感覚で