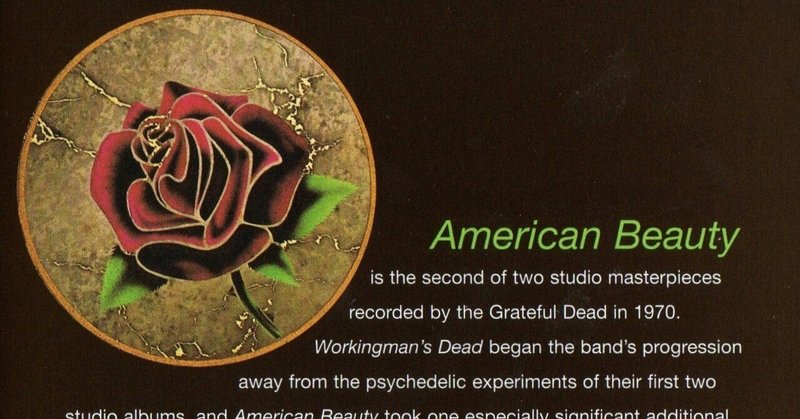
続々々・文字盤上の天使の分け前 Grateful Dead - Wake of the Flood: Angel's Share
(「続々・文字盤上の天使の分け前 Grateful Dead - Wake of the Flood: Angel's Share」)
Wake of the Floodと云っておいて、ほかのアルバムのことばかりだが、さらにAmerican Beauty: Angel's Shareを聴く。エンジニアがテイク番号を挿入できず、Not Slatedと注釈を入れる羽目になったFriend of the Devilのテイク13だが、その後のテイク14と15もなかなか興味深い。
Angel's Share版がリリースされた3枚、Workingman's Dead (1970)、American Beauty (1970)、Wake of the Flood (1973) は、それぞれスタジオも、エンジニアも異なる。いま検討しているAmerican Beautyはサンフランシスコのウォーリー・ハイダーで、スティーヴン・バーンカードが卓に就いて録音された。

Friend of the Devilは、Angel's Shareにテイク1から20まで収録されていて、これを通しで聴いていると、デッドの録音スタイルが見えてくる。ひと言でいえば、止めない、切らない、である。
テイクがブレイクダウンすると、その原因になった個所を弾き直し、きちんと弾けるようにしていたかと思うと、ガルシアがD-E-F#という3音のピックアップを弾いて、プレイをはじめてしまったりする。
アレンジでは、ウィアは(8分音符三つの「ピックアップ」部分は小節数から除外し)1小節目の2拍目からギターを入れることになっているのだが、ガルシアがスッと入ってしまっても、遅れることなく、ついていっている。ここらが、かつて体育会系バンドだった名残というか、七面倒な変拍子の曲(たとえば11拍子のEleven)を毎日毎日何時間も練習して鍛え上げ、年間三桁のライヴ・ギグをつづけてきたグループの強みで、アイコンタクトや身ぶりなどで、相手の意図を読んでいるのだろう。
とりわけ、Friend of the Devilは、ガルシア独りの「ピックアップ」ではじまるので、カウントインも無用、それこそ「無断で」はじめても大丈夫なのだ。テイクによって変化するので、テイク13に準拠してカウントすると、準備しておかないと遅れてしまうのは最初の小節の2拍目に入らないといけないウィアのみ。レッシュのベースは6小節目から、クルツマンのドラムに至っては、第1ヴァースは休みで、第2ヴァース、18小節目の途中からフィルインで入るのだから、構えている必要すらない。フロアタムにスティックを載せ、腕組みをして待っていても十分に間に合う。

たまたまこの曲のアレンジがそうなっていたからでもあるのだが、概してデッドはこういう風に、ずるずるとはじめるのを好む。ライヴでも、なんとなくはじまるのはめずらしくない。「つぎはトラッキンを唄います」なんてことはめったに云わない。カウントインすらしないことが多い。ガルシアかウィアが振り返って、ドラムの二人(クルツマン単独の時期もある)に身振りで合図するだけで入ってしまったりする。
ライヴではそれでよくても、スタジオでは困る。スレイトを入れて、録音過程を管理しなければならないのに、テイクの切れ目がわからないのでは話にならない。いや、それが世間の常識だ。でも、デッドは非常識なバンドだ。この非常識な連中の得手勝手、野放図、無手勝流のセッション・スタイルと、テープ管理、テイク管理という常識のあいだに、なんとか橋を架けなければいけないのだから、エンジニアは楽じゃない。

バーンカードのスレイトを聴いていると、これは大変だ、俺なら割増料金を請求するぞ、と思う。テープは廻っている、雰囲気を適当に読みつつ、そろそろはじめてよ、というニュアンスで、「トゥー」なんてつぶやくが、ガルシアは何かのフレーズの指の動きを確認していて入ってくれず、もう一度「トゥー」と云ってみるがダメ、さらに数秒がすぎ、しようがないとあきらめたのだろう、テイク番号を更新して「スリー」と云ってみたら、やっと入ってくれた。テイク2にはギターの断片的フレーズが入っているだけで、テイクと呼べるようなものは、かけらもないのだ。フォールス・スタートすらない!
なにごとであれ、どんな世界であれ、共同作業をはじめる前に打ち合わせぐらいはするものだ、たぶん、きみたちが自由気ままにやるのはかまわない、でも、スレイトは必要だから、こっちはきみたちのようすを見つつ、適宜、テイク番号を云うので、できるだけ間を開けず、その付近でテイクに入ってくれ、入れなかった場合は、様子を見て、番号を更新するから、そのあとで入ってほしい、なんてことを申し入れたのじゃないだろうか。
非常識なデッドの、ウナギの行き先はウナギに聞いてくれ的フリースタイルと、レコード・エンジニアリングの常識をなんとか擦り合わせようと、バーンカードは努力したに違いない。まったくプロは立派だ、デッドみたいな野生児が相手でも冷静に仕事をしている。非常識なお山の大将ばかりがひしめいている業界を泳ぎ渡るには、こういう能力が必要なのだろう。

テイク12がブレイクダウンしたあと、それぞれが自分のパートの気になるところか何かを弾いているあいだ、バーンカードは一瞬、気を抜いたか、自分の作業のことに気を奪われたか何かしたのだろう、スレイトを入れる前に気が整ったガルシアがD-E-F#を弾いてしまった。はじまった以上、もうスレイトは入れられない。
13がコンプリートしたあと、テープ始動のノイズが入っているので、バーンカードはいったんテープを止めたことになる。テイク番号宣言はしなかったが、改めて、いま終わったプレイをテイク13であるとメモし、そしてたぶん、「スレイトを入れる前にはじめないでくれ」とガルシアに注意したのではないだろうか。
そう想像する根拠はある。つぎのテイクのために、バーンカードが「フォーティーン」と云った直後に、ウィアが「フォーティーン・トゥー」と嫌がらせのようなことをつぶやいて笑いを漏らし、ガルシアも、ハッ、と小さく笑っている。そして、このテイクはイントロだけでブレイクダウンした。気が乗らなかったのだろうが、同時に、俺はそういう風に邪魔されるのは好きじゃない、とバーンカードに警告したのだろう。
もちろん、ウィアの態度は子供っぽく、プロフェショナルではない。しかし、ものを作る人間というのは、なによりも気分をだいじにする。気が整ったから、それを乱さぬように、ガルシアは何も云わず、たぶん身ぶりもせず、ひとりで弾きはじめた。これはこれで、仕方ないと思う。頭の流れ、心の流れを乱すのを嫌う気持は痛いほどよくわかる。録音技術のことに頭を煩わせていたら、ギターなんか弾けないのだろう。
思いだしたことがある。フランク・シナトラは「ワン・テイク・マン」だった。スタジオに入る前に、専属のピアニストと入念にリハーサルをし、完璧に唄えるように準備してから、おもむろに予約し、夕食後、ボディーガードやら取り巻きやら愛人(それがミア・ファーロウだった時期もある)やらを率いて、さっそうとスタジオ(リプリーズ時代はつねにブライアン・ウィルソンやスナッフ・ギャレットと同じユナイティッド・ウェスタン・リコーダー)に入る。一時期は、卓に就くのは「現代サウンド・レコーディングの父」、ユナイティッドおよびユニヴァーサル・オーディオの創業社長、ビル・パトナム自身でなければいけない、という契約まで結んでいた。

シナトラは自分以外の人間がミスをするのを許さなかった。セッションを止められるのはフランク・シナトラただひとり、神である彼がミスをしたら、誰にも何もできない、そこでホールトするしかないが、彼以外の人間がミスをして、フランク・シナトラの唄を止めるのは絶対に禁じられていた。
プレイヤーがミスをするのはもちろん、エンジニアが、機材や技術の問題でリテイクを求めることもできない。スタッフはプレイヤーの椅子をチェックし、軋み音がするものは交換させたとハル・ブレインは証言している。機材異常なし、リハーサルでバンドのプレイも完璧、そうなってはじめて、ブースで談笑していたボスはフロアに降り、一回だけ、完璧に唄い、またブースに戻り、プロデューサーやエンジニアに「OKだな」と確認し、つぎの曲を唄うために、またフロアに降りた。

シナトラは極端だし、同じようなアティテュードをとれる立場にいるアーティストはごく一握りだっただろう。しかし、心の中では、誰もがシナトラと同じような気分だったに違いない。録音の時は横暴な王様であり、百パーセント思うままにやりたいのが人情だ。
しかし、これは仕事で、みな契約で縛られている。スタジオの世界はルールに支配されており、そのルールの運用を司るのはプロディーサーとエンジニアだ。ハル・ブレインは、はじめてスタジオでプレイした時、スネアを思いきりひっぱたいたら、エンジニアに「お前の目の前にぶら下がっているものがわかるか。そいつはマイクロフォンというもので、音を拾うためにそこにある。馬鹿デカい音を出すんじゃない! メーターが吹っ飛ぶだろうが!」と怒鳴られたという。ハル・ブレインはルールを破り、セッションを中断させた罪を問われたのだ。
デッドはWBと契約し、ストーンズがアメリカの壁を破るのにおおいに助力し、やがてジェファーソン・エアプレインにビルボード・チャート・トッパーをもたらすエンジニア兼プロデューサー、デイヴ・ハーシンガーをあてがわれ、ハリウッドまで出向いてノース・ヴァイン・ストリートのスタジオに入った。「RCA世界音楽中心スタジオ」(RCA Victor's Music Center Of The World)という世にも御大層な名前を持つ大スタジオである。
そして生まれたデビュー盤、Gtateful Deadというエポニマス・タイトルのアルバムは、躍動感のまったくない、死んだようなテイクばかりの退屈な代物だった。

1968年、夏休みを控えたある日、自分のバンドのことで相談があって、小学校時分のヴェンチャーズ仲間の家に行ったら、そのデッドのデビュー盤があり、たいしたことはないぜ、と云いながら、彼はあのLPを聴かせてくれた。1965年のある夜、ヴェンチャーズのKnock Me Out!を買ったとき、電話で、すごくいいんだ、いまから聴きに来いよ、と熱心にわたしを誘った子供が、「な、つまんないだろ?」と云った。うん、面白くない!
たぶん、あの退屈なデビュー盤を生んだ、ハーシンガーのハリウッド式のリギッドなスタイルが、デッドにはトラウマになったのだろう。あんなやり方で音楽なんかできるかバカヤロー、とガルシアは怒ったに違いない。
たぶん、それがあったので、セカンドでは、もう自分たちの思い通りにやると決めてスタジオに入り、デイヴ・ハーシンガーに、彼のようなプロフェショナルからしたら常識外れのたわごとにしか思えない要求をあれこれ出し、アーティストはプロデューサーの指示通りに動くのが当然とされた時代を生きてきたヴェテランを激怒させた。
1967年から、スタジオ盤、ライヴ盤とリリースを重ね、とにかく、自分たちのやり方を貫ぬこうとデッドは戦った。当然、会社との軋轢はあっただろう。しかし、時代はアーティスト主導へと移行しはじめたサイケデリック・エラ、保守の牙城はひとつひとつ崩され、デッドは望んだような果実を受け取りはじめていた。
バーンカードとデッドが、ちょっと険悪な関係に陥りそうになりながらも、とにかく、いまでも代表作の一枚と大かたが認めるアルバムを完成させたのには、やはり感嘆する。

バーンカードが録音したAmerican Beautyにはスレイトがあった。いつもこうなら、Angel's Shareシリーズだけに見られる、スレイトのあるなしの注釈などというものははじめから無用だ。いつもはスレイトなんか入れずに済ましていたから、こういう変則的な注釈が必要になったに違いない。
もう疑問の本丸は落としたと思うが、では、デッドはスレイトなしで、どうやって録音していたのか、という小さな疑問が残る。根問いなのだから、これも考究しておきたい。
(「続々々々・文字盤上の天使の分け前 Grateful Dead - Wake of the Flood: Angel's Share」へつづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
