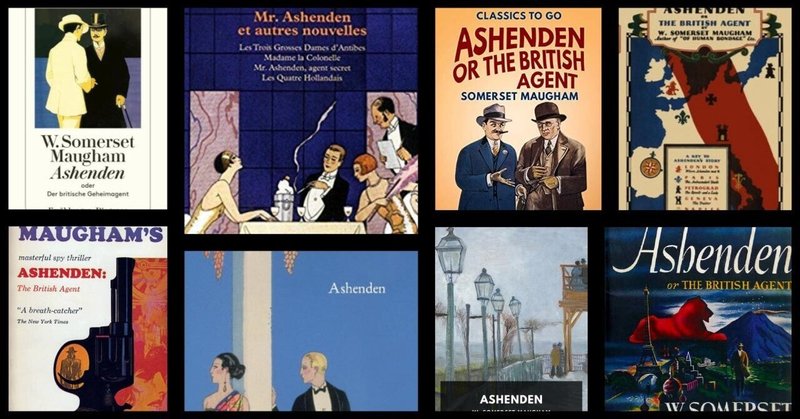
古典ミステリー初読再読終読:サマーセット・モーム『アシェンデン或いは英国諜報員』その3
(「古典ミステリー初読再読終読:サマーセット・モーム『アシェンデン或いは英国諜報員』その2」よりのつづき)
◎寝返りの寝返り
(承前)そして、そのつづきの、アシェンデンがグスタフに「調査中」だと云った、やはりスイスにいるスパイを描く「裏切者」(The Traitor)という章も深い味がある。
その駐在員が住むLucerneまたはLuzern(現在はルツェルンと表記するらしいが、スイス・ドイツ語発音の音声ファイルを繰り返し再生しても、英語発音と同じルザーンまたはルツァーンにしか聞こえなかった。よって原綴のまま)のホテルに入った。英国情報部検閲課に勤めている、というふれこみにするよう、「R」に指示されていた。

今回の「行確対象」はグラントリー・ケイパーというイギリス人で、彼はドイツ人の妻とフリッツィーという名のブル・テリアともにそのホテルに滞在していた。
ケイパーがドイツに寝返っている証拠はすでにあがっていた。英国情報部の「R」は、ケイパーを金で釣って、逆にドイツ側に偽情報を流す二重スパイとして利用したいと考えたのであって、アシェンデンの任務は、それが可能か否かを検討し、できなければ「処分」の判定を下すことだった。

ロシアから亡命してきたスパイが、本当の亡命者なのか、それとも西側情報機関に潜入を試みる二重スパイなのかを見極めようとする、息詰まる尋問劇。何も知らずに二本立ての同時上映としてこの映画に遭遇し、吃驚した。音楽はエンニオ・モリコーネ。ダーク・ボガード助演。
二重スパイ、寝返り、というのは、現代諜報小説のもっとも重要なテーマで、諜報の世界は善悪ではなく、利益不利益を基準に成立していることが明確に語られているあたり、やはり転回点となった小説だけのことはある。
◎ドイツ女、ベートーヴェン、愛国、戦争
しかし、モームの視線はつねに人々に向けられている。このイギリス人夫とドイツ人妻の夫婦、とくに妻のほう、他民族の目には、きわめてドイツ的な心性の持ち主に見える女性は興味深い。いや、二人の依存関係、「愛」のありようが興味深いというべきか。
古典ミステリー初読再読終読:サマーセット・モーム『アシェンデン或いは英国諜報員』でふれた英国大使の若き日の愛人も、ハスキーな声だけが魅力の醜い三流アクロバット芸人だったが、このドイツ婦人もやはり外見の魅力はあまりないようだし、夫のほうも容姿、人柄ともに魅力的には描かれていない。
アシェンデンは疑惑の人物ケイパーが自分にアプローチするように仕向け、病気療養中で暇なので、ドイツ語に磨きをかけたいと偽り、家事も得意だし、教養もありそうで、ドイツ人らしい他民族への軽蔑を隠さない、この気難しい太りじしの四十女に、毎日、語学のレッスンを受けることになる。
彼女のショーヴィニストぶりは、一次大戦敗戦の灰からナチズムが生まれることを、後年の読者に読み取らせる。いや、『アシェンデン』が発表されたのは1928年、この年、ヒトラーはすでにナチス党を再建し、30年の選挙で第二党に躍進させる。
モームはすでに、ドイツの狂信が暴発する未来を見ていたのかもしれない。やはり英国人だ、エリック・アンブラーとまったく同じようにドイツ人を見ている(「古典ミステリー初読再読終読:エリック・アンブラー『あるスパイの墓碑銘』+『シルマー家の遺産』 その2 」)。
彼女は多国語を操り、美術、音楽、文学の知識も豊かで、時に、他民族の美点を認めることはあっても、ドイツ民族の優越という一点は決して譲らない。ピアノの腕も素晴らしく、ある時、ドビュシーの小品を弾いてみせる。
「フランス人が書いた至って軽い曲なので、彼女はいかにも軽蔑したように弾いたが、それでも、その曲の雅致と優美への腹立たしげな賛美をタッチに込めた。アシェンデンの称賛の言葉を聞くと、『退廃的な民族の退廃的な音楽ですわね』と彼女は肩をすくめ、ベートーヴェンのソナタの冒頭の派手な和音を力強く叩きだした」
これには笑った。さすがはモーム。「腹立たしげな賛美」(an angry appreciation)などという洞察、形容は、二流の作家の頭からは断じて生まれない。

ドビュシーは、世界が20世紀音楽(ひとりクラシカル・ミュージックのみならず、4ビートや8ビートも含む音楽の総体)へと舵を切った、大きな転回点となった作曲家と見ているが、ベートーヴェンはいつ聞いてもわたしにとっては「あくび指南」でしかない。
ティーゲルⅡ戦車やユンカース急降下爆撃機は傑作かもしれないが、そのようなものをつくる心性は、音楽、美術、文芸には転用できない。だから、このドイツ女のショーヴィニスティックな傲慢には心底苛立った。
◎スパイの視線/作家の視線
しかし、アシェンデン=モームは辛抱強い。
「アシェンデンは善なるものを賛美するが、だからといって邪なるものに憤慨することはない。時に冷たい人間だと思われることもある。人間に関心はいだくが、誰かに愛着することはあまりなく、たとえ愛情をいだいても、その人物の長所と短所を冷徹に見て取るからだ」
アシェンデンの物語の基盤はここにある。感情よりも理性の勝った、冷静な観察者として人々を瞶め、読み取ったことを客観的に記録しようとしているのだ。
このケイパーという男の裏切りのために、若く有為なエイジェントがドイツ人に処刑された疑いが濃厚であるにも拘らず、アシェンデンはドイツ女の傲慢さとイギリスへのあからさまな敵意にも、まったく反応せず、ケイパーという男を、そしてこのちょっと不思議な夫婦の関係を冷静に観察しつづける。
妻のほうはアシェンデンも理解でき、したがって読者にもわかるように描かれている。きわめて知的だが、女としての魅力は薄い、盲目的愛国者で、たぶん、男に慕われたことなどなく、はじめて彼女に愛情を示した男であるがゆえに夫を深く愛している、ぐらいに要約できる。

これまた裏切りの物語で、一読、大いなる感銘を受けた。
しかし、夫のほうはどうにも枠に収めづらく、アシェンデンは悩み、したがって、読む側もこの男がよくわからない。太っていて容貌も醜いが、ひどく愛想がよく、親切で、植物を愛し、醜い妻を心の底から尊敬し、愛し、依存しているように見える。
金が欲しくてドイツのスパイになったようには思われず、なぜ彼が祖国を裏切ったのか、アシェンデンにはわからない、したがって、読者もそこが理解できない。
それでも、読んでいて、苛立つことはなかった。「理解しようとする」ことと「理解する」ことの、どちらが重要かと云えば、「理解しようとする」ことのほうだ。考えること、この世界の核心へと進もうとする意思を持つことが重要なのであって、その結果は副産物にすぎない。
モームのこの書き方は好ましい。情報部のボスなら、よけいなことを考える前に、スパイとしての仕事をしろ、というだろうと思いながらも、目の前の不可解な人物の心底を理解しようとあがく、スパイである以前に作家であるアシェンデンの姿に興趣を感じる。
◎二重の罠
ケイパーを逆スパイとして利用できる見込みはないと判断したにもかかわらず、アシェンデンはどういう手を打つべきか思い悩み、手をこまねいていたところ、ケイパーがふいにベルンに出かけることになった。ドイツ情報部と接触するのだと読んで、アシェンデンは現地エイジェントをベルンに差し向け、ケイパーが何らかの指示を受けたことを確認する。
そして、見込みどおり、ケイパーはアシェンデンに、英国で仕事をしたい、できれば、(アシェンデンが「カヴァー」として使った)情報部検閲課で働けたらいいのだが、と持ち掛ける。
その瞬間、アシェンデンは、自分の真の役割を覚って愕然とする。彼の任務はケイパーを観察して、二重スパイとして利用できるか判定することではなかった。彼自身がケイパーをハメるための餌、罠として配置されたのだ。
何も成果を上げられないまま、べんべんと日を過ごすことに後ろめたさを感じていた自分の愚かさに、アシェンデンはやっと気づいた。彼はただここにいて、獲物が落ちてくるのを待っていればいいだけの道具にすぎなかったのだ。「R」はケイパーとドイツ情報部だけでなく、自分まで騙したのだとわかって、アシェンデンは笑うしかなかった。
アシェンデンは「R」に報告書を上げ、ケイパーのヴィザを速やかに発給するように依頼するいっぽう、ケイパーには情報部への懇切な紹介状を与え、英国へと送り出す。
一日、一日とたち、ケイパー夫人はクック旅行社へと足を運んでは、夫からの便りの有無を確かめるが、待てど暮らせど何も届かず、彼女はしだいに憔悴し狂乱しはじめる。
この夫婦の愛は本物だと見たアシェンデンは正しかった。そして、狂乱するケイパー夫人とは対照的に、彼はクック旅行社で「R」からの連絡を受け取り、静かにつぎの任務に向かう。

◎文芸の価値
諜報小説がシリアスな人間観察の記録となりうることをはじめて世に示したものとして、やはり『アシェンデン』は一読の価値のある物語であり、いくら観察、考察をしても、読み切れなかった部分は謎のままとするモームの誠実さは非常に好ましい。
アシェンデンは自分はあくまでもニュートラルだと自認し、先入観を排するようにつとめ、観察対象を断罪することもない。そこにモームの作家としての矜持を感じた。いい小説、いい読書だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
