
赤い風車 その2 ジョン・ヒューストン、ジョルジュ・オーリク、トゥールーズ・ロートレック
◎「古典のお勉強」並びに学校図書室と新宿「蝎座」のこと
子供のころは、なにごとにつけ、古典というものを避ける傾向があった。
ミステリーを読むのでも、ヴァン・ダインだの、クリスティーだのはお歯に合わないような気がして避けたし、中学生になり、真新しい学校の図書室で真新しい書架に並んだ真新しい本を漁った時も、ドストエフスキーだの、トルストイだの、スタンダールだの、ジイドだのというのは勘弁願って、たとえば、ノーマン・メイラー『裸者と死者』、ヘンリー・ミラー『北回帰線』、グレアム・グリーン『落ちた偶像』、さらにはぐっとくだけて石坂洋次郎『陽のあたる坂道』『河のほとりで』『あじさいの歌』とか、わりに近年のもの、少なくとも第二次大戦後に書かれた小説を手にした。
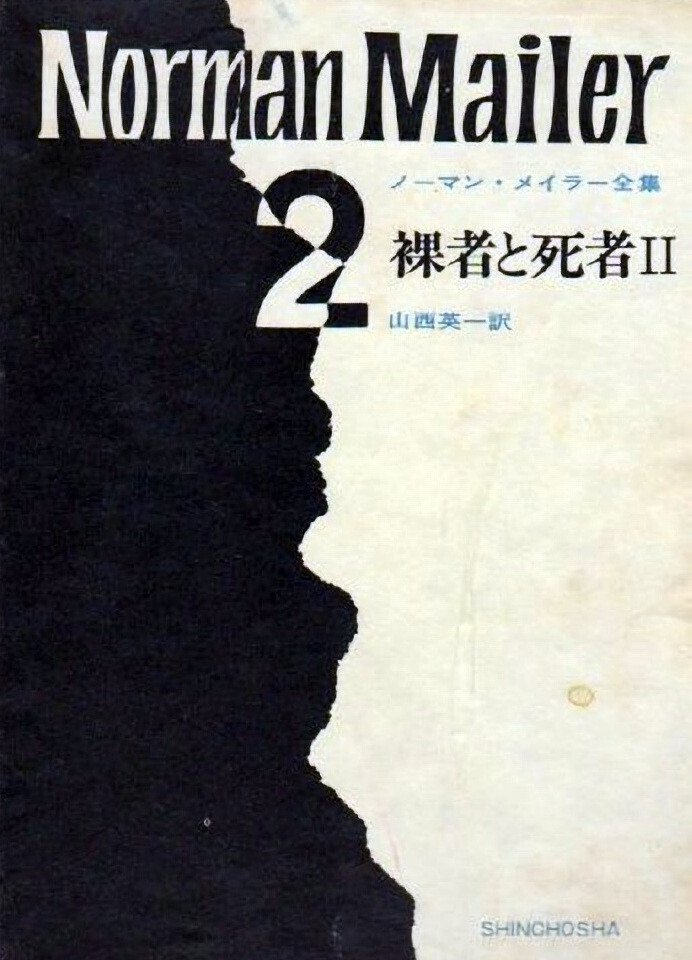
それにしても……まあ、グレアム・グリーンはいいとしよう。しかし、まだ中学一年生しかいない新しい学校の図書室に、いきなりヘンリー・ミラー全集だの、ノーマン・メイラー全集だのを置いてしまう尖鋭的な選書をしたのはどなたなのやら、たしかめておけばよかったのに、もはや手遅れ。
思いだした。高等部に進んでから、新宿文化の地下にあった小劇場・蝎座(星座名はふつう「蠍座」と書くが、あそこは「蝎座」だった)のゴダール・シネマテークに通い、その後、あれはどこの館か記憶していないが、近作の『軽蔑』を見て、図書室でアルベルト・モラヴィアの原作を借りた。母校の図書室はあの時も選書の尖鋭性を失っていなかった!
ついでにもうひとつ思いだした。蝎座の、夜になると酒場になってしまう変な劇場、というあり様が面白くて、うっかり父親にそのことを話したら、こっぴどく怒られ、そんなところに二度と行ってはいけない、と言い渡された。

昼間、酒は出さない時間帯に行っていたのだが、「アングラ演劇」なるものが評判を呼び、大人は眉を顰めていた時代なので、アンダーグラウンド演劇の小劇場だった蝎座に、何か子供には危険なものを感じ取ったのだろう。
いや、大学に入ってから、やはりアンダーグラウンド演劇のひとつだった天象儀館の芝居に通ったが、その時はもう文句は云われなかった。わが父も十六歳と十八歳では、扱いを変えていたわけだ。

映画の古典は、とくに避けて通ったわけではなく、高校に入ってからは、夏休みに京橋の、火災に遭う前の、古い建物のフィルム・センターに通って、おきまりの古典、『戦艦ポチョムキン』『アンダルシアの犬』『国民の創生』『イントレランス』なんてものを見た。
フィルム・センターの後身である現在の国立映画アーカイヴは娯楽映画ばかりかけているようだが、大昔、まだ「フィルム・センター」だった時代には、あの手のお堅い映画ばかりやっていた。まあ、チャプリンのサイレント特集なんていうのも見たが、それにしても、やはりおそろしく古い!
◎なにごとも古典回帰が年寄りのWay of Life
いまどきは、「古典映画」を見るといっても、こういう、いかにも「お勉強」のようなことはしないのだろう。それでいいんじゃないだろうか。わたしは三歳から十代までは「シネマディクト」(cinemadict、この言葉ももやは誰も使わない!)で、高等部に上がる直前ぐらいからシリアスな映画も見るようになっていたが、それでもなお、あのフィルム・センター通いは高校生の夏休みの活動としては、ちょっと苦痛だった。楽しくないことはしないほうがいい。
子供の時は当然ながら、古めかしいものを好まないので、音楽に関しては、自分が聴きはじめる時代より前のものをわざわざ買ったのは、チェック・ベリーのベスト盤一枚だけ、あとはすべて同時代のものだった。

映画は、そもそも、近所ではそれほど古いものは見られず、いわゆる「名画座」も、たんに月遅れの映画をかける三番館というだけで、古い映画を見るなら、東京の名画座、たとえば並木座あたりに行かなければならなかった。いまのように、家にいて、本邦未公開のものですら、古い映画をいくらでも見られるのは驚くべきことだ。
IT社会だとか、AIだとか、ろくなものではなく、これから、人間は疎外されるいっぽうで、オーウェルが考えたよりずっと悪い世界になっていくだろうが、ディジタル技術とウェブのおかげで、昔の本や映画や音楽を、欲しいと思ったその瞬間に入手できるようになったのは、年寄りにとってはじつにありがたい。
これから、スマートフォンという首輪をはめられ、一円の収支に至るまで監視されるディジタル社会に幽閉され、奴隷のように生きねばならない若い人たちにはほんとうに申し訳ないと思うのだが、われわれの世代は、ディジタル化のいい部分、恩恵のほうを享受して死ぬことができる。
◎ロートレック的美術によるロートレック映画
「赤い風車:ディック・コンティーノ発、ブライアン・ウィルソン&斎藤高順経由ジョン・ヒューストン行 その1」に書いたように、IAでもらったディック・コンティーノのAn Accordion in ParisというLPのノイズ除去をしてみたら、久しぶりのThe Song From Moulin Rouge (Where Is Your Heart)が素晴らしいレンディションだったので、この際、この曲が書かれた映画そのものを見ておこうという気になった。

はじまったとたん、こいつはいいぞ、と思った。タイトルがきちんとデザインされているのが嬉しい。ムーラン・ルージュという店を有名にしたロートレックが主人公なので、タイトルバックはそのタブロー、リトグラフ、デッサンなどが鏤められているのだ。
また、クレジットは描き文字だし(昔はみなそうだったのだが!)、その書体はロートレックのポスターのレタリングを模しているのも大いに好もしく、この半世紀の映画にはない、昔の映画ならではの魅力があふれている。


タイトルで流れる音楽は、大作映画の序曲のような組曲的構成で、The Song from Moulin Rougeのメロディーは、そのごく一部としてほんの数小節がコラージュされているにすぎない。昔の映画ではよくあったメイン・タイトルの構成方法で、可もなし不可もなし、ごくふつう、というあたり。
タイトルを見ていてそういう予感がしたが、話に入っても、予想通りで、画面構成、色使いはどこまでも楽しい。ショットはムーラン・ルージュの赤い風車が回転するファサード、入口付近の雑踏、階段、オーケストラ・ボックス、二階席から階下、そしてダンス・フロアのショウ、とつながれていくが、このセットも衣裳も人々も、徹頭徹尾ロートレック的で、たちまち引き込まれた。

◎幸せな「また四月がめぐり来て」
タイトルバックでは大々的にフィーチャーされてはいないものの、あの主題歌がどこかで印象的に使われるはずだと思いながら見ていたが、待つほどもなく、冒頭のムーラン・ルージュ内部のシークェンスで、ホセ・ファーラー演ずるロートレックが登場して数ショット後、ジャ・ジャ・ガボール(「ザ・ザ・ガボール」とは発音しない!)演じるスター・ダンサーのジャン・アヴリルが、ショウの一部として唄う。

じっさいにはジャ・ジャ・ガボールではなく、ミュリエル・スミスというシンガーがスタンドインで唄ったのだそうだ。本式の訓練を受けた正しい発声をしていて、そういうのはふつう好まないのだが、この人の声には劇場を力で制圧するような、オペラ歌手の通弊である不愉快な野太さはなく、やや細めの愛らしい声でクルーニングしているので、気分よく聴ける。
しかし、これは歌詞が違う、いや、わたしが知っているThe Song from Moulin Rouge (Where Is Your Heart)という曲とは異なる歌詞で、ヒット・ヴァージョンの持つ寂しげなニュアンスのない、「また今年もあなたと春を迎えられて幸せ」というラヴ・ソング、というより、たぶん、長年連れ添った夫婦の愛の歌だ。

調べてみると、1952年の映画に使われたのはIt's April Againという歌詞で、まあ、仏語のアヴリルは英語のエイプリル、四月という名前のダンサーだから、四月という歌詞にしたのだろう! そして、映画公開の翌1953年に、Where Is Your Heartという歌詞が新たにつくられた。
この年に録音されたThe Song from Moulin Rougeを探すと、一月にパーシー・フェイスが録音し、The Song from Moulin Rouge (Where Is Your Heart)というタイトルでリリースし、ビルボード・チャート・トッパーになった。
うちにあるパーシー・フェイスの編集盤に収録されているこの曲の歌詞は、映画とは異なる、お馴染みの、あの悲しいものだ。この改作詞による録音はパーシー・フェイスが最初なのだろう。パーシー・フェイス・ヴァージョンが大ヒットしてこの曲が一気に有名になり、その後のヴォーカル・カヴァー(インストゥルメンタル・カヴァーも多数ある)では、It's April Againは使われなかったと思われる。うちには、タイトルをHeartのほうにしたものが20ヴァージョンほどあるのに対し、It's April Againというタイトルの曲はまったくない。

◎女の心と画家の心
主題歌の歌詞というのは微妙なものだ。主題歌が映画の内容を「象徴」するのならかまわないが、「説明」してはいけないので、最初に書かれた歌詞がWhere Is Your Heartだったら、ジョン・ヒューストンは却下し、書き直しを命じただろう。それほどに、Where Is Your Heartは物語にぴったり添った説明になってしまっている。
Moulin Rougeは、ロートレックの伝記ではなく、あくまでもロートレックをモデルにした「お話」で(映画の中ではロートレックのハンディキャップは事故が原因となっているが、じっさいには病気のために成長が止まったのだという)、映画の中のロートレックは二度の恋をし、二度とも手ひどく傷つき、酒におぼれて命を縮めてしまう。
最初の女は街娼で、警察に目をつけられた夜、ロートレックに、連れのふりをしてくれと頼んだことから関係がはじまる。ロートレックは伯爵の息子、女は娼婦、「釣り合わぬは不縁のもと」という古めかしい言葉があるが、これは19世紀末の話、身分の違い、生まれ育ちの違いは決定的に重要だ。そして、ロートレックには子供のような矮躯という大きなハンディキャップがある。画才などより人並みの体を欲していただろうが、彼をこの世につなぎとめていたのはその画才だった。

原作者または脚本家はロートレックの絶望に重きを置いているのだろうが、わたしにはこの娼婦の心のほうが近しいものに感じられた。彼女は「陋巷」の生まれ育ちで、収まり返ったふつうの人びとの生活にはなじめない、というか、どちらかというと、憎しみの目で見ている。そしてなによりも、まともな住まいでまともな生活を送るのは、牢獄に入れられるも同然と感じ、どうしても、ロートレックの庇護のもとに暮らす安穏から逃げてしまう。
彼女の葛藤、引き裂かれた自我は痛々しい。できるものなら、ロートレックとともに安逸な暮らしをしたいのだが、生理的にそれを跳ね除けてしまう。彼女はロートレックの不自由な脚、ふつうではない矮躯を口汚く罵り、ロートレックの怒りを引き出す。

明示的に語られるのは、彼女は情夫のためにロートレックから金を引き出そうとしただけで、ロートレックなど嫌いだった、ということだが、本当の理由はロートレックの歪んだ体ではなく、彼女の心であり、彼女自身もそれを知っている、と解釈した。自由を売って、未来の伯爵夫人になるなどというのは、どうしても我慢できなかったのだろう。

◎赤い風車主題歌のポップ・スタンダード化
子供のころのあれこれを思いだすのは年寄りのつねで、当然、寄り道は長く、わからないこと、知らないことにぶつかるとつい調べてしまう人間だし、また、現代はウェブという格好の調査探索手段があり、ムーラン・ルージュに関しても、じつにさまざまなことを調べた。
また、やみくもに蒐集する性癖もあり、検索したら、わが家には30種ほどのThe Song from Moulin Rougeがあって、それもすべて聴き、さらにはその向こう側、連想した曲も追いかけた。
ジョルジュ・オーリクの手になるこの曲が、映画から離れて、ポップ・ソングとして独立したのは、パーシー・フェイスとマントヴァーニの二種のカヴァーによるのだが、その点についても調べ、考えた。
ムーラン・ルージュのことを書こうと思ったときは、ここまで風呂敷を広げるつもりはなかったのだが、かくてはやむなし、あと一回、あるいは二回、赤い風車の周りをぐるっと回転しようと思う。(「赤い風車 その3 ロートレックとジャンヌ・アヴリルの「日本の寝椅子」、溝口健二、山田風太郎」につづく)

