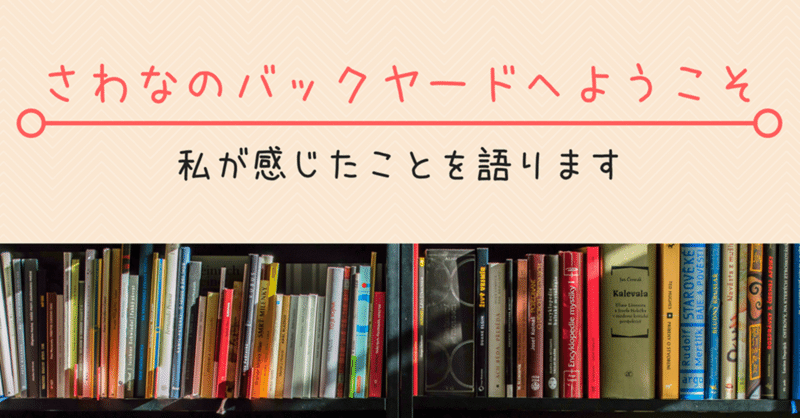
「誰かに見てもらう」は創作の手段にすぎない
自分が作ったものを誰かに見て貰いたいし、出来ればたくさんの人に見てもらいたい。さらに感想も貰えたら嬉しい。だけど、それが創作の全てや着地点ではない気がする。
先日、下記noteを拝見し共感するところがあったので、自分の創作について振り返りつつ考えをまとめておきたいと思う。
▼参照note
「感想はなくていいです」という話。
必ずしも筆者さんと全て同じ考えというわけではないのだが、良い気づきを頂けて感謝している。その気づきをnoteのタイトルにした。それが「誰かに見てもらうは創作の手段にすぎない」だ。
自分だけが楽しむことから始まった創作
内容やクオリティはさておき、私の創作歴は小学生から始まった。
大学ノートにオリジナルキャラのイラストを描き、自分が考えた衣装を着せてみたり。そのオリジナル衣装ランキングとか勝手にノートの中で企画をやっていた。もちろん、ひとりで。自分だけが楽しむために。
RPGゲームをプレイしている時にワクワクっとしてきたら、オリジナルの魔法やモンスター、ダンジョンを考え、ノートで冒険が出きるようにすごろくの図を書いた。魔法を放った時のビジュアルイメージや消費MP、ダメージポイントなどの効果も考え、とにかくこだわっていた。ひとつやふたつではなく何ページにも渡って沢山オリジナル魔法の設定を書いた。合体魔法や高等魔法など、体系も考えていた。
これって何のため?
と言ったら自分のためなのである。自分が楽しむために自己満足で自分勝手に書いて楽しんでいた。
それらのノートは誰かに(特に親)見つかる恥ずかしくなり大学進学と共に捨て去ってしまったが、記憶には残っている。もちろん、創作の詳細までは忘れてしまったが。
「誰も見ることがない」が当たり前
小学生当時は誰かに見せることはなかったし、同人誌を作ってコミケで販売しない限り創作物が人の目に触れることなんてない時代だった。
私は特に行動を起こさなかったし、親にすら見せてこなかった。インターネットも無かったので不特定多数の誰かに見せるツールも場所も無かった。
現在は自分の考えをオープンに出来る場所があり、それを誰でも見れる場所がある。そんな時代が来るとは小学生時代は思わなかった。
誰かに見せるという世界線ではいなかったから、誰かに見て貰う嬉しさも、誰かに見られるプレッシャーも、そんなものは自分の中に存在しなかった。「創作して楽しい」それだけしかなかった。
同級生に見せていたシナリオ処女作
中学生になると、自分だけで楽しんでいた創作を誰かと共有することになる。
当時私は、好きなRPG(ドラクエ、FF)に影響され、オリジナルファンタジーシナリオを書いていた。入学時の自己紹介で「オリジナルのストーリーを創るのが趣味」と話したところ、同じようにRPG好きな同級生から声をかけられた。それがきっかけ。
正直見せるのは怖かった。恥ずかしさもあった。
「創作したストーリーを気に入ってくれなかったら……?」
「自分の趣味を幻滅されたら……?」
受け入れて貰えるか不安が強かったが、それ以上に「見せてくれ」と強く言われバインダに閉じていた紙の束を渡した。(たぶん、ルーズリーフに書いていた)
不安とは裏腹に嬉しい反応
「楽しかった!」
「続きまた読ませて」
「楽しいね」
天にも昇るようなありがたい感想を貰った。誰かに見せる世界は想像以上に暖かくて優しかった。
社交辞令かもしれないけど、もともと悪い印象を与えてしまう不安からマイナス評価を予想していたので、プラスの時点で御の字だった。
作品を見てもらえるってこんなに嬉しいことなんだ
受け入れて貰えた!
自分の創作を褒めてもらえてとても嬉しかった!
幼稚園生の時にアトリエ教室で描いたトビウオの絵(写生)をお母さんがとても褒めてくれた時のことを思い出した。小学生になってからは褒められることが恥ずかしくて親からも避けてきたので、素直に嬉しいと思った。
創作を通じて生まれた繋がりが広がっていく
その後、私は誰かに見せることで得られる恩恵をさらに受けることになる。
イラストが得意な友人が私の創作キャラのデザインを描いてくれたり(今で言うファンアート?)、創作キャラについて語り合ったり(今で言う推し語り?)、自分の創作から世界が広がって新しい繋がりも生まれた。
見てくれる人を意識するように
そこから私は見る(読む)人を意識した。詩を作っても自分で製本して詩集を作ってしまうくらい見せ方に工夫し、創作にのめり込んだ。友人や信頼できる先生に読んで貰い、アンケートを取ってどの作品が心に響いたか反応の調査もしていった。
基本は自分が楽しむための創作ではあるんだけど、人に見せるともっと楽しいことに気づく。見てもらう誰かがいることで筆が進むし、それを何としてでも完成させようとモチベーションが生まれる。
ただ、その時代は長く続かず…。高校進学で友人と離れてしまったことや環境変化をきっかけに創作は止まってしまう。
・ ・ ・
そこから現在までの話は割愛するが、過去の自分を振り返ってみると、自分の中で「誰かに見て貰う」は創作モチベーションを保つための手段なんだなぁと、気づいた。
手段が目的にすり換わらないように
本題に入ろう。
【「誰かに見て貰うことは手段に過ぎない」という解に辿り着いた】
誰かに見て貰い、褒められると嬉しくてそれを励みにに頑張りたくなることは確かだ。だが、褒められること自体が活動目的になってしまわないようにと強く思う。
・たくさんの人に見て貰いたい
→閲覧数増やしたい。
・評価して貰いたい
→感想欲しい。ブクマ・いいね増やしたい。
自分の作品を客観的に評価する指標のひとつと捉えるのは良い。それだけ、それを得ることが目的になってしまうと手段が目的に入れ替わってしまう。
【他人本意な創作は楽しいだろうか?】
たくさんの人に見て貰うための創作、評価されるための創作は果たして楽しいだろうか?
その中に自分のやりたいことはあるだろうか?
自分のやりたいことと一致すれば良いが、相違があるときっと面白くなんてないだろう。
【反応が少ないとかの理由でめげないこと】
約4年の活動で、ある程度の人に見て貰えることや反応を貰えることが当たり前のように感じることろがあった。以前より反応が少ないとか多いとか、正解のない本質ではないことに一喜一憂してしまうことがある。
閲覧数が少ないとか、感想が少ないとか、そんなことで落ち込んでいる自分は小さいなぁと思ったし、そんなことは杞憂だ。小学生時代は誰にも見せなくとも何かを作り出し、自分で楽しんでいたはずだ。
自分から外に向かって起こす行動、外から自分に向かう反応は、創作を楽しむための手段に過ぎない。自分は自分の信じた道を進めばいいんだ。周りが何と言おうと!
「誰かに見せたい」は創作モチベーションを引き出すひとつの手段
この記事は自戒のため、原点を忘れないために書いた。改めて「誰かに見せること」について整理していきたい。
【何のために他人に見せるのか?】
Answer:作品を完成させるため。クオリティを上げるため。
Why:読者(作品を見る人)を意識しないと完成度が上がらないどころか完成すらしない。読者を意識すると創作モチベーションが上がる。
【モチベーションを上げ、リアル生活に創作を組み込んでいくために】
学生時代は寝食忘れて好きなことにのめり込んだけど、今の自分にはやらなきゃいけないことがたくさんある。創作の優先度をあげて日常生活にうまく組み込むには、誰かに見せたい欲をモチベーション(目標)にして書く。そうすることで頭の中で未完のまま終わってしまう作品を外に引っ張り出して具現化することができる。見せたい欲は自分の中で眠らせたままにしないための手段だ。
【誰かに見せるのは作品を創るため。完成させるための手段に過ぎない】
*
改めて行動指針のまとめ
創作の目的:自分の想像したことを思う通りに納得する形に作り出すこと
投稿すること:作品を形にし、完結させ、クオリティを上げるための手段
閲覧数・ブックマーク・いいね数:後からついてくる結果
台本使用・感想コメント:自分の成果物に対して得られる対価のひとつ
評価されること自体が目的にならないようにしたい。
〜最後まで読んで頂き、ありがとうございました〜
ーーーーーーーーー Information ーーーーーーーーー
こちらは音声作品向け台本執筆活動をしている“さわな”が思ったことを徒然に語る場所です。不定期更新です。
2020年10月30日で活動4周年を迎えます。いつもありがとうございます!
さわなの活動場所等↓リンクで飛べます↓
★台本のリクエストやご感想こちらにどうぞ(匿名窓口)
さわなのバックヤードに対するご感想・ご意見・ご要望もお待ちしています。
〓〓 台本まとめリスト・まとめサイト 〓〓
台本探しに是非ご活用ください。
★さわな主催・台本まとめ企画
女性向けフリー台本まとめ(あまあま編)
ーーお世話になっているサイト様 ーー
★SHIKI様まとめサイト
【全年齢・R18女性向け台本広場】台本師様一覧紹介ページ
※10/9時点でリンク先のページが存在していないことが判明したため、リンクを切りました。
★コモド小トカゲ様まとめサイト
【音声作品】演者・台本・イラスト 募集と依頼まとめ
さわなのバックヤードへようこそ! 閲覧ありがとうございます。あなたが見てくれることが一番の励みです。 あなたの「スキ」「感想やコメント」「SNSでのシェア」などのアクションが何よりのサポートです。
![さわなのバックヤード[創作RooM7号室]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/49707315/profile_193e9f66f9a6a44b0357eec63bd3a5f0.png?width=60)