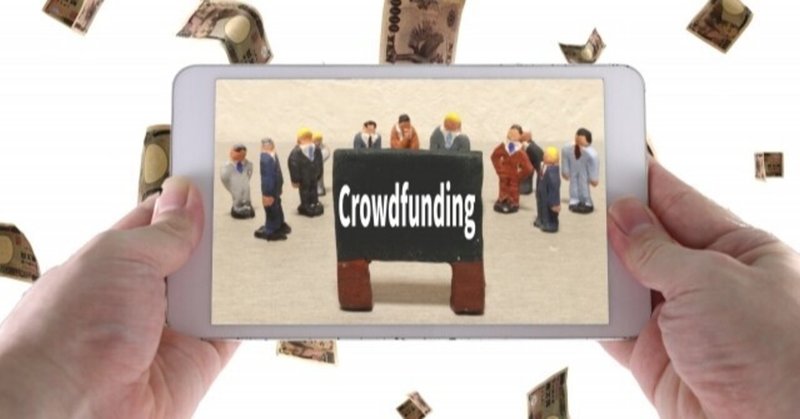
クラウドファンディング 成功の秘訣は共感
これまで、リテールテック関連で色々記事を書いてきましたが、最終的にはクラウドファンディングを通して、公の評価を伺いたいと考えています。そこで、今回CAMPFIREおよびSPARKSを実際に見て、成功につながるポイントを考察したいと思います。
流し見をして、自然と目がいくものと行かないものがあること、読んでも途中でブラウザバックしてしまうことがあることに気付き、以下の仮説を立案しました。
成功するクラウドファンディングの仮説
- ページを見させるファーストビュー
- 見させたひとに続きを読ませるキャッチーさ
- 読み進めた人に援助させたくなる共感性
- 実現に向けての推進力が伝わる熱量
この視点から、自分が投稿を考えているSPARKSから1件、CAMPFIRE全体から3件、記事を紹介します。
SPARKSの記事
ページを見させるファーストビュー
VRサーフィンデバイスというタイトルと、実際にそれを使用しているサムネイル画像をみて、私はクリックしました。体験動画も面白いです。
見させたひとに続きを読ませるキャッチーさ
サーフィンの難しさ、楽しさがわかりやすく記載されており、自分自身がサーフィンをやったことはありませんが、思わず読み進めてしまいました。
読み進めた人に援助させたくなる共感性
海に行けない、道具が高い、けど楽しいから気付いたらうまくなっている。スキーに通ずるものを感じました。
実現に向けての推進力が伝わる熱量
プロにまで動画を頼むなんて。
文句なしです。応援したくなります。
実際に成功されており、納得です。
応援したい記事
見た瞬間に、サービス接客業を価値ある職種にしたいというタイトルに惹かれ、記事を読み進めました。そして、読み進める中で、サービス・接客業の持つ悩みに強く共感しました。
私も、なんで●●(私の会社名)に就職したの?と何度も言われました。更には、自社の従業員にさえも何度も言われ、小売業で働いていることを誇りに思っている人は、本当にいないのだと悲しい気持ちになったことを、この記事を読んで思い返しました。
外食産業と違う業界といえど、同じ接客を伴う職種。このような草の根活動を通して、少しずつ生活になくてはならない産業の価値を上げていただきたいと考えました。
自分自身が計画している、プロトタイピングによるクラウドファンディングとは異なる部分も多く、また目標金額も非常に高いため、私が実施するものとは規模が異なるかもしれませんが、①とにかくページを開かせる、②共感させることができれば、かなりの確率で応援してくれるという気付きになったので、この記事を選ばせていただきました。
惜しいと感じた記事①
認知症をあきらめないというサムネイルを見て、自分の祖父が認知症であったことを思い出し、読み始めました。読み進める中で、BPSDにおける現状の問題と、解決するための主催者の熱量も感じ取りました。
ただ一つ、その解決策は本を出すことなのか?と思いました。BPSDを周知し、その解決策を広く社会に広める目的であれば、見るハードルが低く、最新の知見への更新が容易なweb媒体の方が適していると感じてしまいました。
クラウドファンディング達成額を見ても50万円で初版500部発行となっており、大変僭越ながら500だけかと感じました。
惜しいと感じた記事②
弓道か!と思い見始めました。やはり共感できるテーマは見始めてしまいます。自分自身弓を引いていたので、
時代も変わり、スポーツにも科学の力や、解析の手段が増えています。その中で、今だ弓道界では、諸先生からの感覚的な指導が重要視されています。
という部分にも強く共感でき、応援したいと感じました。
内容としても、巻き藁と的前の乖離という、多くの弓道経験者が感じる部分を取り上げており、私も巻き藁にペットボトルキャップをセットして、似たような練習をした経験があるので、プロトタイプ自体も面白く感じました。
ただ、これ絶対弓道経験者しか投資しないな、とも思いました。ひとつ目のVRサーフィンに合ったような、やっていない人にも共感させる、競技自体の魅力についても伝えられればよりよい企画と思いました。
さらに言うと、先程申し上げたようにペットボトルのキャップでいいなとも思ってしまいました。何となく主張が弱いというか、今あるものじゃダメと言える強さが欲しいとも感じました。
結びに
CAMPFIREの記事数が非常に多く、今回見切れなかったというのが正直なところですが、最後まで読み進める記事は、総じて自分自身も共感できる部分があると感じました。
冒頭にも書きましたが、ファーストビューで捕まえて、共感してもらえる人の目に留まる確率を少しでも上げることが重要と言えるでしょう。
そして、ここからが戦略的な問題。例えば私の視点で言えば、小売業の魅力と辛さをわかりやすく伝えることで、少しでも多くの人に共感してもらうのか、ひたすら尖らせて、小売業以外の人はわからなくても、小売業の人間は絶対に応援してくれるという方向に進むのか。
更に記事を読み進めながら、考察を深めていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?




