
校閲レディの仕事術 Part II・「読み方」について
突然ですが、こちらの文章を読んでみてください。

「こんにちは 皆さんお元気ですか? 私は元気です。」
と読んだ方、もう一度、一文字ずつ読んでみましょう。
「あれ? あぁぁ!」
と、なった方、これからご紹介する「校正的読み方」をぜひご覧ください。
決して、意地悪したわけではないですよ!
今日は校閲レディの仕事術 Part IIとして、文字の「読み方」について書いてみたいと思います。
「校正的読み方」:どう見るのか
上の文章をスルリと読めるのは、「Typoglycemia」という現象だそうです。
「Typoglycemia」とは、単語の最初と最後の文字が合っていれば、中の文字が入れ替わっても読めてしまう現象のこと。
ずいぶん前に話題になりましたよね。まだ日本語の名称はないそうですが、要するに、「そら目」しちゃうということかと思います。
デジタル世界では、「こんちには」と「こんにちは」はまったくの別物。読み間違いという現象は起きません。それはそれでいいのですが、人間がそれをやると疲れてしまいます。だから、“だいたい”のところで“ふんわり”と把握する能力は、生きる知恵なのではないかとわたしは感じるのです。
この大雑把な感じはO型人間にとって、とてもうれしい! 大好き! 人間、サイコー!
なんですが。
校閲レディとして仕事をする時は、この技は使えません。
ダメ。絶対。
校正の読み方とは、こちらです。
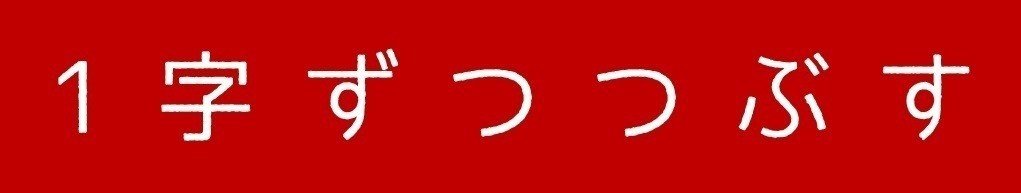
なぜ、「つぶす」と呼ぶのか? 理由はよく分かりませんが、色鉛筆でひと文字ずつマークしていくので、確かに「つぶしている感」はある気がします。
そしてわたしは普段、プライベートや業務外で本やニュースを読んでいる時と、校正の仕事をする時は、読み方を分けています。(きっちりきっちり読んでいたら疲れちゃうので)
Part Iで書いたように、校正の作業の流れは下記のとおりです。
<校正の流れ>
1 情報確認
2 資料合わせ
3 素読み
4 整合性
5 ネガティブチェック
そして、どの作業においても、

のです。
大変でしょ?笑
でも、残念ながら、校正のすべては、このひと言に尽きるのです。
「校正的読み方」:何を見るのか
1字ずつマークするだけなら簡単なのですが、もちろん正しい文字であるかどうかの「確認」も必要です。では、何を見ているのか。
・大文字/小文字
・アキのある/なし
・全角/半角
・同音異義語
こういった点に注意しています。
特に日本語は同音異義語が多いので、「確立」なのか「確率」なのか、「上げる」なのか「挙げる」なのか、1字ずつ自分の中で確認しながら進めます。分からない時は、もちろん辞書を引きます。
とはいえ、ほとんどの校正者が同音異義語の見落としをした経験があるように思います。ですが、過去にミスしたことがある漢字ほど気をつけるようになるので、技術も上がっていきます。
(そうでない校正者は仕事を発注されないので淘汰されていきます)
じゃあ、ひらがなは読みやすいのかというと、決してそういうわけではありません。ひらがな・カタカナのような「カンタンに読める文字」ほど、落とし穴が……。

これは、わりと気が付きやすい例だと思います。
では、こちらはどうでしょう?
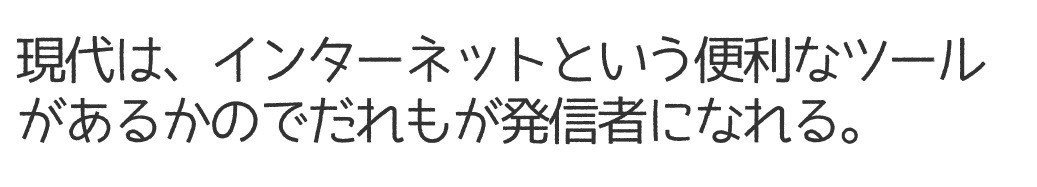
「漢字の連続は読みにくい」は、ライティングの注意点としてよく挙げられますが、校正の場合は逆なんです。「ひらがなの連続は読みにくい」のです。
なぜなら、カンタンに読めてしまうから。
なかなかに因果な商売ですよね……。
Part Iの作業項目でお伝えした、
1 情報確認:水色
2 資料合わせ:緑色
は、特に固有名詞であることが多いので、絶対に絶対に絶対に間違えられません。
全体の校正は無理でも、この部分だけはキッチリと見る工程を入れるだけで、記事の精度は上がると思います。
ぜひ、お試しあれ!
※タイトル画像は福岡で開催されている『トンコハウス展 「ダム・キーパー」の旅』で撮影したものです。ピクサーの元アートディレクターが制作した短編映画『ダム・キーパー』の制作風景が展示されています。ギャラリーの隅々に隠れているキャラクターを探すのも楽しいですよ。入場無料、8月31日まで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
