
「トップシェフの技と思いが超進学校の生徒達の心を動かす」 ~家庭科での食体験レッスンの試み
1 試みの概要
神戸にある灘校は最強の進学校とも言われる中高一貫の男子校です。食を扱う家庭科は高1と中1で週1時間の授業がありますが校内に調理室はなく調理を伴う実習は食堂で行います。調理実習は各学年とも年間1回のみで生徒達が学校生活で食の体験が出来る機会は限られていましたが、食の大切さや奥深さを知るために「食体験」は欠かせません。
勉強に追われ部活動にも意欲的に取り組み多忙な生徒達は食への関心が低い子が多く、食事をないがしろにしている様子も見られました。栄養素などの知識が豊富で頭では食の重要性を理解していても体験からしか得られない事もあります。「食を共に手作りし皆で食べることで心を満たし人とつながる体験」をして欲しいという思いでこの実践を試みました。
2017~2019年の3年間、辻学園調理製菓専門学校教員の鈴木勤シェフを迎えて食の体験実習を行う事にしました。鈴木シェフはかって大阪で著名なイタリア料理店のオーナーシェフと活躍されており飲食業界の経営面のエキスパートでもありました。その豊かな実体験を生徒達に伝えていただければという思いもありました。
高校生は高1高2の希望者を対象に土曜講座*1を利用して「料理講習」を、中学生は中1学年を対象に家庭科の授業で「野菜の食べ比べ」の体験実習を行いました。
食のプロである鈴木シェフを迎えた事で学びの質が驚く程変わり、生徒達の心が大きく動く様子が見られました。そこには鈴木シェフの食への強い思いと生徒達の主体性を大切にする実習の進め方やプロとしての在り方など見習うべき事も多く、その取り組みをまとめました。*1: 総合的な探究の時間の一環として行われる選択制の講座
2 2017年:スクールカフェ構想講座
【料理が動かした生徒の心】

鈴木シェフを迎えた最初の料理講習は2017年10月に実施した「スクールカフェ構想」講座の前半に行われました。この講座は前半90分で生徒達がカフェメニューの参考になる料理講習を受け、後半90分でグループに分かれカフェプランを立て発表する内容でした。 灘校は文化祭等の学校行事で生徒が主体となる食品の模擬店の出店がありません。もし校内でカフェを運営するなら、どんな内容にするかを考える内容の方が料理講習だけよりも興味を持つ生徒が多いと考え企画した講座でした。
当日の参加人数は9名。講座前半、3班に分かれパスタとトマトソースを作り試食となります。試食時には鈴木シェフが「ぜひ生徒達に試飲して欲しい」と学校に持参したポタージュも配られました。「無農薬等こだわりの食材で作った本物の味を知って欲しい」という想いが込められたポタージュ。それを口にした生徒達の表情が一変したのです。灘高の生徒は知的で冷静な子が多く表情があまり変わらないのですが、この時は違っていました。ただ、この時点では後半の講座に向けて片付けを急いでいたので表情の変化の意味は分かりませんでした。
後半は場所を食堂から会議室に移し、鈴木シェフも参加しグループ別にカフェプランを立てていきます。鈴木シェフをオブザーバーとして迎えグループワークは盛り上がりを見せました。
最後に各グループからプレゼンがありますが、先ずカフェの営業時間については、全てのグループが昼休みか休み時間という事で一致。放課後は皆、部活や塾で忙しく人が集まりにくいという理由です。
1つ目のグループの案はドリンクバーとちょっとした食べ物をセットで500円で提供するプラン。晴れた日は屋外。雨の日はフリースペースを使い、ゆっくり落ち着いた空間にするという内容でした。2つ目は図書館横のブックラウンジを使い、前半の講座で作ったパスタ・スープとコーヒーをセットで500円で提供するプラン。単品の場合はパスタが300円それ以外は150円と設定。お祭りみたいに楽しい雰囲気で提供するという内容でした。最後の案は中庭かピロティでコーヒーや紅茶を150円で提供。昼食を出すならオムライスやカレーライス、ハンバーグ、トーストなど当日その場で即席で出来るメニューを机といすを配置して提供するという内容。BGMとしてクラシック研究会の演奏を流すという点がユニークでした。これらの価格設定は今日の講座の材料費が生徒1人500円というところから推定しました。いずれも学校生活と食のニーズを知る当事者である高校生ならではのプランが出揃う結果となりました。
驚いたのは講座直後の生徒達の感想です。「ポタージュが本当に美味しかった」「体に染み渡るようだった」「あんなに美味しいスープ、初めて飲んだ」と料理に関する事ばかりだったのです。一品の料理が生徒達の心をこれだけ動かす事を知り、高校生にとっての食体験の必要性を改めて思い知る経験となりました。
【体験の共有から生まれる深い学び】
料理に加え、料理講習で生徒達を魅了したのは鈴木シェフの調理の技と立ち振る舞いでした。
料理講習は(1)鈴木シェフによるデモンストレーション(2)生徒達による調理(3)試食と片付けという流れでした。デモンストレーションでプロが見せるオレキエッテというパスタの形を作る手際よさ、トマトソースを作る時のフライパンの扱いの美しさに生徒達の目は釘付けになりました。
普段から動画に慣れ親しんだ生徒達動きを見るだけで自分達にも簡単に出来ると思います。ところが実際にやってみると思ったようには行きません。時間をかけて、自分達なりに満足のいく形のオレキエッテを作り鍋の水を沸騰させ、ゆでていきます。
その傍らではソース作りが始まりました。ソースに使う野菜の下ごしらえをしながら「鷹の爪はどの位入れる?」など楽し気に会話がはずみ、それぞれの班で連帯感が生まれ料理がスムーズに進む様子が見られるようになりました。
実習中、一人の生徒が鈴木シェフの真似をしてフライパンを大きく動かした瞬間、中の油に火が燃え移り、炎があがる場面がありました。恐怖で手放したフライパンに火は広がり燃え続けます。我にかえり「すみません。すみません。」と謝り素手で火を消そうとした生徒の手を制し、鈴木シェフは「料理にアクシデントはつきものだよ」と微笑みかけ落ち着かせ、濡らした布巾で火を覆い何事もなかったかのように火を消しました。ショックをうけた生徒もシェフの穏やかな口調に冷静になり、次の作業に取り掛かる事が出来ました。炎はすぐに鎮火しましたが、生徒達にとっては火の扱いについて知る貴重な経験となりました。食の体験は調理を伴う場合、予期せぬ事が起こる可能性があり、それを通して経験値をあげていく事も大切だという事も改めて考えるきっかけとなりました。
【外部との連携の大切さ】
この土曜講座でアシスタントとして雑用をこなしながら生徒達を傍で見ていて痛感したのは外部連携の大切さです。超進学校の男子校にプロを迎えてまでの調理実習は不要と考えていましたが違いました。プロの指導は食への強い思いがベースにあるがゆえ生徒達の心を動かす事が分かりました。
また講座を鈴木シェフの「余計な口出しをせず大らかに見守る」指導法は、時間内に実習を終わらせるために生徒達を急かし上手く出来ない所は手伝っていた自分のやり方を改めるきっかけとなりました。
3 2018年:初心者のためのイタリア料理講座

【本物のシェフの技を見つめる生徒達】
前年の実習を元に2018年10月に実施した「初心者のためのイタリア料理講座」には募集した定員を上回る高1高2の生徒21名が参加しました。今回は90分でジャガイモのポタージュ・米粉パスタ・オイルサーディンを使ったソースの3品を作り、試食と片付けまでを終わらせる内容です。試食時に鈴木シェフから「イタリアの食文化」についての話を聞く時間を設け料理に加え食の知識を深める2本立ての実習としました。
実習ではミキサーやシノア(スープ漉し)等の特別な器具を準備し本格的な料理の仕上げを体験できるようにしました。
実習では5班に分かれて料理を行います。班には初めて顔を合わせる生徒達もいて最初はぎこちない雰囲気の班もあります。すぐに鈴木シェフによる料理の説明とデモンストレーションが始まり、シェフを囲む生徒達の表情は真剣そのもの。プロの技を食い入るように見つめます。それはシェフの「料理の面白さや奥深さを生徒達に体験して欲しい」という
本気が伝わったから。
【調理のグループワークで身体知を学び合う】
そして調理開始です。本来グループ調理は一人で作るより難しく、グループ内で円滑なコミュニケーションが取れないと作業が進まないのですが、この講座ではどの班もスムーズに作業が進みます。
「このパスタの形、どうしたらうまく出来る?」
「ソースの火加減はこんな感じ?」
「ポタージュの味付けはこれでいいのかな?」
「シノアって、こんな風に使うんだ!」など、お互いに助け合う学び合いが見られました。
それはプロのいる安心感と、いつもは一人で全てをこなし気が抜けずピリピリしていた自分がアシスタント役でサポートし余裕のある環境を作れたからだろうと思います。
試食に入るとイタリアの食文化の話が始まり鈴木氏のハンドドリップコーヒーや紅茶が配られます。生徒達は自作の料理と香り高いコーヒーや紅茶と
共に話に静かに耳を傾けます。そこには最初のぎこちなさはみじんもなく不思議な一体感があり、これこそが食の体験を通した深い繋がりだと感じ入りました。
【土曜講座のまとめ】
2年間の土曜講座の取り組みを通してシェフの食への熱い思いとプロの技が高校生の心を動かし、食への興味や調理への関心に心が動く様子を見て来ました。さらに想定外だったのは灘高生が普段は接点のないだろう食のプロと出会う事で、職人の持つ職業意識の高さに触れ「すごい!」と感動していた事でした。高校生は卒業後の人生設計を考える時期ですが、どの分野にしてもプロと呼ばれる外部の方との連携は様々な面で生徒達の刺激となる事を実感しました。
4 灘中2018年:トマトを使った食体験実習

【食体験の概要】
中1学年全体を対象に鈴木シェフを迎えた最初の食体験実習は2018年6月下旬に行われました。「旬の野菜を使った味覚の体験」をテーマとし3種類のトマトについて味・色・食感などを比較するという内容です。場所は生徒達が動きやすいように流し台がある広い会議室を使用。1クラス45名を10班に分けてグループワーク形式で行いました。
生徒主体の体験型実習にするため
(1)鈴木シェフによる野菜についての講義
(2)「野菜」をテーマにしたグループでの話し合い
(3)体験実習についての説明
(4)グループ別の食べ比べと意見交換
(5)まとめ
という流れで実施しました。
【食を通した学び合い】
食体験をより深い学びの場とするための工夫として
(1)食のプロを迎える事
(2)様々な野菜の食体験が出来る事を伝え生徒達のモチベーションを高めるようにしました。
実習当日、いつもはにぎやかな生徒達が入室してシェフ姿の鈴木シェフを見た途端、様子が変わります。プロのいるピンと張りつめた空気を感じとったからです。
授業が始まり鈴木シェフの穏やかな語り口と生徒達と交流を持とうとする姿勢に触れ、場は一気に和やかになります。シェフの「野菜の魅力を知って欲しい」という想いが伝わったようで生徒達は真面目な面持ちで講義に耳を傾けていました。
味覚実習に入ると部屋中に元気な声が飛び交い活発な意見が交わされます。味覚は人により異なり感じ方も様々です。グループの中で他の子の自分とは違う感じ方に触れ、それを共有できる体験実習は生徒が自分とは異なる感じ方がある事を知り他者の感じ方を受け入れる経験の場ともなります。
生徒達の感想には「いろいろなトマトを知る事が出来て面白かった」「同じトマトでも種類が違うと味が全然違う事に驚いた」「果物みたいに甘いトマトを初めて食べて感動した」など自分の五感を使い体験を通してしか得る事が出来なかった内容が見られ学びの広がりを実感しました。
5 灘中2019年:ジャガイモを使った食体験

【2年目で変えた食体験】
2019年6月下旬に行った2度目の食体験実習は食材をジャガイモに変えて実施しました。トマトは苦手意識を持つ生徒が多くアレルギー症状発症の可能性もあった事が理由です。
食材をジャガイモに変更した事で食体験は食材だけの食べ比べから調理法の比較、さらにジャガイモを含む農産物の生産方法の講義にまで学びが広がりました。また生徒達は6月上旬の実習でジャガイモを使い調理体験もしており学びを深めるのに最適な食材となりました。
実習の内容は「ジャガイモの食べ比べ」です。今回は鈴木シェフの強い要望でジャガイモを食べる時に必要な塩とオリーブオイルに “フルール・ド・セル”というフランスの天日塩、オリーブオイルをオーガニック〈有機〉のバージンエキストラオイルを準備しました。
ジャガイモは鈴木シェフに“シャドウクイーン”と“インカの目覚め”という2種類をスチーム加熱したモノを当日学校に持参していただきます。これは蒸し物なので揚げ物のポテトチップスを学校で準備し調理法の比較が出来るようにしました。
【体験を超えた学びの深まり】
この時も(1)講義(2)グループ対話(3)実習説明(4)食体験実習(5)まとめという流れは前年と同じにしました。今回は前年の例も挙げながら食体験の面白さや楽しさを伝える事が出来、生徒達の期待は高まります。
実習開始と同時に「これ本当にジャガイモ!?」シャドウクイーンの紫色を見て声があがります。塩とオイルを一緒に配布したので、生徒の一部はまず塩だけを味見します。
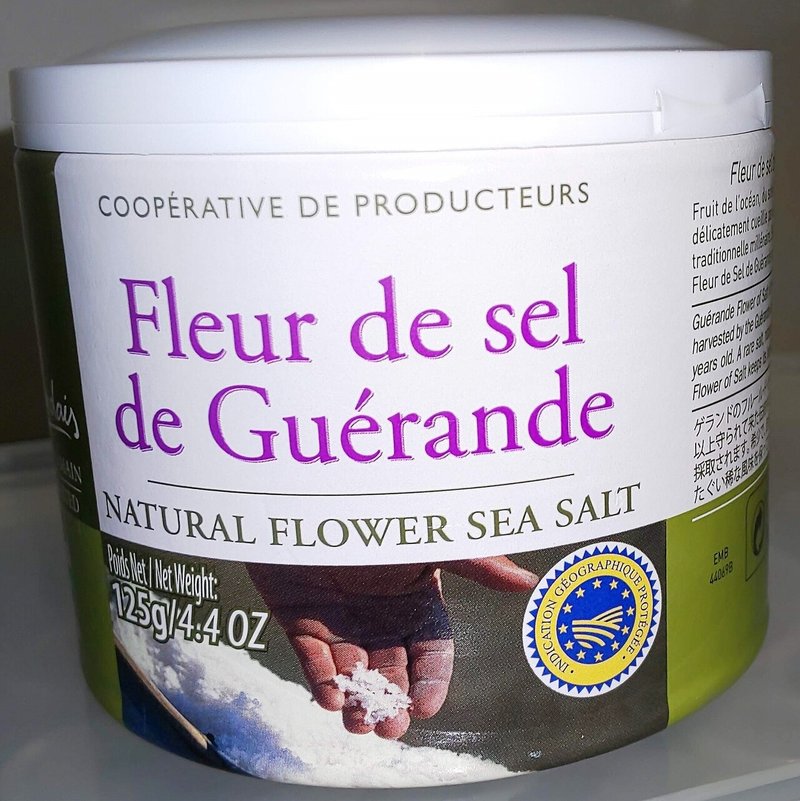
(フルール・ド・セル)
「この塩、美味しい!」と歓声が上がり「ほら食べてみて」「本当に美味しいね、いつもの塩と全然違う!」とあちこちで声が上がります。さらに「オリーブ油って、こんな味なんだ!」と食材と通じて共感の輪が広がって行きました。
“これこそが本物の食の力”。この時初めて鈴木氏のこだわりの理由が理解出来ました。生徒達の無邪気に喜ぶ顔を見て心から本物を使った食体験の重要性と感動を共有できる場の大切さを痛感しました。
実習では最後に食の生産者とつながりの深いシェフから「日本の農業の後継者不足の深刻さ」や「体にも環境にも安全な有機農法を農産物の栽培に取り入れる難しさ」などを聞きます。

(有機エキストラバージンオリーブオイル)
感想には「有機農業を広めるために自分に出来る事は何か考え行動していきたい」「日本の農業の実態を知りショックだった。何とかしなければと思った」「家で有機野菜を使うよう頼み農家を応援したい」等とあり、シェフの「野菜の生産の現情を知って欲しい」という想いが生徒達に届いた事が分かりました。
6 まとめ

今回、退職した灘校での食の取り組みをまとめる機会をいただきレポートの形にしたものをnoteでシェアさせてもらいました。記憶違いをしている所があるかもしれませんが、どの取り組みも深く胸に刻まれています。
初任の農業科での食品加工を始め、選択のフードデザインや女子中高での食物など多くの調理実習を担当して来ましたが、食の体験を伴う取り組みはどんな形であれ子供達にとっては5感を通して記憶される貴重な経験の場になります。今は食を共にする機会が制限されていますが、ここでシェアさせていただいた試みが何かのお役に立てれば幸いです。長文をお読みいただきありがとうございました。(終わり)
